「それ、いらわんといて!」
関西の人がこんな風に言うのを聞いたことはありませんか?この「いらう」という言葉、標準語の「触る」と訳されることが多いですが、実はそれだけでは表せない独特のニュアンスが隠されています。関西人にとってはごく自然な言葉でも、他の地域の人からすると「どういう意味?」と戸惑ってしまうことも少なくないようです。
この記事では、そんな奥深い関西弁「いらう」の基本的な意味から、具体的な使い方、標準語の「触る」との微妙な違い、さらにはその歴史的背景や語源まで、わかりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたも「いらう」を使いこなせる関西弁マスターになれるかもしれません。
関西弁「いらう」の方言の基本的な意味を解説

まずは、「いらう」という言葉が持つ基本的な意味合いについて見ていきましょう。多くの場合は「触る」や「いじる」と同じように使われますが、そこに関西弁ならではの感情的な色彩が加わるのが特徴です。
「いらう」は標準語で「触る」「いじる」
「いらう」の最も基本的な意味は、標準語の「触る」や「いじる」に相当します。 手で物に触れたり、何かを操作したりする行為全般を指す言葉です。例えば、「パソコンをいらう」と言えば「パソコンを操作する」という意味になりますし、「髪の毛をいらう」と言えば「髪の毛をいじる」という仕草を表します。
このように、対象が物であれ人であれ、何かを手で触ったり動かしたりする際に幅広く使える便利な言葉です。しかし、単なる動作を表すだけでなく、そこには独特のニュアンスが含まれていることが多くあります。
多くは否定的なニュアンスで使われる
「いらう」が興味深いのは、肯定的な文脈よりも、むしろ否定的な文脈で使われることが多い点です。特に、誰かの行為をやめさせたい時に「いらわんといて(触らないで)」や「いらうな(触るな)」といった形で頻繁に登場します。
例えば、母親が子どもに向かって「こら、そんなとこいらったらあかん!」(こら、そんな所を触ったらだめ!)と注意する場面を想像してみてください。この場合、「触る」という行為そのものに加えて、「むやみに触るべきではない」「余計なことをするな」といった、少しネガティブな感情や警告のニュアンスが含まれているのが分かります。ただ「触らないで」と言うよりも、どこか親しみを込めた、あるいは少し呆れたような感情がにじみ出るのが「いらう」の特徴です。
物にも人にも使える便利な言葉
「いらう」の対象は非常に幅広く、機械や道具といった「物」から、人の身体の一部、さらには「人」そのものに対しても使うことができます。
物に対しては、「ちょっとその機械いらわして」(ちょっとその機械を触らせて)のように、操作や確認のために触る意味で使われます。 一方で、人の髪や肌、あるいは「かさぶた」のようなデリケートな部分をしきりに触る癖を指して「かさぶた、いらうのやめとき」(かさぶたをいじるのはやめておきなさい)と言ったりもします。
さらに、物理的に触るだけでなく、比喩的に人を「からかう」「なぶる」といった意味で使われることもあります。 「あんまり人のこといらうなや」(あまり人をからかうなよ)といった使い方がそれで、相手を面白半分に扱うような状況で用いられます。このように、文脈によってさまざまな対象に使える、非常に表現力豊かな言葉なのです。
【状況別】関西弁「いらう」の使い方を例文でマスター

言葉の意味を理解したら、次は実際の会話でどのように使われるのかを見ていきましょう。ここでは、具体的なシチュエーションを想定し、例文を交えながら「いらう」の使い方をマスターしていきます。
物を触る・操作するときの「いらう」
日常生活で最もよく耳にするのが、物を触ったり操作したりする際の「いらう」です。特に、精密機械や誰かの大切なものなど、むやみに触ってほしくない物に対して使われることが多いです。
・例文1:「このパソコン、勝手にいらわんといてな。データ消えたら困るし。」
(訳:このパソコン、勝手に触らないでね。データが消えたら困るから。)
この例文では、単に「触るな」と命令するのではなく、「勝手な操作をして問題を起こさないでほしい」という心配や釘を刺す気持ちが込められています。
・例文2:「新しいスマホ買ったん?ちょっといらわせてーや。」
(訳:新しいスマホ買ったの?ちょっと触らせてよ。)
こちらは、新しいガジェットに興味津々で、操作してみたいという気持ちを表しています。 「触らせて」よりも、いろいろと機能を試してみたいという好奇心が強く感じられます。
かさぶたや髪の毛を触るときの「いらう」
自分の体や他人の体の一部を繰り返し触る、いわゆる「いじる」癖に対しても「いらう」は使われます。治りかけのかさぶたや、無意識に触ってしまう髪の毛などがその代表例です。
・例文1:「またかさぶたいろて。そんなことしてたら、跡になるで。」
(訳:またかさぶたをいじって。そんなことをしていたら、跡が残るよ。)
この「いらう」には、「治りを遅らせるような、好ましくない触り方」というニュアンスが含まれています。 親が子を心配して注意するような、温かみのある響きも感じられます。
・例文2:「考え事してるとき、いっつも髪の毛いらう癖あるよな。」
(訳:考え事をしているとき、いつも髪の毛をいじる癖があるよね。)
この場合は、否定的な意味合いは薄く、単にその人の癖を客観的に指摘している表現です。
人をからかうときの「いらう」
物理的に触る行為だけでなく、言葉や態度で相手をからかったり、面白がってもてあそんだりする意味でも「いらう」が使われます。 この用法は少し古い言い方かもしれませんが、文脈によっては今でも耳にすることがあります。
・例文1:「あいつは口ばっかりで、いっつも人のこといろうて楽しんどる。」
(訳:あいつは口先ばかりで、いつも人をからかって楽しんでいる。)
ここでは、相手を尊重せず、おもちゃにするようなネガティブな態度を非難する意味で使われています。「からかう」よりも、少し意地悪な響きを持つことがあります。
・例文2:「あんまり人のこといらうもんやないで。本気で怒られたらどないすんねん。」
(訳:あまり人をからかうものじゃないよ。本気で怒られたらどうするんだ。)
このように、相手の度が過ぎた言動をたしなめる際に用いられることもあります。
「いらう」と「触る」はどう違う?関西弁の絶妙なニュアンス
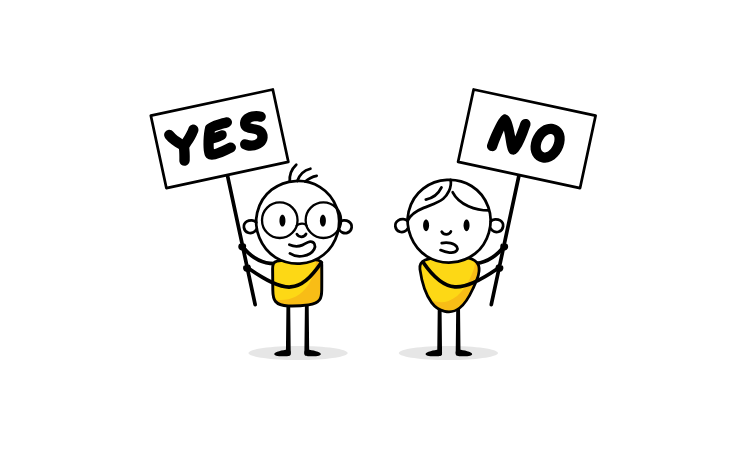
「いらう」は標準語の「触る」に置き換えられることが多いですが、二つの言葉が持つニュアンスは完全には一致しません。ここでは、その微妙な違いについて掘り下げてみましょう。この違いを理解することが、関西弁の奥深さに触れることにつながります。
客観的な行為を表す「触る」
標準語の「触る」は、基本的に価値判断を含まない、客観的な行為を表す言葉です。例えば、「展示品に触る」や「動物に触る」といった場合、その行為が良いか悪いかは文脈によりますが、「触る」という単語自体にネガティブな意味合いはありません。あくまで「物理的に接触する」という事実を淡々と述べているに過ぎません。
関西弁でももちろん「触る(さわる)」という言葉は使いますが、より客観的、中立的な表現をしたいときに選ばれる傾向があります。
「いらう」に含まれる”触るべきでない”というニュアンス
一方、「いらう」には、多くの場合「必要以上に」「むやみに」「下手に」といった、話し手の主観的な評価が含まれます。 特に「いらわんといて」という否定形で使われる際には、「それは触るべきではないものだ」という暗黙の前提が強くにじみ出ます。
例えば、修理中の精密機械があったとします。その状況で「触らないでください」と言うのは、単なる事実の伝達です。しかし、関西弁で「これ、いらわんといてや」と言うと、「下手にいじって壊したらあかんで」「余計なことせんといてな」という、相手の行動をけん制し、結果を心配する気持ちまで伝わってきます。 このように、行為そのものだけでなく、その行為がもたらすであろうネガティブな結果を予見し、それを未然に防ごうとする意図が「いらう」には込められているのです。
「いらわんといて!」と言われたときの対処法
もし関西の人から「それ、いらわんといて!」と言われたら、それは単なる注意以上のメッセージかもしれません。相手は、あなたが触っているものがデリケートであったり、壊れやすかったり、あるいは非常に大切なものである可能性を伝えようとしています。
この言葉を聞いたら、まずは素直にその物から手を離すのが賢明です。そして、「ごめん、知らんかったわ」と一言添えれば、相手も「いや、ええねんけど、これ大事なやつやから」と理由を説明してくれるでしょう。相手の言葉の裏にある「大切に扱ってほしい」という気持ちを汲み取ることが、円滑なコミュニケーションにつながります。関西人以外の人がこの言葉を誤解して「言わないで」という意味だと捉えてしまうこともあるようですが、正しくは「触らないで」という意味です。
知って得する!関西弁「いらう」の語源と歴史

普段何気なく使っている方言にも、実は長い歴史と深いルーツが隠されています。「いらう」もその一つで、古くから日本語に存在する言葉が時代と共に変化し、現代に受け継がれてきたものです。
「いらう」のルーツは古語の「弄う(いろう)」
「いらう」の語源は、古語の「弄う(いろふ、または いろう)」という言葉であると考えられています。 この「弄う(いろう)」が時代を経て「いらう」へと音が変化したという説が有力です。
古語の「弄う(いろう)」には、現代の「いらう」と共通する意味が多く含まれています。例えば、「手で触れる、いじる」という意味のほかに、「関わり合う」「口出しする、干渉する」「言い争う」といった意味もありました。 特に「手で触れる、いじる」という意味が、現代の関西弁「いらう」に色濃く受け継がれていることがわかります。
万葉集にも登場する古い言葉
「弄う」の源流をたどると、さらに古い時代へとさかのぼります。「弄」という漢字自体が、もともと「手でもてあそぶ」という意味を持っており、日本語として定着していきました。はっきりとした用例を万葉集の中に見つけることは難しいですが、関連する言葉や概念は古くから存在していたと考えられます。 古語辞典によれば、「弄う(いろう)」は平安時代の文献などにも見られ、例えば『平家物語』には「弄ふまじき事に弄ひ(関わるべきでないことに関わり)」といった用例が確認できます。 このように、「いらう」は単なる地方の方言というだけでなく、日本語の長い歴史の中で育まれてきた言葉の一つなのです。
なぜ関西や西日本に「いらう」が残ったのか
では、なぜ「弄う(いろう)」という言葉は、標準語からは消えていき、主に関西を中心とした西日本エリアで「いらう」として残ったのでしょうか。
これには、日本の言語史が深く関わっています。かつて日本の政治・文化の中心であった京都や奈良で使われていた言葉(中央語)は、時代が下るにつれて周辺地域へと広がっていきました。一方で、江戸(現在の東京)に政治の中心が移ると、今度は江戸の言葉が新しい中央語として全国に影響力を持つようになります。
この過程で、古い中央語であった言葉が、新しい中央語の影響が比較的及びにくかった関西や西日本の地域に、方言として保存されることがあります。「いらう」もその一例と考えられます。つまり、かつては全国的に使われていたかもしれない「弄う」という言葉が、歴史の中心地であった関西圏に色濃く残り、現代にまで受け継がれてきたと推測できるのです。
「いらう」は関西弁だけじゃない?使われている地域

「いらう」と聞くと多くの人が関西弁を思い浮かべますが、実はこの言葉が使われているのは関西地方だけではありません。西日本を中心に、かなり広い範囲で使われている方言なのです。地域によって少しずつニュアンスや使い方が異なる場合もあります。
近畿地方での「いらう」の使われ方
まず中心地である近畿地方では、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、そして三重県など、ほぼ全域で「いらう」が使われています。 基本的な意味は「触る、いじる」で共通していますが、地域や年代によっては「いろう」という発音になることもあります。
・大阪府:「手で触れる、いじくる」といった意味合いで、日常的に使われます。
・京都府:「触る、いじる」のほかに「もてあそぶ」といったニュアンスで使われることもあります。
・兵庫県、奈良県、和歌山県などでも同様に「触る」という意味で広く浸透しています。
中国・四国地方での「いらう」
近畿地方に隣接する中国・四国地方でも「いらう」はポピュラーな方言です。
・岡山県:「触る、いじる」という意味で、標準語のように日常的に使われます。目上の人に対しても語尾を丁寧にするだけで普通に使うなど、関西地方よりも使用範囲が広い場合があります。
・広島県、山口県、愛媛県、香川県などでも「触る」という意味で使われており、西日本では非常に一般的な言葉であることがわかります。 例えば「かさぶたをいらう」といった表現は、これらの地域でも共通して聞かれます。
九州地方やその他の地域での用例
さらに西へ進んだ九州地方でも「いらう」は使われています。
・福岡県、熊本県:基本的な意味は「触る、いじる」ですが、熊本県の一部では「干渉する」という意味合いで使われることもあるようです。
また、西日本から離れた地域でも、異なる意味で「いらう」という言葉が使われている例があります。
・青森県(下北弁):「要る」という意味で「要らう(いらう)」が使われます。「飴っこいらうが?(飴は要るかい?)」といった具合です。
・山梨県や静岡県の一部:「借りる」という意味で「いらう」が使われることがあるようです。
このように、「いらう」という音を持つ言葉は全国に点在していますが、「触る、いじる」という意味で広く使われているのは、やはり関西を中心とした西日本地域と言えるでしょう。
関西弁「いらう」の意味や使い方まとめ

この記事では、関西弁「いらう」について、その意味や使い方、語源、そして使われている地域まで幅広く解説してきました。最後に、記事の要点を振り返ってみましょう。
・「いらう」の基本は「触る」「いじる」:標準語の「触る」「いじる」とほぼ同じ意味で、物や人に対して幅広く使えます。
・否定的なニュアンスが特徴:「いらわんといて(触らないで)」のように、特に否定形で使われることが多く、「むやみに触るべきではない」という話し手の主観的な気持ちが込められています。
・語源は古語の「弄う(いろう)」:「いらう」は古語の「弄う」が音変化した言葉で、日本語の長い歴史を受け継ぐ由緒ある言葉の一つです。
・西日本で広く使われる方言:関西地方だけでなく、中国、四国、九州地方など、西日本の広範囲で日常的に使われている言葉です。
単に「触る」と訳すだけでは見えてこない、「いらう」という言葉の奥深さや面白さを感じていただけたでしょうか。この言葉が持つ絶妙なニュアンスを理解すれば、関西人とのコミュニケーションがより一層スムーズで楽しいものになるはずです。

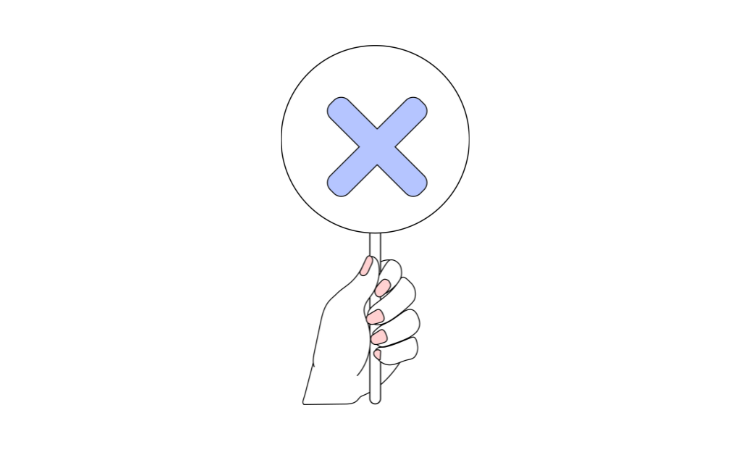

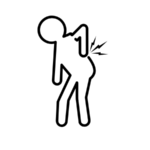
コメント