「行き掛けにコンビニ寄ってくわ」。このような表現を聞いたことはありますか?日常的に使っているという方もいれば、初めて聞いた、あるいは意味は分かるけれど自分では使わない、という方もいるかもしれません。実はこの「行き掛け」という言葉、特定の地域で使われている方言、あるいは方言に由来する言葉だということをご存-じでしたか?
しかし、辞書にも掲載されている言葉であり、その境界はあいまいです。この記事では、「行き掛け」という言葉が方言なのか、どのような意味で使われるのか、その使い方や似たような言葉との違いについて、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、何気なく使っていた言葉の奥深さに気づくかもしれません。
「行き掛け」は方言?標準語じゃないの?

「行き掛け」という言葉の立ち位置について、多くの人が疑問に思うかもしれません。響きから方言だと感じる人もいれば、ごく自然に標準語として使っている人もいます。ここでは、「行き掛け」が主にどの地域で使われているのか、そしてなぜ標準語だと思われやすいのか、その背景を探っていきましょう。
「行き掛け」が使われる主な地域
「行き掛け」という言葉は、特に関西地方をはじめとする西日本で広く使われる傾向があります。 大阪や京都、兵庫などの近畿地方では、日常会話でごく自然に登場する言葉です。
例えば、大阪の吉本新喜劇などでも、役者が「帰り掛けに〜」といったセリフを口にすることがあり、関西圏の人々にとっては非常に馴染み深い表現と言えるでしょう。
また、近畿地方だけでなく、中国地方や四国、九州の一部でも使われることがあり、西日本エリアで広く認知されている言葉と考えられます。
一方で、東日本、特に関東地方ではあまり使われることがなく、「行きがけ」や「行く途中」といった表現の方が一般的です。そのため、西日本の人が関東で「行き掛け」を使うと、意味は通じても少し珍しい言葉だと感じられることがあります。
標準語だと思っていた人も多い?
「行き掛け」を方言だと認識していない人は、特に西日本の出身者に多く見られます。 生まれたときから周囲の大人たちが当たり前のように使っているため、それが地域特有の言葉であるとは夢にも思わず、上京したり、他の地域の人と話したりしたときに初めて方言だと指摘されて驚く、というケースは少なくありません。
この背景には、テレビやメディアの影響も考えられます。関西出身のタレントや芸人が全国ネットの番組で自然に「行き掛け」や「帰り掛け」という言葉を使うことで、全国的に認知され、方言という意識が薄れている可能性があります。
さらに、「行き掛け」という言葉は、実は国語辞典にも掲載されている言葉です。 辞書には「どこかへ行くついで。また、行く途中。」と記載されており、標準語として扱われています。 しかし、実際の使用実態としては西日本に偏っているため、「標準語ではあるが、主に関西圏で使われる言葉」と捉えるのが実情に近いかもしれません。
方言としての「行き掛け」の認知度
「行き掛け」が方言かどうかという認知度は、その人が生まれ育った地域によって大きく異なります。西日本の人々にとっては、あまりにも日常的な言葉であるため、方言としての意識は低いでしょう。 逆に、東日本の人々にとっては、意味は推測できるものの、普段使わない言葉であるため、方言として認識されやすい傾向にあります。
面白いことに、言葉というものは時代と共に変化し、地域を越えて広まっていくものです。近年では、人の移動やメディアの発達により、地域ごとの言葉の境界線はあいまいになりつつあります。
かつては明確な方言だった言葉が、徐々に全国区の言葉になったり、「新方言」として定着したりする例もあります。「行き掛け」も、そうした言葉の変遷の過程にあるのかもしれません。関西圏で生まれ、メディアを通じて全国に広まり、今では多くの人が意味を理解できる言葉として存在しているのです。
「行き掛け」の正しい意味と使い方

「行き掛け」という言葉が、主に西日本で使われることや、辞書にも載っている標準語であることが分かりました。では、具体的にどのような意味で、どのように使えば良いのでしょうか。ここでは、「行き掛け」の基本的な意味から、日常会話で使える例文、そして使用する上でのちょっとした注意点までを詳しく見ていきましょう。
「行き掛け」の基本的な意味とは
「行き掛け(いきがけ、または、ゆきがけ)」の基本的な意味は、「どこかへ行く途中」または「行くついで」です。 ある目的地へ向かっている、その道中や過程を指す言葉です。
例えば、「会社へ行く」という本来の目的がある中で、その途中でコンビニに寄る場合、その「コンビニに寄る」という行為が「行き掛け」に行われたことになります。
この言葉は、単に移動の途中であることを示すだけでなく、「本来の目的のついでに何かをする」というニュアンスも含まれています。 そのため、「〜のついでに」という言葉と非常によく似た意味合いで使われます。 この「ついで」という感覚が、「行き掛け」という言葉を理解する上で大切なポイントになります。
日常会話での「行き掛け」の例文
「行き掛け」は、日常のさまざまな場面で気軽に使うことができます。具体的な例文をいくつか見てみましょう。
・「学校の行き掛けに、この手紙をポストに入れといてくれる?」
これは、通学のついでに手紙の投函を頼んでいる場面です。
・「出張の行き掛けに、駅前のカフェで少し時間をつぶそう。」
出張先へ向かう途中で、カフェに立ち寄ることを提案しています。
・「スーパーへの行き掛けに、クリーニング屋さんに寄るのを忘れないようにしないと。」
買い物に行くというメインの目的の途中で、別の用事を済ませようとしています。
・「ごめん、ちょっと遅れる!会社の行き掛けに忘れ物に気づいて、家に戻ってるんだ。」
出勤途中で起きたアクシデントを説明しています。
このように、「(目的地)への行き掛けに、(別の用事)をする」という形で使われるのが一般的です。とても便利で、日常の細かな行動を的確に表現できる言葉ですね。
「行き掛け」を使う際の注意点
「行き掛け」は非常に便利な言葉ですが、使う際には少しだけ注意しておくと、よりスムーズなコミュニケーションにつながります。
まず、前述の通り、この言葉は主に関西圏をはじめとする西日本でよく使われる表現です。 そのため、関東など他の地域の人と話すときには、相手に意味が通じにくい可能性があります。意味を推測してくれる人がほとんどだとは思いますが、もし相手が少し戸惑ったような表情を見せたら、「行く途中で、ってことなんだけど」のように、分かりやすい言葉で補足してあげると親切です。
また、ビジネスシーンやフォーマルな場面では、相手によっては少しくだけた印象を与えてしまう可能性もゼロではありません。特に、かしこまった文書やメールなどでは、「〜の途中で」や「〜の道すがら」といった、より硬い表現を選ぶ方が無難な場合もあります。
とはいえ、日常会話においては全く問題なく使える言葉です。相手や状況を少しだけ意識することで、この便利な言葉をさらに効果的に活用できるでしょう。
「行き掛け」と似た言葉との違いを解説
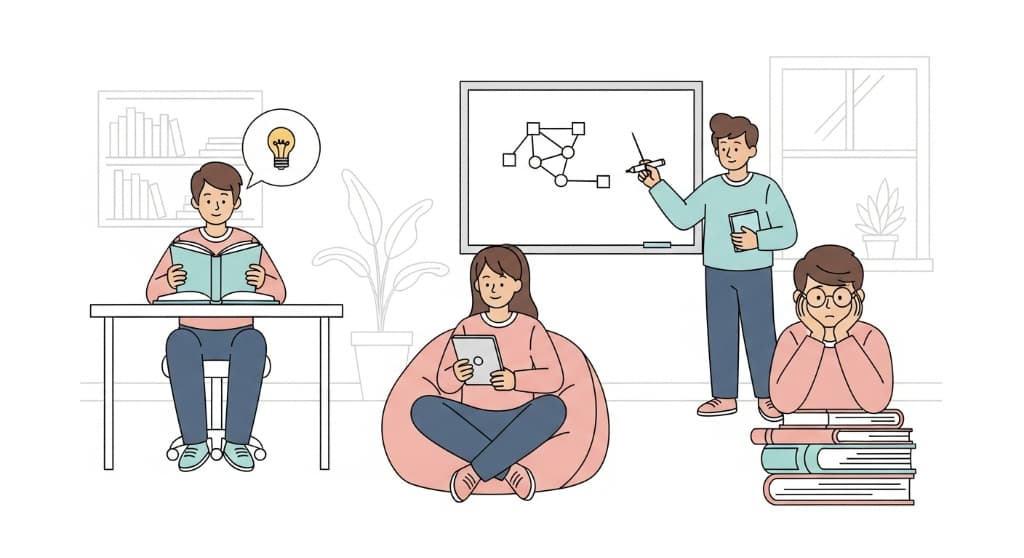
「行き掛け」には、「行きしな」や「道すがら」といった似た意味を持つ言葉がいくつかあります。また、「〜のついでに」という表現も非常によく似ています。これらの言葉は、それぞれ微妙にニュアンスや使われる場面が異なります。ここでは、それらの言葉と「行き掛け」との違いを詳しく解説し、言葉の使い分けができるように整理していきましょう。
「行きしな」との意味・ニュアンスの違い
「行きしな(いきしな)」は、「行き掛け」とほとんど同じ意味で使われる言葉で、「行く途中」「行くついで」を指します。 こちらも主に関西地方でよく使われる方言です。
意味合いとしてはほぼ同じですが、人によってはニュアンスの感じ方が少し異なる場合があります。「行き掛け」の方がやや広い時間帯や範囲を指すのに対し、「行きしな」は「まさに行くその時」「出がけ」といった、より出発に近いタイミングを指す感覚で使う人もいます。
例えば、「寝しな(ねしな)」という言葉が「寝る間際」を指すように、「しな」には「〜する間際、〜するとすぐ」といったニュアンスがあります。
しかし、これはあくまで感覚的な違いであり、多くの場合は同義語として、話者の好みや言いやすさで使い分けられています。「行き掛けに寄る」も「行きしなに寄る」も、日常会話ではほぼ同じ状況で使って問題ありません。
「道すがら」との使い分け
「道すがら(みちすがら)」も、「行き掛け」と同様に「目的地へ行く途中」を意味する言葉です。 しかし、「行き掛け」が日常会話で頻繁に使われる話し言葉であるのに対し、「道すがら」は少し古風で、文学的な響きを持つ言葉です。
日常会話で「道すがら、コンビニに寄って…」と言うと、少しだけ丁寧で、改まった印象を与えるかもしれません。そのため、手紙や文章、あるいは少し落ち着いた雰囲気で話したい時などに適しています。
例えば、旅の思い出を語る際に「京都へ向かう道すがら、美しい琵琶湖の景色を眺めた」のように使うと、情景が目に浮かぶような趣のある表現になります。
使い分けのポイントとしては、普段の友人との会話などカジュアルな場面では「行き掛け」、少し丁寧な表現をしたい時や文章で書き記す際には「道すがら」を選ぶと、より表現の幅が広がるでしょう。
「~のついでに」との関係性
「〜のついでに」は、「行き掛け」の基本的な意味を最も分かりやすく説明できる標準語の表現です。「行き掛けの駄賃」ということわざがあるように、「行き掛け」には元々「何かのついで」というニュアンスが強く含まれています。
このことわざは、馬を使って荷物を運ぶ人が、荷物を取りに行く「ついで」に別の荷物を運んで手間賃(駄賃)を得たことに由来します。 このことからも、「行き掛け」と「ついで」が密接な関係にあることが分かります。
「行き掛け」が方言であるため通じるか不安な場面や、より正確に意図を伝えたい場合には、「〜へ行くついでに」と言い換えるのが最も確実です。例えば、「会社の行き掛けに」を「会社へ行くついでに」と言い換えれば、どの地域の人にも誤解なく意味が伝わります。
意味的にはほぼ同じですが、「行き掛け」の方が言葉として短く、リズムが良いため、特に会話の中では使いやすい表現と言えるでしょう。
「行き掛け」の語源と由来を探る

普段何気なく使っている「行き掛け」という言葉ですが、その成り立ちや歴史をたどると、日本語の面白さが見えてきます。言葉がどのように生まれ、なぜ特定の地域で使われるようになったのか。ここでは、「行き掛け」という言葉の語源や由来について、少し深く掘り下げてみましょう。
言葉の成り立ちから見る「行き掛け」
「行き掛け」という言葉は、その漢字からも分かるように、「行く」という動詞と、「掛ける」という動詞から成り立っています。
具体的には、動詞「行く」の連用形である「行き」に、もう一つの動詞「掛ける」が付いて名詞化した形です。「掛ける」にはたくさんの意味がありますが、この場合は「動作を始める」「動作の途中である」という意味合いで使われています。
例えば、「話しかける」は話すという行為を始めること、「食べかける」は食べるという行為の途中であることを示します。これと同じように、「行き掛け」は「行く」という行為の途中、つまり「行く途中」という意味になるわけです。
このように言葉のパーツを分解してみると、その構造は非常にシンプルで分かりやすいですね。日本語の柔軟な造語能力がうかがえる一例と言えるでしょう。
なぜ特定の地域で使われるようになったのか
「行き掛け」が特に関西地方を中心に使われるようになった背景には、「方言周圏論(ほうげんしゅうけんろん)」という考え方が関係している可能性があります。
方言周圏論とは、かつて文化の中心地(日本では京都など)で生まれた新しい言葉が、波紋のように周辺地域へ広がっていき、中心地ではその言葉が廃れて新しい言葉に変わっても、周辺地域には古い言葉が残りやすい、という考え方です。
つまり、「行き掛け」という言葉も、昔は都であった京都やその周辺で広く使われていたものが、時代と共に全国へ、特に西日本方面へと伝わっていったと考えられます。そして、文化の中心であった近畿地方ではその言葉が残り続け、一方で中心から遠い関東などでは別の言葉(例:「行きがけ」)が主流になった、という可能性が指摘されています。
近畿地方の言葉は、古い日本語の形を比較的多く残していると言われています。 「行き掛け」も、そうした歴史の中で育まれ、地域に根付いてきた言葉の一つなのかもしれません。
文献や資料に見る「行き掛け」の歴史
「行き掛け」という言葉が、いつ頃から使われるようになったのかを正確に特定するのは難しいですが、関連する表現は古くから存在します。
例えば、「行き掛けの駄賃」ということわざは、江戸時代にはすでに使われていたと考えられています。 このことわざは、馬で荷物を運ぶ「馬子(まご)」が、荷物を取りに行く途中で別の荷物を運んで駄賃(手間賃)を得た様子から来ています。 このことからも、「行き掛け」という言葉や概念が、少なくとも江戸時代には庶民の生活の中にあったことがうかがえます。
また、「行き掛かり」という言葉も古くからあり、「物事がすでに進行している状態」や「行く途中」といった意味で使われてきました。
これらのことから、「行き掛け」は、日本の歴史の中で人々が移動し、その「ついで」に何かをするといった生活の知恵から生まれ、特に商業や文化の中心地であった関西圏で色濃く残り、現代に受け継がれてきた言葉であると推測できます。
「帰り掛け」という言葉もある?対義語を調査

「行き掛け」という言葉があると、「それなら反対の言葉もあるの?」と気になるのは自然なことですよね。目的地へ向かう途中があるなら、そこから帰る途中もあるはずです。ここでは、「行き掛け」の対義語として考えられる「帰り掛け」という言葉について、その意味や使われ方を詳しく見ていきましょう。
「帰り掛け」の意味と使われる地域
はい、「行き掛け」の対義語として「帰り掛け(かえりがけ)」という言葉が存在します。 意味はご想像の通り、「帰る途中」や「帰り道」のことです。
「行き掛け」が目的地へ向かう道中を指すのに対し、「帰り掛け」は目的地から出発点(家など)へ戻る道中を指します。
使われる地域も「行き掛け」とほぼ同じで、主に関西地方をはじめとする西日本で広く用いられています。 関西出身の人にとっては、「行き掛け」と「帰り掛け」はセットで覚えているごく自然な言葉です。関東など他の地域では、「帰りがけ」や「帰る途中」という言い方が一般的ですが、「帰り掛け」と言われても意味は十分に伝わるでしょう。辞書にも「帰る途中。帰り道。」として掲載されており、標準語として認められています。
「行き掛け」と「帰り掛け」のセットでの使われ方
「行き掛け」と「帰り掛け」は、日常会話の中でセットで使われることがよくあります。往路と復路での行動を対比させたり、計画を立てたりする際に非常に便利です。いくつか例文を見てみましょう。
・「行き掛けに本を借りて、帰り掛けに返却しよう。」
図書館などでの行動計画を立てています。行きと帰りの両方で用事がある場合に便利な表現です。
・「行き掛けは元気だったのに、帰り掛けにはすっかり疲れてしまった。」
外出の往路と復路での体調の変化を述べています。対比することで状況が分かりやすくなります。
・「A:このお土産、いつ渡そうかな? B:行き掛けに渡すと荷物になるから、帰り掛けでいいんじゃない?」
相手の負担を考えて、渡すタイミングを相談している場面です。
このように、二つの言葉を使い分けることで、行動の順序やタイミングを明確に伝えることができます。特に口頭でのコミュニケーションにおいて、簡潔で分かりやすい表現として重宝されています。
その他の「~掛け」で終わる方言
「行き掛け」や「帰り掛け」のように、動詞の連用形に「掛け」が付く表現は他にもあります。その中には、標準語として広く使われているものもあれば、方言として特定の地域で使われるものもあります。
・「言い掛け(いいかけ)」:何かを言い始めた途中の状態。「言い掛けた言葉を飲み込む」のように使います。これは標準語として一般的です。
・「読み掛け(よみかけ)」:本などを読んでいる途中の状態。「読み掛けの本が何冊もある」のように使います。これも標準語です。
・「死に掛け(しにかけ)」:死にそうになっている状態。これも全国的に通じる表現です。
・「行きかけといて」:これは近畿地方、特に関西弁で使われる表現で、「先に行き始めておいて」という意味の依頼・命令形です。 標準語の「〜しかける」とは少し用法が異なり、方言的な特徴が表れています。
このように、「~掛け」という形は、動作の途中や始まりを表す便利な表現として、標準語や方言の中でさまざまに活用されています。何気なく使っている言葉にも、共通のルールや地域ごとの特色が隠れているのが分かりますね。
まとめ:「行き掛け」という方言の奥深さを知る

この記事では、「行き掛け」というキーワードを軸に、その意味や使い方、方言としての側面、そして関連する言葉について詳しく解説してきました。
「行き掛け」は、「行く途中」や「行くついで」を意味する言葉で、辞書にも載っている標準語ですが、主に関西を中心とした西日本で日常的に使われています。 そのため、他の地域の人にとっては方言のように聞こえることがあります。
「行き掛け」には「帰り掛け」という対義語があり、セットで使うことで行動を明確に表現できます。 また、「行きしな」という非常によく似た方言や、「道すがら」という少し古風な類義語も存在し、場面によって使い分けることで表現の幅が広がります。
言葉の成り立ちは「行く」+「掛ける」というシンプルな構造であり、その背景には、都の言葉が周辺に広まった「方言周圏論」のような歴史的な経緯も考えられます。
何気なく使っている「行き掛け」という一つの言葉から、日本語の地域性や歴史、そして言葉の持つ面白さや奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。


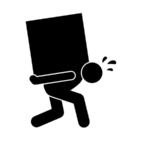

コメント