「友達をからかう」「猫にちょっかいを出す」など、日常的によく使う「からかう」という言葉。実は、日本全国を見渡してみると、この「からかう」という言葉にはたくさんのユニークな方言があることをご存じでしたか?もしかしたら、あなたが普段何気なく使っている言葉も、実は特定の地域の方言かもしれません。
この記事では、「からかう」を意味する様々な方言を、北海道から沖縄まで地域ごとに詳しくご紹介します。それぞれの言葉が持つ独特のニュアンスや語源、さらには使い方まで、やさしくわかりやすく解説していきます。あなたの出身地ではどんな言葉が使われているのか、ぜひ探してみてください。この記事を読めば、方言の奥深さや日本語の豊かさに、きっと新たな発見があるはずです。
「からかう」の面白い方言、全国にこんなにたくさん!

標準語の「からかう」は、相手を困らせたり、冗談を言ったりして面白がる行為を指しますが、地域によっては全く異なる響きやニュアンスの言葉で表現されます。ここでは、全国各地で使われている「からかう」を意味する方言を、地方ごとに見ていきましょう。
北海道・東北地方の「からかう」方言
北国では、寒さだけでなく言葉にも独特の味わいがあります。
・ 北海道:「ちょす」
「触る」「いじる」といった意味合いが強く、そこから転じて「からかう」「ちょっかいを出す」という意味で使われます。 例えば、「人のものちょすな!」(人のものに触るな!)のように注意する場面や、「猫をちょす」(猫をかまう)のように愛情を込めて使う場面もあります。
・ 青森県:「からがる」「すずがる」
標準語の「からかう」に近い音の「からがる」が使われます。
・ 岩手県:「ひずる」
「ひやかす」や「いじる」に近いニュアンスで使われる言葉です。
・ 宮城県:「しずる」
「しずる」は、子どもをあやすようにからかったり、親しい間柄で愛情を込めてちょっかいを出したりする際に使われることが多い言葉です。 悪意のない、温かいニュアンスが含まれています。
・ 秋田県:「ちょす」
北海道と同様に「ちょす」が使われます。
・ 山形県:「おひゃらがす」
「冷やかす」が変化した言葉と考えられ、冗談を言って相手の反応を楽しむような場面で使われます。
・ 福島県:「かまう」「ちょっけ」
「かまう」は、相手に関心があってちょっかいを出すような、好意的なニュアンスで使われることがあります。「ちょっけ」は「ちょっかい」が変化した言葉です。
関東・甲信越地方の「からかう」方言
首都圏を含む関東地方では、標準語の「からかう」が広く使われていますが、地域によっては特有の表現も残っています。
・ 茨城県:「おひゃらがす」
山形県と同様に、「冷やかす」から転じた言葉が使われています。
・ 栃木県:「かまう」
福島県と同じく、「かまう」が「からかう」の意味で使われることがあります。
・ 千葉県:「ちょがす」
「ちょっかいを出す」が訛ったような響きで、親しい友人同士のふざけ合いなどで使われることが多いです。
・ 新潟県:「からこー」「おちょくる」「かんまう」
「からかう」が変化した「からこー」や、全国的にも聞かれる「おちょくる」が使われます。「かんまう」は「かまう」が変化した言葉です。
・ 山梨県:「ちょーす」「かまう」
山梨県では「からかう」という言葉が、標準語とは全く違う意味で使われることで知られています。人に対してではなく、機械などを「修理する」「工夫して手直しする」という意味で使われるのです。 そのため、人をからかう意味では「ちょーす」や「かまう」といった言葉が使われます。
・ 長野県:「おしゃらかす」「かまう」
「おしゃらかす」は「お洒落」から来ているという説もあり、言葉巧みに相手をからかうような、少し洗練されたニュアンスを含むことがあります。
東海・北陸地方の「からかう」方言
日本の真ん中に位置するこの地域では、東西の言葉が混じり合ったような多様な表現が見られます。
・ 富山県:「ちょろがす」
相手をうまくだましたり、はぐらかしたりするような、少しずる賢いニュアンスを含むことがあります。また、富山では「ひやかす」が「水に浸す」という意味で使われることもあります。
・ 石川県:「あをだがす」
相手を小馬鹿にするような、少し意地悪なニュアンスで使われることがある言葉です。
・ 福井県:「なぶる」
標準語の「なぶる」は、しつこくいじめたり、もてあそんだりするといった強い意味合いがありますが、福井弁ではもう少し軽い「からかう」程度の意味で使われることもあります。
・ 岐阜県:「あらそう」「ちょーらかす」
「ちょーらかす」は静岡県や愛知県でも使われる言葉で、リズミカルな響きが特徴です。
・ 静岡県:「ちょーらかす」「おちゃらかす」
「おちゃらかす」は「お茶を濁す」のようにはぐらかすニュアンスも含まれる、ユーモラスな響きの言葉です。
・ 愛知県:「ちょーらかす」「およくる」
「ちょーらかす」は東海地方で広く使われている言葉です。「およくる」は「おちょくる」に近い意味で使われます。
関西(近畿)地方の「からかう」方言
お笑いの本場、関西ではコミュニケーションを円滑にするためのユーモアあふれる表現が豊富です。
・ 三重県:「なぶる」「おちょくる」
福井県と同様に「なぶる」が使われますが、関西圏では「おちょくる」も一般的です。
・ 京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県:「おちょくる」
「おちょくる」は関西を代表する「からかう」の表現と言えるでしょう。愛情表現の一つとして使われることも多く、相手との距離を縮めるためのコミュニケーションツールにもなっています。兵庫では「べろばかす」というユニークな表現もあります。
・ 滋賀県、奈良県:「からかう」
京都や大阪に隣接しながらも、標準語と同じ「からかう」が使われることが多い地域です。
中国・四国地方の「からかう」方言
西日本の中でも、中国・四国地方には独特の響きを持つ言葉が残っています。
・ 鳥取県:「あえる」「ひょーとくる」
「ひょーとくる」は、ひょいとちょっかいを出すような、軽やかなイメージの言葉です。
・ 島根県:「あじゃる」
ふざけたり、おどけたりするという意味合いも含まれる言葉です。
・ 岡山県:「いらまかす」「おちょくる」「えどかす」
「いらまかす」は、相手を困らせて楽しむような、少し強めのからかいを表すことがあります。
・ 広島県:「かもう」「ちょーやがす」
「かもう」は「かまう」が変化した言葉です。「ちょーやがす」は、相手を笑いものにするようなニュアンスで使われることがあります。
・ 山口県:「わやく」「かもう」
「わやく」は、むちゃくちゃにする、台無しにするといった意味もあり、度が過ぎたからかいを表す際に使われることがあります。「かもう」は広島と同様です。
・ 徳島県:「いろべる」「おちょくる」
「いらう」や「いじる」に近い言葉で、手を出してからかうような意味合いがあります。
・ 香川県、愛媛県:「てがう」
手でちょっかいを出す様子から来た言葉と考えられ、子ども同士のじゃれ合いなどでよく使われます。
・ 高知県:「てがう」「ぞぶる」
愛媛などと同様に「てがう」が使われるほか、「ぞぶる」という言葉もあります。これは、相手を翻弄するようなからかい方を指すことがあります。
九州・沖縄地方の「からかう」方言
南国らしい、どこかおおらかな響きを持つ言葉や、力強い表現が九州・沖縄地方の特徴です。
・ 福岡県:「おちょくる」「ちょーくらかす」
関西で使われる「おちょくる」に加え、「ちょーくらかす」という表現があります。これは、しつこくからかうようなニュアンスを含むことがあります。
・ 佐賀県:「きゃーなずっ」
非常にユニークな響きの言葉で、相手をじらすようにしてからかう場面などで使われることがあります。
・ 長崎県:「せびらかす」「ちょくらかす」
「せびらかす」は、しつこくねだったり、困らせたりするという意味合いが強い言葉です。「ちょくらかす」は福岡の「ちょーくらかす」と似ています。
・ 熊本県:「せびらかす」「ぞうくる」
長崎と同様に「せびらかす」が使われます。「ぞうくる」は、相手をだまして楽しむような、いたずらっぽいからかいを指します。
・ 大分県:「せがう」「おちょくる」
「せがう」は、しつこく求める、ねだるという意味もあり、からかいながら何かをさせようとするような場面で使われます。
・ 宮崎県:「もどかす」
相手をじれったくさせる、もどかしい気持ちにさせて楽しむ、といったニュアンスの言葉です。
・ 鹿児島県:「ちょくい」「ちょくらかす」「ひょくらかす」
「ちょっかい」に近い「ちょくい」や、他の九州地方でも見られる「ちょくらかす」などが使われます。「ひょくらかす」は、おどけてみせたり、ひょうきんな態度でからかったりすることを指します。
・ 沖縄県:「わちゃく」
沖縄の方言(ウチナーグチ)で「いたずら」や「ふざけること」を意味し、そこから「からかう」という意味でも使われます。
なぜこんなに違う?「からかう」方言の語源と由来

「からかう」という一つの行為を表すのに、なぜこれほどまでに多様な言葉が生まれたのでしょうか。その背景には、古語の名残や、動作・様子からの変化、そして各地域の文化が深く関わっています。
古語が由来となっている方言
現代では使われなくなった古い言葉が、方言として今も生き続けている例は少なくありません。「からかう」の語源も古語に遡ることができます。古語の「からかふ」は、「負けまいと張り合う、争う」といった意味を持っていました。 これは「絡む(からむ)」という言葉に、行動を表す「かふ」が合わさったもので、言い争う様子を示していたようです。
この「争う」という意味合いが時代と共に薄れ、現在の「揶揄(やゆ)する」といった意味に変化したと考えられています。 また、福井県や三重県で使われる「なぶる」も、もともとは「いじりまわす、もてあそぶ」という意味の古語です。これが方言として残り、地域によっては軽い「からかい」を指す言葉として定着しました。
動作や様子から生まれた方言
言葉の意味は、具体的な動作や様子から生まれることもよくあります。「からかう」という行為も、様々な動作で表現されます。
・ 「ちょっかいを出す」系
「ちょっかい」とは、元々猫が前足で物をかき寄せるしぐさを指す言葉です。 この、ちょっと手出しをする様子から「余計な干渉をする」「異性に戯れかかる」といった意味に転じました。 北海道や東北で使われる「ちょす」、千葉の「ちょがす」、鹿児島の「ちょくい」 などは、この「ちょっかい」がルーツになっていると考えられます。
・ 「いじる」「触る」系
手で触ったり、あれこれと操作したりする「いじる」という行為も、「からかう」に繋がります。 関西地方の「いらう」 や四国の「てがう」 などは、手で触れてちょっかいを出す動作から生まれた方言です。「いじる」という言葉自体、今では「人をからかって楽しむ」という意味でも全国的に使われていますね。
・ 「ひやかす」系
「ひやかす」という言葉は、もともと「冷たくする」という意味です。 これがなぜ「からかう」という意味になったかについては、江戸時代に吉原の遊郭を見物するだけの客を「ひやかし客」と呼んだことに由来するという説があります。 彼らが紙漉き職人で、原料を水で冷やす(ひやかす)間に見物に来ていたからだと言われています。 このように、買う気がないのに店をのぞく行為から「からかう」という意味が生まれ、山形の「おひゃらがす」 などの方言に繋がっていったと考えられます。
地域独自の文化や歴史が反映された方言
言葉は、その土地に住む人々の気質やコミュニケーションのあり方を映し出す鏡でもあります。
例えば、関西地方で多用される「おちょくる」 や「ちょける」 は、単に相手を困らせるだけでなく、場の空気を和ませたり、笑いを生み出したりするための重要なコミュニケーションツールとして機能しています。これは、会話のテンポやユーモアを大切にする関西の文化が色濃く反映された結果と言えるでしょう。
また、山梨県の「からかう」が「修理する、手を尽くす」という意味で使われるのも興味深い例です。 これは、限られた資源を工夫して最大限に活用してきた、地域の歴史や生活の知恵が言葉に込められていると推測できます。 物を大切にし、手間ひまをかけて扱うことを「からかう」と表現するようになったのかもしれません。このように、方言一つひとつに、その土地ならではの文化や歴史の物語が隠されているのです。
使い方に注意!「からかう」方言のニュアンスの違い

「からかう」を意味する方言は全国にたくさんありますが、その言葉が持つニュアンスは地域や言葉によって様々です。同じ「からかう」でも、親しみを込めたものから、少し意地悪な響きを持つものまで幅広いため、使い方には少し注意が必要です。
親しみを込めた軽い「からかい」を表す方言
多くの「からかう」方言は、親しい間柄でのコミュニケーションを円滑にするための、ポジティブな意味合いで使われます。
代表的なのが、関西でよく聞かれる「おちょくる」や「いじる」です。これらは、相手への好意や親しみが根底にある場合がほとんどです。会話を盛り上げたり、相手の面白い一面を引き出したりするために使われる、愛情表現の一種と捉えることもできるでしょう。宮城の「しずる」 も、悪意のない、微笑ましい「からかい」に使われることが多い言葉です。
また、北海道や東北の「ちょす」 も、動物をかわいがって触ったり、子どもにちょっかいを出したりするような、温かい文脈で使われることがよくあります。 このような方言は、人間関係をより親密にする潤滑油のような役割を果たしていると言えます。ただし、いくら親しい間柄でも、相手が嫌がっている場合はもちろん控えるべきなのは言うまでもありません。
少し意地悪なニュアンスを含む「からかい」の方言
一方で、中には相手を小馬鹿にしたり、意地悪く扱ったりするような、少しネガティブなニュアンスを含む方言も存在します。
例えば、福井や三重で使われる「なぶる」 は、標準語では「もてあそぶ」「しつこくいじめる」といった強い意味を持つため、軽い冗談のつもりで使っても、相手に不快感を与えてしまう可能性があります。地域によっては軽い意味で使われることもありますが、言葉の持つ元々の強さを考えると、使う相手や状況を慎重に選んだ方が良いでしょう。
同様に、長崎や熊本の「せびらかす」 は、相手を困らせて楽しむという意味合いが強く、しつこさや執拗さを感じさせる場合があります。岡山の「いらまかす」 や石川の「あをだがす」 も、相手を見下したようなからかい方と受け取られる可能性があるため、注意が必要です。これらの言葉は、友人同士のじゃれ合いの中でも、力関係が対等でないと、いじめと捉えられかねない危険性をはらんでいます。
使う相手や場面を選ぶ方言
方言は、その土地で生まれ育った人々にとってはごく自然な言葉ですが、他の地域の人にとっては耳慣れない言葉です。特に、「からかう」のように人間関係に関わる言葉は、意図が正しく伝わらない可能性があります。
代表的な例が、山梨の「からかう」です。 前述の通り、これは「修理する」「手を尽くす」という意味ですが、県外の人に「この自転車、からかってあげるよ」と言うと、「馬鹿にしているのか?」と誤解されてしまうかもしれません。 逆に、「ひやかす」は標準語では「からかう」の意味ですが、茨城や富山などでは「水に浸す」という意味で使われるため、会話が噛み合わなくなることも考えられます。
このように、同じ言葉でも地域によって意味が全く異なる場合があることを知っておくのは大切なことです。方言を使う際は、相手がその言葉を知っているか、どのようなニュアンスで伝わるかを少し考えることで、無用な誤解を避け、より豊かなコミュニケーションを楽しむことができるでしょう。
あなたの言葉は標準語?それとも「からかう」方言?
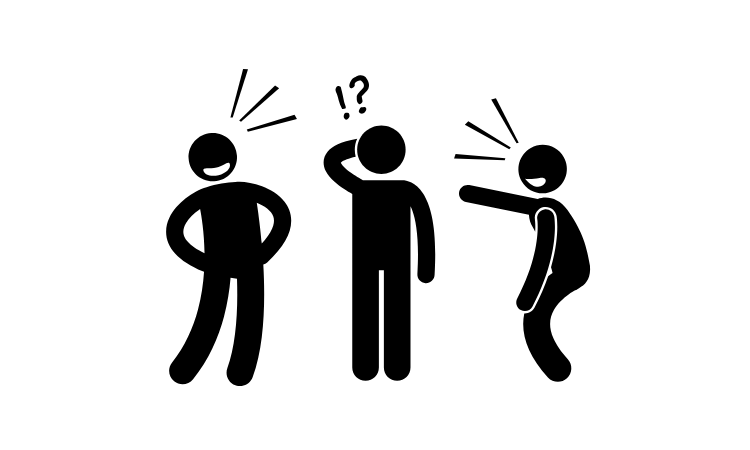
普段、私たちが何気なく使っている言葉の中には、「これは全国共通の標準語だろう」と思っていても、実は特定地域の出身者によく使われる方言や、方言に由来する言葉が隠れていることがあります。あなたの「からかう」は、本当に標準語でしょうか?
方言だと気づかずに使っている言葉たち
「からかう」に関連する言葉で、方言だと気づかれにくい代表格が「いじる」です。今では「趣味で盆栽をいじる」「人をいじるのが上手い」のように全国で使われ、テレビ番組などでも頻繁に耳にする言葉です。 しかし、「人をからかう」という意味での「いじる」は、もともと関西地方でよく使われていた表現で、それがメディアを通じて全国に広まったとされています。 そのため、特に関西出身の人は、これが方言由来のニュアンスを持つとは意識せずに使っていることが多いでしょう。
また、「ちょっかいを出す」という表現も、語源は猫の動作にあるとされ、慣用句として広く定着していますが、 その短縮形である「ちょす」 などは、北海道や東北地方以外の人には通じにくい方言です。
さらに、標準語の「ひやかす」とは別に、茨城や栃木、福島、山梨、富山など広い地域で「水に浸す」という意味で「ひやかす」という言葉が使われています。 この意味で使っている人は、食器を水につけておくことを「ひやかしといて」と言った際に、相手がきょとんとした顔をして初めて方言だと気づく、という経験があるかもしれません。
方言かどうかを調べる方法
自分の使っている言葉が方言かどうか気になった時、どうすれば調べられるのでしょうか。いくつかの簡単な方法があります。
・ 辞書や方言辞典で調べる
最も確実なのは、国語辞典や方言専門の辞典を引いてみることです。最近では、オンラインの辞書サービスも充実しており、手軽に調べることができます。言葉の横に「方言」や「俗語」といった注釈があれば、それが標準語ではないことがわかります。
・ インターネットで検索する
「(調べたい言葉) 方言」などのキーワードで検索してみるのも有効な方法です。多くの地域の方言を紹介するウェブサイトや、個人のブログなどで、その言葉がどの地域で使われているか、どのような意味を持つかの情報を見つけることができます。 Jタウンネットのような、地域情報を専門に扱うサイトで取り上げられていることもあります。
・ 周囲の人に聞いてみる
一番手軽で面白いのが、違う地域の出身の友人や同僚に「この言葉、使う?」と直接聞いてみることです。自分にとっては当たり前の言葉が相手には全く通じなかったり、逆に相手の言葉に驚いたりと、コミュニケーションを通じて方言の面白さを実感できるはずです。
方言の魅力を再発見しよう
方言は、決して「なまり」や「間違った言葉」ではありません。その土地の気候、風土、歴史、そして人々の暮らしの中で育まれてきた、かけがえのない文化です。方言を知ることは、その地域の文化や人々の気質をより深く理解することに繋がります。
普段使っている言葉を少し見直してみることで、「これはうちの地元だけの言い方だったんだ」という新しい発見があるかもしれません。それは、自分自身のルーツを再確認するきっかけにもなります。方言が持つ温かみや独特のリズムを大切にしながら、他の地域の言葉にも耳を傾けてみると、日本語の世界がより一層豊かで面白いものであることに気づくでしょう。
まとめ:「からかう」という言葉に見る方言の豊かさ

この記事では、「からかう」というキーワードを軸に、日本全国の様々な方言とその背景について掘り下げてきました。
北海道の「ちょす」 から沖縄の「わちゃく」 まで、地域ごとに実に多様な表現があることがお分かりいただけたかと思います。同じ「からかう」という行為でも、関西の「おちょくる」 のように親しみを込めたもの、福井の「なぶる」 のように少し強いニュアンスを持つもの、そして山梨の「からかう」 のように「修理する」という全く異なる意味を持つものまで、言葉一つひとつに個性的な響きとニュアンスが宿っています。
こうした方言の多様性は、古語の名残や、動作・様子からの連想、そして各地域の歴史や文化が複雑に絡み合って生まれました。方言は、単なる言葉の違いではなく、その土地の人々の暮らしやコミュニケーションのあり方を映し出す貴重な文化遺産なのです。
自分の使っている言葉が方言かどうかを調べてみたり、違う地域の人と方言について話してみたりすることで、日本語の奥深さや、普段意識することのない自分の地域の文化を再発見できるかもしれません。「からかう」という日常的な言葉を通して、方言の持つ温かさと豊かさに触れるきっかけとなれば幸いです。

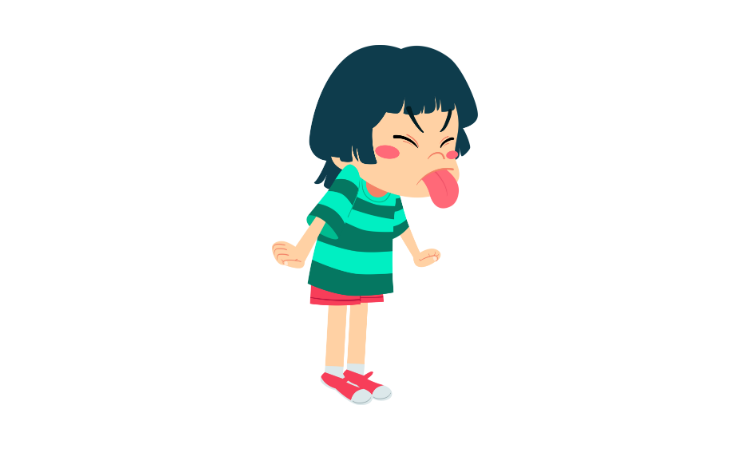

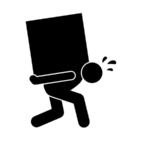
コメント