NHKの連続テレビ小説「べっぴんさん」をご覧になったことはありますか?ヒロインのすみれたちが話す、どこか優しくて温かみのある言葉遣いが印象的だった方も多いのではないでしょうか。このドラマで主に使われていたのが、物語の舞台である神戸の「神戸弁」です。
この記事では、「べっぴんさん」の方言に興味を持った方のために、神戸弁の特徴や魅力、そしてドラマで登場した具体的なセリフなどを詳しく、そして分かりやすく解説していきます。大阪弁との違いや、「べっぴんさん」という言葉そのものの意味にも触れていきますので、この記事を読めば、ドラマの世界をより一層深く楽しめるようになるはずです。一緒に「べっぴんさん」の方言の魅力に触れていきましょう。
「べっぴんさん」という言葉とドラマの基本情報

ドラマのタイトルにもなっている「べっぴんさん」という言葉。日常で耳にすることはあっても、その正確な意味や由来までご存じの方は少ないかもしれません。ここでは、まず「べっぴんさん」という言葉の基礎知識と、ドラマの概要について見ていきましょう。
そもそも「べっぴんさん」ってどういう意味?
「べっぴんさん」とは、主に西日本で使われる言葉で、「とても美しい女性」や「美人」を意味する褒め言葉です。 見た目の美しさを称賛する際に使われますが、単に容姿が整っているだけでなく、明るく気立ての良い、親しみやすい雰囲気の女性に対して使われることが多いようです。
その語源にはいくつかの説がありますが、有力なのは「別品(べっぴん)」という言葉から来ているという説です。 江戸時代、「普通の品物とは違う、特別に良い品物」を指して「別品」と呼んでいました。 これが転じて、物だけでなく優れた人物、特に容姿の美しい女性を指すようになり、「別嬪(べっぺん)」という字が当てられるようになったと言われています。 「嬪」という漢字は、古くは宮廷に仕える高貴な女性を意味する言葉でした。 つまり、「別嬪さん」とは、「別格に美しい、高貴な女性」といったニュアンスを持つ、大変格調高い褒め言葉だったのです。
朝ドラ「べっぴんさん」のあらすじと舞台
NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」は、2016年10月から2017年4月にかけて放送されました。 物語の舞台は、昭和初期から戦後の高度経済成長期にかけての兵庫県神戸市です。
ヒロインの坂東すみれは、神戸の裕福な家庭に生まれ、手芸や刺繍が大好きなお嬢様として育ちます。 しかし、戦争で夫は出征し、家も財産も失ってしまうという過酷な運命に見舞われます。 戦後の混乱の中、すみれは娘のために作った手作りの子供服をきっかけに、商売の道を志すことを決意します。女学校時代の友人たちと共に、幾多の困難を乗り越えながら子供服の会社「キアリス」を立ち上げ、日本の子供たちのために奮闘していく姿を描いた物語です。
戦後の焼け跡から、ひたむきな思いと確かな技術で夢を形にしていくヒロインたちの姿は、多くの視聴者に感動と勇気を与えました。
物語のモデルとなった人物と企業
「べっぴんさん」の物語は、実在の人物と企業がモデルになっています。ヒロイン・坂東すみれのモデルとなったのは、ベビー・子供服メーカー「ファミリア」の創業者の一人である坂野惇子(ばんの あつこ)さんです。
ファミリアは、惇子さんを含む4人の女性によって、1950年に神戸で創業されました。ドラマで描かれたように、自分たちの子どもに着せたいと思えるような、品質が良く、愛情のこもったベビー服や子供服を作りたいという思いが出発点でした。当時の日本では、まだ子供服の既製品は少なく、母親たちが手作りするのが一般的でした。そんな時代に、品質とデザインにこだわったファミ「リア」の製品は、多くの母親たちの支持を集め、やがて日本を代表する子供服ブランドへと成長していきます。
ドラマでは、ヒロインたちが仲間と力を合わせ、情熱を傾けて会社を大きくしていく過程が丁寧に描かれており、その姿はモデルとなった創業者たちの歩みと重なります。
ドラマ「べっぴんさん」で話される方言の正体
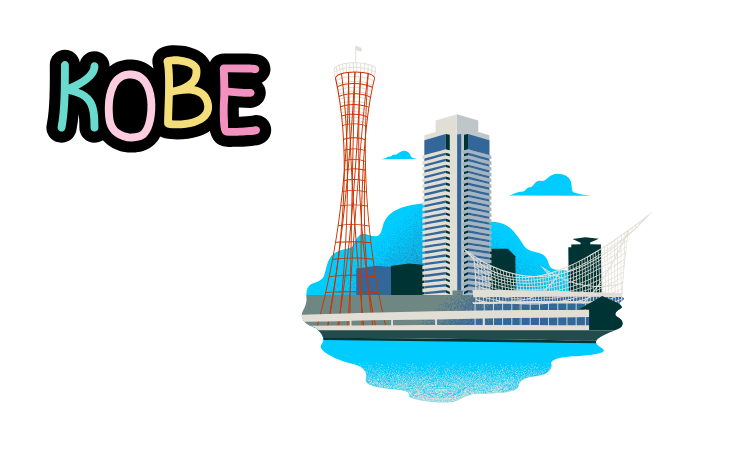
「べっぴんさん」のドラマ内で話される言葉は、標準語とは異なる独特の響きを持っています。この魅力的な言葉遣いの正体こそ、物語の舞台である神戸で話されている「神戸弁」です。ここでは、なぜ神戸弁が使われたのか、そしてその方言がドラマにどのような効果をもたらしたのかを探ります。
ドラマの主要な方言は「神戸弁」
「べっぴんさん」でヒロインたちが話す言葉は、主に関西地方の方言の一つである「神戸弁」です。 関西弁と一括りにされがちですが、大阪で話される大阪弁や、京都で話される京都弁とは、イントネーションや使われる単語に微妙な違いがあります。
神戸弁は、大阪弁などの影響を受けつつも、西に隣接する播州地方の方言(播州弁)の要素も混じり合っているのが特徴です。 特に、語尾に「~とう」や「~とん」が付く表現は、神戸弁を象徴するものとして知られています。 例えば、「何してるの?」は神戸弁で「何しとう?」や「何しとん?」となります。 この独特の語尾が、神戸弁ならではの柔らかく、どこかおっとりとした響きを生み出しているのです。
神戸弁が使われた背景とは?
ドラマの舞台が神戸であるため、登場人物たちが神戸弁を話すのはごく自然な設定です。物語のリアリティを高め、視聴者が神戸という土地の空気感をより身近に感じられるようにするために、方言は重要な役割を果たしました。
昭和初期から戦後にかけての神戸の街並みや文化を再現する上で、当時の人々が実際に使っていたであろう言葉遣いは欠かせない要素です。ヒロインのすみれたちが、上品でありながらも親しみやすい神戸弁を話すことで、彼女たちのキャラクターがより生き生きと、魅力的に描かれました。また、方言を通して、登場人物たちの出身地や育った環境、人間関係といった背景を表現する意図もあったと考えられます。
方言がドラマに与えた効果
「べっぴんさん」における神戸弁の使用は、ドラマ全体に温かく、優しい雰囲気をもたらしました。神戸弁の持つ、おっとりとして上品な響きは、ヒロイン・すみれの優しくも芯の強い人柄と見事にマッチしていました。
また、方言は登場人物たちの感情をより豊かに表現する効果もありました。喜びや悲しみ、戸惑いといった感情が、標準語ではなく神戸弁のセリフで語られることで、よりストレートに、そして人間味あふれる形で視聴者の心に届いたのではないでしょうか。
一方で、ドラマで使われる方言は、全国の視聴者に分かりやすく伝わるように、実際のネイティブな方言を少し調整している場合がほとんどです。 「べっぴんさん」でも、本来の神戸弁を知る地元の人からは「少し違う」といった声も聞かれましたが、これも多くの人に物語を楽しんでもらうための工夫と言えるでしょう。
「べっぴんさん」の魅力的な方言(神戸弁)セリフ集

ドラマ「べっぴんさん」を彩った神戸弁。ここでは、特に印象的だったり、神戸弁の特徴がよく表れていたりするセリフやフレーズをピックアップして、その意味や使い方を詳しく解説します。これらの表現を知ることで、登場人物たちの会話のニュアンスがより深く理解できるはずです。
「~しとう?」「~しとる」の意味と使い方
神戸弁を最も特徴づける表現の一つが、進行形や状態を表す「~しとう」「~しとる」(動詞によっては「~しよる」)です。 これは西日本の方言に広く見られる特徴で、標準語の「~している」にあたります。ドラマ内でも頻繁に使われ、神戸らしさを感じさせる重要な要素となっていました。
例えば、標準語で「(あなたは)知っていますか?」と尋ねる場合、神戸弁では「知っとう?」となります。 イントネーションを平坦にすると「(私は)知っている」という意味にもなり、文脈や抑揚で意味が変わるのが面白い点です。
また、大阪弁では同じ「~している」の意味で「~してる」や「~してんねん」が使われることが多く、この「とう」や「とる」の使用が、神戸弁と大阪弁を区別するポイントの一つになっています。 この柔らかな語尾が、会話全体の雰囲気を和らげる効果を持っています。
「なんどいや」「~やんか」などの特徴的な語尾
神戸弁には、「~とう」以外にも特徴的な語尾や言い回しが数多く存在します。これらが会話の随所に登場することで、より神戸らしい雰囲気が醸し出されていました。
「~やんか」や「~やん」は、「~じゃないか」という意味で、同意を求めたり、念を押したりする際に使われます。関西全域で広く使われる表現ですが、神戸弁でも頻繁に登場します。例えば、「昨日言うてたやんか」(昨日言っていたじゃないか)のように使います。
また、「~ねん」も断定や強調を表す語尾として使われます。 「今日は忙しいねん」は、「今日は忙しいのだ」という強い気持ちを表します。大阪弁のイメージが強いかもしれませんが、神戸でも日常的に使われる表現です。
さらに、少し強い言葉ですが「ダボ」という言葉もあります。これは「馬鹿」や「あほ」といった意味で、親しい間柄でのからかいや、軽い非難の際に使われることがあります。 ドラマの中では、登場人物たちの気取らないやり取りの中で、こうした言葉が効果的に使われていたかもしれません。
ヒロインたちが使った印象的な方言フレーズ
ドラマの中では、ヒロインたちの人柄がにじみ出るような、心に残る方言のフレーズがいくつもありました。
例えば、何かを捨てるときに使う「ほかす」という言葉。 「この布の切れ端、ほかしてええ?」(この布の切れ端、捨てていい?)といった具合に使います。これは関西地方で広く使われる方言で、すみれたちが日常の作業の中で交わす会話にリアリティを与えていました。
また、大変な状況や疲れた時に使う「えらい」という言葉も特徴的です。 標準語の「偉い」とは全く意味が異なり、「しんどい」「疲れた」「大変だ」といったニュアンスで使われます。 「今日の仕事はえらかったわぁ」と言えば、「今日の仕事は大変だったなあ」という意味になります。すみれたちが困難に直面したとき、この一言に様々な感情が込められていたことでしょう。
これらの言葉は、単なる方言というだけでなく、ヒロインたちの感情や置かれた状況を生き生きと伝えるための重要なツールとなっていたのです。
「べっぴんさん」の方言・神戸弁の詳しい特徴

「べっぴんさん」の魅力を深める神戸弁ですが、他の方言、特に隣接する大阪弁とはどのような違いがあるのでしょうか。また、神戸弁が持つ独特の響きはどこから来るのでしょうか。ここでは、神戸弁のより詳しい特徴について掘り下げていきます。
大阪弁との微妙な違い
関西弁と一括りにされがちですが、神戸弁と大阪弁にはいくつかの明確な違いが存在します。
最も分かりやすい違いは、進行形・完了形の表現です。 神戸弁では「雨が降りよう(=今にも降りそうだ)」「雨が降っとう(=既に降っている)」のように、動作の段階を区別することがありますが、大阪弁ではどちらも「降ってる」で済ませることが多いです。 ドラマでも使われた「~とう」という語尾は、神戸弁を特徴づける重要な要素です。
また、「来ない」という否定の表現も異なります。神戸弁では「こーへん」と言うのに対し、大阪弁では「けーへん」と言う傾向があります。 さらに、「すごく」を意味する強調の言葉として、神戸では「ごっつ」や「ばり」が使われるのに対し、大阪では「めっちゃ」が一般的です。
こうした微妙な違いが、それぞれの地域の言葉の個性を作り出しており、「べっぴんさん」では神戸ならではの言葉の響きが大切にされていました。
上品でやわらかい響きが魅力
神戸弁は、関西の他の方言と比較して、おっとりとしていて上品、やわらかい響きを持つと言われることが多いです。 その理由の一つとして、港町として古くから海外の文化に開かれていた神戸の歴史的背景が挙げられます。様々な地域から人が集まり、言葉が混じり合う中で、洗練された独特の言葉遣いが形成されていったと考えられています。
また、言葉のアクセントは大阪弁に近い「京阪式アクセント」ですが、使われる単語は西の播州弁の影響も受けているなど、複数の文化が融合している点も、神戸弁の独特な響きを生み出す一因かもしれません。
ドラマ「べっぴんさん」では、ヒロインのすみれをはじめとする登場人物たちが、この上品でやわらかな神戸弁を話すことで、お嬢様育ちらしい育ちの良さや、穏やかで優しい人柄が効果的に表現されていました。
現代でも使われる神戸弁の単語
ドラマの時代から時は流れましたが、作中で使われた神戸弁の多くは、今も神戸の日常会話で聞くことができます。
例えば、物を「捨てる」ことを意味する「ほかす」 や、大変な時に使う「えらい」 は、世代を問わず広く使われています。また、「大丈夫」「OK」といった意味で使う「いける」も非常にポピュラーな表現です。 「明日、手伝いに行ける?」と聞かれれば、それは能力ではなくスケジュールの都合を確認されていることになります。
親しい友人同士の会話では、別れ際に「ほなね」(それじゃあね)と言ったり、相手を呼び止める際に「ちょー、ちょー」と言ったりすることもあります。 これらの言葉は、神戸の人々のコミュニケーションに温かみと親密さを加えています。ドラマをきっかけにこうした言葉を知っておくと、神戸を訪れた際に地元の人との会話がより楽しくなるかもしれません。
「べっぴんさん」の方言指導と役作りの裏側
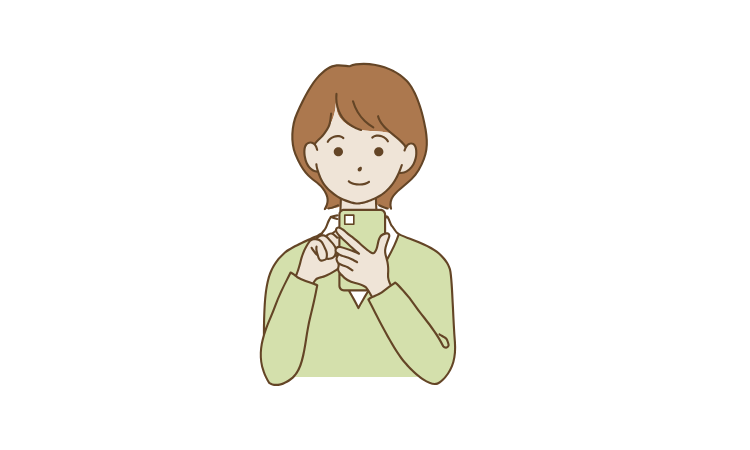
ドラマで話される自然な方言は、俳優たちの演技力はもちろんのこと、それを支えるスタッフの尽力があってこそ成り立っています。ここでは、ドラマ「べっぴんさん」の方言がどのように作られていったのか、その裏側に迫ります。
方言指導を担当したのは誰?
ドラマや映画で地域性の高い言葉を扱う際には、「方言指導」または「方言考証」という専門のスタッフが付きます。彼らは、台本のセリフがその地域で実際に使われる言葉として自然に聞こえるか監修し、俳優たちにイントネーションやアクセントの指導を行います。
「べっぴんさん」においても、専門の方言指導者が制作に参加していました。その方針は、実際の神戸の人が聞いても違和感がなく、かつ全国の視聴者にも理解しやすい関西弁を目指すというものだったようです。 出演者の中には、関西出身ではない俳優も多かったため、方言指導の役割は非常に重要でした。
出演者たちの方言習得の苦労
主演の芳根京子さんをはじめ、多くの出演者にとって、神戸弁の習得は大きな挑戦でした。特に、関西出身ではない俳優にとっては、イントネーションや微妙なニュアンスを掴むまでに大変な努力が必要だったことでしょう。
共演者で神戸弁がネイティブに近い谷村美月さん(大阪府堺市出身)の自然な言い回しは、他の共演者にとって良い手本になったかもしれません。 俳優たちは、方言指導のスタッフからのレクチャーを受けたり、録音された音声を聞き込んだりしながら、セリフを自分のものにしていきます。時には、出身地の違う共演者同士で教え合うこともあったかもしれません。こうした地道な努力が、ドラマのリアリティを支えていたのです。
視聴者から見た「べっぴんさん」の方言の評価
放送当時、「べっぴんさん」の方言は視聴者の間で様々な反響を呼びました。ドラマの舞台となった神戸やその周辺地域の視聴者からは、「実際の神戸弁とは少し違う」「イントネーションに違和感がある」といった厳しい意見も聞かれました。 特に、神戸弁の特徴である「~とう」という語尾があまり使われていないと感じた人もいたようです。
一方で、「優しくて温かい雰囲気が良い」「ドラマの世界観に合っている」といった好意的な意見も多くありました。 方言を完璧に再現することの難しさと、全国放送のドラマとして多くの人に分かりやすく届けることのバランスを取る必要があったことがうかがえます。 賛否両論があったこと自体が、それだけ多くの人々がドラマに注目し、方言に関心を持っていた証拠と言えるでしょう。
「べっぴんさん」の方言を知ってドラマをより深く楽しもう

この記事では、NHKの連続テレビ小説「べっぴんさん」で使われた方言、特に神戸弁に焦点を当てて解説してきました。「べっぴんさん」という言葉が持つ「特別な品」という本来の意味から、ドラマの舞台となった神戸で話される「神戸弁」の具体的な特徴、そして大阪弁との違いまで、多角的に掘り下げてきました。
ヒロインたちが話す「~しとう?」といった柔らかな語尾や、「ほかす」「えらい」といった地域ならではの単語は、物語に温かみとリアリティを与えていたことがお分かりいただけたかと思います。方言の背景を知ることで、登場人物たちの言葉の裏にあるニュアンスや感情がより鮮明になり、ドラマ「べっぴんさん」の世界を、これまでとはまた違った視点から、より深く味わうことができるはずです。




コメント