「かるう」という言葉を聞いたことがありますか?もしかしたら、九州地方出身のご家族や友人が話しているの耳にしたことがあるかもしれません。実はこの「かるう」、特定の地域で「背負う」や「おんぶする」といった意味で使われている、とても温かみのある方言なのです。多くの地元の人にとっては当たり前の言葉すぎて、方言だと意識せずに使っていることも少なくありません。
しかし、他の地域の人からすると「『軽い』ということ?」と聞き間違えてしまうこともある、少しユニークな響きを持つ言葉です。
この記事では、そんな「かるう」という方言が、具体的にどこの地域で使われているのか、どのような意味で、どういった場面で使うのかを、豊富な例文を交えながら詳しく解説していきます。また、言葉の由来や歴史、似た言葉である「からう」との違い、さらには日本全国の「背負う」を意味する多様な方言もご紹介します。この記事を読めば、あなたも「かるう」博士になれるかもしれません。方言の持つ奥深い世界を一緒に楽しんでいきましょう。
「かるう」はどこの方言?基本的な意味を解説

「かるう」という言葉を初めて聞いた方は、その意味や使われる地域について多くの疑問を持つことでしょう。この言葉は、日本の特定の地域で話される方言の一つであり、その地域の文化や生活に深く根付いています。まずは、「かるう」という言葉の基本的な情報から見ていきましょう。標準語でどのような意味になるのか、どのあたりで主に使われているのかを知ることで、この言葉への理解がぐっと深まるはずです。
標準語での意味は「背負う」
「かるう」という方言は、標準語に直すと「背負う(せおう)」や「おぶう」という意味になります。 例えば、リュックサックを背負う、子供を背中におぶうといった動作を指す言葉です。そのため、「荷物をかるう」「赤ちゃんをかるう」といった形で使われます。
初めてこの言葉を聞いた人は、その響きから「軽い(かるい)」という形容詞を連想するかもしれません。しかし、「かるう」は荷物などを背中に乗せるという動詞であり、重さとは直接関係がないのです。九州地方などではごく自然に日常会話で使われるため、地元の人々はこれが方言であると意識していないことも少なくありません。 例えば、学校で先生が「ランドセルをちゃんとかるって帰りましょう」と言ったり、家庭で親が子供に「弟をかるってあげて」と頼んだりする光景は、この言葉が使われる地域ではごく一般的です。このように、「かるう」は人々の生活に密着した、非常に実用的な方言だと言えるでしょう。
「かるう」が使われる主な地域
「かるう」という方言が最もよく使われるのは、九州地方、特に福岡県や大分県です。 しかし、その使用範囲は九州だけに留まりません。海を隔てた山口県や愛媛県の一部でも「かるう」という言葉が使われることがあります。 また、少し意外かもしれませんが、奈良県でも「早くかるうしょって!(早く背負って!)」のように、標準語と組み合わさった形で使われることがあるようです。
さらに面白いのは、同じ福岡県内でも地域によって微妙な違いがある点です。例えば、北九州市周辺では「かるう」と言うのに対し、福岡市のあたりでは「からう」という、少し音が変化した言い方が一般的だとされています。 この「からう」も意味は「かるう」と同じく「背負う」ですが、こうしたわずかな音の違いに、地域ごとの言葉の歴史や人々の交流の軌跡が隠されていると考えると、非常に興味深いですね。このように、「かるう」は九州を中心にしながらも、瀬戸内海を囲む地域や、遠く離れた奈良にまでその影響が見られる、広がりを持った方言なのです。
響きが似ている「軽い」との違い
「かるう」という言葉を初めて聞いたとき、多くの人が標準語の「軽い」と混同してしまうかもしれません。特に、イントネーションや文脈に慣れていないと、聞き間違えやすい言葉の一つです。しかし、この二つは意味も品詞も全く異なります。
「軽い」は物の重さが少ない状態を表す形容詞ですが、「かるう」は荷物などを背中に乗せる動作を表す動詞です。「荷物がかるい」と言えば重量が少ないことを意味しますが、「荷物をかるう」と言えば背負うという行為を指します。
この違いを理解するためには、文脈が重要になります。例えば、「この荷物、かるう?」と聞かれた場合、もし前後の会話で荷物の重さについて話していれば「この荷物、軽いの?」という意味かもしれません。しかし、出かける準備をしている場面であれば、「この荷物、背負うの?」と尋ねている可能性が高いでしょう。
また、実際に話されている場面では、アクセント(イントネーション)にも違いがあります。方言のアクセントは地域によって様々ですが、地元の人であればその微妙な音の違いで自然と区別しています。もし「かるう」という言葉に出会って意味に迷ったときは、それが動作を表しているのか、状態を表しているのかを考えてみると、正しく理解する手助けになるでしょう。
方言「かるう」の具体的な使い方を学ぼう

「かるう」の基本的な意味と使われる地域がわかったところで、次は具体的な使い方を見ていきましょう。言葉は、実際にどのように使われるかを知ることで、より深く理解することができます。日常会話のどのような場面で登場するのか、似た言葉との違いは何か、そしてどのような対象に使われるのか。具体的な例文を交えながら、「かるう」を使いこなすためのポイントを探っていきます。
日常会話で使える「かるう」の例文
「かるう」が日常会話でどのように使われるのか、具体的な例文を通して見てみましょう。場面を想像しながら読むと、言葉のニュアンスがより掴みやすくなります。
・子供にランドセルを背負わせる時
親:「はよランドセルかるうて学校行き!」
(標準語訳:早くランドセルを背負って学校に行きなさい!)
これは、登校前の慌ただしい時間によく聞かれる会話です。「かるう」が「背負う」という意味でごく自然に使われているのがわかります。
・お孫さんを背負っているお年寄りへの声かけ
「まごばかるーて、どこいきよんしゃーと」
(標準語訳:お孫さんをおぶって、どこに行かれるのですか)
地域の人同士の温かい交流が感じられる一文です。人をおぶう場合にも「かるう」が使われます。
・荷物を背負っている人への問いかけ
「大けん風呂敷ぅ、かるうち、どこ行きですな」
(標準語訳:大きな風呂敷を背負って、どこへ行かれるのですか)
風呂敷という言葉に、昔ながらの生活の様子がうかがえます。荷物を背負うという基本的な使い方の例です。
・遠足に行く子供たちの様子
「リュックサックばヒッカロウて2列で歩きよんなった」
(標準語訳:リュックサックを背負って2列で歩いていたよ)
これは「かるう」の強調形である「ひっかるう」の例ですが、楽しそうな子供たちの様子が目に浮かびます。
これらの例文から、「かるう」が人や物を背負うという幅広い場面で、世代を問わずに使われていることがわかります。
「からう」との違いと使い分け
「かるう」と非常によく似た方言に「からう」があります。どちらも「背負う」という意味で、特に九州地方で使われる言葉ですが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
最も大きな違いは、使われる地域です。「かるう」の語源は古語の「担う(かるう)」であると考えられており、この古い形が残っているのが福岡県の北九州地方や大分県、山口県などです。 一方、「かるう」の音が変化して「からう」になった言葉は、福岡県の福岡市周辺や長崎県など、九州のより広い範囲で使われています。 つまり、語源は同じで、地域によって発音が少し変化したものが「からう」だと理解するとよいでしょう。
そのため、どちらの言葉を使うかは、その人がどの地域の出身か、あるいはどの地域に長く住んでいたかによって決まります。北九州市出身の人は「ランドセルをかるう」と言い、福岡市出身の人は「ランドセルをからう」と言う、といった具合です。意味は全く同じなので、どちらの言葉を聞いても「ああ、背負うことなんだな」と理解できれば問題ありません。この微妙な音の違いこそが、方言の地域性を象徴しており、その土地の言葉の歴史を感じさせてくれる面白い点と言えるでしょう。
人を背負う場合と物を背負う場合の使い方
「かるう」という言葉は、背負う対象が人か物かによって使い方が変わるのでしょうか。結論から言うと、「かるう」は人をおぶう場合にも、荷物を背負う場合にも、どちらにも同じように使うことができる便利な言葉です。
例えば、ぐずる子供を背中におぶう場面では、「はよ、こっち来んね。お母さんがかるっちゃるけん(早くこっちにおいで。お母さんがおぶってあげるから)」のように使います。また、ハイキングで重いリュックサックを背負う場面では、「このリュック、結構重たいけど、しっかりかるわんと(このリュック、かなり重いけど、しっかり背負わないと)」といった形で使われます。
例文を見ても、「まごばかるーて(孫をおぶって)」のように人を対象にする場合もあれば、「にもつばかるーて(荷物を背負って)」や「ランドセルかるうて(ランドセルを背負って)」のように物を対象にする場合もあり、区別なく使われていることがわかります。
標準語の「背負う」も、人(責任を背負うなど比喩的な場合を除く)と物の両方に使えるのと同じ感覚です。「おぶう」は主に人を対象にしますが、「かるう」はそれよりも広い範囲をカバーする言葉だと言えるでしょう。この汎用性の高さが、「かるう」が地域の言葉として根強く残っている理由の一つかもしれません。
「かるう」という方言の語源と歴史

どんな言葉にも、その成り立ちや背景には歴史があります。方言である「かるう」も例外ではありません。この言葉がどこから来て、どのようにして今の形で使われるようになったのかを知ることは、日本語の変遷や地域の文化を理解する上で非常に興味深いことです。ここでは、「かるう」という言葉のルーツをたどり、その歴史的な背景に迫ります。
「かるう」の言葉の由来は古語の「担う」
「かるう」という方言のルーツをたどると、古語の「担う(かるう)」に行き着きます。 この古語は、現代の私たちが使う「担う(になう)」とは異なり、「荷物を背負う」という直接的な意味を持っていました。つまり、昔の日本では「背負う」ことを「かるう」と表現していたのです。
この古い言葉が、時代が下っても特定の地域に方言として残り続けたのが、現在の「かるう」です。特に、九州や中国地方の一部でこの古語の形が色濃く保存されました。一方で、九州の広い範囲で使われる「からう」は、この「かるう」の音が時代とともになまって変化したものだと考えられています。 言葉は常に少しずつ変化していくものであり、「かるう」から「からう」への音の変化は、その一例と言えるでしょう。
このように、「かるう」は単なる地方の言葉というだけでなく、日本語の古い形を今に伝える貴重な「言葉の化石」のような存在なのです。方言を通して、私たちは昔の日本の言葉遣いに触れることができるのです。
いつ頃から使われ始めた言葉?
「かるう」という言葉が、具体的にいつ頃から使われていたのかを正確に特定するのは難しいですが、その歴史がかなり古いことは間違いありません。一つの手がかりとして、1603年(慶長8年)に日本でイエズス会の宣教師によって刊行された『日葡辞書(にっぽじしょ)』という日本語とポルトガル語の辞典が挙げられます。 この辞書は、当時の日本語の姿を克明に記録した貴重な資料です。
この『日葡辞書』には、「背負う」という意味で「Carǒ(かろう)」という言葉が記載されているという情報があります。これは「かるう」が変化した「かろう」という形ですが、「背負う」という意味を持つ言葉がこの時代にすでに存在していたことを示しています。安土桃山時代から江戸時代初期にかけての日本で、人々が荷物を「かるう」と表現していた様子がうかがえます。
また、「かるう」の語源が古語の「担う」であることを考えると、その起源はさらに古く、奈良時代や平安時代まで遡る可能性も十分に考えられます。昔話で、おじいさんやおばあさんが薪を背負う場面がありますが、当時はまさに「薪をかるう」と表現されていたのかもしれません。このように、「かるう」は少なくとも400年以上の長い歴史を持つ、由緒ある言葉なのです。
地域文化と「かるう」の関わり
言葉は、その土地の文化や生活様式と深く結びついています。「かるう」という方言もまた、それが使われる地域の文化を色濃く反映しています。
昔の日本では、車などの便利な運搬手段がなかったため、人々は自分の体を使って荷物を運ぶのが当たり前でした。農村では収穫物を、山間部では薪や炭を、そして町では商品を、人々は背中に「かって」運びました。「かるう」という言葉は、こうした人々の日常的な労働の場面で頻繁に使われ、生活に不可欠な言葉として定着していったと考えられます。
また、子育ても同様です。昔はベビーカーなどなく、親は子供を背中におぶって(かるって)農作業や家事をしていました。子供を「かるう」ことは、親の愛情表現であり、子供との大切なスキンシップの時間でもありました。今でも、おじいちゃんやおばあちゃんが孫を「かるう」と言うとき、そこには昔ながらの温かい家族の姿が重なって見えます。
二宮金次郎(尊徳)が薪を背負いながら本を読んでいる像は有名ですが、あの姿もまさに「薪をかるって」いる状態です。 このように、「かるう」という一語の背景には、物を運び、子を育ててきた日本の人々の実直な暮らしの歴史が刻まれているのです。方言は、単なる言葉の違いではなく、その地域の文化そのものと言えるでしょう。
「背負う」を意味する他の方言と「かるう」を比較
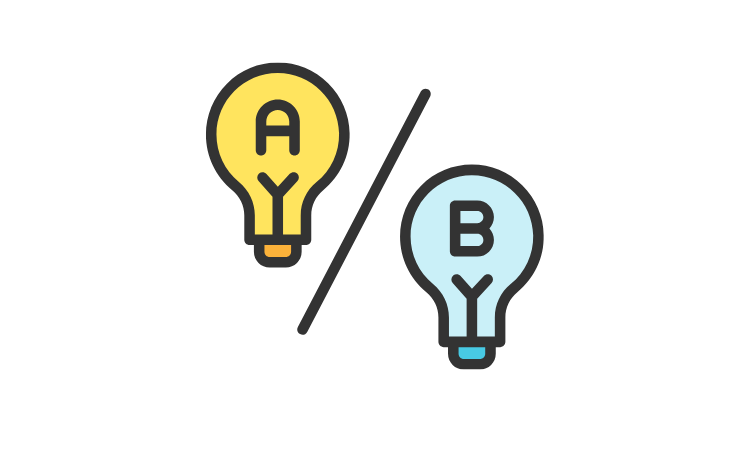
日本は南北に長く、地域ごとに多様な文化や言葉が育まれてきました。「背負う」という一つの動作を表す言葉も、例外ではありません。「かるう」以外にも、日本全国にはユニークで興味深い方言がたくさん存在します。ここでは、他の地域で使われる「背負う」の方言をいくつか紹介し、「かるう」と比較してみましょう。方言の多様性を知ることで、「かるう」の立ち位置もより明確になります。
【東北・関東・甲信越】「しょう」「かつぐ」など
東日本に目を向けると、「背負う」を意味する方言として代表的なのが「しょう」です。 東北地方や関東地方の広い範囲で使われており、聞いたことがある方も多いかもしれません。「リュックをしょう」「荷物をしょう」といった形で使われ、「背負う(せおう)」の音が変化したものだと考えられています。語感も似ているため、比較的理解しやすい方言と言えるでしょう。
また、甲信越地方、特に新潟県や石川県では「かつぐ」という言葉が使われます。 標準語の「担ぐ(かつぐ)」は、一般的に肩の上に乗せる動作を指しますが、これらの地域では背中に負うことも「かつぐ」と表現します。さらに、新潟県の吉田弁という地域方言では、「かたねる」や「かづく」といった、より珍しい表現も聞かれます。 「かづく」は古語の「被く(かづく)」に由来する可能性があり、頭からかぶる、ほうびをいただくといった意味から転じて、背負うという意味になったのかもしれません。
これらの言葉と比べると、「かるう」は古語の「担う」に由来するため、また異なる言葉の流れを汲んでいることがわかります。
【関西・中国・四国】「せたろう」「かける」など
次に関西から中国・四国地方を見てみましょう。この地域でも多様な表現が見られます。例えば、奈良県や兵庫県の播磨地方では「せたろう」というユニークな言葉が使われることがあります。 「背に太郎」とでも言うような面白い響きですが、昔話などで「薪をせたろうて歩く」といった使われ方をします。 語源ははっきりしませんが、「背に負う」が変化したものではないかと考えられています。
また、愛媛県では「かける」という方言があります。「荷物をかける」といった使い方をします。 標準語の「(肩に)掛ける」と意味が近く、そこから背負うこと全般を指すようになったと推測されます。
岡山県では「なおす」という、一風変わった言葉が使われることもあるようです。 標準語の「直す」や関西でよく使われる「片付ける」という意味とは全く異なり、「荷物をなおしてきた」は「荷物を背負ってきた」という意味になります。
これらの言葉と比較すると、九州地方の「かるう」が古語の形を比較的よく留めているのに対し、他の地域では音の変化や意味の転用によって、様々な言葉が生まれていることがわかり、日本語の多様性を感じさせます。
【九州】「しょる」や多様な表現
「かるう」や「からう」が有名な九州地方ですが、「背負う」を表す言葉はそれだけではありません。九州の一部の地域では、東北地方などと同じように「しょる」という言葉も使われます。 これは「背負う」の「しょ」から来た言葉で、九州の中でも地域によって言葉が混在していることがわかります。
例えば、長崎県では「からう」が主流ですが、隣の佐賀県や福岡県との県境ではまた違う言い方が存在するかもしれません。同じ九州という大きな括りの中でも、県や市町村、さらには集落単位で言葉が微妙に異なるのが方言の面白いところです。
「かるう」という言葉が古語の「担う」に由来する一方で、九州内で「しょる」という「背負う」に直接由来する言葉が併存しているのは、人々の移動や交流の歴史が関係しているのかもしれません。昔、異なる地域から移り住んできた人々が持ち込んだ言葉が、元々あった「かるう」という言葉と共存するようになった、という可能性も考えられます。
このように、日本全国を見渡すと、「背負う」という一つの言葉に「かるう」「しょう」「かつぐ」「せたろう」など、驚くほど多くのバリエーションが存在します。それぞれの言葉が持つ独自の響きや歴史を知ることは、日本の文化の豊かさを再発見するきっかけになるでしょう。
「かるう」という方言にまつわる豆知識

ここまで「かるう」の意味や歴史、使い方について詳しく見てきましたが、この言葉にはまだまだ面白い側面が隠されています。単に物を背負うだけでなく、比喩的に使われることもあれば、言葉の意味を強調するユニークな表現も存在します。最後に、「かるう」にまつわる少しマニアックな豆知識をご紹介します。これらを知れば、あなたも「かるう通」になれること間違いなしです。
責任などを「かるう」比喩的な使い方
「かるう」は、ランドセルや赤ちゃんといった物理的なものを背負うだけでなく、目には見えない抽象的なものを背負う、という比喩的な意味で使われることもあります。これは標準語の「背負う」が「責任を背負う」「十字架を背負う」といった使い方をされるのと非常によく似ています。
例えば、大変な借金を抱えてしまった状況を、「えらい借金ばカラウこともあるとバイ」のように表現することがあります。 この場合の「カラウ(かるう)」は、単にお金を背負っているわけではなく、返済の義務や精神的な負担といった重圧を一身に引き受けているというニュアンスを強く含んでいます。
また、一家の大黒柱としての責任や、チームをまとめるリーダーとしての重責など、様々な「背負うべきもの」に対してこの言葉を使うことができます。物理的な重さだけでなく、精神的な重圧をも表現できるこの比喩的な用法は、「かるう」という言葉が人々の生活や人生観にまで深く根付いている証拠と言えるでしょう。言葉の奥深さを感じさせる使い方の一つです。
強調表現の「ひっかるう」とは?
方言には、言葉の意味を強調するための独特な表現が存在することがあります。「かるう」にも、そのような強調表現があります。それが「ひっかるう」です。
言葉の頭に「ひっ」という接頭語がつくことで、「かるう」の意味が強調されます。「ひっ」は「ひったくる」「ひっつかむ」などの言葉にも見られるように、強く、あるいは勢いよくといったニュアンスを加える働きがあります。
そのため、「ひっかるう」は、単に背負うのではなく、「ひょいっと軽々と背負う」「勢いよく背負う」といった、動作の力強さや素早さを表現したい時に使われます。例えば、「婆々さんな…俺がヒッカラウけん(おばあさんは…俺がおんぶするから)」という例文では、おばあさんを力強く、そして安心して任せられるように背負う、という頼もしさが感じられます。 また、「リュックサックばヒッカロウて」という表現からは、子供たちが元気いっぱいにリュックを背負っている様子が目に浮かぶようです。
このように、「かるう」に一味加える「ひっかるう」という表現を知っていると、会話の表現力が豊かになり、より生き生きとした情景を伝えることができます。方言が持つ表現の幅広さを感じさせる、面白い言葉です。
地元の人が方言だと気づかない言葉?
「かるう」にまつわる最も興味深いエピソードの一つは、多くの地元の人々が、この言葉を方言だと全く意識せずに使っているという事実です。 生まれた時から周りの大人たちが当たり前に「荷物をかるう」「ランドセルをからう」と言っている環境で育てば、それが全国共通の標準語だと信じてしまうのも無理はありません。
そして、大学進学や就職で地元を離れ、他の地域の人と話した時に初めて「え、『かるう』って何?」「『からう』ってどういう意味?」と聞かれ、衝撃を受けるのです。 「え、じゃあ何て言うの?」「『背負う』?なんだかお洒落だね」といった反応は、”方言あるある”としてよく語られるエピソードです。
この現象は、「かるう」という言葉が、いかにその地域の生活に溶け込み、空気のような存在になっているかを物語っています。言葉はコミュニケーションの道具であると同時に、その人のアイデンティティや故郷との繋がりを形成する重要な要素です。方言だと知らずに使っていた言葉が、実は故郷だけの特別な言葉だったと知った時、多くの人は驚きと共に、自分の故郷への愛着を再認識するのかもしれません。
「かるう」という方言のまとめ

この記事では、「かるう」という方言について、その意味、使われる地域、語源、具体的な使い方、そして関連する豆知識まで、幅広く掘り下げてきました。
「かるう」は、標準語の「背負う」「おぶう」にあたる言葉で、主に九州地方、特に福岡県や大分県、さらには山口県や愛媛県の一部でも使われています。 その語源は古語の「担う(かるう)」にあり、日本語の古い形を今に伝える貴重な言葉です。 地域によっては「からう」という音に変化していますが、意味は同じです。
使い方としては、ランドセルのような物から赤ちゃんのような人まで、区別なく背負う行為全般に用いることができます。 さらに、「借金をかるう」のように比喩的な重責を表すこともあり、言葉の表現の豊かさがうかがえます。
日本全国には「しょう」「かつぐ」「せたろう」など、「背負う」を意味する多様な方言が存在し、「かるう」もその中の一つとして、地域の文化や歴史を色濃く反映しています。 地元の人々にとっては方言と意識されないほど日常に溶け込んだ「かるう」という言葉。その響きには、人々の暮らしの温かみと、長い歴史が詰まっています。この記事を通して、方言の奥深さと日本語の多様性を感じていただけたなら幸いです。

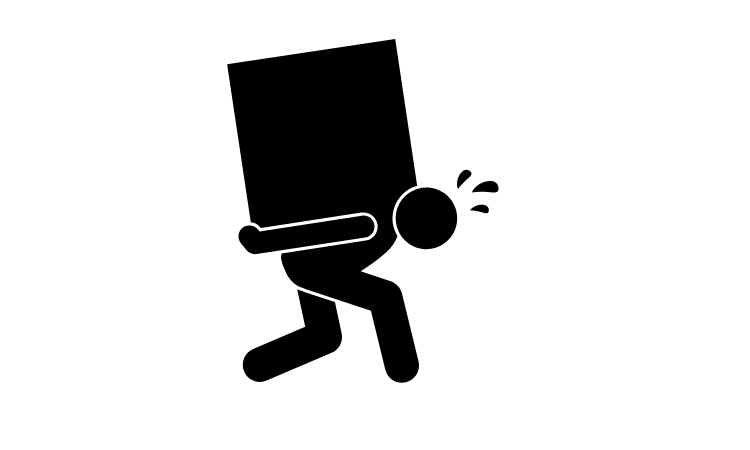


コメント