「ひしゃげる」という言葉を聞いたことはありますか?「車がひしゃげている」や「箱がひしゃげてしまった」のように、物がつぶれた様子を表す際に使われることが多い言葉です。しかし、日常的に使う人もいれば、あまり聞き馴染みがないという人もいるかもしれません。
そのため、「ひしゃげる」は方言なのではないかと疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、「ひしゃげる」の正確な意味や、方言なのか標準語なのか、その語源や由来、さらには具体的な使い方について、例文を交えながらやさしく解説していきます。この記事を読めば、「ひしゃげる」という言葉への理解が深まり、自信を持って使えるようになるでしょう。
「ひしゃげる」の基本的な意味

「ひしゃげる」という言葉は、物がつぶれて変形した様子を表す際に使われます。ここでは、その基本的な意味や漢字表記、似た言葉との違いについて詳しく見ていきましょう。
ぺちゃんこになる、つぶれるという意味
「ひしゃげる」は、外部からの力によって物が押しつぶされ、平らになったり、元の形を失ったりする状態を指す言葉です。 具体的には、「ぺちゃんこになる」「つぶれる」といった意味合いで使われます。 例えば、事故で車のボンネットが大きくへこんだ状態や、重いものの下敷きになって箱が平たくなってしまった状態などが「ひしゃげた」と表現されます。
この言葉は、単にへこんでいるだけでなく、修復が難しいほど大きく形が変わってしまったというニュアンスを含んでいることが多いです。非常に強い力が加わった結果、原形をとどめないほどに変形してしまった様子を的確に伝えることができる言葉と言えるでしょう。
漢字表記と語源
「ひしゃげる」は、漢字では「拉げる」と表記します。 この「拉」という漢字は、常用漢字ではありますが、音読みの「ラ」(例:拉致)しか常用漢字表には掲載されていません。 「ひしゃげる」という訓読みは、常用漢字表には載っていない表外読み(ひょうがいよみ)にあたります。
「拉げる」の読み方には「ひしゃげる」の他に「ひしげる」もあり、どちらも正しい読み方とされています。 一般的には「ひしゃげる」と読むことが多いようです。 語源は古語の「拉ぐ(ひしぐ)」とされており、この古語には「押しつぶす」と「押されてつぶれる」の両方の意味がありました。 現在では、能動態(押す側)を「ひしぐ」、受動態(押される側)を「ひしゃげる」と使い分けるのが一般的とされています。
類義語との違い(つぶれる、へこむなど)
「ひしゃげる」には、「つぶれる」や「へこむ」といった似た意味を持つ言葉(類義語)がいくつかあります。 しかし、それぞれニュアンスが異なります。
・つぶれる:
「つぶれる」は、「ひしゃげる」と非常によく似た意味で使われ、物が押しつぶされて形を失う様子を表します。 「ひしゃげる」が比較的大きな変形を指すことが多いのに対し、「つぶれる」はパンがつぶれる、空き缶がつぶれるなど、より広い範囲で使われる一般的な表現です。
・へこむ:
「へこむ」は、物の表面が内側にへこんだ状態を指します。ボールを指で押して一時的にへこんだり、車のドアに小さなへこみができたりする場合に使います。「ひしゃげる」が全体的な、あるいは大規模な変形を指すのに対し、「へこむ」は部分的で比較的小さな変形を指すことが多いです。
・歪む(ゆがむ):
「歪む」は、物がねじれたり、曲がったりして正しい形を失うことを意味します。 まっすぐだったものが曲がったり、平面だったものが波打ったりする状態です。「ひしゃげる」が押しつぶされるイメージなのに対し、「歪む」はねじれや曲がりによる変形を指すという違いがあります。
これらの言葉は似ていますが、物の変形の度合いや様子によって使い分けることで、より正確に状況を伝えることができます。
「ひしゃげる」は方言?標準語?

「ひしゃげる」という言葉の響きから、特定地域の言葉、つまり方言ではないかと考える人もいるかもしれません。ここでは、「ひしゃげる」が方言なのか、それとも標準語として扱われるのかを解説します。
もともとの由来と広がり
「ひしゃげる」は、辞書にも掲載されている標準語です。 漢字では「拉げる」と書きます。 しかし、その語源をたどると、もともとは特定の地域で使われていた言葉が全国に広まった可能性が考えられます。
特に「へしゃげる」という似た言葉は、大阪府などの近畿地方で使われる方言として認識されていることがあります。 「ひしゃげる」と「へしゃげる」は同じ意味で使われることが多く、広辞苑にも「へしゃげる」は「ひしゃげるに同じ」と記載されているようです。 このように、地域によって微妙に音が変化した言葉が存在することから、方言としての一面も持っていると捉えることができます。
現在では全国的に使われる傾向
現在では、「ひしゃげる」は特定の地域に限らず、全国的に意味が通じる言葉となっています。ニュースの報道で事故の様子を伝える際や、文学作品、漫画など様々なメディアで使われることで、多くの人がその意味を理解するようになりました。
例えば、名古屋地方では方言という認識はないものの、日常的によく使われる言葉として紹介されている例もあります。 このように、もともとは地域性のあった言葉が、人の移動やメディアの発展に伴って共通語として定着していくことは珍しくありません。「ひしゃげる」もその一つと言えるでしょう。
方言として「ひしゃげる」に似た言葉を使う地域
「ひしゃげる」は標準語として扱われていますが、地域によっては音が少し変化した、よく似た言葉が方言として使われています。
・へしゃげる:
先述の通り、大阪府などの近畿地方で使われることがあります。 「ひしゃげる」とほぼ同じ意味で、物がつぶれた状態を指します。
・ししゃげる:
宮城県を中心とした東北地方、特に仙台周辺では「ししゃげる」という言葉が使われることがあります。 これも「つぶれる」「形が崩れる」といった意味で、「ひしゃげる」の地域的なバリエーションと考えられます。
・びしゃがる、べっしゃげる:
三重県の四日市市四郷地区など、一部の地域では「びしゃがる」や「べっしゃげる」といったさらに音が変化した言葉も使われているようです。
これらの言葉は、それぞれの地域に根付いた表現であり、言葉の多様性を示しています。「ひしゃげる」という言葉を軸に、様々な地域で似た響きの言葉が使われているのは非常に興味深い点です。
【状況別】「ひしゃげる」の使い方と例文

「ひしゃげる」は、物がつぶれた状態を具体的に表現できる便利な言葉です。ここでは、どのような状況で使えるのか、具体的な例文を交えて解説します。
物が壊れた時の表現
「ひしゃげる」が最も一般的に使われるのが、物が強い力で押しつぶされて壊れた場面です。事故や災害など、衝撃的な出来事によって物の形が大きく変わってしまった様子を表すのに適しています。
・例文1:
「高速道路での追突事故により、車の後部がひしゃげてしまった。」
この例文では、事故の衝撃で車のトランク部分が大きくつぶれ、原形をとどめていない様子が伝わります。「へこんだ」では表現しきれない、深刻な損傷の度合いを示すことができます。
・例文2:
「台風で飛んできた看板が当たり、物置の扉がひしゃげた。」
この場合も、単なるへこみではなく、扉全体が大きく変形し、開閉もままならないような状態を想像させます。強い力が加わった結果としての破壊的な状況を表現しています。
・例文3:
「カバンを地面に落としたら、中に入れていた弁当箱がひしゃげて、中身が飛び出してしまった。」
この例文のように、必ずしも大規模な事故でなくても、予期せぬ力でプラスチックの容器などがぺしゃんこになってしまった場合にも使うことができます。
食べ物に使われる場合
「ひしゃげる」は、食べ物がつぶれてしまった状態を表すのにも使えます。特に、もともと形が整っていたものが、押されたり圧力がかかったりして見た目が損なわれた際に用いられます。
・例文1:
「買い物袋の一番下に置いてしまったので、パンがひしゃげていた。」
ふんわりとしていたはずのパンが、他の荷物の重みで平たくなってしまった残念な様子が目に浮かびます。
・例文2:
「リュックサックに入れて運んだら、お土産用のケーキの箱が少しひしゃげてしまった。」
この場合、箱が完全につぶれたわけではなくても、角がへこんだり形が歪んだりして、きれいな状態ではなくなってしまったというニュアンスで使われています。
・例文3:
「お弁当のご飯の上に乗せた梅干しが、持ち運ぶ間にひしゃげてご飯にめり込んでいた。」
このように、比較的小さなものでも、元の形から大きく崩れてしまった状態を表現するのに使うことができます。
人や気持ちの状態を表す場合(比喩的表現)
「ひしゃげる」は、物理的な変形だけでなく、人の表情や気持ちが落ち込んでいる様子を比喩的に表現するためにも使われることがあります。
・例文1:
「ゲタがひしゃげたような顔」
これは、不機嫌で歪んだような顔つきを表現する古い言い回しです。実際に顔が物理的につぶれているわけではなく、不満や怒りで表情が醜く歪んでいる様子を、ユーモラスかつ的確に描写しています。
・例文2:
「期待していたプロジェクトが中止になり、彼のプライドはひしゃげてしまった。」
この例文では、「ひしゃげる」を人の自尊心や誇りが深く傷ついた状態の比喩として用いています。「プライドが傷ついた」と言うよりも、再起不能に近いほどの大きな精神的ダメージを受けたという強いニュアンスを伝えることができます。
・例文3:
一部の地域では、「がっかりする」「落胆する」といった心理的な落ち込みを「ひしゃげる」と表現することもあるようです。 このように、物理的な現象を表す言葉が、人の内面や感情を表す言葉へと転用される例は、日本語の面白さの一つと言えるでしょう。
「ひしゃげる」の語源と由来

言葉の意味や使い方を深く理解するためには、その語源や成り立ちを知ることが役立ちます。「ひしゃげる」という言葉は、どのような経緯で生まれ、使われるようになったのでしょうか。
「押し潰す」という意味の「ひしぐ」が変化した説
「ひしゃげる」の語源として最も有力なのが、古語の「拉ぐ(ひしぐ)」が変化したという説です。 この「ひしぐ」という言葉は、もともと「押しつぶす」という意味を持っていました。 また、古語の「ひしぐ」には、「押されてつぶれる」という受け身の意味も含まれていました。
時が経つにつれて、言葉の役割が分化していきました。現代では、自らが力を加えて押しつぶす能動的な行為を「ひしぐ」(例:敵を打ちひしぐ)、外部の力によってつぶされてしまう受動的な状態を「ひしゃげる」と使い分けるのが一般的になったと考えられています。 このように、もとになった動詞から、音を少し変えることで意味合いの異なる言葉が生まれるのは、日本語の動詞の活用や変化によく見られるパターンです。
「ひしゃぐ」という動詞からの派生
「ひしゃげる」と非常によく似た言葉に、「ひしゃぐ」という動詞があります。 これは「押してつぶす」という能動的な意味を持つ言葉です。 「ひしゃげる」は、この「ひしゃぐ」という動詞が、受け身の形に変化したものと考えることもできます。
日本語では、「〜げる」という形になることで、自然にそうなる、あるいはそうなってしまうといったニュアンスを持つことがあります。例えば、「剥ぐ(はぐ)」に対する「剥げる(はげる)」、「向く(むく)」に対する「向ける(むける)」などがその例です。この法則に当てはめると、「ひしゃぐ(押しつぶす)」という行為の結果として、「ひしゃげる(つぶれてしまう)」という状態になる、という関係性が理解できます。
歴史的な文献での使用例
「ひしゃげる」の元になった「ひしぐ」という言葉は、古くから日本の文学作品などに見られます。例えば、有島武郎の小説『生れ出づる悩み』の中には、「艪(ろ)を―・げるほど押しつかんだ」という一節があり、オールが壊れるほど強く握りしめる様子が描かれています。
また、江戸時代の洒落本(しゃれぼん)など、庶民の会話を生き生きと描いた書物の中では、「ひしゃげる」やそれに近い表現が口語として使われていた可能性も考えられます。言葉の歴史をたどると、書き言葉として正式に記録されるだけでなく、人々の話し言葉の中で育まれ、変化してきたものが多くあります。「ひしゃげる」もそうした言葉の一つとして、長い時間をかけて現在の形に定着してきたのでしょう。
まとめ:「ひしゃげる」の意味や方言なのかを再確認

この記事では、「ひしゃげる」という言葉の意味、方言なのかどうか、語源、そして具体的な使い方について詳しく解説してきました。
「ひしゃげる」は、「押されてつぶれる」「ぺちゃんこになる」という意味の標準語です。 漢字では「拉げる」と書きます。 もともとは「押しつぶす」を意味する古語「ひしぐ」から派生した言葉と考えられています。
方言ではありませんが、「へしゃげる」(近畿地方など)や「ししゃげる」(仙台周辺)のように、地域によっては似た響きの言葉が使われていることもあります。
使い方の例としては、事故で「車がひしゃげた」という物理的な破損を表す場合から、「パンがひしゃげる」のように食べ物がつぶれた様子、さらには「プライドがひしゃげる」といった比喩的な表現まで幅広く使うことができます。
「つぶれる」や「へこむ」といった類義語との違いを理解し、状況に応じて使い分けることで、より的確に物事の状態を表現できるようになるでしょう。

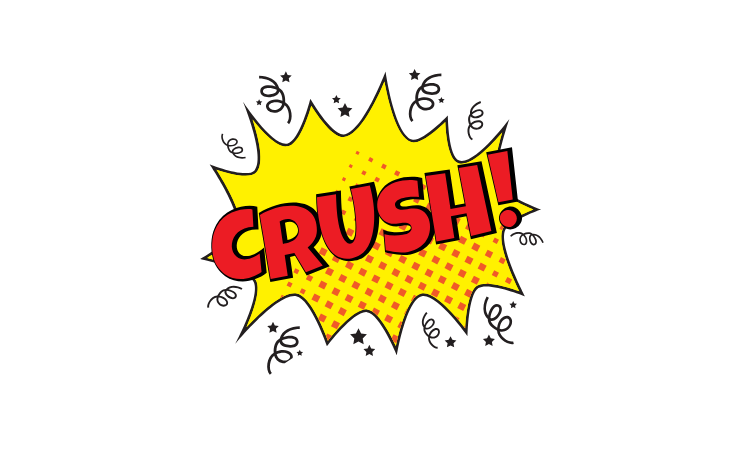

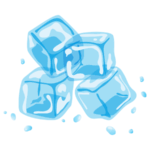
コメント