「Dr.スランプ」に登場する、一度見たら忘れられないユニークな宇宙人、ニコちゃん大王。 彼のトレードマークといえば、頭がお尻で鼻が触角という奇妙な姿と、もう一つ、特徴的な話し方ではないでしょうか。 実は、ニコちゃん大王が話す言葉は「名古屋弁」なのです。「~だぎゃ」「~みゃー」といった独特の語尾は、多くのファンに親しまれ、彼の愛すべきキャラクター性を際立たせています。
この記事では、なぜ宇宙から来たニコちゃん大王が名古屋弁を話すのか、その興味深い背景に迫ります。作者である鳥山明先生と名古屋の深いつながりや、ニコちゃん大王の声を担当した声優さんのエピソードなどを交えながら、その謎を解き明かしていきます。さらに、作中に登場する印象的な名古屋弁のフレーズもご紹介します。この記事を読めば、ニコちゃん大王と名古屋弁の魅力に、より深く気づかされることでしょう。
ニコちゃん大王と名古屋弁の基本的な関係

「Dr.スランプ」を語る上で欠かせない存在のニコちゃん大王と、彼のアイデンティティの一部ともいえる名古屋弁。この二つの要素がどのように結びついているのか、基本的な情報から見ていきましょう。
そもそもニコちゃん大王とはどんなキャラクター?
ニコちゃん大王は、鳥山明先生の漫画「Dr.スランプ」に登場する、ニコチャン星の「玉者(おうじゃ)」です。 地球を征服するためにやってきましたが、主人公の則巻アラレとガッちゃんに宇宙船を食べられてしまい、地球でアルバイトをしながら帰るための資金を稼ぐ羽目になります。
彼の姿は非常にユニークで、緑色の体に手足が生え、頭部がお尻、鼻が触角、耳が足の裏という、地球人から見るとかなり奇妙な構造をしています。 この一度見たら忘れられないデザインは、作者の鳥山先生自身も「最も僕の好きなくだらないキャラの代表格」と語るほど、愛着のあるキャラクターだったようです。 性格は、宇宙の支配者でありながらどこか間が抜けていて、地球を「ちたま」、火星を「ひぼし」と読み間違えるなど、おっちょこちょいな一面も持ち合わせています。 そんな憎めないキャラクター性が、多くの読者から愛される理由の一つとなっています。
ニコちゃん大王が話す言葉は本当に名古屋弁?
ニコちゃん大王が話す「~だぎゃ」「~みゃー」といった特徴的な語尾は、まさしく名古屋弁(尾張弁)の特徴です。 名古屋弁は、愛知県西部、旧尾張国で話される日本語の方言で、語尾に濁音が付いたり、独特の言い回しがあったりします。
作中でも、家来から「宇宙人が名古屋弁をしゃべるのはやめてください」とツッコミを入れられるシーンがあり、作者自身が意図的に名古屋弁を話すキャラクターとして設定していることがわかります。 ニコちゃん大王が使う「だがや」という言葉は、標準語の「~だよ」「~でしょ」にあたり、名古屋弁を象徴する表現としてよく知られています。 ただ、現代の名古屋では「だがや」を使う人は年配の方が多く、若者はあまり使わない傾向にあるとも言われています。 それでも、ニコちゃん大王のおかげで「名古屋弁といえば『だがや』」というイメージが全国的に広まったのは間違いないでしょう。
ファンはニコちゃん大王の名古屋弁をどう思っている?
ニコちゃん大王の名古屋弁は、ファンにとって彼の大きな魅力の一つとして受け入れられています。 SNSなどでは、「ニコちゃん大王のおかげで名古屋弁を覚えた」「宇宙人なのに名古屋弁なのが面白い」といった好意的なコメントが多く見られます。
彼のキャラクターデザインの奇抜さと、どこか人間味あふれる名古屋弁とのギャップが、唯一無二の存在感を生み出しています。 地球征服を企む恐ろしい(はずの)宇宙人が、親しみやすい方言を話すことで、ギャグ漫画としての面白さが一層引き立っているのです。また、鳥山明先生が亡くなられた際には、多くのファンがニコちゃん大王と彼の名古屋弁を懐かしむ声を寄せていました。 このことからも、ニコちゃん大王というキャラクターと名古屋弁が、いかにファンの心に深く刻まれているかがうかがえます。
ニコちゃん大王が名古屋弁を話す理由とは?

宇宙から来た大王が、なぜ日本の特定の地域の方言である名古屋弁を話すのでしょうか。その背景には、作者である鳥山明先生のルーツが深く関係しています。
作者・鳥山明先生と名古屋の深いつながり
「Dr.スランプ」や「ドラゴンボール」の生みの親である漫画家・鳥山明先生は、愛知県名古屋市出身です。 高校卒業後は名古屋市内のデザイン会社に勤務していましたが、退職後に漫画家デビューを果たしました。 デビュー後も名古屋に住みながら創作活動を続けており、まさに名古屋を拠点に世界的なヒット作を生み出してきたのです。
このように、鳥山先生にとって名古屋は生まれ育った故郷であり、自身のアイデンティティと深く結びついた場所でした。先生の作品には、ニコちゃん大王以外にも名古屋弁を話すキャラクターが登場することがあり、故郷の言葉に対する愛着が感じられます。 ファンからも「鳥山明先生は名古屋・愛知県の誇り」という声が上がっており、地元にとっても先生は自慢の存在です。
なぜ宇宙人のニコちゃん大王に名古屋弁を設定したのか
鳥山先生がなぜニコちゃん大王に名古屋弁を話させたのか、その明確な理由は公言されていません。しかし、いくつかの理由が考えられます。
一つは、ギャグ漫画としての面白さを追求した結果でしょう。地球征服という壮大な目的を持ってやってきた宇宙人が、日本のいち地方の方言を流暢に話すという設定は、それだけで非常にシュールで面白いものです。家来に「宇宙人が名古屋弁をしゃべるのはやめてください」と冷静にツッコまれるやり取りは、作中でも人気のギャグシーンとなっています。
また、作者自身の出身地の方言を使うことで、キャラクターに親しみやすさやオリジナリティを与えようとしたのかもしれません。ニコちゃん大王のどこか憎めないキャラクターは、名古屋弁が持つ独特の温かみや響きによって、より一層魅力的に感じられます。
名古屋弁がキャラクターに与えたインパクト
ニコちゃん大王に名古屋弁を話させたことは、キャラクターに絶大なインパクトを与えました。彼の奇抜な見た目と、地方色豊かな言葉遣いの組み合わせは、一度見聞きしたら忘れられない強烈な個性を生み出しています。
もしニコちゃん大王が標準語や、いかにも宇宙人らしい機械的な言葉を話していたら、ここまで愛されるキャラクターにはならなかったかもしれません。名古屋弁という意外な要素が加わったことで、彼は単なる悪役の宇宙人ではなく、人間味あふれるユニークな存在として確立されたのです。
この成功は、後の漫画やアニメにおける方言キャラクターのあり方にも影響を与えたと言えるでしょう。方言がキャラクターの個性を際立たせる有効な手法であることを、ニコちゃん大王は証明してくれました。ファンからは「ニコちゃん大王のおかげで名古屋弁を覚えた」という声も多く、彼の存在が名古屋弁の知名度向上に貢献したことは間違いありません。
ニコちゃん大王の名古屋弁は誰が話している?声優の存在
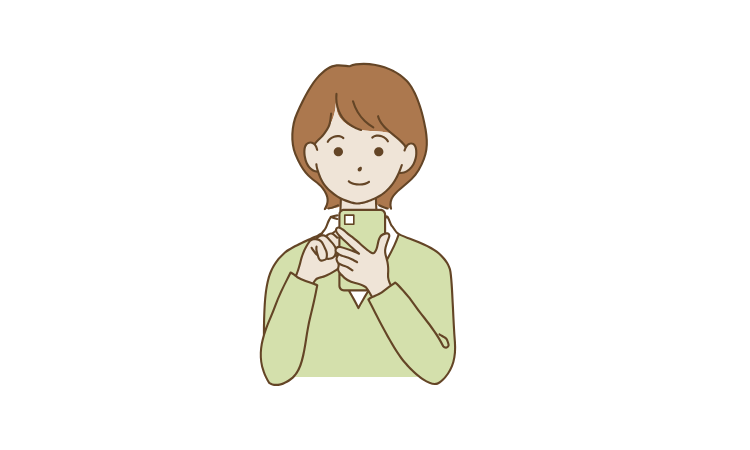
漫画で描かれたニコちゃん大王の名古屋弁に、命を吹き込んだのは声優さんたちの功績です。アニメ「Dr.スランプ アラレちゃん」では、二人の声優がニコちゃん大王を演じました。
初代声優・大竹宏さんと名古屋弁
1981年から放送されたアニメ第1作「Dr.スランプ アラレちゃん」でニコちゃん大王の声を担当したのは、声優の大竹宏さんです。 大竹さんは神奈川県出身で、本来は名古屋弁のネイティブスピーカーではありませんでした。
しかし、彼はニコちゃん大王を演じるにあたり、共演者で愛知県出身の声優・杉山佳寿子さんから名古屋弁の指導を受けてアフレコに臨んだそうです。 杉山さんは、作中で木緑あかね役などを演じていました。 このエピソードからは、制作現場がキャラクターの言葉遣いをいかに大切にしていたかが伝わってきます。大竹さんの演技によって、ニコちゃん大王の「~だぎゃ」という口調は、お茶の間の人気を博し、キャラクターの代名詞となりました。
2代目声優・島田敏さんと名古屋弁
1997年から放送されたリメイク版のアニメ「ドクタースランプ」では、声優の島田敏さんがニコちゃん大王役を引き継ぎました。 島田さんは新潟県出身の声優です。
島田さんもまた、初代の大竹さんが作り上げたニコちゃん大王のイメージを大切にしながら、独自の演技で新たなファンを魅了しました。声優が変わっても、ニコちゃん大王の名古屋弁という基本的な設定は受け継がれ、キャラクターのアイデンティティとして守られ続けたのです。二人の声優の熱演があったからこそ、ニコちゃん大王の名古屋弁は、世代を超えて多くの人々の記憶に残るものとなりました。
声優交代による名古屋弁の表現の違い
初代の大竹宏さんと2代目の島田敏さん、どちらも素晴らしい演技でニコちゃん大王を表現しましたが、出身地が異なるため、名古屋弁のニュアンスには微妙な違いがあったかもしれません。
大竹さんは、共演者からの指導を受け、特徴的な語尾やイントネーションを的確に捉えていました。 一方で、島田さんもベテラン声優として、キャラクターに合わせた方言の演技を巧みにこなしました。
ファンの中には、それぞれの声優が演じたニコちゃん大王に異なる魅力を感じている人もいるでしょう。例えば、初代のほうがよりコテコテの名古屋弁らしさを感じたり、2代目のほうが現代的な響きに聞こえたりするかもしれません。どちらの演技も、ニコちゃん大王というキャラクターを豊かに表現する上で欠かせないものであったことは間違いありません。声優の演技の違いに注目して、二つのアニメシリーズを見比べてみるのも面白いかもしれません。
作中で聞ける!ニコちゃん大王の名古屋弁フレーズ集

ニコちゃん大王のセリフには、名古屋弁の魅力が詰まっています。ここでは、彼の代表的なフレーズをいくつか取り上げ、その意味や背景を解説していきます。
代表的な口癖「~だぎゃ」「~みゃー」の意味
ニコちゃん大王の代名詞とも言えるのが、「~だぎゃ」や「~みゃー」といった語尾です。 「~だぎゃ」は、名古屋弁で「~だよ」「~なのだ」といった断定や主張を表す言葉で、非常に象徴的なフレーズです。 作中でも、家来に名古屋弁を指摘された際に「おみゃー、名古屋弁をバカにするんか」と怒るシーンがあり、この「~か」も名古屋弁の特徴的な使い方の一つです。
また、「~みゃー」という語尾も名古屋弁らしい表現ですが、現代の日常会話で使われることは少なくなってきているようです。 しかし、ニコちゃん大王のようなキャラクターが使うことで、親しみやすさや可愛らしさを感じさせる効果があります。 これらのフレーズは、ニコちゃん大王のキャラクター性を際立たせるだけでなく、名古屋弁という方言の存在を全国に知らしめる大きな役割を果たしました。
印象的な名古屋弁セリフとその背景
作中には、彼のキャラクターがよく表れた印象的な名古屋弁のセリフが数多く登場します。地球征服の第一声として、潜望鏡で地球を眺めながら「むむ~~ あれがチタマか……」と呟くシーンは有名です。 すかさず家来に「『ちきゅう』とよむのです」と訂正されるこのやり取りは、彼のどこか抜けた性格を端的に示しています。
さらに、「あそこをやっつけたりゃあ ちょうど100個の星をせんりょうしたことになるがや」というセリフも、彼の野望と名古屋弁が融合したユニークなものです。 「~たりゃあ」は「~してやれば」、「~がや」は「~だよ」という意味で、強い意志の中にもどこか間の抜けた響きが感じられます。これらのセリフは、大それた野望を語りながらも、その言葉遣いのせいで全く怖く聞こえないという、ニコちゃん大王ならではの面白さを生み出しています。
名古屋弁を知るともっと面白い!セリフのニュアンス
名古屋弁の基本的な意味を知ることで、ニコちゃん大王のセリフはさらに面白く感じられます。例えば、名古屋弁では「とても」を意味する言葉として「でら」という方言があります。 もしニコちゃん大王が「でらすごいがや!」と言ったとしたら、それは「とてもすごいんだよ!」という強い感情が込められていると理解できます。
また、名古屋弁には「~だがね」という、相手に同意を求めるような柔らかい表現もあります。 ニコちゃん大王が「地球は美しい星だがね」と言えば、それは家来に対して「地球は美しい星だよね?」と語りかけているような、親しみのこもったニュアンスになります。
このように、単に「面白い言葉遣い」としてだけでなく、その言葉が持つ本来のニュアンスを理解することで、ニコちゃん大王の感情の機微や、家来との関係性まで、より深く味わうことができるのです。
ニコちゃん大王だけじゃない?名古屋弁を話すキャラクターたち

鳥山明先生の作品をはじめ、アニメや漫画の世界には、ニコちゃん大王以外にも名古屋弁を話す魅力的なキャラクターたちが存在します。方言は、キャラクターに個性とリアリティを与えるための重要な要素として活用されています。
他の鳥山明作品に登場する名古屋弁キャラクター
鳥山明先生の代表作である「ドラゴンボール」にも、名古屋弁を話すキャラクターが登場します。その一人が、刀を背負った食いしん坊の浪人「ヤジロベー」です。 アニメ版のヤジロベーは、時折名古屋弁のような話し方をすることがあり、ニコちゃん大王との共通点としてファンに知られています。
作者である鳥山先生が名古屋出身であることから、自身の作品に故郷の言葉を取り入れるのは自然なことだったのかもしれません。 これらのキャラクターを通じて、鳥山先生は読者や視聴者に、知らず知らずのうちに名古屋弁の響きを届けていたと言えるでしょう。ニコちゃん大王やヤジロベーの存在は、作者の遊び心と地元愛の表れと見ることもできます。
アニメや漫画における方言キャラクターの役割
アニメや漫画において、方言を話すキャラクターは、物語に深みと多様性を与える重要な役割を担っています。方言は、キャラクターの出身地や育った環境を暗示し、その人物の背景を豊かにします。また、標準語を話すキャラクターとの対比によって、会話劇にリズムや面白みが生まれます。
特に、ニコちゃん大王のような宇宙人が方言を話すという設定は、常識を覆す意外性があり、ギャグとして非常に効果的です。また、地方出身のキャラクターが方言を話すことで、視聴者や読者はそのキャラクターにより親近感を覚えたり、その地方に興味を持つきっかけになったりもします。近年では「八十亀ちゃんかんさつにっき」のように、名古屋弁をテーマにした作品も登場しており、方言が持つ魅力が再認識されています。
名古屋弁が持つ独特のキャラクター性
名古屋弁は、その独特の響きから、キャラクターに特定のイメージを与えることがあります。「~だぎゃ」「~みゃー」といった語尾は、時にユーモラスで親しみやすい印象を与え、ニコちゃん大王のような愛すべきキャラクターによく合います。
一方で、言い方によっては少しぶっきらぼうに聞こえることもあるため、豪快な性格や、少し気難しい職人気質のキャラクターに使われることもあります。このように、名古屋弁は一言で「これ」と決めつけられない、多様な側面を持った方言です。
アニメや漫画の制作者は、名古屋弁が持つこうした多面的なイメージを利用して、キャラクターの性格を効果的に表現しています。ニコちゃん大王が成功したことで、名古屋弁は「面白い」「個性的」というポジティブなイメージとともに、多くのクリエイターにとって魅力的な表現の選択肢の一つとなったのです。
まとめ:ニコちゃん大王と名古屋弁の切っても切れない関係

この記事では、「Dr.スランプ」の人気キャラクター、ニコちゃん大王と名古屋弁の関係について掘り下げてきました。
ニコちゃん大王が話す「~だぎゃ」といった特徴的な言葉は、作者である鳥山明先生が愛知県名古屋市出身であることに由来しています。 先生の遊び心と郷土愛から生まれたこの設定は、宇宙の侵略者というキャラクターに人間味とユーモアを与え、唯一無二の存在感を確立させました。
アニメ化にあたっては、声優の大竹宏さんや島田敏さんといった方々が、見事に名古屋弁のニュアンスを表現し、ニコちゃん大王のキャラクターを不動のものにしました。
ニコちゃん大王の存在は、多くの人にとって名古屋弁に触れるきっかけとなり、その知名度を全国区に押し上げたと言っても過言ではありません。 彼の奇抜な見た目と親しみやすい方言のギャップは、今なお多くのファンに愛され続けています。ニコちゃん大王と名古屋弁は、まさに切っても切れない、最高の組み合わせなのです。


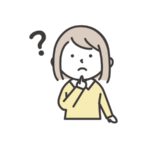

コメント