東北地方と一言でいっても、そのエリアは広く、話される方言もさまざまです。一般的に「東北弁」や「ズーズー弁」として知られるこれらの言葉には、実は地域ごとに細かな違いと豊かな個性があります。厳しい冬の寒さや歴史的な背景から生まれたとされる独特のイントネーションや単語は、どこか温かく、私たちの心を惹きつけます。
この記事では、東北地方6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)で話される方言を一覧でご紹介します。それぞれの地域が持つ方言の魅力や特徴、そして思わず使ってみたくなる面白い表現まで、やさしく丁寧に解説していきます。この記事を読めば、東北地方の方言の奥深さと多様性にきっと驚くはずです。
北奥羽方言と南奥羽方言
東北地方の方言は、大きく「北奥羽(きたおうう)方言」と「南奥羽(みなみおうう)方言」の2つに分類されます。 この区分は、かつての藩の領域や地理的な要因が大きく影響しています。
北奥羽方言が話されるのは、青森県、岩手県の北・中部、秋田県、山形県の庄内地方、そして新潟県の北部です。 こちらはアクセントが東京式に近く、比較的標準語に近いイントネーションを持つとされています。 とはいえ、もちろん地域ごとの独自性は強く、例えば青森県の津軽弁のように非常に難解とされる方言もこのグループに含まれます。
一方、南奥羽方言は、岩手県の南部、宮城県、山形県の内陸部、そして福島県で話されています。 こちらの最大の特徴は「無アクセント」であることです。 単語に特定の抑揚がなく、平坦なトーンで話される傾向があります。そのため、同じ言葉でも「橋」と「箸」のようなアクセントによる意味の違いがありません。 また、関東地方の方言との共通点も多く見られるのが特徴です。 このように、東北地方という一つのエリアの中でも、方言の系統が分かれていることを知ると、より深く言葉の背景を理解できます。
「ズーズー弁」ってどんな意味?
東北地方の方言を語る上で欠かせないのが「ズーズー弁」という言葉です。 これは、東北方言の俗称として広く知られていますが、元々は方言学の専門用語でした。 具体的には、五十音の「さ行」「ざ行」「た行」の発音に特徴がある方言を指します。
ズーズー弁の最も大きな特徴は、「し」と「す」、「ち」と「つ」、そしてその濁音である「じ」と「ず」(「ぢ」と「づ」も含む)の音を区別しない点にあります。 例えば、「寿司(すし)」という単語を発音すると、地域によっては「スス」や「シシ」のように聞こえることがあります。 「3時(さんじ)」が「さんず」のように聞こえるのもこの特徴のためです。 このように「じ」や「じゅう」といった音が「ず」や「ずー」に聞こえることから、「ズーズー弁」という愛称で呼ばれるようになりました。
この発音は、口をあまり大きく開けずに話す、寒い地方ならではの話し方から生まれたという説もあります。 今では高年層の方に残る特徴となりつつありますが、東北方言の温かみや個性を象徴する、非常に興味深い音韻現象といえるでしょう。
短い言葉や語尾の変化が豊か
東北地方の方言には、会話をリズミカルにする短い言葉や、感情のニュアンスを豊かに表現する語尾の変化がたくさんあります。その中でも特に広く使われるのが、推量や意志を表す「〜べ」「〜べぇ」といった語尾です。 「行ぐべ(行こう)」「んだべ?(そうだろう?)」のように使われ、会話に親しみやすい雰囲気を与えます。 北海道から関東地方の一部でも使われる言葉ですが、東北地方では特に頻繁に耳にする表現です。
また、方向や場所を示す助詞「へ」の代わりに「さ」が使われるのも大きな特徴です。 例えば、「東京へ行く」は「東京さ行ぐ」となります。 この「〜さ」という響きも、東北弁らしい温かさを感じさせる要素の一つです。
さらに、東北地方の方言には一文字で意味が通じる言葉も存在します。例えば、食べ物を勧めるときの「け(食べて)」や、それに対する返事の「く(食べる)」などがその代表例です。 口を大きく開けずに効率的に意思疎通を図ろうとした、雪国ならではの工夫から生まれたのかもしれません。このように、短いながらも表現力豊かな言葉の数々が、東北地方の方言の奥深さと面白さを形作っているのです。
【青森・岩手・宮城】東北地方の方言一覧と地域ごとの違い
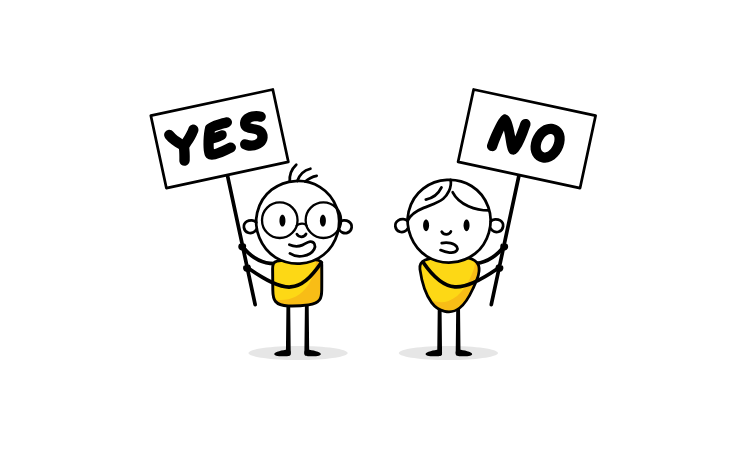
東北地方の北部に位置する青森県、岩手県、宮城県。この3県の方言は、同じ東北弁の枠組みにありながら、それぞれに際立った個性を持っています。歴史的な藩の影響や地理的な要因が、言葉の違いを育んできました。ここでは、各県の方言が持つ特徴や、代表的な言葉を詳しく見ていきましょう。
青森県の方言(津軽弁・南部弁・下北弁)
青森県の方言は、主に「津軽弁」「南部弁」「下北弁」の3つに大きく分けられます。 この区分は、江戸時代の藩政時代の名残が強く影響しており、特に津軽藩であった津軽地方の「津軽弁」と、南部藩であった県南東部の「南部弁」との間には、現在でも明確な違いがあります。
津軽弁は、日本語の中でも特に難解な方言として知られています。 標準語と比べて単語や一文が極端に短く、濁点が多い力強い口調が特徴です。 その独特さから「フランス語のよう」と表現されることもあります。 一方の南部弁は、津軽弁に比べておっとりとしていて柔らかい、女性的な響きを持つとされています。 そして、下北半島で話される下北弁は、津軽弁と南部弁の中間的な特徴を持ちつつ、独自の発展を遂げた言葉です。
代表的な方言には、友達を意味する「けやぐ」、触る・いじるという意味の「ちょす」、かわいいを意味する「めんこい」などがあります。 これらは県内で広く使われる言葉ですが、同じ意味でも津軽と南部で異なる単語を使うことも多く、青森県の方言の多様性を物語っています。
岩手県の方言(盛岡弁・沿岸部の言葉など)
広大な面積を持つ岩手県の方言は、地域によってさまざまな顔を持っています。その背景には、かつて県内が青森県や秋田県にまたがる広大な領地を持っていた「南部藩」と、宮城県に本拠を置いた「伊達藩」の2つに分かれていた歴史があります。 そのため、現在でも旧南部藩領だった県北・県中部と、旧伊達藩領だった県南部では、言葉の文化が異なっています。
県北・中部の中心である盛岡市周辺で話される「盛岡弁」は、ズーズー弁の特徴が強く見られる言葉です。 敬語表現が発達している点も特徴で、「おでれ(おいで)」「おいでん(おいでください)」のように段階的な敬語が存在します。 一方、沿岸部、特に久慈市周辺で使われる言葉で全国的に有名になったのが「じぇじぇじぇ!」です。 これは驚きを表す感嘆詞で、「じぇ」の数が多いほど驚きの度合いが大きいことを示します。 内陸部では同じ驚きを「じゃ!」と表現することが多く、ここにも地域差が見られます。
その他にも、かわいいを意味する「めんこい」や、同意を示す相づちの「んだべ」など、東北地方で広く使われる言葉も日常的に使われています。 広大な土地と複雑な歴史が、岩手県の方言に豊かなバリエーションをもたらしているのです。
宮城県の方言(仙台弁)
宮城県の方言は、一般的に「仙台弁」として知られています。 江戸時代、現在の宮城県のほぼ全域が仙台藩の領内であったため、県内の方言差は東北の他県に比べて比較的小さいとされています。 しかし、細かく見ると地域ごとの違いも存在し、主に「三陸方言(県北東部の沿岸)」「仙北内陸方言(県北西部の内陸)」「仙台方言(仙台市周辺)」「仙南方言(県南部)」の4つに区分されます。
仙台弁の大きな特徴は、南奥羽方言に共通する無アクセントと、ズーズー弁特有の発音です。 また、語尾に「〜だっちゃ」や「〜だべ」がつくのもよく知られています。 特に「〜だっちゃ」は、人気漫画「うる星やつら」のラムちゃんの口癖として全国的に有名になりました。
単語では、標準語の「とても」を意味する「いきなり」が特徴的です。 「いきなりすごい(とてもすごい)」のように使われ、初めて聞く人は少し驚くかもしれません。他にも、服などが体に合わずしっくりこない状態を「いずい」、ごみを「なげる(捨てる)」、穴のあいた靴下を「おはよう靴下」と呼ぶなど、ユニークで面白い表現がたくさんあります。 これらの言葉は、仙台弁の持つ親しみやすさと温かさを伝えてくれます。
【秋田・山形・福島】東北地方の方言一覧と地域ごとの違い

山々に囲まれた内陸部と、日本海に面した沿岸部。秋田、山形、福島は、それぞれが異なる地理的・歴史的背景を持ち、それが言葉にも色濃く反映されています。ここでは、これら3県の方言の魅力と、地域ごとのバリエーションに迫ります。
秋田県の方言(秋田弁)
秋田県で話される「秋田弁」は、東北地方の中でも比較的、県内での方言差が少ないとされています。 しかし、発音に関しては共通語との違いが大きく、独特の響きを持っています。 例えば、母音の「イ」と「エ」の区別が曖昧になったり、言葉の途中のカ行やタ行の音が濁ったり(濁音化)するなどの特徴があります。イントネーションも独特で、知っている単語でも標準語とは違う抑揚で話されるため、聞き慣れないうちは難しく感じることがあるかもしれません。
秋田弁を代表する言葉の一つに、別れの挨拶である「へば」があります。 これは「それじゃあ、また」といった意味で、会話の締めくくりによく使われます。また、「とても」「すごく」を意味する「しったげ」も特徴的です。 「しったげ、うんめぇ(すごく、おいしい)」のように、良い意味でも悪い意味でも使うことができます。
他にも、助詞の「に」や「へ」を「さ」と言ったり、あいづちで「んだ(そうだ)」を多用したり、「まんず(まあ、どうぞ)」といった言葉を会話の最初に使ったりと、秋た弁には味わい深い表現がたくさんあります。 これらの言葉が、秋田の人々の温かい人柄を伝えてくれるようです。
山形県の方言(内陸方言・庄内方言)
山形県の方言は、県内を南北に走る出羽山地を境に、大きく2つに分かれています。日本海側の「庄内方言」と、山形市や米沢市などがある「内陸方言」です。 庄内方言は秋田県の方言に近い北奥羽方言に、内陸方言は宮城県や福島県の方言に近い南奥羽方言に分類され、同じ県内でも言葉にかなりの違いがあります。
さらに、内陸方言は地域ごとに「最上弁(新庄市周辺)」「村山弁(山形市周辺)」「置賜弁(米沢市周辺)」に細分化されます。 例えば「そうだ」という意味の言葉一つをとっても、村山弁では「んだず」、新庄弁では「んだじゅー」、置賜弁では「んだっそ」、そして庄内弁では「んだのー」と、実にさまざまです。
ユニークな表現も多く、庄内地方で「ありがとう」と「ごめんなさい」両方の意味で使われる「もっけだの」は代表的な方言です。 また、お母さんを「ががちゃ」と呼んだり、語尾に「〜にゃー」をつけて「んだずにゃー(そうだねぇ)」と柔らかく表現したりするのも、山形弁の面白いところです。 この多様性こそが、山形県の方言の最大の魅力と言えるでしょう。
福島県の方言(会津弁・中通り弁・浜通り弁)
福島県は、西から順に「会津」「中通り」「浜通り」という3つの地域に大別され、文化や気候だけでなく言葉もそれぞれ大きく異なります。 西部の会津地方で話される「会津弁」、中央部の「中通り弁」、そして太平洋側の「浜通り弁」は、同じ福島県の方言とは思えないほどの違いを見せることがあります。
全体的な特徴としては、南奥羽方言に共通する「無アクセント」であること、そして言葉が濁ることが多い「濁音化」が挙げられます。 例えば「柿」を「カギ」、「酒」を「サゲ」のように発音します。 語尾には「〜だべ」や「〜だっぱい」が使われ、親しみやすい響きを生み出しています。
地域ごとの違いも顕著で、浜通り地方の方言は、北は仙台弁に、南は茨城弁に近い特徴を持ちます。 中通り地方では、相手に同意を求める「だから」の使い方が独特です。普通なら接続詞として使う「だから」を、「そうだよね!」という共感の意味で使うため、他県の人が聞くと少し戸惑うかもしれません。 このように、福島県の方言は、3つの地域の個性が溶け合った、非常に興味深い言葉なのです。
思わず使ってみたくなる!面白い東北地方の方言

東北地方の方言には、標準語にはないユニークな響きや、思わずクスッと笑ってしまうような面白い表現がたくさんあります。その土地の文化や暮らしの中から生まれた言葉は、知れば知るほど愛着が湧いてくるものばかりです。ここでは、そんな東北地方の面白い方言のいくつかをご紹介します。
「け」「く」(食べて・食べる)
東北地方の方言の中でも、特にその短さで有名なのが「け」と「く」です。これは青森、山形など東北の広い範囲で使われることがある一文字の方言で、「け」は命令形の「食べて」、「く」は意思を示す「食べる」を意味します。 例えば、食卓でお母さんが子どもにご飯を勧めるときに「これ、け」と言い、子どもが「うん、く」と答えるような会話が成り立ちます。
初めて聞いた人は、あまりの短さに何を言っているのか分からないかもしれません。しかし、これは口を大きく開けなくてもコミュニケーションが取れるようにという、寒い地域ならではの知恵から生まれたという説もあります。 無駄がなく、それでいてしっかりと意思が伝わるこの言葉は、東北の方言の合理性と面白さを象徴する表現の一つと言えるでしょう。
「おはよう靴下」(穴のあいた靴下)
宮城県を中心に使われる「おはよう靴下」は、そのネーミングセンスが光る面白い方言です。 これは、つま先に穴があいて、指が「おはよう」と顔を出している状態の靴下を指す言葉です。
この表現の由来ははっきりしていませんが、そのユーモラスな情景が目に浮かぶような、非常に巧みな比喩表現です。単に「穴のあいた靴下」と言うよりも、どこか微笑ましく、愛嬌があります。日常のささいな出来事を面白がる、人々の遊び心が感じられる言葉です。もし宮城県出身の人がこの言葉を使っていたら、ぜひその意味を知っていることを伝えてみてください。きっと会話が弾むはずです。
「うるかす」(水に浸す)
「うるかす」は、主に東北地方や北海道で広く使われている便利な方言です。 これは、お米を研いだ後に水に浸しておいたり、食べ終わった食器を水につけて汚れを落ちやすくしたりする行為を指します。
標準語でこの状態を説明しようとすると、「水に浸しておく」「ふやかしておく」など、少し長い言葉になってしまいます。しかし、「うるかす」の一言でその意味が的確に伝わるため、東北地方の家庭では非常に重宝されている言葉です。語源は「潤(うるお)わす」から来ているとされ、言葉の成り立ちを知るとさらに納得感が増します。 日常生活に根付いた、実用性の高い方言の好例です。
「んだ」(そうだ)
「んだ」は、東北地方の方言を代表する相づちの言葉で、「そうだ」という意味で使われます。 相手の話に同意したり、肯定したりする際に、首を縦に振りながら「んだ、んだ」と繰り返す光景は、東北の日常会話でよく見られます。
この「んだ」は非常に応用が利く言葉で、地域によってさまざまなバリエーションがあります。「んだな(そうだね)」「んだべ?(そうだろ?)」「んだっけ?(そうだっけ?)」のように、語尾を少し変えるだけでニュアンスを豊かに表現することができます。 さらに、「んだはんで(だから)」「んだばって(だけど)」のように、接続詞のような役割を果たすこともあります。 まさに、東北弁の会話をスムーズに進めるための万能プレイヤーと言えるでしょう。この言葉を使いこなせれば、あなたも東北マスターに一歩近づけるかもしれません。
まとめ:東北地方の方言一覧で知る言葉の多様性と魅力

この記事では、「東北地方の方言一覧」というテーマで、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の6県で話される言葉の特徴や魅力を解説しました。
東北の方言は、単一の「東北弁」ではなく、北奥羽方言と南奥羽方言という大きなグループに分かれ、さらに各県、各地域で実に多様な言葉が存在していることがお分かりいただけたかと思います。 津軽弁の力強さ、南部弁の柔らかさ、仙台弁の親しみやすさ、そして地域ごとに異なる「んだ」のバリエーションなど、それぞれの言葉が歴史や風土に根ざした独自の個性を持っています。
「ズーズー弁」と呼ばれる独特の発音や、「け(食べて)」のような極端に短い言葉、そして「おはよう靴下」のようなユーモラスな表現は、厳しい自然環境の中で生まれた知恵や、人々の遊び心が詰まった文化遺産ともいえるでしょう。
一見すると難解に聞こえるかもしれませんが、その響きの奥には、人々の温かさや暮らしの息づかいが感じられます。この一覧を通じて、東北地方の言葉の豊かさに触れ、方言への興味を深めるきっかけとなれば幸いです。



