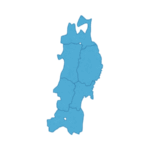島根県と聞くと、多くの人が出雲大社や世界遺産の石見銀山を思い浮かべるかもしれません。しかし、島根県の魅力はそれらの観光名所だけにとどまりません。地域ごとに根付いた特色豊かな方言も、島根の大きな魅力の一つです。その響きや独特の言い回しは非常にユニークで、知れば知るほど面白く感じられるでしょう。
この記事では、「島根県の方言一覧」として、県内で主に使われる「出雲弁」「石見弁」「隠岐弁」という3つの大きな方言グループに焦点を当てます。それぞれの特徴や具体的な単語、そして日常会話で使えるフレーズなどを分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、地元の人々とのコミュニケーションがより一層楽しくなるはずです。一緒に、奥深い島根の方言の世界を探求してみましょう。
島根県の方言一覧|地域でこんなに違う!3つの主な方言

島根県の方言は、一枚岩ではありません。地理的な条件や歴史的背景から、大きく分けて3つのエリアで異なる特徴を持つ言葉が話されています。東部の「出雲弁」、西部の「石見弁」、そして日本海に浮かぶ島々の「隠岐弁」です。 これらは同じ島根県内の方言でありながら、アクセントや語彙、語尾の使い方に違いが見られます。この章では、それぞれの地域で話されている方言の全体的な特徴と、なぜそのような違いが生まれたのかについて解説していきます。
東部の「出雲弁(出雲方言)」の特徴
島根県の東部、松江市や出雲市周辺で話されているのが「出雲弁」です。出雲弁は雲伯(うんぱく)方言に分類され、鳥取県西部の方言とも共通点が見られます。 その最も際立った特徴は、いわゆる「ズーズー弁」に似た発音です。
具体的には、「イ」と「ウ」の母音が中舌母音という少しこもった音で発音されるため、他の地域の人には聞き分けが難しいことがあります。 例えば、「雲州平田(うんしゅうひらた)」が「おんすうふらた」のように聞こえるのは、この発音特性によるものです。
また、文法的には、断定の助動詞に「~だ」を使ったり、動詞の活用でウ音便(例:「買うて」)ではなく促音便(例:「買って」)を用いたりと、西日本の中でも東日本方言と共通する要素を持っている点も興味深い特徴です。 このように、出雲弁は発音と文法の両面で独特の性質を持っており、島根の方言を代表する存在と言えるでしょう。
西部の「石見弁(石見方言)」の特徴
島根県の西部、大田市や浜田市、益田市などで話されているのが「石見弁」です。 石見地方は地理的に広島県や山口県と隣接しているため、石見弁はそれらの地域の方言(安芸弁や山口弁)と似た雰囲気を持っています。
出雲弁のような「ズーズー弁」の特徴は見られず、むしろ力強く歯切れの良い印象を与えることが多いです。 文法的な特徴としては、断定の助動詞に「~じゃ」が使われることがあり、これは山陽地方の方言と共通しています。 また、進行形と完了形で表現を使い分ける点も特徴的です。
例えば、「バスが来よる」はバスが今まさにこちらへ向かっている最中(進行形)を指し、「バスが来とる」はバスが既に到着している状態(完了形)を表します。 ただし、近年は若い世代を中心にこの区別が曖昧になりつつあるようです。 アクセントも、東部の外輪東京式アクセントに対し、西部では中輪東京式アクセントが用いられるなど、同じ県内でも違いが見られます。
離島の「隠岐弁(隠岐方言)」の特徴
日本海に浮かぶ隠岐諸島で話されているのが「隠岐弁」です。隠岐弁も大枠では出雲弁と同じ雲伯方言に属しますが、離島という地理的条件から、本土とは異なる独自の発展を遂げてきました。 他の地域とはアクセントが異なり、独特のイントネーションを持っています。
これは、古くから日本本土だけでなく、他の国との交流もあった歴史的背景が影響していると考えられています。 そのため、隠岐弁には他の地域の方言には見られないユニークな語彙や表現が数多く残っています。 例えば、驚いた時に発する「かっ!!」という感嘆詞は、まさに隠岐ならではの言葉と言えるでしょう。
また、島内でも地区によって言葉にかなりの違いがあるのも隠岐弁の面白い点です。 険しい山々によって各集落が隔てられていたため、昔は地区間の往来が難しく、それぞれが特色ある文化と言葉を育んできたのです。 このように、隠岐弁は島根県の方言の中でも特に個性的な存在感を放っています。
なぜ地域によって言葉が違うのか?
同じ島根県内で、なぜこれほど言葉に違いが生まれたのでしょうか。その理由は、主に地理的な要因と歴史的な背景にあります。日本の地形は険しい山々や川が多く、昔はこれらの自然の障壁によって地域間の自由な交流が妨げられていました。
島根県も中国山地によって東西が分断されており、特に出雲地方は地理的に閉鎖的な環境であったことが、古い時代の言葉や独特の発音(ズーズー弁)が残る一因になったと考えられています。 また、江戸時代には日本各地が「藩」という単位で統治され、藩同士の交流が制限されていました。
この制度も、各地域が独自の言葉を発展させる要因となりました。 島根県は、松江藩が治めた出雲・隠岐と、幕府の直轄地(天領)であった石見とで、政治的にも分かれていました。こうした地理的・歴史的な隔たりが、長い年月をかけて出雲弁、石見弁、隠岐弁というそれぞれの特色ある方言を形作ってきたのです。
【出雲弁】島根県の方言一覧から見る特徴的な言い回し

出雲弁は、島根県の方言の中でも特に知名度が高く、その柔らかくどこか懐かしい響きが多くの人々を惹きつけます。松本清張の小説『砂の器』で、事件解決の重要な手がかりとして登場したことでも有名です。東北方言と似ていると言われることもありますが、独特のイントネーションや語彙を持っており、知れば知るほどその奥深さに気づかされるでしょう。 この章では、出雲弁の代表的な語尾やイントネーション、日常的によく使われる単語、そして実際の会話で使えるフレーズを具体的に紹介していきます。
イントネーションと語尾「~だに」「~けん」
出雲弁の会話を特徴づけているのが、その独特な語尾です。代表的なものに「~だに」があります。これは主に文末に使われ、「~だよ」「~ですよ」といった念押しや伝達の意味合いを持ちます。例えば、「あなたのことが好きだに」というように使われ、どこか温かみと愛嬌を感じさせる響きがあります。 この語尾は、特に女性が使うと可愛らしい印象を与えると評判です。
また、理由や原因を示す接続助詞として「~けん」も頻繁に使われます。これは「~だから」「~なので」という意味で、標準語の「~から」に相当します。 「明日は休みだけん、大丈夫」のように、ごく自然に会話の中に登場します。 これらの語尾は、出雲弁のイントネーションと相まって、独特のリズムを生み出します。動詞の「る」を省略して母音を伸ばす傾向(例:「する」→「すー」)もあり、「僕がすーけん(僕がするからね)」といった言い回しもよく聞かれます。
よく使う単語:「だんだん」「ちょんぼし」「いお」
出雲弁には、標準語にはないユニークで温かみのある単語がたくさんあります。その中でも最も有名で、出雲弁の象徴ともいえるのが「だんだん」です。これは「ありがとう」という意味で、感謝の気持ちを伝える際に使われます。
単に感謝を示すだけでなく、どこかほのぼのとした温かさが感じられる言葉で、出雲地方の人々の人柄を象徴しているかのようです。 次に、「ちょんぼし」という言葉も日常的によく使われます。これは「少し」「ちょっと」という意味です。「ちょんぼし待って(少し待って)」のように使われ、その響きが可愛らしいと人気があります。
さらに、出雲地方では魚のことを「いお」と言います。これは古い言葉が残ったもので、歴史を感じさせる単語の一つです。他にも、元気な様子や健康なことを「まめ」と言ったり(例:「まめなかね?」で「お元気ですか?」)、たくさんあることを「ようけ」や「ごうぎに」と表現したりします。これらの言葉を知っていると、地元の人との会話がよりスムーズで楽しくなるでしょう。
日常会話で使える出雲弁フレーズ集
ここまで紹介した単語や語尾を使って、実際の日常会話で使えるフレーズをいくつか見てみましょう。これらのフレーズを覚えておくと、島根旅行が一層味わい深いものになるかもしれません。
・「ばんじまして、だんだん」
これは夕方の挨拶「こんばんは」と「ありがとう」を組み合わせた表現です。 例えば、お店に入って親切にしてもらった帰り際に「ばんじまして、いろいろお世話になりました、だんだん」のように使うことができます。
・「おちらとしてごさんか?」
「おちらと」は「ゆっくりと、のんびりと」という意味、「~ごさんか」は「~しませんか」という丁寧な誘いの言葉です。 合わせて「ゆっくりしていきませんか?」という意味になります。家庭に招かれた際などに言われるかもしれない、心温まる一言です。
・「そげだに、そげだに」
「そげ」は「そんな、そのような」という意味の指示語で、「そうだね、その通りだね」という同意を示す相槌として使われます。 会話の中で相手の話に頷きながら「そげだに、そげだに」と返すと、とても自然な出雲弁の会話らしくなります。
・「ごめんけど、道を聞いてもええですか?」
「ごめんけど」は「申し訳ないけれど」「すみません」という意味で、人に何かを尋ねたり頼んだりする際に枕詞として使われます。 丁寧な印象を与える便利な言葉です。
【石見弁】島根県の方言一覧で知る力強い響き

島根県の西部に広がる石見地方で話される「石見弁」は、出雲弁ののどかな響きとは対照的に、力強くリズミカルな印象を与える方言です。 地理的に広島県や山口県に近いため、言葉にも共通点が多く見られます。
石見弁は、単に言葉の違いだけでなく、この地方に住む人々の「あっさりしていて、物事をはっきり言う」とされる気質も反映していると言われています。 この章では、そんな石見弁の魅力を、特徴的な語尾や覚えておきたい単語、そして具体的な会話の例文を通して詳しく掘り下げていきます。
語尾に特徴あり!「~けぇ」「~ちゃる」
石見弁を特徴づける要素の一つが、文末に使われる多彩な語尾です。出雲弁の「~けん」に対し、石見弁では「~けぇ」や「~だから」を意味する「~だけぇ」という言い方をします。 例えば、「もう帰るけぇ(もう帰るから)」のように使われ、少し伸ばす音が出雲弁との違いを感じさせます。
また、相手に何かをしてあげる、という時に使う「~(して)ちゃる」という表現も石見弁ならではです。「持ってっちゃる(持っててあげる)」「言うてちゃる(言ってあげる)」のように、親切心や少しお節介なニュアンスを含んだ温かい言葉です。
さらに、「~なさい」という軽い命令や勧めを表す「~んさい」も頻繁に使われます。 「はよ来んさい(早く来なさい)」「食べんさい(食べなさい)」といった具合で、広島弁などでもよく聞かれる言い方です。これらの語尾が、石見弁の持つ独特の力強さと親しみやすさを生み出しています。
覚えておきたい石見弁の単語:「ぶち」「たいぎい」「はよしね」
石見弁には、意味を知らないと驚いてしまうようなユニークな単語が存在します。まず覚えておきたいのが、「ぶち」という言葉です。これは「とても」「すごく」という意味の強調表現で、山口弁や広島弁でも広く使われています。 「ぶち美味い(とても美味しい)」「ぶち疲れた(すごく疲れた)」のように、形容詞の前に付けて使います。
次に、「たいぎい」という言葉も日常会話でよく登場します。これは「面倒くさい」「体がだるい、億劫だ」という意味で、何かをするのが億劫な時に「ああ、たいぎい」と口にします。 そして、最も誤解を招きやすいのが「はよしね」というフレーズです。知らない人が聞くと「早く死ね」と言われたように聞こえてしまいますが、実際は「早くしなさい」と急かす言葉です。
「はよ(早く)+しね(しなさい)」が合わさったもので、決して悪意のある言葉ではありません。これを知っているだけで、石見地方の人とのコミュニケーションでの誤解を避けることができるでしょう。
石見弁を使った日常会話の例文
では、実際に石見弁がどのように使われるのか、会話形式で見ていきましょう。石見地方を訪れた際のシミュレーションとして、ぜひ参考にしてみてください。
Aさん:「まあ、こっち来て、あがりんさい。よう来んさったねぇ」
(訳:まあ、こちらに来て、上がってください。よく来てくださいましたね)
Bさん:「お邪魔します。これ、つまらんもんじゃけど、皆さんで食べんさい」
(訳:お邪魔します。これ、つまらないものですが、皆さんで食べてください)
Aさん:「ありゃあ、わざにすまんねぇ。ぶち嬉しいわ、だんだん」
(訳:あらあ、わざわざすみませんね。とても嬉しいです、ありがとう)
Bさん:「いやいや。ところで、まめなかな?」
(訳:いえいえ。ところで、お元気ですか?)
Aさん:「おかげさんで、なんとかしとるよ。最近、ちょっとけんびきが出とってたいぎいんじゃけどね」
(訳:おかげさまで、なんとかしていますよ。最近、少し疲れからくる肩こりがあって、体がだるいんですけどね)
この会話例からも分かるように、石見弁は一見するとぶっきらぼうに聞こえるかもしれませんが、その言葉の裏には相手を気遣う温かさや親しみが込められています。
【隠岐弁】島根県の方言一覧の中でも特にユニークな言葉

島根半島の北方、日本海に浮かぶ隠岐諸島。この地で話される「隠岐弁」は、本土の出雲弁や石見弁とはまた一味違った、非常にユニークな方言です。 離島という地理的環境が、言葉を独自の形で保存・発展させてきました。
本土との交流はもちろん、古代には大陸との交易もあった歴史的背景から、他の方言には見られない異色のアクセントや語彙が生まれたと言われています。 この章では、そんなミステリアスで魅力あふれる隠岐弁の世界を、その独特なアクセントや特徴的な単語、そして実際の会話フレーズを通してご紹介します。隠岐の人々の暮らしや文化が垣間見える、言葉の旅に出かけましょう。
他の地域と異なる独自のアクセント
隠岐弁を耳にしてまず気づくのが、その独特なイントネーションです。言葉の上がり下がりが本土の方言とは異なり、聞き慣れない人にとっては外国語のように聞こえることさえあるかもしれません。 この独特のアクセントは、隠岐が古くから独自の文化圏を形成してきたことの証しです。
例えば、驚いた時に発する感嘆詞「かっ!!」は、短く強いアクセントが特徴で、隠岐の人々の感情の機微を端的に表しています。 また、同じ隠岐諸島の中でも、島後(どうご)と島前(どうぜん)、さらには島内の各地区によっても言葉のアクセントや言い回しが微妙に異なります。
これは、かつて険しい山によって集落間の移動が困難だった時代に、それぞれの地域で言葉が独自に発展したためです。飲み会の席などで方言の話になると、自分の地区の言葉がスタンダードだと熱く語り合う光景も見られるそうで、言葉に対する人々の愛着の深さがうかがえます。
隠岐ならではの単語:「まい」「げに」「~だっちゃ」
隠岐弁には、本土ではあまり聞かれない古風でユニークな単語が数多く残っています。その代表格が「まい」と「げに」です。「まい」は「大丈夫」や「うまい」といった肯定的な意味で幅広く使われます。
「仕事はうまいもんかや?」と聞かれたら、「仕事は大丈夫かい?」という意味になります。 決して「美味しい仕事か?」と尋ねているわけではないので注意が必要です。一方、「げに」は「本当に」「実に」という意味の副詞で、何かを強調したい時に使われます。
例えば、「げに、おぞい(本当に、恐ろしい)」のように使います。さらに、語尾に「~だっちゃ」が付くのも隠岐弁の可愛らしい特徴の一つです。これは断定や念押しを表す言葉で、親しみを込めて使われます。どこか他の地方のアニメキャラクターを彷彿とさせる響きですが、隠岐では日常的に聞かれる言葉です。これらの単語を知っていると、隠岐の人々との会話がより一層楽しくなること間違いありません。
隠岐弁が学べるフレーズと会話例
それでは、隠岐弁を使った実際の会話フレーズを見ていきましょう。これらの表現を覚えておけば、隠岐の島々を訪れた際に、地元の人々とより深く交流できるかもしれません。
・「こわい、こわい」
隠岐弁で「こわい」は、「疲れた」「しんどい」という意味で使われます。 ホラー映画を見て「恐ろしい」と感じた時ではなく、一日中働いて疲れた時に「ああ、こわいこわい」と口にします。決して何かに怯えているわけではないので、心配する必要はありません。
・「このさん、えーて!」
「このさん」は「この人」という意味です。 そして「えーて」は、若い世代ではあまり使われなくなった言葉かもしれませんが、年配の方が使うことがあります。 文脈によりますが、誰かを指して何かを伝える際に使われる表現です。
・会話例:
Aさん:「いやー、今日はよう歩いたけぇ、こわいわい」
(訳:いやー、今日はよく歩いたから、疲れたなあ)
Bさん:「げに、わしもだ。もう、いなげな道ばっかりで」
(訳:本当に、私もだよ。もう、変な道ばかりで)
Aさん:「ほんなら、どっかでたばこせんか?」
(訳:それじゃあ、どこかで休憩しないか?)
Bさん:「そうしわいや。あそこにお店があるけぇ、寄っていかいや」
(訳:そうしようよ。あそこにお店があるから、寄っていこうよ)
これらの会話から、隠岐弁の持つ独特のリズムと温かさが伝わってくるのではないでしょうか。
島根県の方言一覧で学ぶ!使ってみたくなる可愛い&面白い方言

島根県の方言は、地域ごとの違いだけでなく、その表現の豊かさも大きな魅力です。響きが可愛らしくて思わず真似したくなる言葉や、標準語に訳すと少し意外な意味になる面白い言葉がたくさんあります。地元の人々が日常的に使っているこれらの言葉を知ることで、島根県への理解がさらに深まり、コミュニケーションがもっと楽しくなるはずです。この章では、島根県の数ある方言の中から、特に「可愛い」と評判の言葉や、意味を知ると「なるほど」と唸ってしまうユニークな言葉、そして少しマニアックで方言好きの心をくすぐる言葉をピックアップしてご紹介します。
思わずキュンとする可愛い島根の方言
島根県の方言には、その響きから「可愛い」と評されるものが少なくありません。特に語尾に特徴があり、柔らかく親しみやすい印象を与えます。
・「~だに」
出雲弁で使われる「~だよ」という意味の語尾です。 「好きだに」と告白されたら、その素朴で温かい響きに心を掴まれてしまうかもしれません。
・「~ちょる」
出雲弁などで「~している」という現在進行形を表す言葉です。 「何しちょる?」と聞かれると、その少し舌足らずな響きが可愛らしく感じられます。
・「~(して)ごさんか?」
出雲弁で「~しませんか?」という丁寧な誘いの言葉です。「お茶でも飲んでごさんか?」と優しく誘われたら、断る理由が見つからないかもしれません。
・「おんぼらと」
「穏やかに」「のんびりと」といった意味を持つ出雲弁です。 「おんぼらとした天気」のように使われ、言葉そのものが持つ、ゆったりとした雰囲気が心を和ませてくれます。
これらの言葉は、特に女性が使うと、その魅力がさらに増すと言われています。島根を訪れた際には、ぜひ耳を澄まして探してみてください。
意味を知ると面白いユニークな方言
方言の中には、標準語の感覚で聞くと意味が全く想像できない、面白い言葉がたくさんあります。意味を知ることで、その土地の文化や人々の発想に触れることができます。
・「はしる」
標準語では「走る」という意味ですが、島根県を含む中国地方では「(歯などが)ズキズキ痛む」という意味で使われることがあります。 「歯がはしる」と言われたら、虫歯を心配してあげましょう。
・「たばこする」
喫煙することではなく、「休憩する」という意味で使われます。 農作業などの合間に一服していた習慣から来た言葉で、今でも「ちょっとたばこしようか」は「少し休憩しよう」という意味で使われます。
・「いんのくそ」
非常にインパクトのある言葉ですが、これは「役に立たないもの」「つまらないもの」を指す方言です。 人に対して使うことはあまりありませんが、物の価値を低く言う際に使われることがあります。
・「はっぱくさい」
直訳すると「葉っぱが臭い」ですが、実際の意味は「悪臭がする」です。 直接的ではないユーモラスな表現で、不快な状況を少し和らげる効果があるのかもしれません。
これらの言葉は、知らずに聞くと誤解してしまう可能性もありますが、意味を知れば会話の幅が広がる面白い表現です。
地元の人も驚く?少しマニアックな方言
基本的な方言に慣れてきたら、もう少しマニアックな言葉に挑戦してみるのも一興です。使いこなせれば、地元の人から「お主、できるな」と一目置かれるかもしれません。
・「けんびき」
これは「疲れからくる不調」や「肩こり」などを指す言葉です。 昔の言葉のようですが、今でも年配の方を中心に使われています。「最近けんびきが出てかなわん」のように使います。
・「やっきっき」
じゃんけんをする際の掛け声、またはじゃんけんそのものを指す言葉です。 地域によっては他の言い方もありますが、子どもたちが「やっきっきで決めよう!」と言っているのを聞くと、微笑ましくなります。
・「あばかん」
「手に負えない」「どうしようもない」といった意味で使われます。 「この子のいたずらは、もうあばかんわ」といった具合です。また、「あばかんほど」となると「ありあまるほどたくさん」という意味にもなります。
・「おぞい」
「恐ろしい」という意味ですが、時には「粗末な」「質の悪い」といった意味でも使われます。 「この服はおぞい作りだ」のように、物の出来が悪いことを指して言うこともあります。
これらの言葉は、より深く島根の文化に根差した表現であり、知っていると方言上級者と言えるでしょう。
まとめ:魅力あふれる島根県の方言一覧

この記事では、「島根県の方言一覧」として、県内を代表する「出雲弁」「石見弁」「隠岐弁」の3つの大きな枠組みから、それぞれの特徴、語彙、そして日常で使えるフレーズまでを詳しくご紹介しました。
出雲弁の「だんだん(ありがとう)」や「~だに」といった温かく柔らかな響き、石見弁の「ぶち(とても)」や「~けぇ」といった力強く親しみやすい口調、そして隠岐弁の「こわい(疲れた)」や「げに(本当に)」といった離島ならではのユニークな言葉たち。 これらは単なる言葉の違いではなく、その土地の歴史や風土、人々の気質が色濃く反映された文化そのものです。
「はよしね(早くしなさい)」のように、意味を知らないと驚いてしまうような言葉もありましたが、その裏には相手を思う気持ちが込められていることを知っていただけたかと思います。方言を少し知るだけで、地元の人々との距離がぐっと縮まり、旅や交流が何倍も味わい深いものになります。次に島根県を訪れる際には、ぜひこの記事で覚えた方言を少しだけ使ってみてください。きっと、温かい笑顔と「だんだん」の言葉が返ってくるはずです。