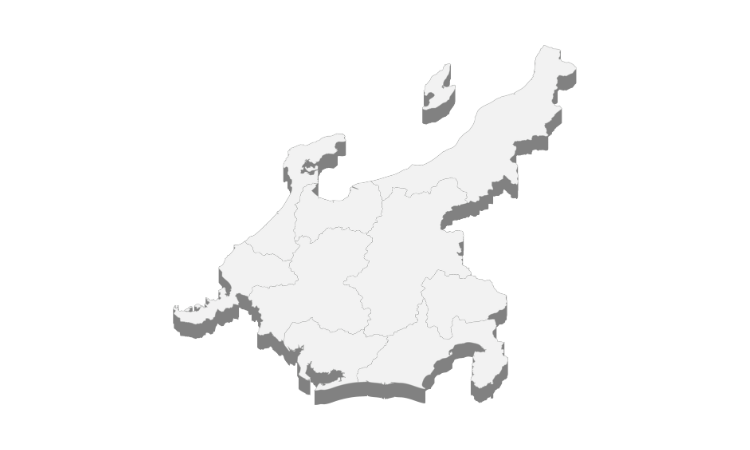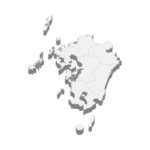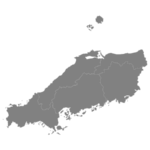「ずく出して、やってみようずら」。長野県を訪れたり、長野県出身の方と話したりしたときに、このような独特の言い回しを耳にしたことはありませんか。標準語に近いと言われることもある長野県の方言ですが、実は「信州弁」とも呼ばれ、親しみやすく、どこか温かみのある言葉がたくさんあります。 しかし、その一方で、南北に広い地形の影響から地域によって言葉が異なり、「同じ長野県民でも話が通じない」なんてことも。
この記事では、そんな魅力あふれる「長野県方言でよく使う」言葉を、初心者の方にもやさしくわかりやすく解説します。日常会話で使える基本フレー正から、思わず「へぇ!」となるような面白い単語、そして知っていると便利な地域ごとの違いまで、詳しくご紹介していきます。この記事を読めば、あなたもきっと長野県の方言が使いたくなるはずです。
日常でよく使う長野県方言の基本フレーズ

長野県の方言、信州弁は、日常のさりげない会話の中に溶け込んでいます。 まずは、あいさつや返事など、コミュニケーションの基本となるフレーズから見ていきましょう。これらを覚えるだけで、地元の人との距離がぐっと縮まるかもしれません。
あいさつで使う方言:「おやすみなさい」の意外な意味
長野県の方言で特徴的なあいさつの一つに「おやすみなさい」があります。 一般的には就寝前のあいさつですが、長野県では、その日に会った人と別れる際に、時間帯を問わず「さようなら」の意味で使われることがあります。 初めて日中に言われると少し驚いてしまうかもしれませんが、これは相手への労いの気持ちが込められた、温かい別れのあいさつなのです。
このほかにも、「おつかいです」という「こんばんは」を意味する方言や、「はーるかぶり」という「お久しぶり」を意味する言葉など、ユニークなあいさつ表現が存在します。 こうした言葉を知っていると、長野県民との会話がより一層楽しくなるでしょう。
返事でよく使う方言:「~ずら」「~だに」の活用法
長野県の方言と聞いて、多くの人が思い浮かべるのが「~ずら」ではないでしょうか。 これは「~だろう」「~でしょう」といった推量や同意を求める意味で使われる代表的な語尾です。 例えば、「明日は晴れるずら」と言えば「明日は晴れるだろう」、「そうずら?」と語尾を上げて尋ねれば「そうでしょう?」と相手に同意を求めるニュアンスになります。
また、「~だに」という語尾もよく使われます。 これは「~ですよ」という意味で、文章の最後につけることで、表現が柔らかく、親しみやすい印象になります。 例えば、「このりんご、美味しいだに」といった形で使われ、会話に温かみを加えてくれます。 これらの語尾を使いこなせると、一気に信州弁らしくなります。
感情を表すときによく使う方言:「てきない」「ごしたい」
疲れた時に使う方言も、長野県では特徴的なものがあります。代表的なのが「てきない」と「ごしたい」です。 「てきない」は、富山県や石川県などでも使われますが、長野県では特に「疲れて苦しい」「身体がつらい」といった、急な疲労感を表す際に用いられます。 例えば、急な坂道を登った後などに「あー、てきない!」というように使います。
一方、「ごしたい」は、より身体的なダメージを伴う慢性的な疲労感を表す言葉です。 「疲れた」の最上級とも言われ、疲れて腰が痛い、足がだるいといった具体的な身体の不調を伴う際に「ああ、ごしたい」と口にします。 この二つの言葉は似ていますが、疲れの種類によって使い分けられており、特に中信地方や諏訪地方でよく耳にする方言です。
よく使う長野県方言【単語編】

信州弁には、標準語にはないユニークな単語がたくさんあります。ここでは、日常の様々な場面でよく使う単語をいくつかピックアップして、その意味や使い方を詳しく見ていきましょう。知っていると、長野県での生活や旅行がさらに面白くなること間違いなしです。
これだけは覚えたい最重要単語:「ずく」
長野県の方言を語る上で絶対に欠かせないのが「ずく」という言葉です。 これは標準語で一言で表すのが非常に難しい方言で、「やる気」「根気」「気力」「面倒くさがらずに何かをする力」といったニュアンスを含んでいます。
例えば、面倒な作業や骨の折れることをやり遂げた人に対して「ずくがあるねぇ」と感心したり、逆に行動に移せない状態を「ずくが出ない」と言ったりします。 また、面倒くさがり屋で、やるべきことをなかなかやらない人のことを「ずくなし」と呼びます。 この「ずく」は、長野県民の気質を表す言葉とも言われ、ローカルテレビ番組のタイトルにもなるほど、地域に深く根付いています。
食べ物に関する方言:「おごっつぉ」「ぼける」
食文化が豊かな長野県には、食べ物に関する独特の方言も存在します。「おごっつぉ」は「ごちそう」を意味する言葉です。 お客様をもてなす際や、お祝いの席などで豪華な食事が並んだ時に「今日はおごっつぉだねぇ」といった形で使われます。響きからも、ごちそうを前にした嬉しい気持ちが伝わってくるような温かい言葉です。
また、果物、特にりんごの生産が盛んな長野県ならではの方言が「ぼける」です。 これは、りんごなどの果物が収穫から時間が経ち、水分が抜けて食感が柔らかく、味が落ちてしまった状態を指します。 例えば、「このりんご、ちょっとぼけてるね」というように使います。新鮮さが失われてしまった少し残念な気持ちを表す、ユニークな表現です。
状態や様子を表す方言:「こわい」「しみる」
長野県では、標準語と同じ言葉でも全く違う意味で使われることがあります。その代表例が「こわい」です。一般的には「恐ろしい」という意味ですが、信州弁では「硬い」という意味で使われます。 例えば、ご飯の炊きあがりが硬かった時に「このご飯、こわいね」と言ったりします。 知らずに聞くと、何が恐ろしいのかと驚いてしまうかもしれません。
もう一つ、冬の寒さが厳しい長野県ならではの表現が「しみる」です。 標準語では「液体が染み込む」や「心に深く感じる」といった意味で使われますが、信州弁では「凍るように寒い」という意味になります。 「今朝はしみるねぇ」と言えば、「今朝は凍えるように寒いですね」という意味になります。厳しい寒さを的確に表した、地域性を感じさせる方言です。
地域で違う?よく使う長野県方言のエリア別特徴

南北に長く、山々に囲まれた長野県は、「方言のるつぼ」と称されるほど、地域によって言葉に違いが見られます。 大きく分けて、北信・東信・中信・南信の4つのエリアに区分され、それぞれが隣接する県の影響を受けながら独自の方言を発展させてきました。 ここでは、各エリアでよく使われる方言の特徴を見ていきましょう。
北信地方でよく使う方言(長野市・飯山市など)
県の北部に位置する北信地方は、新潟県と隣接していることから、越後方言の影響が見られます。 イントネーションは比較的平坦で、落ち着いた話し方が特徴です。
この地域でよく使われる語尾には「~だっぺ」や「~だべ」があり、「~だろう」という意味で使われます。 また、何かをすることを「~すん」と表現することもあります。
特徴的な方言として、「~するしない?」という誘い方があります。 これは「~しませんか?」という意味で、例えば「お茶するしない?」と使います。 他の地域の人からすると「するの?しないの?」と戸惑ってしまうかもしれませんが、北信地方ではごく自然な誘い文句です。
東信地方でよく使う方言(上田市・佐久市など)
群馬県や埼玉県に接する東信地方は、関東地方の方言(西関東方言)に近い特徴を持っています。 挨拶で「おめでとうごあす」のように、丁寧な表現として語尾に「~ごあす」を付けることがあります。
この地域で特徴的なのが、「らっちもねぇ」という言葉です。 これは「くだらない」「つまらない」「どうしようもない」といった意味で使われ、呆れた時や物事がうまくいかない時などに口にします。 甲州弁(山梨県の方言)にも同じ言葉があり、地域的なつながりを感じさせます。
また、佐久地域などでは、推量を表す際に「~べえ」という西関東方言的な言い方をすることもあり、長野県内でも地域による言葉のグラデーションが見られます。
中信地方でよく使う方言(松本市・諏訪市など)
県のほぼ中央に位置する中信地方は、比較的標準語に近いと言われることもありますが、信州弁らしい特徴的な言葉も多く使われています。 このエリアは、安曇、松本、諏訪など、さらに細かい地域に分けられ、それぞれに特色があります。
松本地域周辺では、疲労を表す「てきない」や「ごしたい」がよく使われます。 また、人気があって繁盛しているお店を見て「あの店、盛ってるね」と言ったりします。
諏訪地域では、代表的な語尾「~ずら」が特に頻繁に使われることで知られています。 さらに、甲州弁に近い「~け」という疑問の語尾が使われることもあります。 このように、中信地方はまさにナヤシ方言(長野・山梨・静岡の方言)の典型的な特徴が見られるエリアと言えるでしょう。
南信地方でよく使う方言(飯田市・伊那市など)
愛知県や静岡県に接する南信地方は、西日本の方言に近い特徴が見られるエリアです。 例えば、否定の表現で「行かない」を「行かん」と言ったり、言葉の響きが関西弁のように柔らかい印象を与えることがあります。
この地方でよく聞かれる語尾に「~だら?」があります。 これは「~だよね?」と相手に確認や同意を求める際に使われる言葉です。また、意志や勧誘を表す際に「~まいか」という表現も使われます。
さらに、食事を終えた際の「ごちそうさまでした」を「いただきました」と言うのも南信地方、特に飯田市周辺で見られる特徴的な習慣です。 標準語の「(内定などを)いただく」とは意味が全く異なるため、知っておくと面白い文化の違いです。
知っていると面白い!長野県方言の豆知識

これまで紹介してきた言葉以外にも、長野県の方言には面白いものがたくさんあります。その語源や背景を知ることで、信州弁への理解がさらに深まるでしょう。ここでは、少し変わった方言や、知っているとコミュニケーションが円滑になるかもしれない豆知識をご紹介します。
「とぶ」は走ること!?意外な意味を持つ動詞
長野県で「ちょっと、とんできて!」と言われたら、あなたはどうしますか?ジャンプする準備をしてしまうかもしれませんが、信州弁の「とぶ」は「走る」という意味で使われます。 ですから、この場合は「ちょっと、走ってきて!」という意味になります。
この「とぶ」は、特に急いでいる時や、子どもに指示する際などによく使われる言葉です。陸上競技の短距離走を「とびっくら」と言う地域もあるほど、ごく自然に浸透しています。初めて聞くと驚くかもしれませんが、長野県民にとっては「走る」よりも「とぶ」の方がしっくりくる、勢いのある表現なのかもしれません。
人見知りすることを「わにる」と表現
赤ちゃんや小さい子どもが、知らない人を見て恥ずかしがったり、親の後ろに隠れたりする様子。この「人見知りする」という行動を、長野県では「わにる」という可愛らしい響きの言葉で表現します。
「この子、わにっちゃって」というように、主にはにかんだり臆したりする幼児に対して使われる言葉です。 なぜ「わにる」と言うようになったのか、その語源ははっきりしていませんが、言葉の響きから、少し困りながらも微笑ましく見守っているような温かい視線が感じられます。もし長野県でこの言葉を耳にしたら、人見知りしている子どもの愛らしい姿を思い浮かべてみてください。
「くれる」と「やる」の独特な使い方
長野県では、動詞の「くれる」と「やる」が、標準語とは少し違うニュアンスで使われることがあります。特に、植物に水をあげたり、動物にエサをあげたりする際に「水をくれる」「エサをくれる」といった表現を使います。 標準語では「(私が)~に水をあげる(やる)」となるところを、水やエサをもらう側(植物や動物)の視点に立ったかのような言い方をするのが特徴です。
この表現は広く浸透しており、学校の「水くれ当番」のように、公的な場面でも使われることがあります。 一方で、「やる」という言葉は、親しい間柄で「あげる」という意味合いで使われることがあり、他県の人からは少しぶっきらぼうに聞こえてしまう可能性もあるかもしれません。 このような細かなニュアンスの違いも、方言の面白さの一つです。
まとめ:長野県の方言でよく使う言葉を覚えてコミュニケーションを楽しもう

この記事では、長野県でよく使う方言について、基本的なフレーズから地域ごとの特徴まで幅広くご紹介しました。
信州弁の代名詞ともいえる「ずく」や、特徴的な語尾の「~ずら」「~だに」は、会話に温かみと親しみを加えてくれます。また、「こわい(硬い)」や「とぶ(走る)」のように、標準語と同じ言葉でも意味が全く異なる単語があるのも、長野県方言の面白いところです。
さらに、南北に長い長野県では、北信、東信、中信、南信という4つのエリアで言葉に違いがあり、それぞれが隣接する県の影響を受けながら独自の文化を育んできました。 この地域差を知ることで、長野県という土地の多様性や奥深さをより感じることができるでしょう。
方言は、単なる言葉の違いだけでなく、その土地に暮らす人々の生活や文化、気質が詰まったコミュニケーションの素です。 最初は少し戸惑うかもしれませんが、今回紹介した言葉をいくつか覚えて実際に使ってみることで、長野県の方々との交流がより一層楽しく、心に残るものになるはずです。