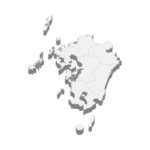大分県で話されている「大分弁」。どこか温かみがあって、一度聞いたら忘れられない魅力的な方言です。この記事では、そんな大分弁の方言一覧を、日常会話で使える面白い言葉から、思わず「かわいい!」と言ってしまうような表現まで、たっぷりとご紹介します。
大分出身の方はもちろん、大分に旅行や出張で訪れる方、方言に興味がある方も、ぜひこの記事を読んで大分弁の奥深い世界に触れてみてください。知っていると、地元の人とのコミュニケーションがもっと楽しくなるかもしれませんよ。
大分弁の基本!知っておきたい方言一覧

大分弁を初めて知る方のために、まずは基本的な言葉からご紹介します。日常の挨拶や感情表現、相づちなど、すぐに使える便利なフレーズを集めました。これらを覚えるだけで、大分県民との距離がぐっと縮まるはずです。
日常でよく使う基本のあいさつ
大分でのコミュニケーションの第一歩は、元気なあいさつから始まります。標準語と大きく変わらない言葉も多いですが、特有のイントネーションや語尾に注目すると、より大分らしさを感じられます。例えば、朝の「おはよう」や昼の「こんにちは」は標準語と同じですが、親しい間柄では語尾が少し変わったり、温かみのある響きになったりします。
「ありがとう」も標準語と同じですが、感謝の気持ちを強く伝えたいときには「しんけんありがとう」と言うこともあります。「ごめんなさい」は「ごめん」や「ごめんね」と短くなることが多いです。別れの挨拶である「さようなら」は、少しくだけた言い方で「さいなら」や「じゃあね」がよく使われます。「おつかれさま」は「おつかれさん」と言うと、より親しみがこもったニュアンスになります。このように、基本的なあいさつでも、大分弁ならではの温かみや親しみやすさが感じられます。
感情を豊かに表現する言葉
大分弁には、感情をストレートに、そして豊かに表現する言葉がたくさんあります。その代表格が「しんけん」と「えらい」です。「しんけん」は「とても」や「すごく」という意味の強調表現で、「しんけん美味しい」「しんけん嬉しい」のように使います。 真剣な気持ちを伝えたいときにもぴったりの言葉です。
一方、「えらい」という言葉には注意が必要です。標準語の「偉い」という意味で使われることもありますが、大分弁では「疲れた」や「しんどい」という意味で使われることが非常に多いのです。「今日の仕事はえらかった~」と言われたら、「大変だったんですね」とねぎらってあげましょう。驚いたときには「たまげた!」や「びびった!」という言葉がよく使われます。 特に「たまげた!」は、目が飛び出るほどびっくりした時に使われる表現です。 これらの言葉を使いこなせると、自分の気持ちをより生き生きと伝えることができ、会話がさらに弾むでしょう。
返事や相づちで使える便利な一言
会話をスムーズに進めるためには、返事や相づちが欠かせません。大分弁にも、会話のリズムを作るのに役立つ便利な言葉があります。肯定の返事である「はい」は、親しい間柄では「うん」となりますが、「そうだね」という同意を示す際には「そうやな」「そうやに」がよく使われます。「よか」や「よかよか」も便利な言葉で、「良い」という意味の肯定的な相づちとして幅広く使えます。
相手の話に「なるほど」と納得したときは「なるほどな」と相づちを打ち、「本当に?」と聞き返したい場合は「ほんとけ?」や「まじけ?」と言います。この「〜け?」という語尾は、大分弁の疑問形の特徴の一つです。また、「大丈夫?」と尋ねられた際に「しゃあねぇな?」と返すこともあります。 このように、短い言葉の中にも大分弁ならではの響きとニュアンスが詰まっており、これらを自然に使えるようになると、より会話が円滑に進むでしょう。
【シーン別】大分弁の方言一覧と使い方

ここでは、買い物や食事、友人との会話といった具体的なシーンで使える大分弁を一覧にしてご紹介します。それぞれの場面に合わせた言葉選びで、より自然なコミュニケーションを目指しましょう。
買い物や食事の場面で使える大分弁
大分県のお店や飲食店で、地元の人々が使う言葉を知っていると、旅の楽しみが一つ増えます。例えば、食堂で「このお味噌汁、うっせーなあ」という言葉が聞こえてきても、悪口ではありません。 これは「味が薄い」という意味で使われる方言です。 逆においしい時は、「うまい!」や「しんけんうまい!」とストレートに表現します。
お店で商品を買うとき、「これをください」は標準語と同じで通じますが、「これをこうてくれん?」と言うと、より地元らしい響きになります。 「こうて」は「買って」という意味のかわいらしい表現です。 また、値段を尋ねる際は「いくらですか?」でももちろん大丈夫ですが、「なんぼですか?」と聞く人もいます。お腹がいっぱいになったら「はらいっぱい」、お店を出る際には「ごちそうさん」と言ってみましょう。こうしたちょっとした方言を使うだけで、お店の人との距離も縮まり、心温まる交流が生まれるかもしれません。
友達との会話で盛り上がる大分弁
気心の知れた友人との会話では、ユニークで味のある大分弁が飛び交います。その中でも特に有名なのが「よだきい」という言葉です。 これは「めんどくさい」「おっくうだ」という意味で、大分県民の気質を表す言葉としてよく知られています。 「宿題するのがよだきい」のように、何かをするのが億劫な時に使います。
また、部屋が散らかっている状態を「しゃあしい」と言ったりもします。友達に「今、何してるの?」と聞きたいときは「なんしよん?」や「なにしよん?」が使われます。これは、動作が進行中であることを示す「〜よん」という語尾を使った表現です。 遊びに誘うときは「遊ぼうや」と気軽に声をかけます。「よだきい」「なんしよん?」といった代表的な大分弁を会話に取り入れることで、友人とのやりとりがより一層楽しくなること間違いなしです。
職場や学校で使える丁寧な大分弁
方言というと、くだけた表現ばかりが注目されがちですが、大分弁にも丁寧な言い方があり、職場や学校などの公的な場面でも使うことができます。基本的には標準語の丁寧語(です・ます調)と同じように話せば問題ありませんが、大分弁らしい柔らかさを加えることも可能です。
例えば、誰かに何かをお願いする時、「〇〇していただけますか?」を少し親しみを込めて「〇〇してくれん?」や、より丁寧に「〇〇してくれんですか?」と言うことができます。相手に許可を求める際も、「〇〇してもよろしいですか?」を「〇〇してええかね?」と尋ねることができます。「〜かね?」は相手の意向を伺う、柔らかい疑問の表現です。このように、語尾や言い回しを少し変えるだけで、丁寧さを保ちつつも、大分弁ならではの温かみのあるコミュニケーションが取れます。ただし、場面や相手との関係性を考えて使い分けることが大切です。
かわいいと評判!胸キュンする大分弁の方言一覧

大分弁には、その響きから「かわいい」と評される言葉が多く存在します。 特に女性が使うと、その魅力が一層引き立つと言われています。ここでは、思わず胸がキュンとしてしまうような、かわいらしい大分弁を集めてみました。
女性が使うと特にかわいい大分弁
大分弁のかわいらしさを象徴するのが、語尾に使われる「〜っち」や「〜ちゃ」です。 例えば、好意を伝えるときに「好きです」と言う代わりに「好きっち」と言うと、一気に愛らしい響きになります。 また、「一緒にいたいな」は「一緒におりたいな」、「会いたいな」は「会いたいな」と、言葉自体は標準語と近くても、そのイントネーションや柔らかな言い方がかわいらしさを生み出します。
少し怒った時の表現でさえ、かわいく聞こえることがあります。例えば「むかつく」を意味する「はらかく」という言葉も、言い方によっては拗ねているような愛嬌が感じられます。また、「かわいいね」と褒めるときに使う「えらしいね」という言葉も、響きがとても優しく、言われた側も嬉しくなる表現です。 このように、大分弁には女性の魅力を引き立てる、かわいらしい言葉がたくさんあります。
語尾につけるとかわいい大分弁
大分弁のかわいさは、特徴的な語尾に秘密があります。 最も有名なのは「〜っち」でしょう。 「そうだっち」(そうだよ)、「知ってるっち」(知ってるよ)のように、断定や同意の文末につけることで、会話全体に明るく親しみやすい雰囲気をもたらします。アニメのキャラクターを彷彿とさせるこの語尾は、大分弁のかわいさの代名詞とも言えるでしょう。
ほかにも、「〜ちゃ」も同様に使われ、「好きっちゃ」(好きだよ)のように、告白の言葉にも使われます。 疑問を表す「〜と?」や「〜ん?」も特徴的で、「何しよんと?」(何してるの?)のように使われ、優しい問いかけのニュアンスになります。「〜だよね」にあたる「〜やろ?」も、相手に同意を求める際に使われる柔らかい表現です。また、軽い命令や促しの際に使う「〜しいや」「〜しよ」(〜しなよ)も、きつい印象を与えず、優しく背中を押すような響きがあります。
恋愛で使えるかもしれない大分弁
ストレートな告白も素敵ですが、大分弁ならではの表現を使うと、より気持ちが伝わり、相手をドキッとさせられるかもしれません。「すごく好きです」という気持ちを伝えるなら、「しんけん好きやに」や「しらしんけん好き!」という表現があります。 「しんけん」という言葉が、真剣な想いを強調してくれます。
「ずっと一緒にいてほしい」という願いは、「ずっと一緒におってくれん?」と問いかける形にすると、相手の気持ちを尊重する優しさが感じられます。「私のこと、どう思ってるの?」と聞きたいときは、「うちのこと、どう思うとん?」と尋ねてみましょう。少し遠回しに「なんでだろう?あなたのことばかり考えてる」と伝えたいなら、「なんでやろう?あんたんことんじょー考えちょん」という表現もあります。 方言での告白は、少し照れくさいかもしれませんが、その素朴さと温かさが、きっと相手の心に響くはずです。
ちょっと面白い?ユニークな大分弁の方言一覧

大分弁には、標準語の知識だけでは意味が全く推測できない、ユニークな単語や表現がたくさんあります。聞いただけでは「どういう意味?」と首を傾げてしまうような、面白くて奥が深い大分弁の世界を覗いてみましょう。
意味が推測しにくいユニークな単語
大分弁には、古語が由来とされる言葉や、独特の変化を遂げた単語が数多く残っています。例えば、「なおす」という言葉。標準語では「修理する」という意味ですが、大分弁や他の九州・関西地方の方言では「片付ける」「しまう」という意味で使われます。 「このお皿、なおしとって」と言われたら、食器棚に片付けてほしいという意味になります。
他にも、「むげねぇ」は「かわいそう」「むごい」、「しゃあしい」は「うるさい」「やかましい」、または「散らかっている」という意味で使われます。「ほうきで掃く」ことを「はわく」、「仲間に入れる」ことを「かたる」と言います。 「かたらんかえ?(仲間に加わらないかい?)」と誘われたら、ぜひ輪の中に入ってみましょう。 このように、意味を知ると納得するものの、初見では戸惑ってしまうような単語の数々が、大分弁の面白さの一つです。
聞き間違いやすい面白い大分弁
大分弁の中には、標準語と同じ響きなのに全く違う意味を持つ言葉があり、時に面白い誤解を生むことがあります。その代表が「えらい」です。前述の通り、これは「偉い」ではなく「疲れた」「しんどい」という意味で使われることが多いです。 知らずに聞くと、文脈が全く分からなくなってしまうかもしれません。
また、「からう」という動詞は、標準語の「辛い」ではなく「背負う」という意味で使われます。「リュックをからう」のように言います。道を尋ねて「あっちに行きよん」と言われた場合、標準語の「あちら」よりも近い距離を指していることもあります。このように、同じ音の言葉でも意味が異なるため、大分県民との会話では文脈をよく聞くことが大切です。こうした聞き間違いも、方言の面白さを体験する良い機会と捉えると、コミュニケーションがより楽しくなるでしょう。
大分県民が思わず笑ってしまう表現
日常的に使っているため、普段は意識していなくても、県外の人から指摘されたり、改めて文字にしてみたりすると、その響きの面白さに気づかされる大分弁もあります。「びびんこ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは「肩車」を意味する、なんとも可愛らしい響きの言葉です。
また、相手を促す際に使う「いってこんかえ」は、「行ってきなさい」という意味です。独特のリズム感があり、親が子に言う時などの温かい光景が目に浮かぶようです。他にも、「どうくっちょん」は「ふざけている」という意味で、言葉の響き自体が少しふざけているようにも聞こえて面白いです。 こうした表現は、大分県の豊かな言語文化を象徴しており、県民の生活に彩りを添えています。
大分弁の地域差と特徴

一口に「大分弁」と言っても、実は県内でも地域によって言葉やアクセントに違いが見られます。 これは、大分県が地理的に広く、隣接する県の文化的な影響を受けてきた歴史があるためです。 ここでは、そうした地域差や、大分弁に共通する文法的な特徴について掘り下げていきます。
県北・県央・県西・県南の地域ごとの違い
大分県の方言は、大きく分けて北部、西部、東海岸部、南部などで特徴が異なります。
・北部(中津市・宇佐市など)
福岡県に隣接しているため、北九州弁の影響が強く見られます。「〜ちゃ」「〜っち」といった語尾は、この地域でもよく使われます。
・西部(日田市・玖珠郡など)
福岡県や熊本県との県境に位置するため、肥筑方言(福岡・佐賀・長崎・熊本などで話される方言)の特徴が見られます。 他の大分県の地域ではあまり使われない、逆接の「ばってん」や、終助詞の「〜ばい」「〜たい」が聞かれることもあります。
・県央(大分市・別府市など)
一般的に「大分弁」として知られている「よだきい」や「しんけん」などの言葉が広く使われている地域です。
・南部(佐伯市・臼杵市など)
宮崎県に近いため、宮崎弁の影響を受けた言葉やイントネーションが特徴的です。
このように、大分県内を移動すると、少しずつ言葉の雰囲気が変わっていくのが分かります。それもまた、大分を旅する上での楽しみの一つと言えるでしょう。
大分弁の文法的な特徴(語尾など)
大分弁を特徴づける要素として、文法、特に助詞や助動詞の使い方が挙げられます。理由を説明する際の接続助詞には、「〜けん」「〜き」がよく使われます。「雨が降ってきたけん、傘持って行こう」のように言います。これは多くの西日本の地域で共通して見られる特徴です。
また、動作の状態を表すアスペクト表現の使い分けも特徴的です。 「雨が降りよる(降りよん)」と言うと、「今、雨が降っている」という進行中の状態を表します。 一方で、「雨が降っちょる(降っちょん)」と言うと、雨が降った結果として「(今も)雨が降っている」という完了・結果の状態を表します。 この微妙なニュアンスの使い分けは、標準語にはない豊かさを持っており、大分弁の表現力を高めています。 疑問を表す終助詞としては「〜か」「〜け」「〜の」などが使われ、文脈によって使い分けられます。
他の九州の方言との比較
大分弁は九州方言の一つである「豊日方言」に分類されますが、他の九州の方言と比べてみると、その独自性がより際立ちます。
例えば、福岡県の博多弁でよく使われる終助詞「〜ばい」「〜たい」や、逆接の「ばってん」は、大分県のほとんどの地域では使われません(日田市などの西部を除く)。 この点が、肥筑方言に属する博多弁と大分弁の大きな違いの一つです。
一方で、熊本弁とは似ている言葉もありますが、やはり微妙な違いがあります。宮崎弁とは、特に県南地域でイントネーションや語彙の面で近い部分が見られますが、「めんどくさい」を宮崎では「ひんだりい」、大分では「よだきい」と言うなど、代表的な方言には違いがあります。
このように、九州という枠組みの中でも、大分弁は中国・四国地方の方言との共通性も指摘されるなど、やや異質な位置づけにあり、独自の発展を遂げてきたことがわかります。
まとめ:大分弁の方言一覧を覚えてコミュニケーションを楽しもう

この記事では、日常の挨拶から、感情表現、かわいい言葉、ユニークな単語まで、様々な角度から大分弁の方言一覧をご紹介しました。大分弁は、単に標準語と違う言葉というだけではなく、その土地の文化や人々の温かい人柄が深く根付いています。特徴的な語尾である「〜っち」や「〜けん」、強調の「しんけん」、そして大分県民の心を表すかのような「よだきい」など、知れば知るほど奥深く、魅力的な言葉の宝庫です。
また、県内でも地域によって言葉に違いがあることも、大分弁の面白さの一つです。今回ご紹介した方言は、ほんの一部にすぎません。ぜひ、実際に大分を訪れて、地元の人々との会話の中で、生き生きとした大分弁に触れてみてください。方言を知ることは、その地域への理解を深め、人々との心の距離を縮めるきっかけになります。この一覧が、あなたのコミュニケーションをより豊かで楽しいものにする一助となれば幸いです。