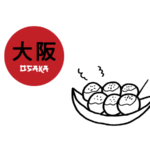大分弁と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?「ちょっと怖そう」「どんな方言かよくわからない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実は大分弁には、日常会話でよく使う親しみやすい言葉や、思わず「可愛い!」と言ってしまいたくなるような魅力的な表現がたくさんあるんです。有名な「よだきい」や「しんけん」はもちろん、語尾につける「~っちゃ」や「~けん」など、知れば知るほど奥深いのが大分弁の魅力です。
この記事では、大分県出身者も納得の、よく使う大分弁をたっぷりの例文とともにご紹介します。この記事を読めば、あなたも大分弁の虜になること間違いなし!大分への旅行や、大分出身の方とのコミュニケーションがもっと楽しくなるはずです。
大分弁でよく使う基本フレーズ!これだけは覚えたい!

大分弁には、日常会話で頻繁に登場する基本的なフレーズがいくつかあります。これらを覚えておくと、大分県民との会話がぐっとスムーズになり、親近感も湧くはずです。まずは、使用頻度の高い代表的な言葉からマスターしていきましょう。
語尾につける特徴的な表現
大分弁の大きな特徴の一つが、文末につく可愛らしい語尾です。 代表的なものに「~っちゃ」「~けん」「~やに」「~ちょん」などがあります。 例えば、「~だよ」という意味で使われる「~っちゃ」は、「明日、一緒に帰るっちゃ」のように使います。
また、「~だから」という意味の「~けん」は、「雨が降ってきたけん、傘がいるよ」という風に使われます。 「~なの」という意味の「~やに」は、「あの映画、しんけんおもしろいんやに」といった形で、柔らかいニュアンスを加えたいときに便利です。
さらに、「~している」という意味の「~ちょん」または「~よる」は、現在進行形や状態の継続を表す際に使われ、「今、何しちょん?」(今、何してるの?)のように日常的に使われます。 これらの語尾を使いこなせると、一気に大分弁らしくなります。
感動や驚きを表す「しんけん」「えらい」
感情を豊かに表現する大分弁もたくさんあります。中でも「しんけん」と「えらい」は、よく使う言葉として覚えておくと便利です。「しんけん」は「とても」「すごく」といった意味の強調表現で、ポジティブなことにもネガティブなことにも使えます。
例えば、「このケーキ、しんけん美味しい!」や「今日のテスト、しんけん難しかった」のように使います。「しんけん」の最上級として「しらしんけん」という言葉もあり、これは「一生懸命」という意味合いが強くなります。
一方の「えらい」は、標準語の「偉い」とは少し異なり、「大変だ」「疲れた」といった意味で使われます。「今日の仕事はえらかった~」と言えば、「今日の仕事は大変で疲れたよ」というニュアンスになります。感動や驚きを表現する際には、「たまげた」という言葉もよく使われます。これは「びっくりした」という意味です。
標準語と少し違う?「なおす」「はわく」
標準語と同じ言葉なのに、大分弁では全く違う意味で使われる単語もあります。その代表例が「なおす」と「はわく」です。「なおす」と聞くと、多くの人は「修理する」という意味を思い浮かべるでしょう。
しかし、大分弁での「なおす」は「片付ける」「元の場所に戻す」という意味で使われます。 「この本、なおしちょって」と言われたら、「この本を片付けておいて」という意味になります。
同様に、「はわく」は標準語の「掃く」と同じ意味で、ほうきでゴミなどを集める行為を指しますが、大分県民にとってはごく自然な日常語です。 このように、標準語と同じ響きでも意味が異なる言葉があるのは、方言の面白いところですね。知らずに聞くと勘違いしてしまう可能性もあるので、覚えておくと役立つでしょう。
否定を表す「~ん」「~ねえ」
何かを否定するときの表現も、大分弁には特徴があります。一般的に、動詞の後に「ん」をつけることで否定形になります。例えば、「行かない」は「行かん」、「食べない」は「食べん」となります。
これは西日本の多くの方言と共通する特徴でもあります。さらに、形容詞や形容動詞の否定では「~ねえ」という語尾がよく使われます。 例えば、「美味しくない」は「美味しくねえ」、「きれいじゃない」は「きれいやねえ」といった具合です。
また、「あるはずがない」といった強い否定を表す際には、「~せん」という言い方もします。 例えば、「そげんこたぁ、あらせん」と言うと、「そんなことは、あるわけがない」という強い否定のニュアンスになります。 これらの否定表現は、日常会話で頻繁に出てくるので、覚えておくと聞き取りやすくなるでしょう。
大分弁でよく使うと可愛く聞こえる?胸キュン方言
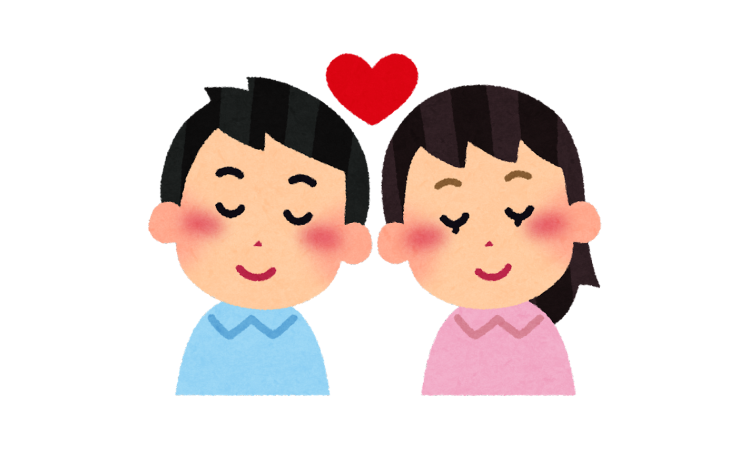
方言女子が注目されるように、地域独特の言葉遣いに「可愛い」と感じる人は少なくありません。大分弁も例外ではなく、その独特の響きや言い回しが、聞く人によってはとても魅力的に感じられることがあります。ここでは、特に可愛いと評判の、よく使う大分弁をいくつかご紹介します。
親しみを込めた「なしか!」
「なしか!」は、「なんで?」「どうして?」という意味で使われる大分弁です。 疑問を投げかける言葉ですが、その響きからか、どこか柔らかく、親しみを込めたニュアンスで聞こえることが多いようです。例えば、友達との会話で「昨日、なんで連絡くれんかったん? なしか!」のように使います。少し拗ねたような、甘えたような響きにも聞こえるため、特に女性が使うと可愛らしい印象を与えるかもしれません。単に理由を問いただすだけでなく、相手へのちょっとした不満や甘えを表現するのにぴったりの言葉です。日常会話で頻繁に登場する言葉なので、大分を訪れた際には耳にする機会も多いでしょう。
甘えた響き?「~っち」
語尾に「~っち」がつくのも、大分弁の可愛い特徴の一つです。 この語尾は、主に「~だよ」や「~ってば」といったニュアンスで使われ、主張や呼びかけを少し柔らかく、そして親しみを込めて伝える効果があります。 例えば、告白の場面で「好きやけん、付き合っちくれんかなぁ」 と言われると、ストレートな言葉の中にも優しさや照れが感じられます。また、友達同士の会話で「もう、はよ行くっち!」のように使うと、少し急かすような場面でも、きつい印象を与えずに伝えることができます。漫画『うる星やつら』のラムちゃんを彷彿とさせる語尾ですが、大分県ではごく自然に使われている日常的な表現です。
優しい響きの「よだきい」
「よだきい」は、大分弁を代表する言葉の一つで、「面倒くさい」「おっくうだ」「疲れた」といった意味で使われます。 標準語の「面倒くさい」に比べると、言葉の響きが柔らかく、どこか気の抜けたような、ほんわかとした印象を与えます。例えば、「あー、今日の宿題、よだきいなー」 といった使い方をします。この言葉の語源は、平安時代の古語「よだけし」(大儀だ、ものうい)とされており、歴史のある言葉でもあります。 大変な状況を口にしているにもかかわらず、どこか憎めない、優しい響きを持つのが「よだきい」の魅力です。宮崎県の一部でも使われる言葉として知られています。
ほんわかする「むげねぇ」
「むげねぇ」は、「かわいそう」という意味で使われる大分弁です。 小さな子供が転んで泣いていたり、動物が寂しそうにしていたりする場面で、「あー、むげねぇなぁ」といった形で使われます。この言葉には、相手への同情やいたわりの気持ちが込められており、聞いていると心が温かくなるような優しい響きがあります。標準語の「かわいそう」よりも、どこか素朴で温かみのある表現に感じられるかもしれません。日常会話の中で自然に出てくる言葉で、大分県民の優しさや情の深さが感じられる方言の一つと言えるでしょう。
思わず笑っちゃう?大分弁でよく使う面白い表現

大分弁には、意味を知らないと首をかしげてしまうような、ユニークで面白い表現もたくさん存在します。標準語に直訳できない独特のニュアンスを持つ言葉や、その言葉が生まれた背景を知ると、より一層面白みが増します。ここでは、そんな大分弁の中でも特によく使う、面白い表現をいくつかご紹介します。
怒っているわけじゃない「いっすんずり」
「いっすんずり」という言葉を聞いて、どんな状況を想像しますか?実はこれ、「渋滞」や「物事が少しずつしか進まない状態」を表す大分弁です。 例えば、道が混んでいて車がノロノロ運転のときに、「うわー、全然進まん。完全ないっすんずりや」というように使います。一寸法師が少しずつ進む様子から来ているのか、その語源は定かではありませんが、言葉の響きがユニークで一度聞いたら忘れられません。渋滞でイライラしている状況でも、この言葉を使うとなんだか少し和んでしまうような、不思議な魅力を持った表現です。
聞き間違いやすい?「ちちまわす」
「ちちまわす」という言葉は、その可愛らしい響きとは裏腹に、「殴る」や「叩く」といった少し物騒な意味を持つ大分弁です。 例えば、親が子供を叱る際に「言うこと聞かんと、ちちまわすど!」のように使われることがあります。
もちろん、本気で殴るというよりは、「こら!」というようなニュアンスで使われることが多いですが、初めて聞く人は意味のギャップに驚くかもしれません。 響きだけで判断すると誤解を招きかねない、大分弁の奥深さを感じさせる言葉の一つです。
食べ物に関するユニークな表現
大分弁には、食べ物に関する面白い表現もあります。例えば、「びっきょ」という言葉。これは「カエル」を意味する方言ですが、地域によっては食用ガエルのことを指す場合もあります。また、「なば」は「キノコ」の総称として使われる言葉です。 スーパーのキノコ売り場を指して「なばコーナー」と呼ぶこともあります。
さらに、「うっせー」という言葉は、標準語の「うるさい」とは全く違い、「まずい」という意味で使われることがあります。 特に県西部で使われる方言で、「この味噌汁、うっせーなあ」と言われたら、味が良くないという意味になります。 このように、食文化と密接に関わったユニークな方言が残っているのも、大分弁の面白いところです。
大分弁の地域差!県内でもこんなに違う?

一口に大分弁と言っても、実は県内でも地域によって言葉やアクセントに違いがあります。 これは、江戸時代に大分県域が複数の小藩に分かれていたため、地域ごとに独自の文化や言葉が育まれたことによると言われています。 大きく分けると、県北、県央、県南、西部(日田・玖珠)の4つのエリアで特徴が見られます。
県北(中津・宇佐)エリアの特徴
中津市や宇佐市を中心とする県北エリアは、福岡県の京築地域(旧豊前国)と文化的なつながりが深く、方言も北九州弁に近い特徴を持っています。 例えば、理由を表す接続助詞として「~けん」の他に「~き」や「~け」が使われることがあります。また、語彙においても福岡県と共通する言葉が多く見られます。アクセントも他の大分県の地域とは少し異なり、より北九州地方のそれに近いと言われています。同じ県内でも、県南の人が聞くと少し違和感を覚えることがあるほど、独特の発展を遂げたエリアです。
県央(大分・別府)エリアの特徴
県庁所在地である大分市や、国際的な観光地である別府市を含む県央エリアは、一般的に「大分弁」としてイメージされる言葉が話されている地域です。テレビなどで紹介される「~っちゃ」や「~よん」「~ちょん」といった特徴的な語尾は、このエリアで広く使われています。交通の要所であり、人の往来が盛んなことから、県内各地の方言が混じり合い、現在のような形になったと考えられます。大分県のタレントである指原莉乃さんなどが話すのも、基本的にはこのエリアの言葉がベースになっていると言えるでしょう。
県南(佐伯・臼杵)エリアの特徴
豊後水道に面した佐伯市や臼杵市を中心とする県南エリアは、海を隔てて四国や宮崎県と隣接しているため、そちらの方言の影響を受けているのが特徴です。 特に宮崎弁と共通する語彙が見られることがあります。例えば、感動詞や語尾などに独特の表現があり、他の地域とは一線を画しています。イントネーションも穏やかで、ゆったりとした話し方をする人が多いと言われています。漁師町が多いこともあり、海の男たちの間で使われるような、威勢のいい言葉遣いが残っている地域もあります。
西部(日田・玖珠)エリアの特徴
日田市や玖珠郡を中心とする県西部エリアは、福岡県や熊本県との県境に位置するため、九州の他の地域の方言、特に肥筑方言の影響を強く受けています。 他の大分県の地域ではほとんど使われない、逆接の接続助詞「ばってん」や、終助詞の「~ばい」「~たい」が使われるのが大きな特徴です。 アクセントも他の地域とは異なり、無アクセントに近い地域もあるなど、非常に個性的です。 このように、同じ大分県内でも、隣接する県や地理的な条件によって、方言に多様なバリエーションが生まれているのです。
もっと知りたい!大分弁をよく使うための豆知識

ここまで、よく使う大分弁のフレーズや地域差について見てきましたが、大分弁の魅力はまだまだ尽きません。ここでは、大分弁のイントネーションの特徴や、大分弁が登場する作品、そしてもっと大分弁を深く知るための方法など、一歩進んだ豆知識をご紹介します。
大分弁のイントネーションの特徴
大分弁のアクセントは、大部分の地域が「外輪東京式アクセント」に分類されます。 これは、標準語のアクセントと比較的近い体系であることを意味します。そのため、単語単体では標準語とあまり変わらないように聞こえることもあります。
しかし、語頭にアクセントが置かれる傾向があるという特徴も指摘されています。 例えば、標準語では平板に発音される「熊(くま)」や「橋(はし)」が、大分弁では「クま」「ハし」のように、最初の音にアクセントが来ることがあります。 この微妙なイントネーションの違いが、大分弁独特の響きを生み出しています。また、文末のイントネーションは、質問でなくても少し上がり気味になることがあり、これが他県の人からは親しみやすく、あるいは少し問いかけるように聞こえる要因かもしれません。
大分弁が登場する作品
大分弁の魅力を知るには、実際に使われているのを聞くのが一番です。実は、アニメや漫画、映画などにも大分弁は登場しています。世界的に人気の漫画『進撃の巨人』の作者、諫山創先生は日田市(旧大山町)の出身で、作中には大分弁を思わせるセリフが登場することがファンの間で話題になりました。
また、お笑いコンビ「パンクブーブー」の佐藤哲夫さんや、「かまいたち」の濱家隆一さんの奥様が話す方言としても知られています。 さらに、大分県出身のタレント、指原莉乃さんや阿部華也子さんがテレビで話す言葉も、大分弁の響きを感じさせてくれます。 こうした作品やメディアを通じて、生きた大分弁に触れてみるのも面白いでしょう。
大分弁を学ぶのにおすすめの方法
この記事を読んで、大分弁にもっと興味が湧いた方もいるかもしれません。大分弁を学ぶ一番の方法は、やはり大分県を訪れて地元の人とたくさん話すことです。温泉地として有名な別府や湯布院だけでなく、県内各地には豊かな自然と温かい人々がいます。
観光地だけでなく、地元の商店街や食堂などに足を運んでみると、活気あふれる本物の大分弁に触れることができるでしょう。また、大分県のローカルテレビ番組やラジオをインターネットで視聴するのも一つの手です。地元の話題やCMには、方言がふんだんに使われています。YouTubeなどの動画サイトで「大分弁」と検索してみるのも良いでしょう。様々な人が大分弁を紹介する動画が見つかり、楽しみながら学ぶことができます。
まとめ:大分弁をよく使うと、もっと大分が好きになる!

今回は、日常会話でよく使う大分弁について、基本的なフレーズから可愛い表現、面白い言葉、そして地域による違いまで、幅広くご紹介しました。一見、とっつきにくいイメージがあるかもしれませんが、「~っちゃ」や「~けん」といった特徴的な語尾や、「よだきい」「しんけん」といった代表的な言葉を知ることで、大分弁が持つ温かみや面白さ、そして奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。
方言は、その土地の文化や歴史、人々の暮らしが詰まった大切な宝物です。 大分弁を少しでも知っていると、大分県を旅したときに地元の人との距離がぐっと縮まったり、大分出身の友人との会話がもっと楽しくなったりするはずです。この記事が、あなたが大分弁、そして大分県そのものに興味を持つきっかけになれば幸いです。ぜひ、実際に大分弁を使ってみて、その魅力を肌で感じてみてください。