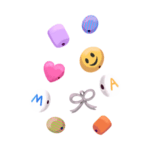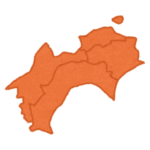香川県で話される讃岐弁は、うどん県ならではの温かみと、どこか懐かしさを感じさせる方言です。この記事では、そんな讃岐弁の魅力を余すところなくお伝えします。まずは、讃岐弁がどのような方言なのか、その基本的な特徴から見ていきましょう。
讃岐弁一覧をチェックする前に、基本的な知識を深めることで、より一層、讃岐弁への理解が深まるはずです。歴史や地域による違いを知ることで、言葉の背景にある文化にも触れることができます。さあ、一緒に讃岐弁の奥深い世界を探検してみましょう。
讃岐弁とは?香川県で話される方言の魅力

讃岐弁(さぬきべん)は、香川県、かつての讃岐国で話されている日本語の方言です。 四国地方の方言に分類されますが、瀬戸内海を挟んで関西地方と近いため、徳島弁と同様に近畿方言の影響を受けているのが特徴です。 そのため、関西弁に似たイントネーションや言葉も多く聞かれます。
しかし、単に関西弁に近いというだけではありません。「~けん」「~やけん」といった中国地方の方言と共通する表現も見られるなど、様々な地域の文化が混じり合って形成された独特の魅力を持っています。
讃岐弁の魅力は、その響きの柔らかさと親しみやすさにあります。 例えば、何かを頼むときに「~してまい」と言う表現は、命令形でありながらも、どこか優しく、相手への配慮が感じられます。また、少しユーモラスな響きを持つ単語も多く、会話を和ませてくれるのも讃岐弁ならではの魅力と言えるでしょう。県外の人が聞くと「かわいい」と感じる表現も少なくありません。
讃岐弁の主な特徴(音韻・文法)
讃岐弁をより深く理解するために、その音や文法の主な特徴を見ていきましょう。
まず音の特徴として、促音便(「っ」の音)と撥音便(「ん」の音)が他の地域に比べてよく使われる傾向があります。 例えば、「おもしろい」が「おもっしょい」、「にぎやか」が「にんぎゃか」または「にっぎゃか」のように変化します。 このような音の変化が、讃岐弁独特のリズム感を生み出しています。また、「アウ」のような母音が連続する「連母音」を避ける傾向も見られます。
文法で最も特徴的なのは、現在進行形を表す「~している」を、動作の継続と状態の継続で使い分ける点です。 具体的には、動作が今まさに行われている場合は「~しよる」、そして動作が終わってその結果の状態が続いている場合は「~しとる」というように区別します。 この使い分けは、他の四国地方の方言にも見られる特徴ですが、讃岐弁を特徴づける重要なポイントです。
さらに、理由を表す接続助詞として「~けん」「~きん」が広く使われるのも大きな特徴です。 これは「~だから」という意味で、日常会話で頻繁に登場します。
讃岐弁の地域による違い(東讃・西讃)
香川県は日本で最も面積が小さい県ですが、その中でも方言には地域差が存在します。 大きく分けると、県の中央部を流れる土器川を境にして、東側の「東讃(とうさん)弁」と西側の「西讃(せいさん)弁」に分けられます。
東讃は高松市やさぬき市などを指し、西讃は丸亀市や観音寺市などを指します。 もちろん、現在では交通網の発達やメディアの影響で東西の差は少なくなってきていますが、語彙や語尾に違いが見られます。
最も分かりやすい違いの一つが、文末に付ける終助詞です。東讃、特に高松市周辺では男女問わず語尾に「~の」を使う傾向があるのに対し、西讃では「~な」がよく使われます。 例えば、「そうだね」は東讃では「そうやの」、西讃では「そうやな」という具合です。
また、瀬戸内海に浮かぶ小豆島や伊吹島では、さらに独自の言葉が使われていることもあります。 小豆島弁は東讃弁がベースですが、関西や中国地方の影響も受けており、伊吹島では古い言葉が残っているなど、同じ香川県内でも多様な方言が存在するのは興味深い点です。
【シーン別】讃岐弁一覧|日常会話で使える基本フレーズ

讃岐弁の基本的な特徴がわかったところで、ここからは具体的なフレーズを一覧で見ていきましょう。日常の様々なシーンで使える基本的な言い回しを知れば、香川県民とのコミュニケーションがもっと楽しくなるはずです。挨拶から感情表現、お願い事まで、実用的なフレーズを例文とともに紹介します。これらの言葉を少し覚えるだけで、香川への旅行や移住の際に、地元の人々とぐっと距離が縮まるかもしれません。
挨拶で使う讃岐弁
日常の挨拶は、コミュニケーションの第一歩です。讃岐弁には、親しみを込めた温かい挨拶表現がたくさんあります。
・なんしょん?
「何をしていますか?」という意味ですが、親しい間柄では「やあ」「元気?」といった軽い挨拶として使われます。 道端でばったり友人に会った時などに「おーい、なんしょん?」と声をかけるのが香川ではおなじみの光景です。会話を始めるきっかけになる便利な言葉です。
・なんがでっきょんな?
これも「最近どう?」「調子はどう?」といった意味で使われる挨拶です。 直訳すると「何ができていますか?」となりますが、相手の近況を尋ねる親しみを込めた表現として使われます。 しばらく会っていなかった友人に会った時などにぴったりの挨拶です。
・ほんだらな
「それじゃあね」「またね」という意味の別れの挨拶です。 関西地方で使われる「ほな」や「ほいなら」と似ており、比較的意味を推測しやすいかもしれません。 友人との会話の最後に「ほんだらな、また連絡するわ」といった形で使います。
これらの挨拶を覚えておくと、香川県民との会話がよりスムーズで温かいものになるでしょう。
気持ちを伝える讃岐弁(嬉しい・怒る・悲しい)
感情を表現する言葉は、方言の個性が特に表れる部分です。讃岐弁にも、喜怒哀楽を豊かに表現するユニークな言葉があります。
・嬉しいとき:「うまげな」
「立派な」「素晴らしい」「良い感じ」といった意味で、ポジティブな感情を表す時に幅広く使えます。 例えば、素敵なプレゼントをもらって「わー、うまげなもん、ありがとう!」と言ったり、物事が順調に進んでいる時に「うまげな話やな」と表現したりします。
・怒るとき:「おらぶ」「どくれる」
「おらぶ」は「大声で叫ぶ」「怒鳴る」という意味です。 「昨日、お父さんにおらばれたわ(昨日、お父さんに怒鳴られたよ)」のように使います。一方、「どくれる」は「すねる」「へそを曲げる」という意味合いで使われます。 「ちょっと注意しただけやのに、すぐどくれるんやから」といった具合です。
・悲しい・つらいとき:「えらい」「たいぎい」
讃岐弁で「えらい」は「偉い」という意味ではなく、「しんどい」「疲れた」という意味で使われます。 「今日は一日中歩き回ってえらかったわ」のように使います。「たいぎい」も同様に「だるい」「面倒くさい」といった、少し気乗りしない、つらい気持ちを表す言葉です。
これらの言葉を知っていると、相手の感情をより深く理解でき、自分の気持ちも豊かに表現できるようになります。
質問やお願いで使う讃岐弁
何かを尋ねたり、お願いしたりする場面でも、讃岐弁ならではの表現があります。丁寧でありながらも親しみやすい言い回しが特徴です。
・質問するとき:「~かいね?」
標準語の「~ですか?」にあたる、丁寧な疑問の表現です。 年配の方がよく使う傾向にありますが、柔らかい響きが特徴です。「このバス、高松駅に行きまかいね?(このバスは高松駅に行きますか?)」のように使います。相手に何かを尋ねる際に、この語尾を使うと、より地元らしい、丁寧な聞き方になります。
・お願いするとき:「~してまい」「~してつか(だ)さい」
「~してまい」は「~しなさい」という意味ですが、命令というよりは「~してね」というような、促しや軽いお願いのニュアンスで使われます。 親が子供に「はよ、宿題してまいよ(早く宿題しなさいよ)」と言ったりします。より丁寧にお願いしたい場合は「~してつかさい」や、さらに丁寧な「~してつださい」を使います。これは「~してください」という意味です。
・値段を尋ねるとき:「なんぼ?」
「いくらですか?」と値段を尋ねる時の言葉です。 これは関西地方でも広く使われているので、馴染みのある人も多いかもしれません。市場や商店で「このお魚、なんぼ?」と聞けば、活気のあるやり取りが楽しめるでしょう。
これらの表現を使いこなせば、旅行先での買い物や道案内を頼む際にも、スムーズにコミュニケーションが取れるようになります。
面白くてユニークな讃岐弁一覧

讃岐弁には、標準語に訳すのが難しい、独特の響きやニュアンスを持つ面白い言葉がたくさんあります。県外の人が聞くと、その意味を想像するだけでも楽しいかもしれません。ここでは、特にユニークで興味深い讃岐弁を、カテゴリーに分けて一覧でご紹介します。食べ物に関するものから、人の様子を表す言葉、そして思わず笑ってしまうような変わった表現まで、讃岐弁の奥深さと面白さに触れてみてください。
食べ物に関する讃岐弁
「うどん県」としても知られる香川県では、食に関するユニークな方言も豊かです。
・お腹がおきる
これは「お腹がいっぱいになる」「満腹になる」という意味で使われる代表的な讃岐弁です。 「起きる」という言葉から、お腹が目を覚ますようなイメージを持つかもしれませんが、全く違う意味で使われます。バイキングなどでたくさん食べた後に「もう、お腹がおきて食べれんわ」というように使います。 広島など中国地方の一部でも使われることがあるようです。
・ぴっぴ
主に幼児言葉として「うどん」を指す言葉です。 小さな子供に「ぴっぴ食べる?」と聞く光景は、香川ではよく見られます。 その可愛らしい響きから、うどんへの親しみが感じられる言葉です。
・たいたん
「煮物」全般を指す言葉です。 関西地方でも使われることがありますが、香川の家庭料理の話をする際には頻繁に登場します。「今晩のおかずは、大根のたいたんやで」といった具合です。
これらの言葉を知っていると、香川の食文化をより深く味わうことができるでしょう。
人の様子や状態を表す讃岐弁
人の性格や様子、体の状態などを表す讃岐弁にも、独特で面白いものがたくさんあります。
・おとっちゃま
「臆病者」「怖がり」という意味です。 「おとっちゃまやのー、暗いところが怖いんか?」のように、少しからかうようなニュアンスで使われることもあります。
・へらこい
「ずる賢い」「要領がいい」といった意味で使われます。 必ずしも悪い意味だけで使われるわけではなく、「あの人はへらこいけん、うまく立ち回るわ」のように、感心した気持ちを込めて使われることもあります。
・ぞろい(ぞろな)
「だらしない」「しまりがない」「不潔な様子」を指す言葉です。 部屋が散らかっている人に対して「あんたは、ほんまにぞろいやな」と呆れたように言ったりします。
・がいな
「強い」「すごい」「乱暴な」といった、程度が甚だしい様子を表す言葉です。 「がいな雨やな(すごい雨だなあ)」「あの人はがいな人や(あの人は豪快な人だ)」など、良い意味でも悪い意味でも使われる便利な言葉です。
これらの表現は、人の特徴を的確に、そしてユーモラスに捉えており、讃岐弁の面白さがよく表れています。
ちょっと変わった面白い表現の讃岐弁
日常の何気ない動作や状況を表す言葉の中にも、標準語にはないユニークな表現がたくさんあります。
・まける(まけた)
標準語では「負ける」ですが、讃岐弁では「(液体が)こぼれる」という意味で使われます。 コップの水をこぼしてしまった時に「あ、まけてしもうた!」と言います。また、「漆にまけてかぶれた」のように「かぶれる」という意味で使われることもあります。
・なおす
これも関西地方と共通ですが、「片付ける」「元の場所に戻す」という意味です。 使った道具を「そこになおしといて」と言われたら、修理するのではなく、片付けるようにしましょう。
・ちみきる
「(爪などで)つねる」という意味の動詞です。 「言うこと聞かんと、ちみきるで!」と、子供を叱る時などに使われることがあります。似た言葉に「ひにしる」もあり、こちらは皮膚をねじるような、より強いニュアンスを持つようです。
・手袋をはく
標準語ではズボンや靴下を「はく」と言いますが、香川では手袋も「はく」と表現することがあります。 これは、全国的にも見られる方言ですが、知らない人が聞くと少し不思議に感じるかもしれません。
これらの言葉は、知れば知るほど面白く、讃岐弁の多様性を感じさせてくれます。
讃岐弁一覧でよく見る有名・かわいい方言

讃岐弁には、その響きの可愛らしさや独特の言い回しから、特に有名になった方言がいくつかあります。テレビドラマや漫画などで耳にしたことがある人もいるかもしれません。ここでは、讃岐弁の中でも特によく知られている表現や、そのイントネーションが「かわいい」と評される言葉をピックアップして、意味や使い方を詳しく解説します。これらの言葉をマスターすれば、あなたも讃岐弁の魅力をもっと深く理解できるはずです。
「~まい」の意味と使い方
讃岐弁を代表する語尾の一つが「~まい」です。これは、主に相手に何かを促したり、軽い命令や提案をしたりする際に使われます。 標準語の「~しなさい」や「~したらどう?」に近いニュアンスですが、より柔らかく、親しみを込めた響きを持つのが特徴です。
例えば、子供に「はよ、寝まいよ(早く寝なさいよ)」と言ったり、友人に「まあ、食べまい(まあ、食べなよ)」と食事を勧めたりする際に使います。 強い強制力はなく、相手への配慮が感じられる優しい表現です。
また、「~しまい」という形でもよく使われます。「行きしまい(行きなさい)」「見しまい(見なさい)」のように、動詞の連用形に接続します。
この「~まい」という語尾は、讃岐弁の温かい人情を表すかのような、優しい響きが魅力です。香川県を訪れた際には、地元の方がこの言葉を使っているのを耳にする機会も多いでしょう。使い方を覚えておくと、より自然なコミュニケーションがとれるようになります。
「~しよる」と「~しとる」の違い
讃岐弁の文法的な特徴として非常に重要なのが、現在進行形を表す「~しよる」と「~しとる」の使い分けです。 これは、県外の人が讃岐弁を学ぶ上で少し混乱しやすいポイントかもしれませんが、意味の違いは明確です。
・「~しよる」:動作の進行中
「~しよる」は、話している今まさにその動作が行われている状態を表します。英語の現在進行形(-ing)に近いイメージです。
(例)「今、弟は宿題をしよる。」→今まさに宿題という動作の真っ最中である。
(例)「雨が降りよる。」→今、空から雨が降っている。
・「~しとる」:動作の結果の状態
一方、「~しとる」は、ある動作が完了し、その結果の状態が続いていることを表します。英語の現在完了形(have+過去分詞)の継続用法に似ています。
(例)「弟は宿題をしとる。」→宿題を終えて、その状態にある。(例えば、もう遊びに行ける状態)
(例)「雨が降っとる。」→雨が降った結果、地面が濡れている状態。(今は降っていなくてもよい)
このように、讃岐弁話者は無意識のうちに「動作」と「状態」を区別して話しています。この違いが分かると、会話のニュアンスをより正確に理解できるようになり、讃岐弁の奥深さを感じることができるでしょう。
イントネーションがかわいい讃岐弁
讃岐弁が「かわいい」と言われる理由の一つに、その独特のイントネーションや語尾が挙げられます。 全体的に言葉の響きが柔らかく、どこか親しみやすい印象を与えます。
・語尾の「~な」「~の」
特に西讃地方で使われる「~な」や、東讃地方の「~の」は、会話の調子を和らげ、かわいらしい雰囲気を醸し出します。 「そうやな(そうだね)」「ええの?(いいの?)」といった相槌は、聞いている側をほっこりさせてくれます。
・「~やけん」
理由を説明する「~やけん(~だから)」も、響きがかわいいと人気の方言です。 好きな相手に気持ちを伝える際に、「好きやけん、付き合ってつかさい」と告白されると、その素朴でまっすぐな響きに心を打たれる人も多いようです。
・全体的に丸いイントネーション
讃岐弁は、関西弁に近い京阪式アクセントを基調としていますが、言葉の端々が少し丸みを帯びて聞こえることがあります。 断定するような強い言い方よりも、相手に問いかけるような、あるいは同意を求めるような柔らかなイントネーションが多く使われるため、全体として優しい印象を与えます。
これらの「かわいい」とされる表現は、讃岐弁の持つ温かさや人懐っこさの象徴と言えるかもしれません。
讃岐弁一覧をさらに楽しむための豆知識

讃岐弁の基本的な言葉やフレーズを知ると、さらにその背景にある文化や、他の地域との関係性にも興味が湧いてくるのではないでしょうか。ここでは、讃岐弁がどのような作品に登場するのか、また、お隣の愛媛県で話される伊予弁とはどのような違いがあるのか、そして讃岐弁をもっと深く学びたい人のためのおすすめの方法についてご紹介します。これらの豆知識を通じて、讃岐弁の世界をより多角的に楽しんでみましょう。
讃岐弁が登場する作品(ドラマ・漫画など)
讃岐弁の響きは、物語に温かみやリアリティを与えてくれます。そのため、香川県を舞台にしたドラマや映画、漫画など、様々な作品で讃岐弁を聞くことができます。
有名なところでは、2023年後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』のヒロイン、笠置シヅ子さんは香川県の出身です。 ドラマの中では主に関西弁が話されていますが、彼女のルーツには東讃の言葉があります。
また、香川県を「うどん県」として全国に広めたPR企画に関連する映像作品や、地元を舞台にした映画『UDON』などでも、ネイティブな讃岐弁の会話がふんだんに盛り込まれています。これらの作品を見ることで、単語だけでなく、実際の会話の中でのイントネーションやリズム、使われるシチュエーションなどを学ぶことができます。
漫画では、香川県観音寺市が舞台となった『結城友奈は勇者である』シリーズが有名です。登場人物たちが話す言葉の端々に讃岐弁のニュアンスが感じられ、ファンにとっては聖地巡礼とともに、方言も楽しむ要素の一つとなっています。
これらの作品に触れることは、生きた讃岐弁を楽しく学ぶ絶好の機会と言えるでしょう。
讃岐弁と他の四国の方言との比較
四国には、香川の讃岐弁のほかに、徳島県の「阿波弁」、愛媛県の「伊予弁」、高知県の「土佐弁」があります。 これらは同じ四国方言に分類されますが、それぞれに特徴があり、聞き比べてみると面白い発見があります。
例えば、お隣の愛媛県で話される伊予弁と比べてみましょう。 讃岐弁と同じく、理由を表す「~けん」を使ったり、「いる」を「おる」と言ったりする点は共通しています。 しかし、アクセントには違いが見られます。讃岐弁が京阪式アクセントの亜種であるのに対し、伊予弁は地域によって京阪式、東京式、さらには一つの音で発音する一型アクセントなど、多様なアクセントが混在しています。
また、語彙にも違いがあります。例えば、伊予弁では「だから」という意味で「ほやけん」という言葉がよく使われますが、これは讃岐弁ではあまり聞きません。 逆に、讃岐弁の特徴である「~まい」のような言い方は、伊予弁では一般的ではありません。
このように、隣接する県の方言でも、似ている部分と全く異なる部分があり、それぞれの地域の歴史や文化の交流のあり方を反映していて非常に興味深いです。
讃岐弁を学ぶのにおすすめの方法
讃岐弁をもっと深く知りたい、話せるようになりたいと思った方のために、いくつかおすすめの学習方法をご紹介します。
・地元の人と積極的に話す
やはり一番の近道は、実際に香川県を訪れて、地元の人々とたくさんコミュニケーションをとることです。うどん屋さんや商店街、地元の居酒屋などで、店員さんやお客さんの会話に耳を傾けてみましょう。勇気を出して、覚えたての讃岐弁で話しかけてみれば、きっと温かく応じてくれるはずです。
・方言スタンプや動画コンテンツの活用
最近では、LINEスタンプにも「日常で使えるかわいい讃岐弁スタンプ」のような、ネイティブが監修したものが登場しています。 日常会話で使いやすいフレーズがまとめられており、楽しく方言に親しむことができます。 また、YouTubeなどの動画サイトで「讃岐弁」と検索すれば、地元クリエイターによる方言講座や、方言を使ったコントなど、様々なコンテンツが見つかります。
・香川県関連のメディアに触れる
地元のテレビ局やラジオ局の番組をインターネット経由で視聴するのも良い方法です。地域のニュースや情報番組からは、日常的に使われている自然な讃岐弁を学ぶことができます。また、前述したドラマや映画などの作品を繰り返し見ることで、リスニング力も向上するでしょう。
これらの方法を組み合わせることで、讃岐弁への理解をより一層深めていくことができるはずです。
まとめ:讃岐弁一覧で知る香川の言葉の奥深さ

この記事では、讃岐弁の基本的な特徴から、日常会話で使えるフレーズ、ユニークな単語まで、幅広く「讃岐弁一覧」としてご紹介してきました。讃岐弁は、単なる言葉のバリエーションではなく、香川県の歴史や文化、そして人々の温かい人柄が色濃く反映された、魅力あふれる方言です。
東讃と西讃での微妙な違い、動作と状態で使い分ける「~しよる」と「~しとる」の表現、そして「~まい」に代表される柔らかい物言いなど、知れば知るほどその奥深さに気づかされます。
はじめは少しとっつきにくく感じるかもしれませんが、一つ一つの言葉の意味を知ることで、香川県民とのコミュニケーションがより円滑になるだけでなく、旅先での体験も一層豊かなものになるでしょう。この記事が、あなたが讃岐弁、そして香川県そのものに興味を持つきっかけとなれば幸いです。ぜひ、覚えた讃岐弁を使って、地元の人々との会話を楽しんでみてください。