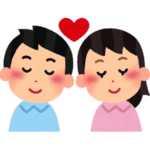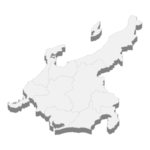埼玉県は東京都に隣接し、長年「東京のベッドタウン」として発展してきました。 そのため、「埼玉に方言はない」「標準語が話されている」というイメージを持つ人が少なくありません。 実際に、さいたま市や川口市などの南部地域では東京の影響が強く、方言を話しているという意識は希薄な傾向にあります。
しかし、実は埼玉県にも地域ごとに根付いた特色ある方言が存在します。 関東地方の中央に位置する内陸県である埼玉は、周辺地域と相互に影響を受けながら、独特の言葉の文化を育んできました。 そのため、埼玉県の方言は「関東地方各地の方言の縮図」と表現されることもあります。
この記事では、そんな埼玉県の魅力あふれる方言を一覧でご紹介します。代表的な言い回しから、地域ごとの違い、そして個性豊かな秩父弁まで、その奥深い世界を一緒に探っていきましょう。
そもそも埼玉県に方言はあるの?

「埼玉県に方言なんてあるの?」と思う方も多いかもしれませんが、答えはもちろん「はい、あります!」。 東京に近い南部では標準語化が進んでいますが、北部や西部、特に秩父地方などでは、今でも日常的に方言が使われています。 埼玉県民自身も、自分が話している言葉が方言だと気づいていないケースも少なくありません。
埼玉県の方言は、言語学的には「西関東方言」に分類されます。 しかし、県内でも地域によって隣接する県の影響を受けているのが特徴です。例えば、東部は栃木弁や茨城弁、北部は群馬弁、西部(入間地域など)は東京の多摩弁との関連性が指摘されています。 このように、様々な地域の影響が混ざり合っている点が、埼玉県の方言の面白さの一つと言えるでしょう。若者世代では使う機会が減りつつある伝統的な方言もありますが、一方で「なにげに」や「かたす」のように、埼玉から広まり若者言葉として定着した言葉も存在します。
大きく分けて2つ!秩父方言と武州方言
埼玉県の方言は、非常に大まかに分けると、県西部の山間地で使われる「秩父方言(秩父弁)」と、それ以外の平野部で使われる「武州方言(埼玉弁)」の2つに大別できます。
「武州」とは、かつての武蔵国(むさしのくに)の別称で、現在の埼玉県、東京都、神奈川県の一部を含む広い地域を指します。その中で話される方言であるため「武州弁」とも呼ばれますが、一般的には「埼玉弁」として知られています。 こちらは東京の言葉の影響を受けつつも、地域ごとに細かな違いが見られます。
一方、「秩父方言」は、四方を山に囲まれた秩父地方で話されている、非常に個性的な方言です。 山梨県の甲州弁や群馬県の方言とも共通点を持ち、埼玉県内の他の方言とは一線を画す古い言葉や独特の表現が多く残っているのが特徴です。 このように地理的な要因から独自の変化を遂げた秩父弁は、埼玉の方言文化の中でも特に興味深い存在です。
地域による微妙な違いとは?東部・西部・北部・南部
「武州方言」と一括りにされる平野部の方言も、実は地域ごとに微妙なバリエーションがあります。 周辺の県と接しているため、それぞれの地域の影響が言葉に反映されているのです。
・東部(春日部市、越谷市など)
茨城県や栃木県と接しているこの地域では、東北方言に近い要素が見られることがあります。 イントネーションや一部の語彙に、東関東方言の特徴が感じられるかもしれません。
・西部(所沢市、入間市など)
東京都の多摩地域と隣接しているため、言葉の面でも関連が強いとされています。 「かたす(片付ける)」のように、多摩地域と共通で使われる方言も見られます。
・北部(熊谷市、行田市など)
群馬県と県境を接しているため、群馬弁の影響を強く受けています。 「~だべえ」といった語尾は、群馬に近い地域でよく使われる表現です。
・南部(さいたま市、川口市など)
東京に最も近く、ベッドタウンとして発展したこの地域では、方言が最も薄まっています。 使われる言葉は共通語に非常に近く、方言を話しているという意識を持つ人は少ない傾向にあります。
これだけは押さえたい!埼玉県の代表的な方言一覧と使い方

埼玉県の方言には、県内で広く使われる特徴的な言い回しがいくつかあります。東京に近く標準語に似ているとはいえ、細かな部分に埼玉らしさが表れます。ここでは、特に代表的な方言をピックアップし、その意味や使い方を例文とともに分かりやすく解説します。これらの言葉を知れば、あなたも埼玉の言葉の魅力に気づくはずです。
語尾が特徴的!「~だべ」「~だんべ」
「~だべ」や「~だんべ」は、埼玉県だけでなく関東地方の広い範囲で使われる代表的な方言の語尾です。 意味としては、標準語の「~だろう」「~でしょう」にあたり、推量や同意を求める際に用いられます。 例えば、「明日は晴れるだろう」と言いたい時に「明日は晴れるだべ」といった形で使います。
この語尾は親しい間柄での会話でよく登場し、温かみのある響きを持っています。 例えば、友人との会話で「あの映画、面白いらしいよ」と伝えた時に、相手が「へぇ、そんなに面白いんだべか」と返したりします。また、何かを提案する際に「そろそろ行くだんべ」のように使うこともあります。 埼玉県内でも特に北部地域、群馬県に近いエリアで頻繁に聞かれる言葉です。 クレヨンしんちゃんの舞台である春日部市が有名ですが、作品中で使われることで全国的に知られるきっかけになったとも言えるでしょう。
親しみを込めて使う「~かい」「~だいね」
「~かい」や「~だいね」も、埼玉の会話で耳にすることがある親しみやすい語尾です。 「~かい」は、標準語の「~ですか?」という疑問を表す表現で、相手に優しく問いかけるニュアンスがあります。例えば、「もうご飯は食べたかい?」のように使われます。秩父地方では「~かぁねぇけぇ(~くはないかい)」のような応用形も存在します。
一方、「~だいね」は、相手に念を押したり、同意を求めたりするときに使われる言葉です。 標準語の「~だよね」「~ですね」に近い意味合いです。会話の中で、「今日の祭りは賑やかだいね」といった形で使われ、話している内容への共感を促す効果があります。これらの表現は、会話の雰囲気を和らげ、相手との距離を縮める役割を果たしています。どちらも少し古風な響きがありますが、年配の方を中心に、今でも地域のコミュニケーションの中で生き続けている言葉です。
ちょっと変わった動詞や名詞の例
埼玉県の方言には、標準語とは異なるユニークな動詞や名詞も存在します。これらは日常生活の中で何気なく使われていることが多く、意味を知ると面白い発見があります。
・おっぺす(押す)
「押す」ことを「おっぺす」と言います。 例えば、「そのボタンをおっぺして」のように使います。これは千葉県などでも聞かれる方言です。
・かたす(片付ける)
「片付ける」という意味で、「かたす」という言葉が使われます。 「部屋をかたしなさい」といった具合です。この言葉は元々、東京の多摩地区や埼玉県南部の方言でしたが、一時期衰退した後、1990年頃から再び埼玉を中心に使われ始め、全国的に広まったという面白い歴史があります。
・あらいまて(食器洗い)
秩父地方などで使われる言葉で、「食器洗い」や「後片付け」を意味します。
・のめっこい(なめらか)
「なめらかだ」や「すべすべしている」という状態を表す形容詞です。 うどんなど食べ物の口当たりや、人の肌などを表現する際に使われます。
・あめんぼー(つらら)
冬にできる「つらら」のことを、埼玉県の一部では「あめんぼー」と呼びます。
これらの言葉は、地域の生活に根差した表現であり、埼玉の文化の一端を垣間見せてくれます。
個性派の響き!秩父地方の方言一覧と特有の表現

埼玉県の中でも、ひときわ個性的な方言が息づいているのが秩父地方です。四方を山々に囲まれた地理的条件が、独自の言語文化を育んできました。 その響きはどこか懐かしく、温かみを感じさせます。ここでは、埼玉県内の他の方言とは一味違う、秩父弁の魅力に迫ります。その成り立ちから特有の言葉、そして独特のリズムまで、詳しく見ていきましょう。
秩父方言の成り立ちと地理的背景
秩父方言、通称「秩父弁」が埼玉県内の他の方言と大きく異なるのは、その地理的な背景に理由があります。 秩父地方は、奥秩父の山々に囲まれた盆地であり、古くから他の地域との交流が限られていました。この地理的隔絶が、外部からの言語的影響を少なくし、古い言葉や独自の変化を遂げた表現が現代まで色濃く残る要因となったのです。
また、秩父は群馬県や山梨県、長野県と隣接しているため、それらの地域の方言との共通点も多く見られます。 特に、山梨県の甲州弁とは似ている点が多く指摘されており、言葉のルーツを探る上で非常に興味深い関係性を持っています。例えば、語尾に使われる「~ずら」は甲州弁でも使われる表現です。このように、秩父弁は埼玉にありながら、周辺の山間地帯と共通の文化圏を形成してきた歴史を持っているのです。荒川を境に東西で言葉に微妙な違いがあるとも言われています。
秩父でよく聞く独特な言葉たち
秩父弁には、標準語話者には意味の推測が難しい、ユニークな単語や語尾がたくさんあります。これらは秩父の人々の暮らしの中で生まれ、受け継がれてきました。
・語尾の「~だに」「~ずら」「~むし」
秩父弁を特徴づける代表的な語尾です。 「~だに」は「~だよ」という断定、「~ずら」は「~だろう」という推量を表します。「そうだむし」は「そうですね」という意味で、丁寧な同意を示す際に使われます。
・こわい(疲れた、きつい)
標準語の「怖い(fearful)」とは全く意味が異なり、「疲れた」「体がだるい、しんどい」という意味で使われます。 例えば、「今日は畑仕事でこわいよ」と言った場合、「仕事が大変で疲れた」という意味になります。
・おかっこ(正座)
「正座」することを「おかっこ」と言います。 小さい子供に「おかっこして座りなさい」と教える際に使われる、可愛らしい響きの言葉です。
・あらいまて(食器洗い)
食事の後片付け、特に食器を洗うことを指します。 「あらいまてしといて」は「食器を洗っておいて」という意味になります。
・ひがっぷしい(まぶしい)
「まぶしい」ことを「ひがっぷしい」と表現します。 「太陽がひがっぷしくて目があけられない」のように使います。
これらの言葉は、秩父の豊かな自然や生活文化を反映した、地域固有の宝物と言えるでしょう。
秩父弁のイントネーションとリズム
秩父弁の魅力は、個々の単語や語尾だけにとどまりません。その独特のイントネーションやアクセント、そして会話全体のリズムも、大きな特徴の一つです。標準語とは異なる音の高低があり、全体的に穏やかで、どこか古風な響きを持っています。
例えば、単語のアクセントが標準語とは異なる場合が多く、それが独特の「なまり」として感じられます。また、会話のテンポは比較的ゆったりとしており、言葉の端々に温かみが感じられることが多いです。秩父音頭の合いの手に出てくる「♪そうとも、そうとも、そうだんべ♪ あちゃ、むし、だんべ、につるし柿♪」というフレーズは、秩父弁のリズム感をよく表しています。 「あちゃ(それでは)」「むし(~ですね)」「だんべ(~でしょう)」といった言葉がリズミカルに使われています。
こうしたイントネーションやリズムは、文字だけでは伝わりにくい部分ですが、実際に秩父の人々の会話に耳を傾けると、その心地よい響きを実感することができます。言葉の音色そのものが、秩父の風土や人々の気質を映し出していると言えるでしょう。
場面別で見る!埼玉の方言一覧・会話シミュレーション

方言は、実際の会話の中で使われてこそ、その魅力が輝きます。ここでは、これまで紹介してきた埼玉県の方言が、どのような場面で、どのように使われるのかを具体的な会話例を通して見ていきましょう。日常の何気ないやりとりから、感情が高ぶった時の一言まで、シミュレーションを通して埼玉の言葉の息遣いを感じてみてください。また、現代の若者たちが方言とどう向き合っているのか、その最新事情にも触れていきます。
日常会話で使ってみよう
友人同士や家族とのリラックスした会話では、埼玉の方言がごく自然に登場します。意識せずに使っていることが多いのも特徴です。
(友人同士の会話)
A:「昨日のサッカーの試合、見たかい?」
B:「見た見た!すごかっただいね。最後のゴールなんて、おったまげたよ。」
A:「だんべ?俺もテレビの前で叫んじゃったよ。それにしても、相手チームのディフェンス、かたかったなあ。」
B:「そうなんよ。でも、よく勝てたよな。これで次の試合も楽しみだべ。」
【解説】
・~かい?:疑問を表す優しい問いかけ。
・~だいね:同意を求める表現。
・おったまげる:非常に驚くこと。
・だんべ?:同意を求める「~だろう?」の意味。
・そうなんよ:「そうなんだよ」が変化した言い方で、相づちとしてよく使われる。
このように、語尾や感嘆の言葉に方言が混じることで、会話に親しみやすさが生まれます。
ちょっと驚いた時、感情を表す一言
感情が動いた時には、思わず方言が口をついて出ることがあります。特に驚きや怒り、感嘆といった強い感情を表す言葉には、地域独特の表現が見られます。
(驚いた時)
「え、あの二人が結婚したって?おったまげたなあ!」
「おったまげる」は「たまげる(驚く)」を強調した言葉で、「ひどく驚いた」というニュアンスです。
(怒っている時)
「何やってんだ、このいごっぱちが!」
「いごっぱち」は「意固地な人」や「頑固者」を指す言葉です。
(あきれた時)
「部屋がささらほうさらになってるじゃないか!早くかたしなさい!」
「ささらほうさら」は「めちゃくちゃ」「散らかった状態」を意味します。 「かたす」は「片付ける」です。
これらの言葉は、標準語で表現するよりも直接的に、そして力強く感情を伝えることができます。日常的に頻繁に使うわけではありませんが、いざという時にその土地ならではの言葉が飛び出すのは、方言の面白い側面です。
若者世代と方言の今
現代の若者たちの間では、伝統的な方言は使われなくなりつつあるのが現状です。 特に東京に近い南部ではその傾向が顕著で、ほとんどの若者が標準語に近い言葉を話します。しかし、方言が完全になくなったわけではありません。
例えば、「なにげに」「かたす」「~じゃね?」といった言葉は、もともと埼玉の方言や若者言葉が発祥とされ、それが東京を経由して全国的に広まった例です。 若者たちは、古い方言とは知らずに、ごく自然にこれらの言葉を使っていることがあります。また、SNSなどでは、あえて方言を使うことで親しみやすさや個性を表現する「方言かわいい」という風潮も見られます。
アニメ『クレヨンしんちゃん』の影響で、「~だゾ」「~だべ」といった言葉に親しみを持っている若者も少なくないでしょう。方言は、古い世代から受け継がれる伝統という側面だけでなく、時代とともに形を変え、新たなコミュニケーションツールとして若者文化の中にも息づいているのです。地域への愛着から、意識的に方言を使おうとする動きもあり、方言の価値は見直されつつあります。
埼玉の方言一覧のまとめ

この記事では、「埼玉県 方言一覧」をテーマに、その特徴や地域ごとの違い、具体的な言葉などを詳しく解説してきました。
「埼玉に方言はない」というイメージとは裏腹に、実際には多様で魅力的な方言が存在することをお分かりいただけたかと思います。 埼玉県の方言は、大きく分けると山間部の「秩父方言」と平野部の「武州方言」に大別され、さらに武州方言も東部、西部、北部、南部で隣接する県の影響を受け、それぞれに微妙な違いがあります。
「~だべ」「~かい」といった関東地方で広く聞かれる表現から、「こわい(疲れた)」「おかっこ(正座)」のような秩父地方独特の言葉まで、その種類は様々です。 これらの言葉は、単なる言葉の違いだけでなく、埼玉の歴史や地理、そして人々の暮らしや文化を映し出す鏡のような存在です。
方言を知ることは、その土地をより深く理解することにつながります。普段何気なく使っている言葉が実は方言だったという発見や、旅先で耳にする温かい響きは、埼玉という土地への親しみを一層深めてくれるでしょう。