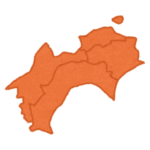「行きしな(いきしな)」「帰りしな(かえりしな)」という言葉を聞いたことはありますか?「行きしなにコンビニ寄ってくれる?」といった形で、日常会話の中で自然と使っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この「行きしな」「帰りしな」という言葉の正確な意味や、どのような場面で使うのが適切なのか、また、その言葉がどこから来たのか(語源)については、あまり知られていないかもしれません。一見すると方言のようにも聞こえるこの言葉ですが、実は奥深い背景を持っています。
この記事では、「行きしな」「帰りしな」の基本的な意味から、具体的な使い方、言葉のルーツである語源、そして似たような意味を持つ類語との違いまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、これらの言葉に対する理解が深まり、より自信を持って使いこなせるようになっていることでしょう。
「行きしな」「帰りしな」の基本的な意味

「行きしな」「帰りしな」は、ある場所へ向かう途中や、ある場所から帰る途中を指す便利な言葉です。日常のふとした瞬間に使われることが多いですが、そのニュアンスを正確に理解することで、コミュニケーションがより円滑になります。ここでは、それぞれの言葉が持つ具体的な意味と、言葉の核となる「しな」の部分について掘り下げていきます。
「行きしな」が指す具体的なタイミング
「行きしな」とは、「行く途中」や「行くついでに」という意味を持つ言葉です。 例えば、家から会社へ向かう道のりの途中、あるいは目的地へ向かう道すがらといった、特定の移動の過程を指します。 ただ単に「行く時」というだけでなく、「目的地に着くまでの間のどこかの時点で」というニュアンスが含まれているのが特徴です。
例えば、「行きしなに郵便局へ寄る」という文を考えてみましょう。これは、目的地へ向かうルートの途中で郵便局に立ち寄ることを意味します。目的地そのものではなく、そこへ至るまでの行動を表す際に非常に便利な表現です。この言葉を使うことで、わざわざ「目的地に行く途中で」と長く説明しなくても、簡潔に意図を伝えることができます。友人との会話で「待ち合わせ場所に行くしなに、飲み物を買っていくね」と言えば、相手はあなたが来る途中で何かを買ってくるのだとすぐに理解できるでしょう。このように、「行きしな」は日常の様々な移動シーンで活用できる言葉なのです。
「帰りしな」が指す具体的なタイミング
「帰りしな」は、「行きしな」の対義語で、「帰る途中」や「帰りがけ」という意味で使われます。 学校や会社、あるいは出かけた先から家など、本来の出発点に戻る道のりの途中を指します。 「帰りぎわ」という意味合いも含まれますが、多くは移動の途中を指して使われることが一般的です。
具体的な使い方としては、「帰りしなにスーパーで牛乳を買ってきて」というような依頼が挙げられます。 この一言で、会社や学校から家に帰るその途中で、スーパーに立ち寄って買い物をしてほしいという意図が明確に伝わります。また、「今日の帰りしなに、本屋で雑誌をチェックしよう」といったように、自分自身の予定を表現する際にも使えます。この場合も、帰宅するルートのどこかで本屋に寄る、という行動を示しています。わざわざ「家に帰る途中で」と説明するよりも、「帰りしな」と表現する方が、より自然で口語的な響きになります。このように、「帰りしな」は、帰路の途中で何かをする際に、その状況を的確に表現できる便利な言葉なのです。
「〜しな」という言葉の正体
「行きしな」や「帰りしな」の「しな」とは、一体何なのでしょうか。これは「〜の時」や「〜のついでに」といった意味を表す接尾語(せつびご)です。 接尾語とは、単語の後ろについて意味を付け加える働きをする言葉の一部です。この「しな」は、動詞の連用形(「行く」なら「行き」、「帰る」なら「帰り」のように、動詞が他の言葉に続く時の形)に付きます。
つまり、「行きしな」は「行く」の連用形「行き」+「しな」で「行く時、行くついで」となり、「帰りしな」は「帰る」の連用形「帰り」+「しな」で「帰る時、帰るついで」という意味になるわけです。この「しな」は他の言葉にも付くことがあり、例えば「寝しな(ねしな)」は「寝ようとするとき」という意味になります。「寝しなに電話が鳴った」のように使われます。 このように、「しな」は特定の動作が行われる、まさにその時や機会を指し示す役割を持っており、日本語の表現の幅を広げてくれる要素の一つと言えるでしょう。
「行きしな」「帰りしな」の正しい使い方と例文

「行きしな」と「帰りしな」の意味がわかったところで、次は実際の会話でどのように使われるのかを見ていきましょう。日常会話で自然に使える例文から、ビジネスシーンでの使用の可否、そして間違いやすい点まで、具体的に解説していきます。これらのポイントを押さえることで、自信を持って使いこなせるようになります。
日常会話で使う「行きしな」の例文
「行きしな」は、友人や家族との気軽な会話で非常によく使われます。移動の途中でのちょっとした用事を伝えたい時に便利で、会話をスムーズに進めることができます。
例えば、友人との待ち合わせ前に次のような使い方ができます。
・「ごめん、少し遅れるかも。行きしなにATM寄ってから行くね」
・「今日のライブ、行きしなにグッズ買っておこうか?」
また、家族との会話では、以下のように使うことができます。
・「学校の行きしなに、駅前のパン屋さんで昼食買っていこう」
・「おじいちゃんの家に行くしなに、お花を買っていきましょう」
このように、「行きしな」を使うことで、「〜へ行く途中で」と回りくどく説明する必要がなくなり、簡潔かつ自然に意図を伝えることが可能になります。 この手軽さが、日常会話で頻繁に使われる理由の一つと言えるでしょう。相手との関係性が近い場面で使うと、より親密なコミュニケーションにつながります。
ビジネスシーンでも使える?「帰りしな」の例文
「帰りしな」は、主に親しい間柄で使われる口語的な表現ですが、状況や相手によってはビジネスシーンでも使うことができます。ただし、非常にフォーマルな場や、目上の方に対して使うのは避けた方が無難でしょう。同僚や親しい先輩・後輩との会話で使うのが適切です。
例えば、同僚に対しては次のように使えます。
・「お疲れ様です。帰りしなに駅前の書店に寄るので、もし何か必要な本があれば買ってきますよ」
・「今日の帰りしな、軽く一杯どうですか?」
もし上司など目上の方に帰る途中の用事を伝える場合は、「帰りしな」よりも「帰宅途中」や「帰りがけ」といった、より丁寧な言葉を選ぶのが望ましいでしょう。
・(上司に対して)「失礼します。帰宅途中に市役所に寄るため、本日はこのあたりで失礼いたします」
このように、ビジネスシーンで「帰りしな」を使う際は、相手との関係性や場面のフォーマルさを考慮することが大切です。言葉遣い一つで相手に与える印象が変わるため、状況に応じた適切な表現を心がけましょう。
間違いやすい使い方と注意点
「行きしな」「帰りしな」は便利な言葉ですが、使い方を間違えると意図が正しく伝わらない可能性があります。注意すべき点の一つは、これらが「移動の途中」を指すという点です。目的地に到着した後の行動や、出発する前の行動に対して使うのは誤りです。
例えば、「会社に着きしなにコーヒーを買う」というのは間違いです。この場合は「会社に着いてからコーヒーを買う」が正しい表現になります。同様に、「家を出るしなにゴミを出す」というのも不自然で、「家を出るときにゴミを出す」とするのが適切です。
また、関西地方などでは「行きしな」を「いきし」と略して使うことがあります。 例えば、「いきしにコンビニ寄ってかへん?」といった具合です。 これは方言的な使い方であり、他の地域では通じない可能性が高いので注意が必要です。 全国的に通じる言葉として使うのであれば、「行きしな」「帰りしな」と略さずに言うのが良いでしょう。これらの言葉は口語的な表現であるため、公的な文書や非常に改まった場面での使用は避けるべきです。場面に応じて、より丁寧な「行きがけに」「帰りがけに」などの言葉と使い分けることが重要です。
「行きしな」「帰りしな」の語源と成り立ち

普段何気なく使っている「行きしな」「帰りしな」という言葉ですが、そのルーツを探ると、日本語の古い形にたどり着きます。言葉の成り立ちを知ることで、なぜこのような意味で使われるようになったのか、その背景への理解が深まります。ここでは、言葉の核心である「しな」の語源や、歴史的な変遷について解説します。
「しな」の語源はどこから?
「行きしな」や「帰りしな」に使われる「しな」の語源については、いくつかの説があります。その一つとして、古い日本語である「しだ」という言葉が変化したという説が挙げられます。 この「しだ」は、万葉集などにも見られる言葉で、「時」や「機会」といった意味を持っていました。 時の流れとともに「しだ」が「しな」へと音が変化し、動詞の連用形に付いて「〜する時」「〜するついで」という意味を表す接尾語として定着していったと考えられています。
また、別の説では、「しな」は「際(きわ)」が変化したもの、あるいは「しながら」の「し」に、場所や時を示す助詞「な」が付いたものとも言われています。いずれの説も、「しな」が「何かをするときの、ちょうどその時」というタイミングを指す言葉であるという点で共通しています。現代では「行きしな」「帰りしな」「寝しな」といった限られた言葉で使われることが多いですが、その背景には日本語の長い歴史が隠されているのです。こうした語源を知ると、普段使っている言葉にも新たな発見がありますね。
古典文学に見る「行きしな」「帰りしな」
「行きしな」「帰りしな」という言葉は、実は江戸時代の文献にもその用例を見ることができます。例えば、1711年に書かれた浮世草子『傾城禁短気(けいせいきんたんき)』には「おかへり品(シナ)の不首尾」という記述があり、これが「帰りしな」の古い用例の一つとされています。 また、1749年の浄瑠璃『源平布引滝(げんぺいぬのびきのたき)』にも「しな」が接尾語として使われている例が見られます。
さらに時代を下って、明治時代の作家・石川啄木の小説『鳥影』(1908年)にも、「帰途(カエリシナ)に買って来た」という表現が登場します。 これらの例から、「帰りしな」という言葉が、少なくとも300年以上前から現代と近い意味で使われていたことがわかります。当時は、現代よりも多くの動詞に「しな」が付いて使われていた可能性も考えられます。古典文学の中にこれらの言葉を見つけると、昔の人々も同じように「帰る途中に〜」といった状況を表現していたのだと、時代を超えた言葉のつながりを感じることができます。
なぜ「〜する途中」という意味になったのか
「しな」がもともと「時」や「際」を意味していたのに、なぜ「〜する途中」という移動の過程を指す意味で定着したのでしょうか。これは、「行く」「帰る」という動詞が持つ性質と深く関係しています。
「行く」「帰る」という行為は、出発点から目的地まで、ある程度の時間と距離を伴う「線」の動きです。一方で、「寝る」という行為は、比較的その場で行われる「点」の動きに近いと言えます。「寝しな」が「寝ようとする、まさにその瞬間」を指すのに対し、「行きしな」や「帰りしな」は、移動という時間の幅がある行為に付くため、その行為が継続している「間」、つまり「途中」という意味合いを自然と帯びるようになったと考えられます。「行く、そのついでに」「帰る、その道すがらに」という感覚が、「行く途中」「帰る途中」という意味として定着したのです。言葉の意味は、結びつく単語の性質によって少しずつ形を変えていく、という好例と言えるでしょう。
「行きしな」「帰りしな」は方言?標準語?

「行きしな」「帰りしな」という言葉を聞いて、「これって方言じゃないの?」と感じる人は少なくないようです。 特に関西地方でよく使われるイメージがあるため、関西弁だと思っている方も多いかもしれません。 しかし、この言葉は本当に方言なのでしょうか、それとも標準語なのでしょうか。ここでは、その使われ方や現在の位置づけについて見ていきます。
「行きしな」「帰りしな」が使われる地域
「行きしな」「帰りしな」という言葉は、特に関西地方で日常的に頻繁に使われることが知られています。 そのため、「関西弁」というイメージが強い言葉です。 しかし、実際には関西だけでなく、三重県、富山県、新潟県、愛知県、広島県など、西日本を中心に広い地域で使われています。
一方で、関東地方など東日本ではあまり使われない傾向があり、意味が通じないこともあります。 このように、使用される地域に偏りがあることが、「方言ではないか?」と思われる大きな理由の一つです。しかし、辞書にも掲載されている言葉であり、完全に「方言」と断定することは難しい側面も持っています。 地域によって使用頻度に差がある言葉、と捉えるのが実情に近いかもしれません。あなたが住んでいる地域では、この言葉は使われているでしょうか?周りの人と話してみると、新たな発見があるかもしれません。
方言だと思われる理由
「行きしな」「帰りしな」が方言だと考えられがちな理由は、主に二つあります。一つ目は、前述の通り、使用される地域に偏りがあることです。特に関西地方での使用頻度が高く、テレビのバラエティ番組などで関西出身のタレントが使っているのを耳にする機会が多いため、「関西弁」という印象が強く根付いています。 関東など、この言葉を日常的に使わない地域の人にとっては、聞き慣れない響きが方言のように感じられるのです。
二つ目の理由は、若い世代での使用頻度が減ってきていることが挙げられます。 もともとは標準語として使われていた言葉でも、時代とともに使われなくなると、一部の地域や世代でのみ使われる言葉として残ることがあります。そうなると、その言葉を知らない世代にとっては、まるで方言のように聞こえてしまうのです。「行きしな」「帰りしな」も、世代によっては「おじいちゃんやおばあちゃんが使っていた言葉」という認識かもしれません。このように、使用地域の偏りと世代間の認知度の差が、この言葉を「方言」だと感じさせる大きな要因となっているのです。
標準語としての現在の位置づけ
では、「行きしな」「帰りしな」は、現在、標準語としてどのような位置づけにあるのでしょうか。結論から言うと、これらの言葉は国語辞典にも掲載されている正式な日本語であり、方言ではありません。 辞書では、「行きしな」は「行くときのついで、ゆきがけ」、「帰りしな」は「帰る途中、帰りぎわ」と説明されています。
しかし、辞書に載っているからといって、誰もが知っている共通語であるとは限りません。現代では、特に若い世代や関東地方などではあまり使われない傾向があるため、「地域や世代によっては通じにくい標準語」と考えるのが実態に近いでしょう。 ビジネス文書やニュースのような改まった場面では「行きがけに」「帰りがけに」といった表現が使われるのが一般的です。一方で、親しい間柄での日常会話では、「行きしな」「帰りしな」という表現が、より口語的で温かみのあるニュアンスを伝えることがあります。方言ではないものの、使う相手や場面を少しだけ選ぶ言葉、と理解しておくと良いでしょう。
「行きしな」「帰りしな」の類語と言い換え表現

「行きしな」「帰りしな」には、似たような意味を持つ言葉がいくつか存在します。場面や伝えたいニュアンスによってこれらの言葉を使い分けることで、より表現の幅が広がります。ここでは、代表的な類語である「行きがけ」「帰りがけ」との違いや、その他の言い換え表現について解説します。
「行きがけ」「帰りがけ」との違い
「行きしな」「帰りしな」と非常によく似た言葉に、「行きがけ(いきがけ)」「帰りがけ(かえりがけ)」があります。 これらはほぼ同じ意味で使うことができ、「行きしな」=「行きがけ」、「帰りしな」=「帰りがけ」と置き換えても、意味はほとんど変わりません。どちらも「〜する途中」という意味を表します。
しかし、ニュアンスにはわずかな違いがあります。「行きしな」「帰りしな」の方が、より口語的で、少し柔らかく親しみやすい響きがあります。そのため、家族や友人とのカジュアルな会話に向いています。一方、「行きがけ」「帰りがけ」は、より一般的で少し改まった印象を与えます。そのため、ビジネスシーンや目上の方との会話では、「帰りしなに寄ります」と言うよりも「帰りがけに寄ります」と表現する方が、より丁寧で適切な印象になるでしょう。どちらも正しい日本語ですが、「しな」はややくだけた表現、「がけ」はより標準的な表現、と覚えておくと使い分けの参考になります。
「行き」「帰り」だけでも意味は通じる?
「行きしな」「帰りしな」をさらにシンプルに、「行き」「帰り」だけで表現することはできるのでしょうか。文脈によっては、意味が通じる場合もあります。例えば、「帰りにコンビニ寄ってきて」と言えば、多くの場合は「家に帰る途中でコンビニに寄ってきて」という意味で伝わるでしょう。
しかし、「行きしな」「帰りしな」が持つ「〜の途中で、ついでに」というニュアンスは少し薄れてしまいます。「帰り」だけだと、帰るという行為全体を指すため、「帰宅した直後に」と解釈される可能性もゼロではありません。「帰りしな」と言うことで、「まだ家に到着していない、移動の過程で」という点がより明確になります。同様に、「行きにパンを買う」と言うよりも、「行きしなにパンを買う」と言った方が、「目的地へ向かうその道中で」というニュアンスが強調されます。簡潔さも大切ですが、意図を正確に伝えたい場合は、「しな」や「がけ」を付けた方が、誤解が生じにくいと言えるでしょう。
状況に応じた言い換え表現のバリエーション
「行きしな」「帰りしな」の言い換え表現は、「行きがけ」「帰りがけ」だけではありません。状況や伝えたい内容に応じて、様々な表現を使い分けることができます。
よりシンプルに表現したい場合は、
・「行く途中に」「帰る途中で」
・「行く道で」「帰る道で」
・「道すがら」
といった言葉が使えます。「道すがら」は少し文学的で、丁寧な響きがあります。
ビジネスメールや改まった文章で使いたい場合は、
・「往路(おうろ)にて」(行く途中)
・「復路(ふくろ)にて」(帰る途中)
といった漢語表現を使うと、よりフォーマルな印象になります。 例えば、「出張の復路にて、支社に立ち寄ります」のように使います。
また、「〜のついでに」というニュアンスを強調したい場合は、
・「行くついでに」
・「帰るついでに」
とそのまま表現することもできます。
このように、同じような状況でも、相手や場面に合わせて言葉を選ぶことで、コミュニケーションはより豊かになります。
まとめ:「行きしな」「帰りしな」の意味を理解して正しく使おう

この記事では、「行きしな」「帰りしな」という言葉について、その意味や使い方、語源、類語などを詳しく解説してきました。
・「行きしな」は「行く途中、行くついでに」、「帰りしな」は「帰る途中、帰りがけに」という意味を持つ。
・言葉の「しな」は、「〜の時、〜のついでに」という意味の接尾語である。
・方言だと思われがちだが、辞書にも載っている標準語。ただし、関西など西日本でよく使われる傾向がある。
・親しい間柄での会話に適した口語的な表現で、改まった場では「行きがけ」「帰りがけ」などを使う方が無難。
「行きしな」「帰りしな」は、移動の途中での行動を簡潔に、そして親しみを込めて伝えることができる便利な言葉です。その背景にある歴史や、地域による使われ方の違いを知ることで、言葉への理解がより一層深まったのではないでしょうか。これからは、ぜひ自信を持って「行きしな」「帰りしな」を使いこなし、日々のコミュニケーションに役立ててみてください。