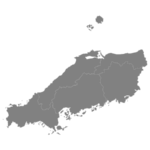「群馬に方言なんてあるの?」と思っている方もいるかもしれません。実は、多くの群馬県民が自分たちの言葉を標準語だと思っていることが多いのです。 しかし、昔ながらの「上州」という呼び名に由来する「上州弁」と呼ばれる、魅力的な方言がしっかりと存在します。
この記事では、「群馬県方言一覧」というキーワードで検索された皆さまのために、群馬県で話される言葉の特徴から、日常で使える具体的なフレーズ、そしてちょっぴり変わった面白い表現まで、やさしくわかりやすく解説していきます。力強くもどこか温かみのある群馬の方言の世界を、一緒にのぞいてみましょう。きっと、この記事を読み終わる頃には、あなたも上州弁の虜になっているはずです。
群馬県方言(上州弁)の基本的な特徴

群馬県で話されている方言は、一般的に「群馬弁」または「上州弁」と呼ばれています。 この方言は、房総弁や埼玉弁などと同じ「西関東方言」に分類されます。 同じ北関東でも、茨城弁や栃木弁は「東関東方言」に属するため、群馬弁とは異なる特徴を持っています。 ここでは、そんな上州弁の歴史や発音、地域ごとの違いについて掘り下げていきます。
上州弁とは?その歴史的背景
群馬県はかつて「上野国(こうずけのくに)」、通称「上州(じょうしゅう)」と呼ばれていたことから、その方言は「上州弁」という名前で親しまれています。 群馬県の言葉は、西関東方言に属しており、東京の言葉と近い部分もありますが、独特の進化を遂げてきました。
特に、群馬県の主要産業であった養蚕との関わりは深く、方言の中にもその名残が見られます。 例えば、カイコに関する言葉が日常的な表現として残っていることがあります。 「お蚕様」を縮めた「おこさま」という呼び方や、繭を作る蚕を「ずー」、作らない蚕を「たれこ」と呼ぶなど、かつての暮らしが言葉の中に息づいているのです。 このように、上州弁は地域の歴史や文化を色濃く反映した、生活に根ざした言葉であると言えるでしょう。
発音やアクセントの特徴
群馬弁のアクセントは、多くの地域で東京式アクセントが用いられており、標準語話者にも比較的理解しやすいとされています。 しかし、東部の館林市や邑楽郡周辺では、栃木県や茨城県の方言に近い無アクセント(単語の音の高低で意味を区別しない)の傾向が見られます。
発音の特徴としては、歯切れが良く、少し早口で勢いがあるように聞こえる点が挙げられます。 そのため、初めて聞く人は「怒っているのかな?」と勘違いしてしまうこともあるかもしれません。 また、「い」と「え」の区別が曖昧になることがあるのも特徴の一つです。さらに、江戸言葉の「べらんめえ調」のように、母音が変化する「母音の転訛」も見られます。 例えば、文の終わりに「〜べえ」という言葉が付くことが多く、これが上州弁の代表的なイメージとなっています。
地域による方言の違い
一口に「群馬弁」と言っても、県内全域でまったく同じ言葉が話されているわけではありません。 群馬県の方言は、大きく分けて以下の3つ、あるいは東部とそれ以外の2つに区分されることがあります。
・北部・西部(山間部)の方言
山に囲まれた地域では、昔ながらの古い言葉が色濃く残っている傾向があります。 例えば、吾妻郡では「来る」の否定形を「こない」「こねえ」と言いますが、他の多くの地域では「きない」「きねえ」となります。
・中部(平野部)の方言
前橋市などを中心とする中部は、都市部に近いこともあり、標準語の影響を受けて比較的共通語に近い表現が使われます。 とはいえ、「〜だんべ」といった上州弁らしい言い回しは日常的に使われており、方言の魅力は健在です。
・東南部(邑楽郡など)の方言
利根川を挟んで埼玉県や栃木県と接する東南部の地域、特に邑楽郡あたりでは、西関東方言と東関東方言の中間的な特徴が見られます。 栃木弁の影響で、語尾に「〜っぺ」という表現が使われることもあり、他の群馬県の地域とは少し違った味わいがあります。
このように、地域によって微妙な違いがあるのも群馬弁の面白さの一つです。
【場面別】群馬県方言一覧(日常会話編)

ここでは、実際の会話で使える群馬弁を場面ごとに分けてご紹介します。挨拶や感情表現など、日常のさまざまなシーンで登場するユニークな言い回しを知れば、群馬県民とのコミュニケーションがもっと楽しくなるはずです。
挨拶や相槌で使う方言
群馬の日常会話では、標準語とは少し違う、温かみのある挨拶や相槌が使われます。例えば、病院や薬局では「お大事にしてください」という意味で「おだいじなさい」という言葉がよく聞かれます。 また、誰かと偶然会った時には「いきあう」という表現を使います。 「昨日、駅前で田中さんと行き会ったよ」のように使えば、すっかり地元民のようです。
相槌のバリエーションも豊かです。最も有名なのが「あーね」で、「ああ、なるほどね」「そうなんだ」といった意味合いで非常に広く使われます。 会話の中でとりあえず「あーね」と返しておけば、会話がスムーズに進むことも多い便利な言葉です。 さらに、同意や納得を示す際には「そうだんべ」「そうだいね」といった表現も頻繁に登場します。 「だんべ」は強い同意、「だいね」はもう少し柔らかい相槌として使われることが多いです。
感情を表現する方言
驚きや喜び、怒りといった感情を表す言葉にも、上州弁ならではの表現がたくさんあります。非常に、すごく、とても、といった強調を表す言葉として「なっから」があります。 「このケーキ、なっからうまい!」(このケーキ、すごくおいしい!)のように使います。
また、大変なことや面倒なことを指して「おおごと」と言ったり、どうにも始末が悪い、手がかかるといった状況を「もちゃつけ」と表現したりします。 驚いた時や感心した時には、「まーず」という言葉が口をついて出ることもあります。「まーず、よくできたいね」(まあ、よくできているね)といった具合です。心配ない、大丈夫だよ、と相手を安心させたい時には「あんじゃーねー」という頼もしい一言が使われます。 これらの言葉を使いこなせれば、感情のニュアンスがより豊かに伝わるでしょう。
日常の動作や状態を表す方言
日常生活の中での何気ない動作や状態を表す言葉にも、群馬ならではのユニークなものがたくさんあります。例えば、「片付ける」ことを「かたす」と言います。 「この部屋、早くかたしてちょうだい」というように使われます。また、「かき混ぜる」ことは「かんます」と言い、料理の場面などでよく耳にする言葉です。
物を「捨てる」ことを「ぶちゃる」または「なげる」と言います。 これは県外の人が聞くと誤解しやすい方言の代表格で、「そのゴミ、なげといて」と言われて、本当に投げてしまわないよう注意が必要です。また、「押す」ことを「おっぺす」と言ったりもします。 疲れてだるい状態や、気分がすぐれないことを「こわい」や「きいがわりい」と表現することもあります。 この「こわい」は恐怖を感じる意味ではないため、初めて聞くと少し驚くかもしれません。
【品詞別】群馬県方言一覧(単語編)

ここでは、名詞、動詞、形容詞といった品詞(言葉の種類)ごとに、特徴的な上州弁の単語を一覧で見ていきましょう。標準語とは意味が異なる単語や、独特の響きを持つ言葉など、上州弁の語彙の豊かさに触れてみてください。
名詞でよく使われる方言
上州弁には、標準語とは異なる意味で使われる名詞や、独特の単語が存在します。例えば、ザリガニのことを「エビガニ」と呼びます。 これは県内で広く使われている呼び名です。また、家の敷地への入り口を「けえど」、家屋の玄関を「とぶぐち」と言ったりします。
少し変わったものでは、クワガタムシを「おにむし」と呼ぶことがあります。 また、体の部位を表す言葉にも特徴があり、顎(あご)を「あぐ」と言ったりします。 人を指す言葉もユニークで、「男たち」を「おとこし」、「女性たち」を「おんなし」や「おんなのしゅう」と表現します。 このように、日常的に使われる名詞の中に、地域独自の言葉が息づいているのがわかります。知っていると、地元の人との会話がより一層深まるかもしれません。
動詞・形容詞で特徴的な方言
動詞や形容詞には、上州弁の魅力が詰まった言葉が多くあります。例えば、動詞では「来る」の否定形として「きない」という言い方が広く使われます。 「彼はまだきないね」(彼はまだ来ないね)のように使います。また、「作る」ことを「こさえる」や「こしゃう」と言ったり、「茹でる」を「うでる」と言ったりします。
形容詞では、「疲れた、だるい」という意味で「こわい」という言葉が使われます。これは「恐ろしい」という意味ではないので注意が必要です。 また、「面倒だ」という意味で「よいじゃあねぇ」という表現があります。 「だらしない、不衛生だ」といった意味合いで「びしょったねえ」という言葉も使われます。 さらに、「気さくだ、さっぱりしている」という性格を表すのに「さくい」という形容詞が使われることもあります。 これらの言葉は、感情や状態の微妙なニュアンスを伝えるのに役立ちます。
独特な言い回しや語尾
上州弁を最も特徴づけているのが、文末に付けられる独特な語尾です。最も有名なのが、推量や同意を意味する「〜だんべ」または「〜べえ」でしょう。 「行くだんべ」(行くだろう/行こうよ)のように使われ、上州弁の代名詞的な存在です。 これと似た表現で、より柔らかい同意を示す「〜だいね」もよく使われます。
また、「〜なんだ」という意味で「〜なんさ」という語尾も頻繁に登場します。 「昨日、高崎に行ったんさ」のように、自分の行動を説明する際によく使われます。 この「さ」は、時に「さぁ」と強く発音され、他県の人には少し耳慣れないかもしれません。 さらに、相手に問いかける時には「〜かい?」という語尾が使われることもあります。 「元気かい?」のように、親しみを込めた温かい響きが特徴です。 これらの語尾を覚えるだけで、ぐっと上州弁らしい話し方になります。
群馬県方言の面白い使い方・ユニークな表現
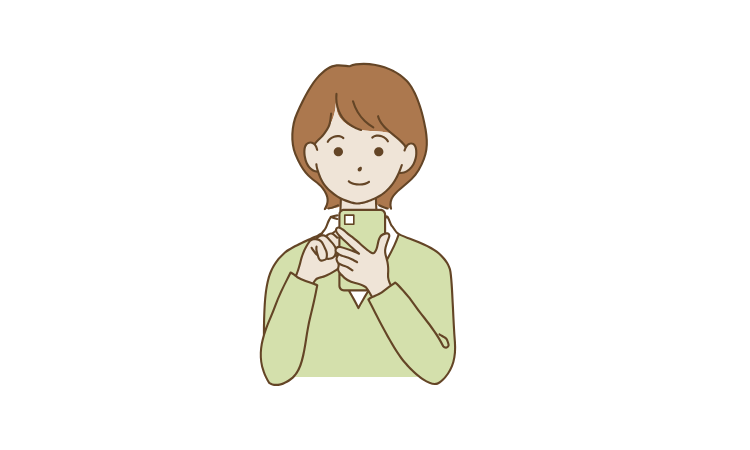
上州弁には、標準語に慣れた耳には新鮮に、時には誤解を招くほどユニークに聞こえる表現があります。ここでは、そんな面白い方言や、現代における使われ方、そして群馬の文化に根付いた方言の例をご紹介します。
県外の人が聞くと誤解しやすい方言
上州弁には、県外の人が文字通りに受け取ってしまうと、とんでもない誤解を生む可能性のある言葉がいくつか存在します。その代表格が「なげる」です。標準語では「投げる」ですが、上州弁では「捨てる」という意味で使われます。 そのため、「このゴミ、なげといて」と頼まれたら、ゴミ箱に捨ててあげるのが正解です。間違っても遠くに放り投げてはいけません。
同様に、「車、うらに回しといて」と言われた場合も注意が必要です。ここでの「うら」は建物の裏手ではなく、「後ろ」を指す言葉として使われることがあります。つまり、「車を(少し)後ろに下げておいて」という意味になります。また、「この漬物、こわいね」と言われても、決して漬物があなたを怖がらせているわけではありません。これは「(歯ごたえが)硬いね」という意味で使われています。 このように、意味を知らないと会話が成り立たなくなる可能性もあるため、覚えておくと役立つでしょう。
若者言葉と混ざり合う現代の上州弁
伝統的な方言である上州弁も、時代と共に変化しています。特に若い世代の間では、昔ながらの方言と現代的な若者言葉が融合した、新しい言い回しも生まれています。例えば、相槌で使われる「あーね」は、もともと群馬弁ですが、その使いやすさから若者を中心に全国的に広まりつつある言葉の一つです。
また、SNSなどでは、群馬県を指すインターネットスラングとして「グンマー」という言葉が使われることがあります。 これは、群馬県を少し面白おかしく表現する際に用いられる言葉で、若者の間では親しみを込めて使われることもあります。 このように、伝統的な方言が新しい文化と結びつきながら形を変えていく様子は、言葉が生きている証拠と言えるでしょう。昔ながらの「〜だんべ」と、現代的な言い回しが共存しているのが、今の群馬弁の面白いところです。
上州弁が使われるメディアや作品
群馬県民のアイデンティティともいえる「上毛かるた」には、上州弁そのものが登場するわけではありませんが、その読み札の内容は群馬の歴史や文化に深く根ざしており、県民の心に刻まれています。このかるたを通して、子供たちは自然と郷土への愛着を育んでいきます。
また、メディアで群馬が舞台になる際、登場人物が話す言葉はしばしば注目されます。2005年に放送されたNHKの連続テレビ小説「ファイト」は群馬が舞台でしたが、登場人物が話す言葉が標準語に近かったため、地元では「もっと方言を使ってほしかった」という声も聞かれました。 これは、県民がいかに自分たちの言葉に愛着を持っているかの表れと言えるでしょう。地元のラジオやテレビ番組、ローカルなキャラクターなどが話す言葉に耳を傾けてみると、生き生きとした上州弁に触れることができます。
群馬県方言一覧をさらに深く知るために

この記事で紹介した以外にも、群馬の方言にはまだまだ奥深い世界が広がっています。もし、あなたが上州弁にもっと興味を持ったなら、次のような方法でさらに知識を深めることができます。
方言を学ぶのにおすすめの方法
上州弁を最も効果的に学ぶ方法は、やはり実際に群馬県を訪れ、地元の人々と会話をしてみることです。草津や伊香保といった温泉地、あるいは地元の商店街などで、人々の日常会話に耳を傾けてみてください。教科書には載っていない、生きた方言に触れることができるでしょう。
また、群馬県出身の友人がいれば、積極的に方言で話してもらうのも良い方法です。最初は聞き慣れないかもしれませんが、次第にその響きやリズムに親しみが湧いてくるはずです。もし身近にそうした機会がない場合は、方言を紹介するウェブサイトや書籍を活用するのも有効です。 特に、例文や音声付きで解説しているサイトは、イントネーションや使い方を理解するのに大いに役立ちます。
方言を守り伝える地域の取り組み
多くの方言がそうであるように、上州弁もまた、話者の高齢化や若者の県外流出などにより、その継承が課題となっています。しかし、地域ではその文化的な価値を認識し、守り伝えようとする動きも見られます。
例えば、地域の学校教育の中で方言を取り上げたり、地元の郷土史研究会などが方言の採集や記録を行ったりする活動があります。また、「上毛かるた」のように、遊びを通して自然と地域の言葉や文化に親しむ機会も、方言の継承に間接的に貢献していると言えるでしょう。 方言は、単なるコミュニケーションの道具ではなく、その土地の歴史や人々の暮らしを映す文化遺産です。こうした地域の地道な取り組みが、上州弁の魅力を未来へとつないでいくのです。
群馬県民とのコミュニケーションで方言を使う際のポイント
もしあなたが群馬県民と話す機会に、覚えたての上州弁を使ってみようと思うなら、いくつか心に留めておくと良い点があります。まず、完璧な発音や使い方にこだわりすぎないことです。少し間違っていても、相手の言葉に興味を持ち、使ってみようとする姿勢は、きっと好意的に受け取られるでしょう。
特に「あーね」や「〜だいね」といった相槌は、自然に会話に挟みやすく、おすすめです。 相手との距離を縮めるきっかけになるかもしれません。ただし、いきなり「おめー」のような二人称を使うのは、相手との関係性によっては失礼にあたる可能性があるので避けた方が無難です。 大切なのは、方言をリスペクトする気持ちです。上州弁をきっかけに、コミュニケーションを楽しみ、群馬の文化への理解を深めていってください。
群馬県方言一覧で知る上州弁の魅力まとめ

この記事では、群馬県の方言、通称「上州弁」について、その特徴から具体的な単語、面白い表現までを「群馬県方言一覧」として詳しく解説してきました。
上州弁は、関東方言の一つでありながら、「〜だんべ」や「〜なんさ」といった独特の語尾、そして「なげる(捨てる)」や「こわい(疲れた)」のような標準語とは異なる意味を持つ単語など、たくさんの魅力にあふれています。 また、地域によって微妙な違いがあることも、その奥深さを示しています。
多くの県民は自分たちが方言を話している自覚がないと言いますが、その言葉の端々には、養蚕が盛んだった歴史や、力強くも温かい県民性がにじみ出ています。 この記事を通じて、単なる言葉のリストとしてだけでなく、群馬の文化や人々の暮らしを感じるきっかけとなれば幸いです。ぜひ、実際に群馬を訪れた際には、生き生きとした上州弁に耳を傾けてみてください。