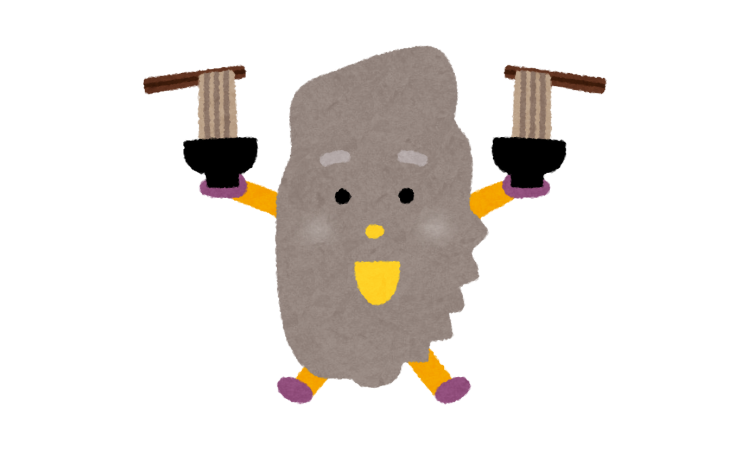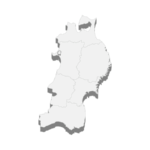広大な面積を誇る岩手県は、その広さゆえに地域ごとに特色ある文化が根付いています。言葉もその一つで、「岩手の方言」と一括りにはできないほど、実に多様な方言が存在します。NHKの連続テレビ小説『あまちゃん』で一躍有名になった「じぇじぇじぇ」という驚きの表現は、多くの人の記憶に新しいでしょう。
しかし、それは岩手の方言のほんの一部にすぎません。県北、県南、沿岸部では言葉の響きや使われる単語、イントネーションも異なります。 この記事では、そんな奥深い岩手の方言の世界を、地域ごとの特徴から日常で使えるフレーズ、さらには言葉の背景にある歴史や文化まで、やさしくわかりやすく解説していきます。あなたもきっと、岩手の方言が持つ温かみや面白さの虜になるはずです。
岩手の方言の全体像と地域による違い

岩手県と聞くと、多くの人が「じぇじぇじぇ!」という方言を思い浮かべるかもしれません。 しかし、実は岩手県の方言は、この一つの言葉だけでは語り尽くせないほど、豊かで多様な世界を持っています。 広大な県土を持つ岩手では、歴史的な背景や地理的な条件によって、地域ごとに異なる言葉が育まれてきました。 ここでは、なぜ岩手の方言がこれほど多様なのか、そして具体的にどのような地域差があるのかを見ていきましょう。
なぜ岩手県は方言が多様なの?その地理的背景
岩手県の方言が多様である大きな理由の一つに、その広大な面積と地理的な特徴が挙げられます。岩手県は、北は青森県、西は秋田県、南は宮城県と接しており、東は太平洋に面しています。内陸部には雄大な北上山地が南北に走り、この山地が自然の障壁となって、地域間の交流をある程度隔ててきました。
特に、交通が不便だった時代には、内陸部と沿岸部、あるいは県北と県南とでは人々の往来が限られていました。 その結果、それぞれの地域で独自の言葉が育まれ、維持されてきたのです。例えば、沿岸部の宮古市で話される方言は、口をあまり大きく開けずに話す特徴があるとされていますが、これは寒い気候に適応した結果ではないか、とも言われています。 このように、地理的な隔たりや気候風土が、各地域の方言に独特の色彩を与えているのです。
大きく分けて4つ?内陸と沿岸の方言区分
岩手県の方言は、専門家の間でも様々な分け方がされていますが、一般的に大きく4つのエリアに区分されることがあります。
- 中部方言地区:盛岡市を中心としたエリアで、純粋な南部領の方言が話されています。
- 北部方言地区:青森県や秋田県と隣接しており、これらの方言の影響を強く受けたエリアです。
- 沿岸方言地区:太平洋に面した地域で、内陸とはまた違った特徴を持つ方言が使われています。
- 南部方言地区(県南方言):旧伊達藩の領地だった地域で、仙台弁などに近い伊達方言が話されています。
このように、同じ岩手県内でも、内陸部と沿岸部、さらに内陸部の中でも地域によって言葉が異なります。 例えば、沿岸部で「ありがとう」を意味する「おおきに」という言葉は、他の地域ではあまり使われません。 交通網が発達した現代でも、こうした地域ごとの言葉の違いは色濃く残っており、岩手の文化の豊かさを物語っています。
旧南部藩と旧伊達藩の文化が言葉に与えた影響
岩手の方言の多様性を語る上で欠かせないのが、江戸時代の藩政の影響です。現在の岩手県の大部分は盛岡藩(南部藩)が治めていましたが、南部の北上市や遠野市以南は仙台藩(伊達藩)の領地でした。 この藩境が、言葉の境界線としても機能していたのです。
盛岡藩領で話されていた方言は「南部弁」と呼ばれ、青森県の一部でも使われる広域な方言です。 一方、伊達藩領で話されていた方言は「伊達弁」や「仙台弁」とも呼ばれ、現在の宮城県の方言と共通する特徴を持っています。 例えば、盛岡を中心とする旧南部藩エリアでは敬語表現が豊かに発達したのに対し、旧伊達藩エリアではまた違った言葉遣いが根付いていました。この歴史的な背景が、現代に至るまで岩手県の方言を大きく二分する要因となっており、中北部と南部とでは言葉の響きや語彙に明確な違いが見られます。
これだけは知っておきたい!代表的な岩手の方言

岩手の方言には、聞いているだけで心が和むような温かい言葉や、思わず笑ってしまうユニークな表現がたくさんあります。 ドラマで有名になった言葉から、地元の人々が日常的に使う便利なフレーズまで、ここでは岩手の方言の魅力を感じられる代表的な言葉をいくつかご紹介します。これらの言葉を知れば、岩手への旅行や、岩手出身の人との会話がもっと楽しくなること間違いなしです。
驚きを表す魔法の言葉「じぇじぇじぇ」の秘密
「じぇじぇじぇ」は、NHKの連続テレビ小説『あまちゃん』をきっかけに全国区となった、驚きを表す感嘆詞です。 主に岩手県の北三陸地方、ドラマのロケ地にもなった久慈市周辺で使われる方言です。 驚きの度合いによって「じぇ!」、「じぇじぇ!」、「じぇじぇじぇ!」と使い分けられます。
もともとは、海女さんたちの間で使われていた言葉だったとも言われています。 しかし、興味深いことに、地元の人々が日常的に頻繁に使うかというと、必ずしもそうではないという声もあります。 実際には、驚いた時に「じゃ!」と言う地域の方が広いようです。 また、盛岡市では「じゃじゃじゃ」、宮古市では「ざざざ」という似たような表現があるなど、地域によってバリエーションが存在します。 この言葉のルーツは、室町時代の京都で使われていた感動詞にあるという説もあり、言葉の歴史の面白さを感じさせます。
日常でよく使う便利な方言フレーズ集
岩手県民の日常会話には、便利で味わい深い方言が数多く登場します。
・「おばんです」:これは「こんばんは」を意味する挨拶で、夕方以降に使われます。東北地方で広く使われる言葉ですが、岩手でも親しみを込めて交わされる挨拶の一つです。
・「んだ」:「そうだ」という意味の相槌で、同意を示す際に非常に広く使われます。「んだんだ」と繰り返したり、「んだべ」(そうだろう)、「んださ」(そうだよ)のように語尾が変化したりと、バリエーションが豊富です。
・「めんこい」:「かわいい」という意味で、特に小さな子供や動物、小物などに対して使われることが多い言葉です。 北海道や東北の他の地域でも使われますが、岩手でも愛情を込めて使われる代表的な方言です。
・「なげる」:標準語では「投げる」ですが、岩手(や他の東北・北海道の地域)では「捨てる」という意味で使われます。「ごみをなげる」は「ごみを捨てる」という意味になります。
・「うるかす」:米や豆などを「水に浸しておく」という意味です。料理の下ごしらえの際によく聞かれる言葉で、「米うるかしといて」のように使います。
・「けっぱれ」:「がんばれ」という意味の応援の言葉です。 スポーツの応援などで「もっとけっぱれ!」(もっと頑張れ!)のように使われ、聞く人を力づけます。
ちょっとユニーク?面白い響きの岩手の方言
岩手の方言には、標準語話者が聞くと意味がわからなかったり、その響きが面白く感じられたりするユニークな単語もたくさんあります。
・「ごしっぱらげる」:「腹が立つ」「頭にくる」という強い怒りの感情を表す言葉です。 「約束を破られて、ごしっぱらげだ」のように使います。
・「かだびっこ」:靴下や手袋など、二つで一組のものの片方が違っている、ちぐはぐな状態を指す言葉です。 「靴下がかだびっこだ」と言うと、左右違う靴下を履いていることを意味します。
・「こちょがしい」:「くすぐったい」という意味です。 「こちょがしいからやめて」のように使います。全国的にも「こそばい」「こしょばい」など似た響きの方言があり、言葉のつながりを感じさせます。
・「ぺっこ」:「少し」という意味で、非常によく使われる方言です。「ぺっこだけちょうだい」(少しだけちょうだい)のように、量の少なさを表します。
これらの言葉は、地元の人々の生活に深く根付いており、方言ならではの表現の豊かさを示しています。
文法から見る岩手の方言のユニークな特徴

岩手の方言の魅力は、単語やフレーズだけにとどまりません。言葉の組み立て方、つまり文法にも、標準語とは異なるユニークな特徴がたくさん隠されています。アクセントやイントネーション、会話の最後を彩る語尾、そして助詞の使い方など、少し専門的な視点から岩手の方言をのぞいてみると、その奥深さと面白さがさらに見えてきます。ここでは、岩手の方言が持つ文法的な特徴について、分かりやすく解説していきます。
アクセントとイントネーションの謎
岩手県の方言のアクセントは、地域によって大きく異なります。特に宮古市を中心とした沿岸中北部地域では、東京式のアクセントと似た体系を持っていると言われています。 一方で、県南部のアクセントはより特徴的で、曖昧な、いわゆる平板なアクセントが多く見られます。
また、東北方言全体の特徴として、言葉の響きが独特なのは音韻(おんいん:言葉を発音するときの音の仕組み)の違いも影響しています。例えば、「シ」と「ス」、「ジ」と「ズ」、「チ」と「ツ」の区別が曖昧になる傾向があり、「寿司」も「煤」も「スス」のように聞こえることがあります。 さらに、言葉の中や終わりにあるカ行やタ行の音が濁音化したり(例:「頂きます」が「イタダギマス」のように聞こえる)、ガ行やダ行の前に「ン」のような鼻音が入ったりする(例:「肌」が「ハンダ」のように聞こえる)のも、岩手を含む北東北方言の音韻的な特徴です。
語尾に隠された岩手県民の気持ち
会話の最後につく「語尾」は、話し手の気持ちやニュアンスを伝える大切な要素です。岩手の方言には、特徴的な語尾がいくつもあります。
・「~さ」「~のさ」:文の終わりに「さ」や「のさ」がつくことがよくあります。 「んださ」(そうだよ)、「行くのさ」(行くんだよ)のように、断定や念押し、あるいは単に調子を整えるために使われます。特に意味なく付けられることも多いのが特徴です。
・「~べ」「~っぺ」:「~しよう」「~だろう」といった意志や勧誘、推量を表す語尾で、東北地方で広く使われます。 「行ぐべ」(行こう)、「そうだべ」(そうだろう)のように活用されます。
・「~がんす」:「~です」「~ます」を意味する丁寧な表現です。 「そうでがんす」(そうです)、「ありがとがんす」(ありがとうございます)のように使われ、盛岡の城下町言葉として発達した敬語表現の一つです。 相手への敬意を示す、温かい響きを持っています。
助詞の使い方が標準語とこんなに違う!
文と文、単語と単語をつなぐ「助詞」の使い方も、岩手の方言の面白いところです。標準語の「~を」にあたる目的格の助詞として、「ば」が使われることがあります。 例えば「本ば読む」は「本を読む」という意味になります。
また、理由を表す接続助詞として「~すけ」や「~すけぁ」が使われるのも特徴です。「雨降るすけ、傘持ってげ」(雨が降るから、傘を持っていきなさい)のように、原因や理由を示します。
さらに、標準語では「に」や「へ」が使われる場面で「さ」が使われることもあります。「盛岡さ行ぐ」(盛岡に行く)というように、方向や目的地を示すのに「さ」が活躍します。 このような助詞の使い方の違いは、一見すると些細なことに思えるかもしれませんが、方言全体の響きやリズムを特徴づける重要な要素となっているのです。
岩手の方言に触れられる作品と学習方法
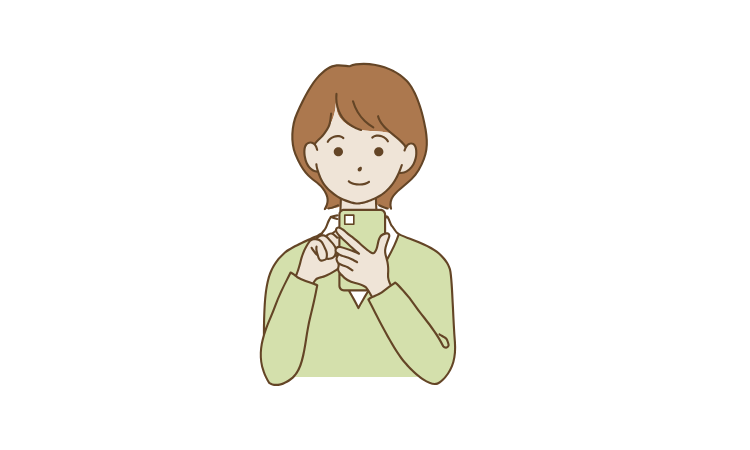
岩手の方言に興味を持ったら、次はその言葉が実際に使われている場面に触れてみたくなりますよね。幸いなことに、テレビドラマや文学作品などを通じて、岩手の方言の温かい響きやユニークな表現を楽しむ機会はたくさんあります。また、「少し話せるようになってみたい」という方のために、今日から始められる学習のヒントもご紹介します。作品の世界に浸ったり、実際に言葉を使ってみたりすることで、岩手の方言はもっと身近で楽しい存在になるはずです。
ドラマ『あまちゃん』で有名になった方言たち
2013年に放送されたNHK連続テレビ小説『あまちゃん』は、岩手の方言、特に県北の久慈市周辺の言葉が全国的に知られる大きなきっかけとなりました。 このドラマを通じて、多くの人が「じぇじぇじぇ」という驚きの言葉を覚えました。 ドラマの中では、主人公のアキや地元の海女さんたちが、生き生きとした方言で会話を繰り広げ、物語に温かみとリアリティを与えていました。
「じぇじぇじぇ」以外にも、ドラマにはたくさんの岩手の方言が登場しました。例えば、同意を示す「んだんだ」や、かわいいを意味する「めんこい」など、日常的な表現もふんだんに盛り込まれていました。このドラマをもう一度見返してみると、方言がどのような場面で、どんなニュアンスで使われるのかを楽しく学ぶことができます。物語を楽しみながら、自然な形で岩手の方言に親しむことができるでしょう。
文学や漫画で楽しむ岩手の方言の世界
岩手県は、日本を代表する詩人であり童話作家の宮沢賢治を生んだ地でもあります。賢治の作品には、彼が生まれ育った岩手(特に花巻地方)の方言が色濃く反映されています。例えば、彼の詩や童話の中に出てくる独特のオノマトペ(擬音語・擬態語)や言葉遣いには、岩手の方言の響きやリズムが息づいています。賢治の作品を読むことは、少し昔の岩手の言葉の姿に触れる貴重な機会となります。
また、現代の作品に目を向ければ、岩手県を舞台にした漫画や小説でも方言が効果的に使われていることがあります。登場人物たちのセリフを通じて、リアルな言葉遣いやイントネーションを想像しながら読み進めるのも一興です。文字で方言に触れることで、音で聞くのとはまた違った形で、言葉の細かなニュアンスや表現の面白さを発見できるかもしれません。
今日から使える!岩手の方言を学ぶためのヒント
岩手の方言を実際に学んでみたいと思ったら、まずは簡単な挨拶や相槌から始めてみるのがおすすめです。「おばんです(こんばんは)」や「んだ(そうだね)」、「めんこい(かわいい)」といった基本的な単語は、覚えやすく使いやすいでしょう。
さらに学習を進めたい場合は、インターネット上の辞書サイトや方言を紹介するウェブサイトが役立ちます。 多くのサイトでは、方言の意味だけでなく、例文や音声を確認できる場合もあり、実践的な学習が可能です。また、岩手県出身の人が運営するSNSや動画配信をチェックするのも、生きた方言に触れる良い機会になります。何よりも大切なのは、間違いを恐れずに使ってみることです。もし岩手を訪れる機会があれば、地元の人との会話の中で「これ、方言では何て言うんですか?」と尋ねてみるのも良いでしょう。きっと温かく教えてくれるはずです。
岩手の方言の歴史とこれからの展望

言葉は、時代とともに生まれ、変化し、時には消えていく生き物です。岩手の方言もまた、長い歴史の中で育まれ、人々の暮らしとともに変化を続けてきました。古くから伝わる言葉のルーツを探り、現代社会の中で方言がどのように変わってきているのかを知ることは、その言葉が持つ文化的な価値を深く理解することにつながります。そして、この先、岩手の豊かな言葉をどのように未来へ伝えていくのか、その取り組みにも目を向けてみましょう。
昔の言葉が今も残る?方言のルーツを探る
方言は、昔の中央語(都で話されていた言葉)が地方に伝わり、その地で独自の変化を遂げたり、あるいは古い形のまま残ったりして形成されると考えられています。 岩手の方言にも、その歴史の痕跡を見つけることができます。
例えば、驚いた時に使う「じぇじぇ」という言葉は、元をたどれば室町時代の京都あたりで使われていた感動詞だったという説があります。 都では新しい言葉が生まれる中で消えてしまいましたが、遠く離れた東北の地に残り続けた、というわけです。これは「方言周圏論(ほうげんしゅうけんろん)」という考え方の一例で、文化の中心地から遠い場所ほど古い言葉が残りやすいという理論です。 岩手の方言を一つひとつ調べていくと、このように言葉が旅してきた長い道のりが垣間見え、まるで歴史ロマンを感じるような面白さがあります。
時代とともに変わりゆく方言の今
かつては地域ごとの違いが大きかった方言も、テレビやインターネットの普及、交通網の発達などによって、少しずつその姿を変えています。 若い世代を中心に、日常的に伝統的な方言を使う人は減ってきており、標準語とのミックスが進んでいます。
しかし、これは必ずしも方言が失われていることを意味するわけではありません。むしろ、現代では方言の価値が見直され、地域固有の文化として積極的に評価する動きも見られます。 メディアを通じて他の地域の方言に触れる機会が増えたことで、人々は自分たちの言葉の面白さやユニークさに改めて気づくようになりました。また、昔ながらの方言とは少し違う、現代的な言い回し、いわゆる「新方言」が生まれることもあります。方言は、その時代に生きる人々のコミュニケーションに合わせて、柔軟に形を変えながら今も生き続けているのです。
方言を守り、伝えていくための取り組み
地域のアイデンティティともいえる方言を、大切な文化遺産として未来に残していこうという動きも活発になっています。岩手県では、県のウェブサイト「いわての文化情報大事典」で、県内5つの地域の方言を実際の音声付きで紹介するなど、デジタルアーカイブ化を進めています。 こうした取り組みは、地元の人々が自分たちの言葉を再認識する機会になるだけでなく、県外の人々が岩手の方言に触れる貴重な窓口にもなっています。
また、地元の菓子店が「じぇじぇじぇ」を商品の名前として商標登録出願した例もあります。 これは、単にブームに乗るだけでなく、地域で生まれた言葉を外部の業者から守り、地元の大切な財産として保守していこうという考え方の表れともいえます。 こうした地域の人々の強い思いがある限り、岩手の温かく豊かな方言は、これからも様々な形で活用され、次の世代へと確かに受け継がれていくことでしょう。
まとめ:魅力あふれる岩手の方言を未来へ

この記事では、広大で多様な「岩手の方言」の世界を探求してきました。単に「じぇじぇじぇ」だけではない、地域ごとの豊かなバリエーションがあることをお分かりいただけたかと思います。 旧南部藩と旧伊達藩という歴史的な背景、そして内陸と沿岸という地理的な要因が、言葉に独特の彩りを与えてきました。
「めんこい」や「けっぱれ」といった心温まる言葉から、「ごしっぱらげる」のようなユニークな表現まで、岩手の方言は人々の暮らしや感情を豊かに映し出してきました。 アクセントや語尾、助詞の使い方といった文法的な特徴も、その魅力を一層深めています。 『あまちゃん』などの作品をきっかけに、方言の価値は改めて見直されています。 時代とともに変化しながらも、地域の人々の努力によって、この素晴らしい言葉の文化は未来へと受け継がれていくことでしょう。