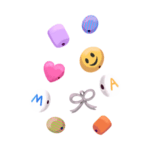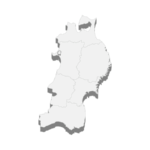「関東弁」や「関東方言」と聞くと、多くの人が「標準語と同じじゃないの?」と思うかもしれません。しかし、実は関東地方にも地域ごとに特色豊かな方言、「関東方言」が存在します。この記事では、そんな関東弁の一覧を交えながら、東京、神奈川、千葉、埼玉といった南関東から、茨城、栃木、群馬の北関東まで、それぞれの地域で話されている言葉の魅力に迫ります。
本記事を読めば、普段何気なく使っている言葉が実は関東方言だった、という発見があるかもしれません。あなたもこの記事を読んで、関東方言の奥深い世界を覗いてみませんか?
関東弁・関東方言の基礎知識

関東地方で話される言葉、いわゆる関東方言は、私たちが普段「標準語」だと思っている言葉と深い関係にありながら、実は多様な顔を持っています。一括りに関東弁と呼ぶことはできず、地域ごとにさまざまな違いがあるのが実情です。まずは、その基本的な分類や歴史背景について見ていきましょう。
関東方言とは?標準語との関係
「関東方言」は、関東地方で話されている日本語の方言の総称で、「関東弁」とも呼ばれます。 多くの人が「関東の言葉=標準語」と認識しがちですが、言語学的にはこれらは異なる概念です。
標準語は、明治時代に日本の近代化を進める中で、「全国どこでも通じる共通の言葉」として、主に東京の山の手地域(知識人や上流階級が住んでいたエリア)の言葉を基盤に作られました。 つまり、関東方言の一部をベースに、特定の目的のために整備されたのが標準語なのです。
一方、関東方言には、標準語にはならなかった地域特有の言葉や発音、イントネーションが今も残っています。特に現代の若者層の間では、共通語をベースにした「首都圏方言」と呼ばれる新しい言葉遣いが広がっており、これもまた関東方言の一つの姿と言えるでしょう。
関東方言の主な分類(東関東方言と西関東方言)
関東方言は、大きく「東関東方言」と「西関東方言」の2つに大別されます。 この二つは、文法的に「〜べ(〜でしょう、〜しよう)」という表現を共通して使うことが多いですが、発音やアクセントの面で大きな違いがあります。
・東関東方言
主に茨城県と栃木県で話されている方言です。 特徴は、東北方言(特に南奥羽方言)と多くの共通点を持つことです。 アクセントに高低差がほとんどない「無アクセント」で、言葉の響きが平坦に聞こえる傾向があります。 また、母音の発音も特徴的で、「い」と「え」の区別が曖昧になることがあります。
・西関東方言
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で話される方言が含まれます。 こちらは、標準語に近い「東京式アクセント」が用いられるのが大きな特徴です。 ただし、同じ西関東方言の中でも地域による違いは大きく、例えば千葉県や埼玉県東部では東関東方言に近い音声的な特徴が見られるなど、両者の中間的な性質を持つ地域も存在します。
なぜ関東にも方言があるのか?その歴史的背景
関東地方は日本の中心地であり、人の往来が激しい地域です。そのため、言葉も均一化されているように思われがちですが、歴史を紐解くと多様な方言が生まれた背景が見えてきます。
江戸時代、徳川家康が江戸に幕府を開いたことで、江戸は日本の中心として発展しました。 この時、家康の出身地である三河(現在の愛知県東部)の言葉や、当時の中央語であった京都の言葉など、日本各地の方言が江戸に持ち込まれました。 これらが、もともと関東地方で話されていた言葉と混ざり合うことで、江戸方言(後の東京方言)の基礎が形作られたのです。
一方で、江戸から離れた地域や、山々に囲まれた地域では、古くからの言葉がそのまま残ったり、独自の発展を遂げたりしました。例えば、埼玉県の秩父地方では古い言葉が残り、群馬県は養蚕業の盛衰と共に言葉が変化するなど、各地域の産業や地理的な条件が方言の形成に大きく影響を与えてきました。 このように、関東地方は歴史的な経緯や地域ごとの環境の違いから、多様な方言が育まれてきたのです。
【南関東編】身近な関東弁一覧と特徴

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を含む南関東は、首都圏として一体的に見られることが多いですが、言葉に注目するとそれぞれに個性的な方言が存在します。標準語に近いとされながらも、日常会話の中に根付いている独特の表現や言い回しを見ていきましょう。
東京都で使われる方言(江戸言葉・東京方言)
東京の方言は、大きく分けて上流階級が使った「山の手言葉」と、庶民が使った「江戸言葉(下町言葉)」があります。 標準語の基礎となったのは山の手言葉ですが、今でも下町情緒あふれる地域では江戸言葉の名残を聞くことができます。
江戸言葉の代表的な特徴の一つに、特定の母音が変化する「母音の融合」が挙げられます。「あい」や「おい」という音が「えー」に変わるのが典型で、「危ない(あぶない)」が「あぶねー」、「遅い(おそい)」が「おせー」となるのは、よく知られています。
また、「ひ」と「し」の音が混同されるのも特徴的で、「東(ひがし)」を「しがし」と発音したり、「七(しち)」を「ひち」と言ったりします。威勢の良さを感じさせる「てやんでえ!」といった表現も、江戸っ子言葉の象徴です。
現代の東京では、これらの伝統的な方言に加え、「〜じゃん」「〜しちゃう」といった首都圏方言が広く使われています。 これらは新しい言葉のようですが、そのルーツを探ると古くからの方言に行き着くこともあり、東京の言葉が常に変化し続けていることがわかります。
神奈川県で使われる方言(横浜弁・相州弁)
神奈川県の方言として最も有名なのが、語尾につける「〜じゃん」でしょう。 「いいじゃん」「そうじゃん」といった使い方は、今や全国的に広まりましたが、もともとは横浜を中心に使われ始めた言葉だと言われています。 その起源には諸説あり、静岡や山梨方面から伝わったという説が有力です。
「〜じゃん」は「〜ではないか」という意味合いで使われ、同意を求めたり、物事を指摘したりする際に便利な表現です。 親しみを込めたニュアンスがあり、会話をリズミカルにする効果もあります。
もう一つ、神奈川、特に湘南地域でよく聞かれるのが「〜だべ」という語尾です。 これは「〜でしょう」という意味で、同意を求める際に使われます。 元SMAPの中居正広さんが藤沢市出身で、メディアで使ったことから「だべ=湘南」というイメージが定着した側面もあります。
その他にも、列に割り込むことを「横入り(よこはいり)」と言ったり、蹴っ飛ばすことを「けっぱぐる」と言ったりするような、地域に根差した言葉も存在します。 「横入り」は神奈川以外でも使われることがありますが、方言だと知らずに使っている人も多いかもしれません。
千葉県で使われる方言(房州弁など)
千葉県の方言は、地域によって大きく3つに分けられると言われています。 県南部で話される「房州弁」、北東部の「東総弁」、そして野田市周辺の「野田弁」です。
特に知られているのが房州弁で、代表的なのが「〜だっぺ」「〜だべ」という語尾です。 これは「〜でしょう」という意味で、相手に同意を求める際などに使われます。 茨城などでも使われる表現ですが、千葉では館山市のマスコットキャラクター「ダッペエ」の名前に採用されるほど、地域に根付いた言葉です。
単語では、「押す」ことを「おっぺす」、「片付ける」ことを「かたす」と言ったりします。 「かたす」は関東の広い範囲で使われる言葉ですが、千葉でも日常的に聞かれます。 また、房州弁では「やんべぇ(〜しよう)」、東総弁では「やあっこい(柔らかい)」といった言葉もあり、同じ県内でも地域による違いが楽しめます。 東京に近い北西部では標準語化が進んでいますが、地域に根差した言葉は今も大切に受け継がれています。
埼玉県で使われる方言(秩父弁など)
埼玉県は、東京に隣接しベッドタウン化が進んでいるため方言のイメージは薄いかもしれませんが、実は地域ごとに特徴的な方言が存在します。 周辺の都県と接しているため、地域によって群馬弁、茨城弁、東京の多摩弁などの影響が見られるのが特徴です。
県内で話される方言は「武州弁」と総称されることもあり、特に西部の秩父地方で話される「秩父弁」は古い言葉が残っていることで知られています。
埼玉の方言で特徴的なのは語尾です。若者言葉と思われがちな「〜じゃね?」も、実は埼玉が発祥という説があります。 同意を求めたり、念を押したりする際に使われ、年配の方も「〜だからね」といったニュアンスで使うことがあります。 また、「いいんじゃないの」という意味で使われる「いんじゃん」も、響きの可愛らしさから若者を中心に広まった埼玉弁の一つです。
単語では、「疲れた」を「こわい」と言ったり、かき混ぜることを「かんます」と言ったりするのも特徴的です。 「だからね」という相槌を「あーね」と略して言うなど、穏やかで親しみやすい表現が多いのも埼玉弁の魅力と言えるでしょう。
【北関東編】個性豊かな関東方言一覧と特徴

茨城県、栃木県、群馬県からなる北関東エリアは、南関東とは一味違った、より個性的で力強い響きを持つ方言が話されています。東北地方の方言とも共通点が多く、イントネーションや単語にその名残が色濃く感じられます。ここでは、そんな北関東三県の魅力あふれる関東方言を見ていきましょう。
茨城県で使われる方言(茨城弁)
茨城弁は、東関東方言の代表格で、その特徴的なイントネーションや言葉遣いは、関東地方の中でも特に個性が際立っています。 アクセントに高低差が少なく平坦なのが特徴で、語尾が上がるような独特の抑揚があります。また、文中の「か行」「た行」が濁音化し、「柿(かき)」が「カギ」、「肩(かた)」が「カダ」のように聞こえるのも特徴の一つです。
茨城弁を象徴する言葉として有名なのが「ごじゃっぺ」です。 これは「でたらめ」「いい加減なこと」を意味し、愛情を込めた叱咤激励のニュアンスで使われることもあります。 また、語尾には「〜だっぺ」「〜け」などがよく使われます。 「そうだっぺ」は「そうでしょう」、「やったっけ?」は「やったっけ?」と思い出すようなニュアンスで使われます。
食べ物に関する方言もユニークで、「おにぎり」を「おぬぐる」と言ったりします。 日常の挨拶では、「こんばんは」を「おばんです」と言うなど、東北地方と共通する言葉も多く見られます。 このように、茨城弁は力強さと温かみを併せ持つ、非常に魅力的な方言です。
栃木県で使われる方言(栃木弁)
栃木弁も茨城弁と同じく東関東方言に分類され、東北地方の方言、特に福島弁と多くの共通点を持っています。 発音の特徴として、「い」と「え」の区別がつきにくい傾向があり、「色鉛筆」を「いろインピツ」と発音することがあります。
栃木弁で最もよく使われる言葉の一つが「だいじ」です。これは標準語の「大事」とは異なり、「大丈夫」という意味で使われます。 例えば、「これくらい、だいじだいじ」は「これくらい、大丈夫大丈夫」という意味になります。 また、「疲れた」を「こわい」と言うのも特徴的です。
語尾には、「〜だべ」がよく使われ、「行くだべ(行こうよ)」のように、誘いかけの場面で頻繁に登場します。 他にも、「後ろ」を「うら」と言ったり、洗濯物を取り込むことを「こむ」と言ったり、独特な単語が数多く存在します。 お笑いコンビ「U字工事」の活躍により、栃木弁の知名度は全国区になり、その素朴で温かい響きが多くの人に親しまれています。
群馬県で使われる方言(上州弁)
群馬県の方言は「上州弁」とも呼ばれ、西関東方言に分類されます。 埼玉県の北部や栃木県の足利市周辺とも似た特徴を持っています。 全体的に言葉が短くなる傾向があり、テンポが良く力強い印象を与えるのが特徴です。
上州弁を代表する言葉に「なっから」があります。これは「とても」や「かなり」といった意味の強調表現で、「なっからすごい」のように使われます。あいづちとして「そうだね」という意味で使われる「そうなん」も、群馬でよく聞かれる表現です。
語尾も特徴的で、埼玉県の一部でも使われる「〜だんべえ」は「〜だろう」という意味で、強い同意や推量を表します。 また、疑問を表す際に「〜ん?」という語尾が使われることもあり、「どうするん?」は「どうするの?」という意味になります。
面白い単語としては、「かき混ぜる」ことを「かんます」、「捨てる」ことを「ほかる」などがあります。「ほかる」は関西地方でも使われることがありますが、群馬でも日常的に使われる言葉の一つです。上州弁は、その歯切れの良さと力強さで、群馬県民の気質を表しているかのようです。
シーン別でみる面白い関東方言の使い方
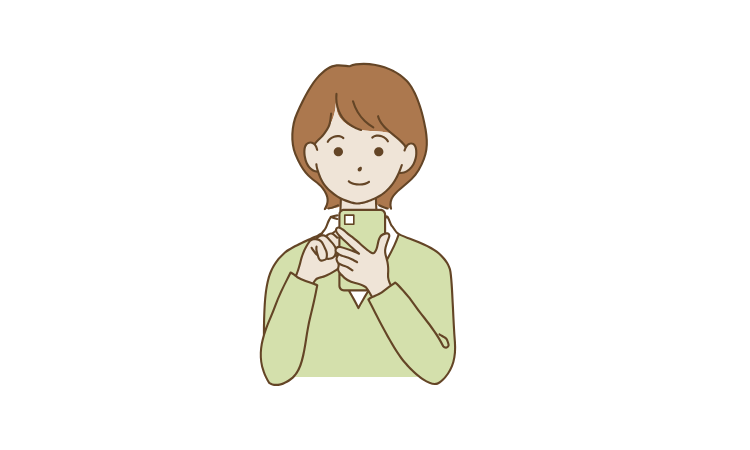
関東方言の魅力は、個々の単語だけにとどまりません。特徴的な語尾の響きや、標準語とは異なるイントネーション(アクセント)、そして「これも方言だったの?」と驚くような意外な言葉の数々。ここでは、具体的な使い方やその背景に迫りながら、関東方言の面白さをさらに深く掘り下げていきます。
語尾に特徴のある関東方言「〜だべ」「〜じゃん」
関東方言を象徴する二大語尾といえば、「〜だべ」と「〜じゃん」でしょう。これらは使われる地域やニュアンスに違いがあり、関東の言葉の多様性をよく表しています。
「〜だべ」(または「〜っぺ」)は、「〜だろう」「〜でしょう」という意味で、関東地方の広い範囲で使われる表現です。 特に、北関東の茨城・栃木や、南関東でも千葉・埼玉などで頻繁に聞かれます。 元々は推量や同意を求める意味合いが強い言葉で、「行くだべ(行こうよ)」のように、相手を誘う際にも使われます。 この「べー」を使う言葉は「ベーベーことば」とも呼ばれ、関東方言の大きな特徴の一つです。
一方、「〜じゃん」は、主に神奈川県の横浜を中心に広まったと言われる比較的新しい方言です。 「〜ではないか」が短縮された形で、相手への同意を求めたり、発見を伝えたりする際に使われます。 「その服、いいじゃん!」のように、軽やかでリズミカルな響きが特徴で、若者言葉として全国に広まりましたが、そのルーツは神奈川の方言にあります。
イントネーション(アクセント)の違い
関東地方と一括りにいっても、地域によって言葉のイントネーション(アクセント)は大きく異なります。これが、同じ単語でも全く違う響きに聞こえる理由です。
例えば、東関東方言(茨城・栃木)は、単語に特定の高低アクセントがない「無アクセント」が特徴です。 そのため、「橋」「箸」「端」のような同音異義語をアクセントで区別せず、文脈で判断します。この平坦な話し方は、東北地方の方言と連続性を持っています。
対照的に、西関東方言(東京、神奈川、埼玉など)は、標準語のベースにもなった「東京式アクセント」が主流です。 しかし、同じ東京式アクセントでも地域差はあります。例えば、埼玉県の東部では「埼玉特殊アクセント」と呼ばれる、標準語とは少し違うアクセントが存在します。 標準語で「雨が」と言うとき、「あ」を高く発音するのに対し、この地域では「め」を高く発音する、といった違いが見られます。 このように、微妙なイントネーションの違いが、それぞれの地域の言葉の個性を生み出しているのです。
こんな言葉も実は関東方言だった?意外な単語一覧
私たちが普段、標準語だと思って何気なく使っている言葉の中には、実は関東地方、あるいはもっと狭い地域でしか通じない方言が隠れていることがあります。
例えば、「片付ける」という意味で使う「かたす」という言葉。 これは千葉県や東京都など、関東の広い範囲で使われる俗語的な表現ですが、厳密には方言に分類されます。 同様に、列に「割り込む」ことを「横入り(よこはいり)」と言うのも、神奈川県横浜市が発祥とされる方言です。
また、「捨てる」を意味する「うっちゃる」や「ほかる」、青あざを指す「あおなじみ」、とても・すごくを意味する「なから」なども、特定の地域で使われる関東方言です。 「疲れた」という意味で埼玉県などで使われる「こわい」や、栃木県などで使われる「いじやける(腹が立つ、じれったい)」のように、標準語と同じ単語でも全く違う意味で使われる言葉もあります。
このように、日常に潜む方言を知ることは、言葉の奥深さや地域の文化を発見する面白いきっかけになります。
まとめ:関東弁一覧で振り返る関東方言の多様性

この記事では、「関東弁一覧」「関東方言」をテーマに、関東地方で話されている言葉の多様性と魅力について解説してきました。
「関東弁=標準語」というイメージを覆すように、関東地方には「東関東方言」と「西関東方言」という大きな分類があり、さらに各都県、各地域によって異なる特徴があることがお分かりいただけたかと思います。
茨城や栃木の力強く温かみのある響き、群馬の歯切れの良さ、そして東京、神奈川、千葉、埼玉の身近な会話に潜む独特の言い回し。 「〜だべ」や「〜じゃん」といった特徴的な語尾から、「かたす」や「横入り」のように方言と気づかずに使っている言葉まで、関東方言の世界は非常に奥深いものです。
今回ご紹介した関東弁の一覧は、そのほんの一部に過ぎません。皆さんの地元や、訪れたことのある土地の言葉に耳を澄ませてみると、そこにはきっと、地域の人々の暮らしや歴史が息づいた、愛すべき方言との出会いが待っているはずです。