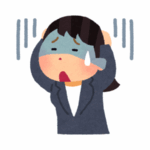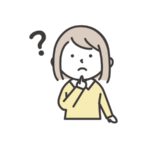「とても」という言葉、普段何気なく使っていますが、日本全国にはこの「とても」を表現するユニークな方言がたくさんあることをご存知でしたか?旅行先で耳にした面白い言葉や、アニメ・漫画でキャラクターが話していた印象的な方言も、もしかしたら「とても」を意味する言葉かもしれません。
この記事では、北海道から沖縄まで、日本各地で使われている「とても」の方言を、地域ごとの特徴や面白い表現を交えながら詳しくご紹介します。あなたの出身地の方言や、聞いたことのある言葉が登場するかもしれません。さあ、一緒に「とても」を巡る方言の探求に出かけましょう。
日本全国の「とても」の方言マップ

日本は北から南まで、その土地ならではの気候や文化が根付いており、言葉も例外ではありません。「とても」という一つの強調表現をとっても、驚くほど多くのバリエーションが存在します。ここでは、日本を大きく4つのエリアに分け、それぞれの地域で使われている特徴的な「とても」の方言を巡っていきます。力強い響きの言葉から、ユーモラスな表現まで、その多様性に触れてみましょう。
北海道・東北地方の力強い「とても」
北国ならではの、力強くインパクトのある響きを持つ方言が多いのが北海道・東北地方の特徴です。寒さや自然の厳しさに負けない、人々のパワフルな気質が言葉にも表れているのかもしれません。
・北海道:「なまら」「わや」
北海道の「とても」と言えば「なまら」が有名です。 テレビなどで活躍する北海道出身のタレントが使うことで、全国的に知られるようになりました。 「このラーメン、なまら美味しい!」のように、感動を込めて使われることが多い言葉です。 「なまら」は「とても」の最上級の表現とされ、若者言葉から生まれた「なんまら」というさらに強い表現も存在します。 また、「わや」も「とても」や「ひどい」といった意味で使われ、「わや疲れた(とても疲れた)」のように使います。
・東北地方:「いぎなり」「たげ」など
東北地方も個性的な「とても」の宝庫です。宮城県では、サンドウィッチマンの決め台詞でもおなじみの「いぎなり」が使われます。 「いぎなり好きだっちゃ(とても好きです)」のように、親しみを込めて使われるのが特徴です。 青森県では「たげ」や「たんげ」、秋田県では「しったげ」といった言葉が「とても」を意味します。 いずれも力強い響きで、言葉の勢いから意味が伝わってくるような表現です。
関東・甲信越地方の多彩な「とても」
日本の首都である東京を中心とする関東地方では、共通語の「とても」が広く使われていますが、少し範囲を広げると、そこには豊かな方言の世界が広がっています。甲信越地方も含め、地域ごとに異なる多彩な表現を見ていきましょう。
・関東地方:「ごじゃっぺ」「なっから」
茨城県や栃木県の一部では、「ごじゃっぺ」が「とても」や「いい加減」といった、少しネガティブなニュアンスを含む強調表現として使われることがあります。 また、群馬県では「なっから」という言葉が「とても」や「かなり」という意味で使われています。 一方で、東京や神奈川など都市部では、共通語の「とても」や、若者言葉である「超(ちょう)」が主流となっています。
・甲信越地方:「ごっちょ」「ずく」
山梨県では「ごっちょ」という言葉が使われることがあります。これは元々「ごちそう」を意味する言葉が転じて、「とても」という強調の意味合いを持つようになったと言われています。長野県では、「骨が折れる」「面倒」といった意味を持つ「ずく」という言葉があり、これが転じて大変さを強調する際に使われることがあります。また、山梨県や長野県では、西日本で広く使われる「えらい」も「とても」や「大変」という意味で使われることがあります。
東海・北陸地方の個性的な「とても」
日本の真ん中に位置する東海・北陸地方は、東と西の文化が交じり合う場所であり、言葉もまた独特の発展を遂げてきました。聞いて驚くような意外な言葉から、リズミカルな表現まで、個性あふれる「とても」の方言が存在します。
・東海地方:「でら」「ばか」
愛知県名古屋市周辺で有名なのが「でら」です。 「でら暑い」「でら美味しい」のように使われ、名古屋弁の代名詞的な存在です。 さらに強い表現として「どえりゃー」という言葉もあります。 一方、静岡県では「ばか」や「ど」が「とても」の意味で使われることがあります。 「ばか暑い」のように使いますが、もちろん相手を罵っているわけではないので、初めて聞く人は驚くかもしれません。
・北陸地方:「なーん」「まんで」
富山県では「なーん」という、一見すると否定しているかのような言葉が「とても」という意味で使われることがあります。 「なーん美味しい」と言われたら、それは最高の褒め言葉です。石川県では「まんで」という言葉が使われます。 また、福井県では「ひっで」や「ぎょうさん」といった表現があり、「ぎょうさん」は「たくさん」という意味から転じて強調表現として使われています。
近畿地方のユニークな「とても」
大阪や京都、兵庫など、それぞれに強い個性を持つ地域が集まる近畿地方。もちろん、「とても」を表す方言も地域ごとに特色があります。今や全国区となった言葉から、その土地ならではのユニークな表現まで、奥深い近畿の方言の世界を覗いてみましょう。
・滋賀・奈良・和歌山:「えらい」「ごっつ」「てち」
滋賀県や奈良県では「えらい」や「ごっつ」がよく使われます。 「えらい」は「大変」という意味も持ち合わせている便利な言葉です。 「ごっつ」は元々「ごつい」という言葉から来ており、その音の響きから程度の大きさが伝わります。和歌山県では「やにこぉ」や、少し珍しい「てち」という言葉が「とても」の意味で使われることがあります。
関西圏でよく聞く「とても」を表す方言

関西と一括りにされがちですが、実は大阪、京都、兵庫では「とても」の表現にそれぞれ特徴があります。テレビのバラエティ番組などを通じて全国的に知られている言葉も多いですが、その微妙なニュアンスやルーツを知ると、より深く関西の文化を理解できるかもしれません。
全国区になった?大阪の「めっちゃ」
「とても」を意味する方言の中で、今や全国で最も知られ、使われている言葉の一つが大阪の「めっちゃ」でしょう。 若者を中心に自然に使われ、方言という意識すらない人も多いかもしれません。元々は「滅茶苦茶(めちゃくちゃ)」という言葉が省略されたもので、1990年代頃から若者言葉として広まり、メディアを通じて全国に定着しました。
「めっちゃ」と似た言葉に「むっちゃ」もありますが、意味はほぼ同じで、「とても」という強調を表します。 人によっては「むっちゃ」の方がより強いニュアンスを感じる場合もあるようです。現在では「アホほど」や「死ぬほど」といった、さらに強調度合いの強い表現も使われており、表現の豊かさが伺えます。 大阪人のコミュニケーションにおける、感情表現の豊かさやストレートさが、こうした言葉を生み出しているのかもしれません。
上品な響き?京都の「えらい」
古都・京都で使われる「えらい」という言葉は、多義的で奥深いニュアンスを持つのが特徴です。 標準語の「偉い(地位が高い、立派だ)」という意味でも使いますが、それ以上に「とても」や「大変」「疲れた」といった意味で日常的に使われます。 例えば、「今日はえらい人出やな」と言えば「今日はとても人が多いね」という意味になり、「昨日歩きすぎてえらいわ」と言えば「昨日歩きすぎて疲れたよ」という意味になります。
アクセントも特徴的で、標準語の「えらい」が「ら」にアクセントを置くのに対し、京都弁では「え」にアクセントがきます。 この一言で様々な状況や感情を表現できる「えらい」は、京都の言葉の奥深さを象徴する言葉の一つと言えるでしょう。言葉を省略したり、一つの言葉に多くの意味を持たせたりする京都ならではの言語文化が感じられます。
神戸発祥?兵庫の「ばり」
兵庫県、特に神戸の若者を中心に広まったのが「ばり」という言葉です。 「めっちゃ」と同様に「とても」「すごく」という意味で使われ、「このケーキ、ばり美味しい!」といった形で使います。 今では関西圏だけでなく、福岡など西日本の他の地域でも使われるポピュラーな方言となっています。
その語源には諸説ありますが、一説にはバイクのアクセルを「バリバリ」回す様子から来ているとも言われています。勢いの良さや程度の激しさを表現するのにぴったりの言葉として若者に受け入れられたようです。「ばり」を使うことで、より感情がこもったニュアンスを伝えることができるため、友人同士の会話では欠かせない言葉となっています。 他にも広島県で使われる「ぶち」も、同じように若者言葉として定着しています。
西日本に広がる「とても」のバリエーション

関西を越えて西へ進むと、さらに多様で力強い「とても」の方言が待ち受けています。中国・四国地方のインパクトのある言葉や、九州地方の熱量が伝わってくるような表現、そして南国・沖縄の独特な響きを持つ言葉まで、その豊かさは尽きることがありません。
中国・四国地方のインパクト大な「とても」
中国・四国地方には、一度聞いたら忘れられないような、音の響きが印象的な「とても」の方言が数多く存在します。
・中国地方:「ぶち」「ぼっけぇ」
広島県で広く使われるのが「ぶち」です。 「ぶち好きじゃけえ(とても好きだよ)」のように、愛情表現にも力強さが加わります。山口県でも同様に「ぶち」が使われます。 岡山県では「ぼっけぇ」や「でぇれぇ」といった、さらにインパクトの強い言葉が使われます。 「ぼっけぇ」は「ものすごい」という意味で、映画のタイトルになったこともあり、知名度が高まりました。鳥取県の「がいな」も、力強さを感じさせる表現です。
・四国地方:「こじゃんと」「ものっそい」
高知県を代表する「とても」の方言が「こじゃんと」です。 「こじゃんと美味しい」と言えば、最高級の賛辞です。「徹底的に」「たくさん」といった意味も含まれており、高知の豪快な県民性を表すかのような言葉です。香川県では「ものっそい」、徳島県では「ごっつい」といった言葉が使われ、いずれも程度の甚だしさをストレートに表現しています。
九州地方の力強い「とても」
九州地方は、各県がそれぞれ非常に個性的な方言を持っており、「とても」の表現も実に多彩です。その土地の熱気や情熱が伝わってくるような、力強い言葉が特徴的です。
・福岡・佐賀:「バリ」「ちかっぱ」「がばい」
福岡県では、兵庫でも使われる「バリ」が若者を中心に広く浸透しています。 さらに強調したい時には、「力いっぱい」が語源とされる「ちかっぱ」が使われます。 「ちかっぱすごい」は、最上級の驚きや感動を表す言葉です。 佐賀県では、映画で有名になった「がばい」が使われます。「がばいすげえ(とてもすごい)」のように使われ、佐賀弁の象徴的な言葉となっています。
・熊本・大分・宮崎・鹿児島:「だご」「しんけん」「てげ」「わっぜ」
熊本県では「だご」が「とても」を意味し、「だご汁」という郷土料理の名前にもその名残が見られます。大分県では「しんけん」が使われ、「真剣」という言葉通り、本気度合いを強調するニュアンスがあります。 宮崎県では「てげ」、鹿児島県では「わっぜ」という、短くも力強い言葉が使われます。
南国らしい響き?沖縄の「でーじ」
日本の最南端、沖縄県で「とても」を表す代表的な言葉が「でーじ」です。 「でーじ美味しい」「でーじ可愛い」のように使われ、日常会話で頻繁に耳にします。 「でーじ」は良い意味だけでなく、「大変なこと」という意味でも使われ、「でーじなことになった(大変なことになった)」のようにも表現されます。
「でーじ」の他にも、「しに」という言葉も同じく「とても」という意味で使われます。 若者を中心に使われることが多く、「しに面白い」といった形で使われます。また、「いっぺー」という言葉もあり、これは元々「いっぱい」を意味しますが、転じて「とても」という意味でも使われます。 このように、沖縄には複数の強調表現が存在し、状況や世代によって使い分けられています。
なぜ「とても」の方言はこんなに多様なの?

「とても」という一つの意味を表すのに、なぜこれほどまでに多くの言葉が日本中に存在するのでしょうか。その背景には、日本語の歴史的な変遷や、各地域の文化、そして現代社会の変化が複雑に絡み合っています。言葉の多様性は、日本の文化の豊かさそのものを映し出しているのです。
言葉の由来と歴史的な変化
方言が多様である大きな理由の一つに、歴史的な言葉の変化が挙げられます。かつて日本の中心であった京都などの都で使われていた言葉が、時間をかけて地方へ伝わっていく過程で、その土地独自の音韻変化を遂げたり、意味合いが少しずつ変わったりしていきました。これを「方言周圏論」と呼びます。例えば、都で新しい言葉が生まれると、それは同心円状に地方へ広がっていきますが、都から遠い地域ほど古い言葉が残りやすい、という考え方です。
「とても」という言葉自体も、元々は「とてもかくても(どうあろうとも)」という言葉が省略されたもので、現在のような「非常に」という意味で広く使われるようになったのは、比較的新しい時代からだと言われています。 それ以前は、各地域で「いと」「いみじ」などの古語から変化した言葉や、別の言葉が強調の意味を持つようになるなど、独自の発展を遂げてきました。
地域文化と人々の気質
言葉は、その土地で暮らす人々の文化や気質を色濃く反映します。例えば、厳しい自然環境で暮らす地域では、力強く断定的な響きを持つ言葉が好まれる傾向があるかもしれません。東北地方の「いぎなり」や九州地方の「わっぜ」などは、その一例と言えるでしょう。
また、商人の町として栄えた大阪では、相手に感情をストレートに伝え、コミュニケーションを円滑にするための表現として「めっちゃ」のような分かりやすい言葉が広まったと考えることもできます。一方で、歴史と伝統を重んじる京都では、「えらい」のように一つの言葉に複数の意味を持たせ、文脈によって使い分ける奥ゆかしい表現が育まれたのかもしれません。 このように、方言にはその土地の風土や歴史、人々の気質が溶け込んでいるのです。
現代における方言の進化
方言は決して固定的なものではなく、時代と共に変化し続ける「生き物」です。 特に現代では、テレビやインターネットなどのメディアの発達が、方言のあり方に大きな影響を与えています。大阪の「めっちゃ」や福岡の「バリ」のように、元々は一地方の若者言葉だったものが、テレビ番組やSNSを通じて全国に広まり、方言の枠を越えて共通語のように使われるケースも増えています。
また、こうした新しい方言が生まれる一方で、伝統的な方言は使う人が減り、消滅の危機に瀕しているものも少なくありません。しかし、近年では方言の持つ温かみや独自性が見直され、地域振興のために方言を積極的に活用する動きも見られます。 方言は、常に古いものと新しいものが混在し、変化しながら受け継がれていく文化なのです。
面白い!ユニークな「とても」の方言

日本全国に存在する「とても」の方言の中には、その由来や響きが非常にユニークで面白いものがたくさんあります。標準語の感覚からすると、なぜその言葉が「とても」になるのか不思議に思うような表現や、思わず口に出してみたくなるような楽しい響きの言葉など、知れば知るほど方言の奥深さに引き込まれていくでしょう。
意外な言葉が「とても」の意味に?
普段私たちが使っている言葉の中には、特定の地域に行くと全く違う「強調」の意味で使われるものがあります。その代表例が、静岡県で使われる「ばか」です。 「ばか暑い」「ばか美味しい」のように使われ、悪意は全くありません。初めて聞いた人は驚いてしまうかもしれませんが、地元の人にとってはごく自然な表現です。
また、茨城県などで使われる「ごじゃっぺ」は、「いい加減」や「馬鹿」といったネガティブな意味合いで使われることが多いですが、文脈によっては「とても」という強調の意味にもなります。 さらに、ランキング調査によると、福井県などで使われる「ほっこりする」という言葉が、標準語の「和む」という意味とは逆に「疲れる、うんざりする」という意味で使われたり、「こわい」という言葉が長野県では「(味が)濃い」、北海道では「つらい、だるい」という意味で使われたりする例もあります。 このように、同じ言葉でも地域によって意味が全く異なるのが方言の面白いところです。
音の響きが楽しい方言たち
意味だけでなく、言葉の音の響きそのものが楽しいのも方言の魅力です。声に出して言ってみると、その土地の空気感が伝わってくるような気がします。
例えば、岡山県の「ぼっけぇ」や、高知県の「こじゃんと」、宮崎県の「てげ」などは、そのリズミカルで特徴的な響きが耳に残ります。 これらの言葉は、地元の活気や人々の陽気な気質を表しているかのようです。富山県で使われることがある「はんごろし」は、物騒な響きとは裏腹に、実は「おはぎ」や「ぼたもち」を指す方言です。 これは、もち米の粒が半分残る程度に粗くつぶすことから来ているそうで、言葉の響きと意味のギャップが非常にユニークです。こうした言葉を知っていると、地元の人との会話がより一層楽しくなることでしょう。
地域限定?レアな「とても」の方言
全国的にはあまり知られていなくても、特定の地域で大切に使われている「とても」の方言もたくさんあります。そうしたレアな方言に出会うのも、旅の醍醐味の一つかもしれません。
例えば、岩手県には「らずもね」という、少し不思議な響きの言葉があります。 また、香川県の「いかさま」や愛媛県の「よいよ」も、「とても」を意味する地域限定の表現です。 こうした言葉は、その地域以外では通じないかもしれませんが、だからこそ、その土地のアイデンティティを示す大切な役割を担っています。もし旅行先などで耳慣れない言葉を聞いたら、それはその土地ならではの「とても」を表す宝物のような言葉かもしれません。勇気を出して「それ、どういう意味ですか?」と尋ねてみれば、そこから新しいコミュニケーションが生まれるかもしれません。
まとめ:「とても」の方言から見える日本語の豊かさ

この記事では、「とても」という一つの言葉に焦点を当て、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国の実に多様な方言をご紹介してきました。 力強い響きの言葉、ユーモラスな表現、そして意外な意味を持つ言葉など、そのバリエーションの豊かさに驚かれた方も多いのではないでしょうか。
「なまら」「いぎなり」「でら」「めっちゃ」「ぶち」「こじゃんと」「バリ」「でーじ」など、各地の方言には、その土地の歴史や文化、そして人々の気質が色濃く反映されています。 なぜこれほどまでに多様な表現が生まれたのかを探ると、都から地方への言葉の伝播や、各地域の地理的な要因、そして現代のメディア社会の影響など、様々な背景が見えてきました。
方言は、単なる言葉のバリエーションではなく、その土地に暮らす人々のアイデンティティであり、世代を超えて受け継がれてきた大切な文化遺産です。普段何気なく使っている言葉の向こう側にある、日本語の奥深さと豊かさを、この記事を通して少しでも感じていただけたなら幸いです。