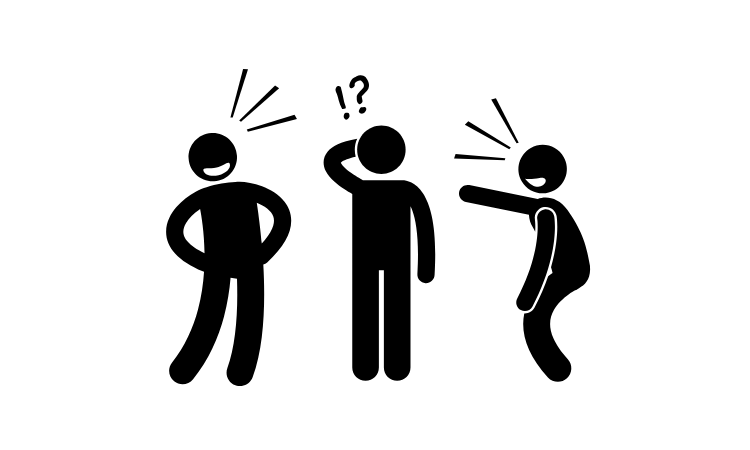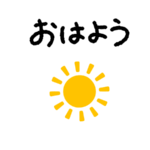「あの人、人のことおちょくってばっかりだよね」。こんな会話、耳にしたことはありませんか?「おちょくる」という言葉は、相手をからかったり、ばかにしたりする際に使われる表現ですが、実は主に関西地方で使われてきた方言だということをご存知でしたか?
今では全国的に知られるようになりましたが、その語源や、似たような意味を持つユニークな方言が日本各地に存在します。この記事では、「おちょくる」の基本的な意味やルーツを探るとともに、北海道から沖縄まで、地域色豊かな「おちょくる」の仲間たちをたっぷりとご紹介します。あなたの知っている言葉、使っている方言が登場するかもしれません。言葉の奥深さに触れる旅へ、一緒に出かけてみましょう。
おちょくるとは?基本的な意味と語源を探る

「おちょくる」という言葉について、私たちはどれくらい知っているでしょうか。日常的に使ったり聞いたりする言葉でも、その正確な意味や成り立ちを深く考える機会は少ないかもしれません。ここでは、「おちょくる」という言葉の基本的な情報に焦点を当て、その意味、語源、そして方言なのか標準語なのか、という疑問について詳しく解説していきます。言葉の背景を知ることで、コミュニケーションがより豊かになるはずです。
「おちょくる」という言葉の正しい意味
「おちょくる」とは、一般的に「人をからかう、ばかにする、なぶる」といった意味で使われる動詞です。 相手を困らせたり、わざとふざけた言動をとって反応を楽しんだりする、少し意地悪なニュアンスが含まれることが多いでしょう。例えば、友人の小さな失敗を大げさに指摘して笑いの種にする、といった状況で「人をからかうなよ」の代わりに「人をおちょくるなよ」と使われます。
ただし、そのニュアンスは単なる「からかい」よりも、相手を少し下に見ている、あるいは小馬鹿にしている感じが強いと捉える人もいます。 そのため、親しい間柄での冗談として使われることもあれば、言われた側が不快に感じる可能性も秘めている言葉です。使う相手や状況を選ぶ必要がある、デリケートな側面も持ち合わせていると言えるでしょう。
「おちょくる」の語源は?どこから来た言葉?
「おちょくる」の語源については、いくつかの説があり、はっきりと一つに定まっているわけではありません。
有力な説の一つとして、古語の「嘲繰(ちょうくる)」が変化したというものがあります。 「嘲」は「あざける」、「繰」は「操作する」といった意味合いを持ち、これが合わさって「人をあざけりながら操る」ようなニュアンスの言葉となり、音便化して「ちょくる」、そして「おちょくる」になったと考えられています。
また、別の説では、酒器の「お猪口(おちょこ)」が関係しているとも言われています。 小さくて簡単に扱えるお猪口を手玉に取って転がすように、相手を軽くあしらってからかう様子から「おちょくる」という言葉が生まれた、という見方です。
さらに、東北地方などで使われる「ちょくる」という言葉との関連も指摘されています。 この「ちょくる」は、ふざけて相手を小突いたり、なでたりするという意味を持ち、こうした身体的なじゃれ合いのニュアンスから発展した可能性も考えられます。これらの説が複合的に絡み合って、現在の「おちょくる」という言葉が形成されたのかもしれません。
「おちょくる」は方言?標準語?
結論から言うと、「おちょくる」は主に関西地方で使われてきた方言とされています。 辞書などでも「主に関西地方でいう」と解説されていることが多く、特に関西出身者にとっては非常に馴染み深い言葉です。 大阪や京都、兵庫、和歌山などの地域では、日常会話の中で自然に登場します。
しかし、現在ではテレビのバラエティ番組などを通じて芸人さんが使う機会が増えたことなどから、全国的に認知度が上がり、関西以外の地域でも意味が通じることが多くなりました。若者を中心に、方言であるという意識なく使っている人も少なくありません。
そのため、「元々は関西の方言だったが、今では全国区になりつつある言葉」と理解するのが最も実態に近いでしょう。完全に標準語とまでは言えませんが、多くの人が意味を理解できる準標準語的な地位を確立しつつある言葉と言えそうです。それでも、改まった場や目上の方に対して使うのは避けた方が無難な、くだけた表現であることは覚えておくと良いでしょう。
【地域別】おちょくるの面白い方言の世界

「おちょくる」という言葉は関西地方がルーツですが、人をからかったり、ばかにしたりするという意味の言葉は、日本全国に存在します。その土地ならではの響きやニュアンスを持つ方言は、聞いているだけでも面白いものです。ここでは、日本をいくつかのエリアに分け、それぞれの地域で使われている「おちょくる」の仲間たち、つまり「からかう」を意味する方言を紹介していきます。あなたの故郷の言葉や、旅先で耳にしたことのある言葉が見つかるかもしれません。
北海道・東北地方で使われる「おちょくる」の仲間たち
北国、北海道・東北地方には、寒さを吹き飛ばすようなユニークな方言が根付いています。
北海道や秋田県では「ちょす」という言葉が使われます。 これは「からかう」という意味のほかに、「触る」「いじる」といった意味も持っています。例えば、「変なとこちょすな(変なところを触るな)」のように、物理的に触れる行為を指す場合もありますが、「人をちょすんでない(人をからかうもんじゃない)」といった使い方で、からかいの意味にもなります。文脈によって意味が変わる、面白い言葉です。また、北海道では「はんかくさい」という言葉もあり、これは「ばからしい、あほらしい」といった意味ですが、からかうニュアンスで使われることもあります。
東北に目を向けると、青森県では「からがる」「すずがる」、岩手県では「ひずる」、宮城県では「しずる」といった言葉があります。 音の響きが似ていて、地域的な繋がりを感じさせます。山形県の「おひゃらがす」や福島県の「ちょっけ」なども、味わい深い表現です。 このように、同じ東北エリアでも県によって多様な言い方が存在していることがわかります。
関東・甲信越地方のユニークな表現
首都圏を含む関東・甲信越地方にも、興味深い「おちょくる」系の方言が見られます。
関東地方では、標準語に近い言葉が使われることが多いですが、千葉県では「ちょがす」、栃木県では「かまう」、茨城県では「おひゃらがす」といった方言が使われることがあります。 「かまう」は標準語では「相手をする」といった意味ですが、これが転じて「からかう」のニュアンスで使われるのが特徴的です。
甲信越地方に目を移すと、さらに多様な表現が見つかります。長野県の「おしゃらかす」や新潟県の「からこー」は、一度聞いたら忘れられないようなユニークな響きを持っています。
特に興味深いのが山梨県で使われる「からかう」です。これは標準語の「からかう」とは全く意味が異なり、「修理する」「工夫を凝らして手入れする」といった意味で使われます。 例えば、「壊れた機械をからかう」は「機械を修理する」という意味になります。 知らないで聞くと、機械をいじめているのかと誤解してしまいそうな、非常に面白い用法の例です。同じ言葉でも地域によって意味が全く異なる、方言の奥深さを示しています。
東海・北陸地方ではどう言う?
日本の真ん中に位置する東海・北陸地方は、東西の文化が混じり合うエリアであり、言葉にもその影響が見られます。
東海地方では、岐阜県や愛知県で「ちょーらかす」、静岡県で「おちゃらかす」といった言葉が使われます。 これらは「ちゃかす」という言葉にも通じるような、軽やかな響きが特徴的です。三重県では「なぶる」という言葉も使われ、これは標準語の「なぶる」と同じく、しつこくからかったり、もてあそんだりするニュアンスが強い表現です。
一方、北陸地方では、富山県で「だらにする」や「ちょろがす」という言葉があります。 「だらにする」の「だら」は「馬鹿」や「阿呆」を意味する方言で、そこから「馬鹿にする」という意味合いで使われていると考えられます。石川県の「あをだがす」や福井県の「なぶる」など、地域ごとに個性的な言葉が使われています。 これらの言葉は、その地域の人々の気質やコミュニケーションのスタイルを反映しているのかもしれません。
関西地方のバリエーション豊かな「おちょくる」
「おちょくる」という言葉の本場である関西地方は、やはりこの種の表現のバリエーションが豊かです。
大阪府、京都府、和歌山県など、多くの地域で「おちょくる」が日常的に使われています。 「あんまり人をおちょくったらあかんで(あまり人をからかったらダメだよ)」といった形で、会話の中に自然に溶け込んでいます。また、関西弁には「おちょくる」と似た言葉で「ちょける」というものもあります。これは「ふざける」を意味する自動詞で、「あいつ、またちょけとるわ(あいつ、またふざけてるよ)」のように使います。「おちょくる」が他動詞で相手をからかうのに対し、「ちょける」は自分自身がふざける、という違いがあります。
兵庫県では「おちょくる」の他に「べろばかす」というユニークな言葉も使われます。 「べろ」は舌を連想させ、言葉巧みに相手を騙したり、ばかにしたりするようなニュアンスが感じられます。三重県や岡山県、徳島県など、関西周辺の地域でも「おちょくる」が使われており、この言葉が関西文化圏で広く共有されていることがうかがえます。
中国・四国地方の味のある言い方
中国・四国地方にも、独特の響きを持つ「からかう」の方言が数多く存在します。
中国地方を見てみると、鳥取県では「ひょーとくる」や「あえる」、島根県では「あじゃる」といった言葉が使われます。 どれも音の響きが面白く、どこか愛嬌のある印象を受けます。広島県では「かもー」や「ちょーやがす」、山口県では「わやく」といった表現があり、力強い響きが特徴的です。 岡山県では「いらまかす」や「えどかす」など、複数の言い方が存在し、地域内での多様性が見られます。
四国地方では、香川県や愛媛県で「てがう」という言葉が共通して使われています。 高知県でも「てがう」が使われるほか、「ぞぶる」という表現もあります。 徳島県では「いろべる」という言葉があり、これも「いじる」や「触る」といったニュアンスから来ているのかもしれません。 このように、瀬戸内海を挟んだ地域で共通の言葉が見られるなど、地理的なつながりも感じさせるのが中国・四国地方の方言の面白い点です。
九州・沖縄地方の個性的な方言
日本の南に位置する九州・沖縄地方は、歴史的・地理的な背景から、他とは一線を画す個性的な方言文化を持っています。
九州地方では、地域ごとに非常に多彩な表現が見られます。福岡県では「ちょーくらかす」、長崎県では「せびらかす」や「ちょくらかす」、熊本県では「せびらかす」「ぞうくる」、鹿児島県では「ちょくい」「ひょくらかす」など、「〜かす」という語尾がつく言葉が多いのが特徴です。 これは動詞を強める接尾語で、からかう行為を強調するニュアンスがあるのかもしれません。大分県の「せがう」や宮崎県の「もどかす」、佐賀県の「きゃーなずっ」など、ユニークな言葉の宝庫です。
そして、琉球方言が話される沖縄県では、「からかう」ことを「わちゃく」と言います。 これは「いたずら」を意味する言葉でもあり、子どもが悪さをするような、少しやんちゃなニュアンスが含まれているようです。 その響きからも、どこか南国らしい大らかさが感じられます。九州・沖縄地方の方言は、その土地の文化や歴史と深く結びついた、個性あふれる言葉の魅力を伝えてくれます。
「おちょくる」と似ている言葉との違い
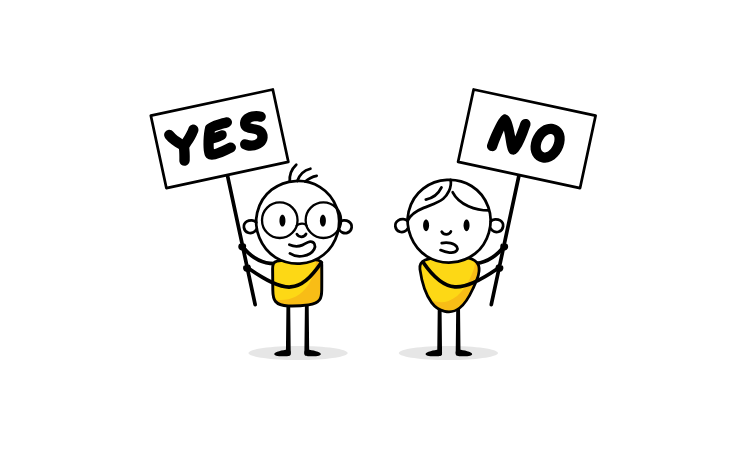
「おちょくる」には、「からかう」「ひやかす」「ちゃかす」といった似たような言葉がいくつかあります。どれも相手を面白がるような言動を指しますが、実はそれぞれに微妙なニュアンスの違いがあります。これらの言葉を正しく使い分けることで、自分の意図をより正確に伝え、誤解を避けることができます。ここでは、それぞれの言葉が持つ独特のニュアンスや使われる場面について、詳しく見ていきましょう。
「からかう」とのニュアンスの違い
「からかう」は、「おちょくる」の類語として最も一般的で、広い意味で使われる言葉です。 相手に冗談を言ったり、困るようなことをしたりして面白がる行為全般を指します。 動物に対しても使うことができ、「猫じゃらしで子猫をからかう」といった表現が可能です。
一方、「おちょくる」は、この「からかう」よりも相手を「ばかにする」「見下す」というニュアンスが強い傾向にあります。 親しい間柄での愛情表現として使われることもありますが、一歩間違えると相手に侮辱されたと受け取られかねません。「おちょくる」と言われた方が、「からかわれる」よりもカチンとくる、と感じる人もいるでしょう。
使い分けのポイントとしては、悪意の度合いが挙げられます。比較的軽い冗談やじゃれ合いであれば「からかう」が適しています。しかし、相手を少し見下したような、あるいは意地悪な気持ちを込めて面白がる場合には「おちょくる」が使われることが多い、と考えることができます。
「ひやかす」との使い分け
「ひやかす」は、「からかう」の中でも特定の状況で使われることが多い言葉です。その大きな特徴は、相手の恋愛ごとやうまくいっていることなど、少し羨ましい状況に対して使われる点にあります。 例えば、仲睦まじいカップルに対して「お熱いねえ」と声をかけたり、新婚の同僚に「昨日は楽しかった?」と聞いたりするのが典型的な「ひやかす」です。相手の高揚した気分に少し水を差すような、茶化すニュアンスが含まれます。
また、「ひやかす」にはもう一つ、全く別の意味があります。それは、買う気もないのに店先で商品を眺めたり、値段を尋ねたりすることです。 「ウインドーショッピング」に近い行為で、「商店街をひやかして歩く」のように使います。
「おちょくる」が相手をばかにするニュアンスが強いのに対し、「ひやかす」は羨ましさや嫉妬の気持ちが根底にあることが多い、という点で異なります。恋愛話などで友人同士がじゃれ合うのは「ひやかす」、相手の弱点や失敗をあげつらって笑うのは「おちょくる」と使い分けると、その違いが分かりやすいでしょう。
「ちゃかす」はどんな場面で使う?
「ちゃかす」は、真面目な雰囲気や議論を、意図的に冗談めかして台無しにしてしまうような行為を指します。 「お茶を濁す」という言葉があるように、その場の空気をかき混ぜて、本題から逸らしたり、ごまかしたりするニュアンスが強いのが特徴です。
例えば、会議で真剣な議論が続いているときに、誰かが全く関係のないダジャレを言って場の空気を壊してしまう、といった状況が「話をちゃかす」に当たります。 相手を直接攻撃するというよりは、その場の状況や話題そのものを軽んじて、ふざけた態度で向き合うことを意味します。
「おちょくる」が特定の「人」を対象にしてばかにする行為であるのに対し、「ちゃかす」は「話」や「雰囲気」といった「状況」を対象にすることが多いと言えます。もちろん、真面目に話している人を「ちゃかす」こともありますが、その目的は相手をやり込めることよりも、真剣なムードを壊して冗談にしてしまいたい、という点にあるのが違いと言えるでしょう。
「おちょくる」方言の面白い使い方・例文

言葉は、意味を知るだけでなく、実際に使ってみることでその面白さやニュアンスがより深く理解できます。「おちょくる」やその類語である全国の方言も、具体的な会話の中でどのように使われるかを知ることで、生き生きとした表情を見せてくれます。ここでは、各地の方言を使った例文や、方言がもたらすコミュニケーション上の効果、そしてメディアでの役割について掘り下げていきます。
日常会話で使ってみよう!方言例文集
ここでは、これまで紹介してきた「おちょくる」系の方言を、日常会話の形で紹介します。言葉の響きや雰囲気を楽しんでみてください。
・関西地方の会話
A:「さっき、隣のクラスの女の子が泣いとったな。どないしたんやろ?」(さっき、隣のクラスの女の子が泣いてたね。どうしたんだろう?)
B:「ああ、また山田くんが余計なこと言うて、おちょくったんちゃうか?」(ああ、また山田くんが余計なことを言って、からかったんじゃないかな?)
・北海道での会話
A:「昨日、新しい髪型にしたんだ。」
B:「へえ、似合うじゃん。でも、ちょっと寝癖ついてるぞ。」
A:「うそ!どこ?やめてよ、人ちょすんじゃないよ。」(うそ!どこ?やめてよ、人をからかうなよ。)
・山梨県での会話
A:「この古いラジオ、もう動かないと思ってたよ。」
B:「昨日、一日かけてからかってみたら、直ったんだ。」(昨日、一日かけて工夫して修理してみたら、直ったんだ。)
A:「え、すごい!からかうの上手だね!」(え、すごい!修理が上手だね!)
このように、同じような状況でも地域によって全く違う言葉が使われるのが方言の面白いところです。特に山梨の「からかう」のように意味が大きく異なる場合は、知っているとコミュニケーションがより円滑になります。
方言がもたらすコミュニケーション効果
方言は、単なる地方の言葉というだけではありません。コミュニケーションにおいて、さまざまな効果をもたらします。
一つは、親近感や一体感を生む効果です。同じ方言を話す人同士が出会うと、初対面でもすぐに打ち解けられることがあります。共通の言葉を使うことで、「同郷である」という仲間意識が芽生え、心の距離がぐっと縮まるのです。
また、会話を和ませ、豊かにする効果もあります。標準語だけの会話に比べて、方言が混じることで会話にリズムや温かみが生まれます。特に「おちょくる」のようなユーモラスなニュアンスを持つ方言は、場の雰囲気を和らげ、笑いを生み出すきっかけになることも少なくありません。相手をからかう言葉であっても、きつい標準語で言うよりも、味のある方言で言われた方が、愛情が感じられて許せてしまう、という経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。
文学やメディアに見る方言の役割
小説や映画、ドラマ、漫画といったメディアの世界でも、方言は非常に重要な役割を果たしています。
方言を使うことで、登場人物のキャラクターを際立たせることができます。例えば、特定の地域の方言を話すことで、その人物の出身地や育った環境を読者や視聴者に伝え、人物像に深みとリアリティを与えることができます。映画『舟を編む』では辞書作りの過程が描かれ、言葉の多様性がテーマの一つとなっていますし、映画『国宝』では歌舞伎の世界を舞台に、関西弁などが重要な役割を果たしていると考えられます。
さらに、物語の舞台となる地域の雰囲気を醸し出す上でも方言は不可欠です。その土地の言葉が聞こえてくることで、まるでその場所にいるかのような臨場感が生まれます。「おちょくる」という言葉が聞こえてくれば、多くの人が「ああ、この物語の舞台は関西なのだな」と感じるでしょう。このように、方言は単なるセリフの一部ではなく、作品の世界観を構築するための重要な要素として機能しているのです。
【まとめ】おちょくる方言の多様性を知って言葉をもっと楽しもう

この記事では、「おちょくる」という言葉を中心に、その意味や語源、そして日本全国に散らばる「からかう」を意味する様々な方言について旅をしてきました。「おちょくる」が元々は関西の方言であったこと、そしてその語源には「嘲繰(ちょうくる)」や「お猪口」など複数の説があることがわかりました。
日本各地に目を向ければ、「ちょす」(北海道・秋田)、「おしゃらかす」(長野)、「ちょーらかす」(愛知)、「てがう」(四国)、「ちょーくらかす」(福岡)、「わちゃく」(沖縄)など、実に個性的で豊かな表現が存在します。 また、山梨の「からかう」が「修理する」という意味を持つように、同じ言葉でも地域によって全く意味が異なる場合があることも、方言の奥深さを示しています。
さらに、「からかう」「ひやかす」「ちゃかす」といった似た言葉との間にも、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあることも確認しました。 これらの言葉の多様性を知ることは、私たちのコミュニケーションをより豊かで、味わい深いものにしてくれます。普段何気なく使っている言葉の背景に思いを馳せ、方言の面白さに触れることで、日本語の魅力を再発見するきっかけになるのではないでしょうか。