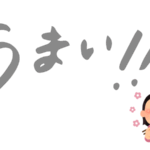沖縄の言葉「うちなーぐち」に興味はありませんか?沖縄旅行を計画している方、沖縄の文化にもっと触れたい方にとって、うちなーぐちを知ることは、沖縄をより深く理解するきっかけになります。この記事では、すぐに使える基本的な挨拶から、日常会話で役立つ単語やフレーズまで、さまざまな「うちなーぐち一覧」を分かりやすく紹介します。
うちなーぐちには、日本語の古い言葉が残っていたり、地域によって言葉が異なったりと、非常に奥深い魅力があります。 例えば、歓迎を表す「めんそーれ」は有名ですが、感謝の「にふぇーでーびる」や元気かどうかを尋ねる「ちゃーがんじゅーねー?」など、知っていると地元の人々とのコミュニケーションがぐっと豊かになる言葉がたくさんあります。 この記事を読んで、うちなーぐちの温かい響きと表現の豊かさに触れ、沖縄の旅や文化体験をさらに楽しいものにしてください。
うちなーぐちとは?沖縄の言葉の魅力を知ろう

沖縄で話されている言葉は、一般的に「うちなーぐち」や「しまくとぅば(島言葉)」と呼ばれています。これらは単なる方言というだけではなく、琉球王国時代から続く沖縄の歴史や文化、人々の暮らしが色濃く反映された大切な言葉です。まずは、うちなーぐちがどのような言葉なのか、その基本的な情報から見ていきましょう。独特の響きや表現の背景を知ることで、うちなーぐちへの理解がより一層深まるはずです。
うちなーぐちの歴史と背景
うちなーぐちの歴史は、1429年から1879年まで続いた琉球王国時代にさかのぼります。 そのルーツは日本語と同じですが、奈良時代より前には分かれていたと考えられており、発音や文法に独自の変化を遂げてきました。 琉球王国の公用語は首里の言葉が中心でしたが、民衆の間では各地域で異なる言葉が話されていました。
明治時代に入り、政府が標準語の使用を推進したことで、学校教育の場でうちなーぐちの使用が禁止された歴史があります。うちなーぐちを話した児童が「方言札」を首から下げる罰を受けたこともありました。 このような背景から、一時はうちなーぐちを話す人が減少しましたが、近年では沖縄の文化やアイデンティティを象徴するものとして、その価値が見直されています。2006年には9月18日が「しまくとぅばの日」に制定されるなど、うちなーぐちを次世代に継承しようという動きが活発になっています。
地域によって違う?沖縄本島と離島の言葉
「うちなーぐち」と一括りにされがちですが、実は地域によって大きな違いがあるのが特徴です。沖縄本島内でも北部、中南部、そして離島の宮古や八重山、与那国など、それぞれの地域で独自の言葉が発展してきました。
ユネスコ(国連教育科学文化機関)は、琉球列島の言葉を「奄美語」「国頭語(くにがみご)」「沖縄語」「宮古語」「八重山語」「与那国語」の6つの言語に分類しており、これらは互いに意思疎通が困難なほど異なっています。 例えば、ありがとうという感謝の言葉も、沖縄本島では「にふぇーでーびる」ですが、石垣島では「にーふぁいゆー」、宮古島では「たんでぃがーたんでぃ」と全く異なります。
このように、沖縄の言葉は非常に多様性に富んでいます。沖縄本島の中でも、政治や文化の中心であった首里と、商業の街として栄えた那覇とでは言葉に違いがあり、さらに北部の「やんばる」と呼ばれる地域や、各離島でも独自の表現やイントネーションが今なお残っています。
うちなーぐちと標準語の違い
うちなーぐちと標準語には、いくつかの明確な違いがあります。最も顕著な特徴の一つが母音です。標準語の母音が「ア・イ・ウ・エ・オ」の5つであるのに対し、うちなーぐち(特に首里・那覇方言)の基本的な母音は「ア・イ・ウ」の3つとされています。 そのため、標準語の「エ」の音は「イ」に、「オ」の音は「ウ」に変化する傾向があります。例えば、「雨(あめ)」は「あみ」、「雲(くも)」は「くむ」といった具合です。
また、文法にも違いが見られます。動詞や形容詞の活用形が標準語とは異なり、独特の言い回しが生まれます。 例えば、沖縄の人がよく使う「だからよー」という相槌は、標準語の「そうだね」といった同意を示すだけでなく、文脈によってさまざまなニュアンスで使われる便利な言葉です。
さらに、現代の若い世代が話す言葉として「うちなーやまとぐち」というものもあります。これは、伝統的なうちなーぐちと標準語が混ざり合った言葉で、イントネーションや一部の単語にうちなーぐちの特徴を残しつつ、標準語話者にも比較的理解しやすいのが特徴です。
【基本】うちなーぐち一覧|まずは覚えたい挨拶と返事

うちなーぐちを学ぶ上で、最初の一歩となるのが挨拶です。人と会った時や別れる時、感謝を伝える時など、基本的な挨拶を知っているだけで、地元の人々との距離がぐっと縮まります。ここでは、日常生活や旅行中にすぐに使える、基本中の基本となる挨拶のフレーズを一覧でご紹介します。男性と女性で言い方が変わる言葉もあるので、その点もチェックしてみてください。
朝昼晩の挨拶
うちなーぐちの挨拶で最も有名なのが「はいさい」と「はいたい」です。これは時間帯を問わず使える「こんにちは」にあたる便利な言葉で、男性は「はいさい」、女性は「はいたい」を使います。 親しい間柄で使われることが多く、沖縄のローカル番組などでも頻繁に耳にするフレーズです。
より丁寧な「こんにちは」の表現として、「ちゅーうがなびら」があります。 これは「今日拝なびら」と書き、「今日お目にかかります」という意味を持つ、かしこまった場面や目上の人に対して使う言葉です。
朝の挨拶としては「起きみそうちい(起きましたか)」、別れの挨拶としては「んじちゃーびら(さようなら)」や、より気軽な「またやーさい(男性)」「またやーたい(女性)」(またね)などがあります。 お店などに入る際の「ごめんください」は「ちゃーびら」と言います。
感謝と謝罪の言葉
感謝を伝える「ありがとう」は、うちなーぐちで「にふぇーでーびる」と言います。 親切にしてもらった時などに、この言葉をさらっと言えると素敵です。過去形は「にふぇーでーびたん(ありがとうございました)」、さらに感謝の気持ちを強調したい場合は「いっぺーにふぇーでーびる(本当にありがとうございます)」となります。
謝罪の言葉である「ごめんなさい」は、「わっさいびーん」と言います。 また、何かを許す場面で「いいよ」という意味で使われる「済むさ」という言葉もあります。
沖縄には「黄金言葉(くがにくとぅば)」と呼ばれる、人生の教訓や道徳を示すことわざのようなものがあります。その一つに「言葉、銭使(くとぅば、じんじけー)」という言葉があり、「言葉はお金を使うように大切に使いなさい」という意味が込められています。 感謝や謝罪の言葉も、心を込めて使うことが大切にされています。
自己紹介で使えるフレーズ
自己紹介の場面では、まず自分の名前を伝えることが基本になります。「私の名前は〇〇です」は、うちなーぐちで「我(わん)ねー、名前(なめー)や〇〇やいびーん」のように表現できます。「わん」が一人称の「私」にあたります。
相手の名前を尋ねる場合は、「御名前(うなめー)や、何(ぬー)とぅ言い(い)みせーが(お名前は何とおっしゃいますか)」のように聞くことができます。
出身地を伝える際は、「〇〇から来ました」を「〇〇から来(ちゃ)ーびたん」と言います。例えば、「東京から来ました」であれば「東京からちゃーびたん」となります。
これらのフレーズを覚えておけば、沖縄で新しい出会いがあった時に、うちなーぐちで簡単なコミュニケーションをとることができるでしょう。最初は少し恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出して使ってみると、きっと相手も喜んでくれるはずです。
【シーン別】うちなーぐち一覧|旅行や会話で使ってみよう
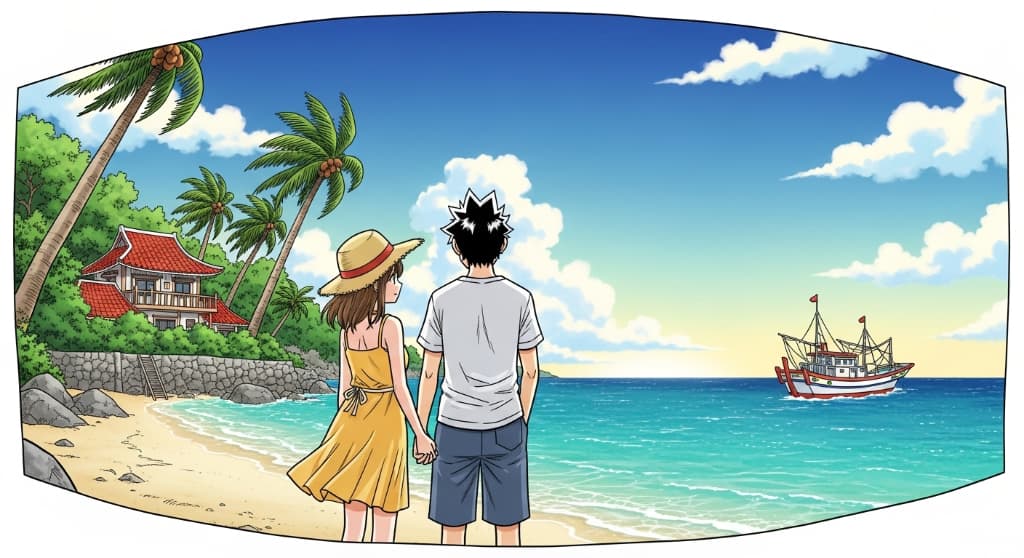
基本的な挨拶を覚えたら、次はさまざまなシーンで使えるフレーズにも挑戦してみましょう。食事の場面や買い物、感情を表現したい時など、具体的な状況で使える言葉を知っていると、沖縄旅行や地元の人との会話がさらに楽しくなります。ここでは、場面ごとに役立つうちなーぐちのフレーズを一覧でご紹介します。
食事の場面で使える言葉(美味しい、乾杯など)
沖縄の食堂や居酒屋でぜひ使ってみたいのが、食事にまつわるうちなーぐちです。食事を始める前の「いただきます」は「くわっちーさびら」と言います。 「くわっちー」は「ごちそう」を意味する言葉で、これに丁寧な表現が加わっています。 食事を終えた後の「ごちそうさまでした」は「くわっちーさびたん」となります。
料理を食べて「美味しい!」と伝えたい時は「まーさん」と言います。 とても美味しいと強調したい場合は、「とても」を意味する「いっぺー」や「でーじ」を付けて、「いっぺーまーさん」や「でーじまーさん」と表現します。 逆に、味が濃くてコクがあることを「あじくーたー」と言います。
お酒の席では、乾杯の音頭として「かりー!」が使われます。 これは「嘉例(かりー)」という言葉から来ており、「めでたい」という意味があります。 沖縄の楽しい雰囲気の中で「かりー!」と声を合わせれば、場が盛り上がること間違いなしです。
買い物で役立つフレーズ
市場やお店での買い物も、うちなーぐちを使ってみる絶好の機会です。「これは何ですか?」と尋ねたい時は「くりや、ぬーやいびーが?」と言います。「これ」は「くり」、「何」は「ぬー」です。「これはいくらですか?」は「くりや、ちゃっさやいびーが?」となります。
何かをお願いする時の「お願いします」は「ゆたしくうにげーさびら」という便利な言葉があります。これは「よろしくお願いします」という意味で、さまざまな場面で使える丁寧な表現です。
お店の人に「ありがとう」と伝える「にふぇーでーびる」はもちろん、店を出る時に「また来ますね」という意味で「またやーさい(男性)」「またやーたい(女性)」と言ってみるのも良いでしょう。 地元の人との温かいやり取りが、旅の良い思い出になるはずです。
感情を伝える言葉(嬉しい、楽しい、驚き)
感情を表現する言葉を知っていると、会話がより生き生きとします。驚いた時に思わず口から出る言葉として「あきさみよー」があります。 これは「あらまあ」「なんてことだ」といったニュアンスで、良いことにも悪いことにも使える便利な感嘆詞です。
嬉しい、楽しいといった気持ちは「うぃーりきさん」と表現します。 美しい景色を見た時などに「きれいだね」と言いたい場合は「ちゅらさんやー」と言います。「ちゅらさん」は「美しい、きれい」という意味です。 とても美しい人、美人を指す場合は「ちゅらかーぎー」という言葉もあります。
愛しい、かわいいという感情は「かなさん」で表します。 子供や孫に対して使うほか、恋人への愛情表現としても使われる素敵な言葉です。 また、気分が良い状態を「いーあんべー」と言います。これは「良い按配」から来ており、お酒を飲んで気持ちよくなった時などにも使われます。
【単語】うちなーぐち一覧|覚えておくと便利な名詞・動詞・形容詞

挨拶やフレーズだけでなく、基本的な単語をいくつか知っておくと、うちなーぐちの理解がさらに深まります。ここでは、人や家族、食べ物、数字といった名詞から、日常でよく使われる動詞や形容詞まで、覚えておくと便利な単語を一覧でご紹介します。これらの単語を組み合わせることで、簡単な文章を作るヒントにもなります。
人や家族を表す言葉
うちなーぐちでは、人や家族を指す独特の言葉があります。まず、沖縄の人のことを「うちなーんちゅ」、本土の人を「やまとぅんちゅ」または「ないちゃー」と呼びます。
家族については、父親を「すー」、母親を「あんまー」と呼びます。 おじいさんは「うすめー」や「たんめー」、おばあさんは「はーめー」や「あんまー」と言うこともあります。 年上の兄弟は「しーじゃ」、年下の兄弟は「うっとぅ」です。 兄弟全般を指して「ちょーでー」という言葉もよく使われます。
また、子供は「わらばー」、男性は「いきが」、女性は「いなぐ」と言います。友達は「どぅし」です。これらの言葉は、沖縄の歌の歌詞などにもよく登場するので、覚えておくとより楽しめるでしょう。
食べ物や飲み物の名前
沖縄の食文化に触れるなら、食べ物の名前をうちなーぐちで覚えておくのがおすすめです。沖縄料理の代表格である炒め物は「ちゃんぷるー」と呼ばれます。 これは「混ぜる」という意味で、ゴーヤーチャンプルー(ゴーヤーの炒め物)などが有名です。
豚の角煮は「らふてー」、豚足は「てびち」です。 豚のあばら肉は「そーき」と呼ばれ、沖縄そばの具としても人気です。 また、ピーナッツから作られる豆腐は「じーまみー豆腐」と言います。「じーまーみ」は落花生を意味します。
野菜では、ヘチマを「なーべーらー」、ヨモギを「ふーちばー」と呼びます。 飲み物では、泡盛の古酒を「くーす」と言います。 このように、沖縄の食卓にはうちなーぐちの名前を持つ食材や料理がたくさん並んでいます。
数字の数え方
うちなーぐちでの数字の数え方は、日本語の「ひとつ、ふたつ」という数え方に似ています。1から10までは以下のようになります。
・1:てぃーち
・2:たーち
・3:みーち
・4:ゆーち
・5:いちち
・6:むーち
・7:ななち
・8:やーち
・9:くくぬち
・10:とぅー
この数え方は、沖縄のわらべ歌などにも登場し、今でも年配の方々の会話で使われることがあります。 11以上になると、標準語と同じように「じゅういち、じゅうに」と数えることが一般的です。 しかし、基本的な1から10までの数え方を知っていると、うちなーぐちの文化に一歩近づけるでしょう。
日常でよく使う動詞・形容詞
日常会話で頻繁に使われる動詞や形容詞も覚えておくと便利です。「行く」は「いちゅん」、「来る」は「ちゅーん」、「食べる」は「かみゅん」、「飲む」は「ぬみゅん」となります。
形容詞では、「大きい」を「まぎー」、「小さい」を「ぐまー」と言います。 「暑い」は「あちさん」、「寒い」は「ひーさん」です。 「良い」は「いー」、「悪い」は「やな」となります。 また、沖縄らしい表現として「てーげー」があります。これは「適当」「ほどほど」といった意味で、沖縄のおおらかな県民性を表す言葉としてよく使われます。
これらの単語は、他の言葉と組み合わせることで、さまざまな表現が可能になります。例えば「でーじあちさん」で「とても暑い」となります。少しずつ単語を覚えて、うちなーぐちの表現の幅を広げていきましょう。
もっとうちなーぐちを学びたいあなたへ

基本的な挨拶や単語に触れて、うちなーぐちにもっと興味が湧いた方もいるのではないでしょうか。幸いなことに、現在ではうちなーぐちを学ぶためのさまざまなツールや機会が存在します。ここでは、独学で学習を進めたい方や、実際にうちなーぐちに触れられるコンテンツを探している方のために、おすすめの学習方法をいくつかご紹介します。
おすすめの学習サイトやアプリ
インターネット上には、うちなーぐちを学べるウェブサイトや辞書が数多く存在します。単語やフレーズを一覧で確認できるサイトや、音声を聞きながら発音を学べるサイトは、初学者にとって非常に役立ちます。 検索エンジンで「うちなーぐち 辞書」や「うちなーぐち 学習」と入力すれば、多くのリソースを見つけることができるでしょう。
また、スマートフォンアプリの中にも、うちなーぐち学習に特化したものがあります。ゲーム感覚で単語を覚えられたり、クイズ形式で理解度を確認できたりするアプリは、隙間時間を使って楽しく学習を続けるのに最適です。YouTubeなどの動画プラットフォームでも、うちなーぐち講座の動画が多数公開されており、ネイティブの発音を聞きながら文法を学ぶことができます。
うちなーぐちが出てくる沖縄の歌や映画
うちなーぐちをより自然な形で耳から学ぶには、沖縄の音楽や映画に触れるのが一番です。沖縄の民謡やポップスには、歌詞のうちなーぐちがふんだんに盛り込まれています。歌詞の意味を調べながら聴くことで、言葉の使われ方や文化的な背景も一緒に学ぶことができます。
また、沖縄を舞台にした映画やテレビドラマも、生きたうちなーぐちに触れる絶好の機会です。登場人物たちの会話の中から、これまで学んだ単語やフレーズが聞こえてくると、学習のモチベーションも上がるでしょう。最初は聞き取れなくても、繰り返し触れているうちに、だんだんと耳が慣れてくるはずです。
うちなーぐち教室やイベント情報
より本格的に学びたい、あるいは実際に話す練習がしたいという方には、うちなーぐち教室や関連イベントに参加することをおすすめします。沖縄県内や、首都圏など沖縄出身者が多く住む地域では、うちなーぐちの講座が開かれていることがあります。 講師から直接指導を受けることで、発音やニュアンスの細かい部分まで理解を深めることができます。
また、沖縄関連の物産展や文化イベントなどでも、うちなーぐちに触れる機会があります。沖縄出身者の方と話す機会があれば、勇気を出して挨拶などを使ってみるのも良い練習になります。多くのうちなーんちゅは、自分たちの言葉に興味を持ってもらえることを喜んでくれるはずです。 聞き流すだけで学べるCD教材なども市販されているので、自分に合った学習方法を見つけてみてください。
うちなーぐち一覧で沖縄をもっと深く知る

この記事では、基本的な挨拶から日常会話で使える単語やフレーズまで、さまざまな「うちなーぐち一覧」をご紹介しました。うちなーぐちは単なる言葉の集まりではなく、琉球王国時代から続く沖縄の豊かな歴史と文化、そして人々の温かい心が詰まった宝物です。
「めんそーれ(いらっしゃい)」や「にふぇーでーびる(ありがとう)」といった言葉一つひとつに、沖縄のおもてなしの精神が表れています。 また、「あきさみよー(あらまあ!)」のような感情豊かな表現や、「なんくるないさ(なんとかなるさ)」という前向きな言葉には、沖縄の人々のしなやかで大らかな気質が感じられます。
地域による言葉の違いを知ることも、沖縄の多様性を理解する上で非常に興味深い点です。 今回紹介した一覧を参考に、ぜひうちなーぐちを覚えて使ってみてください。言葉を知ることで、沖縄の景色がいつもと違って見えたり、地元の人々との交流がより思い出深いものになったりするはずです。うちなーぐちは、あなたと沖縄との距離をぐっと縮めてくれるでしょう。