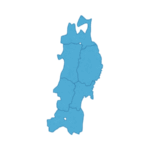兵庫県と聞くと、多くの人が「関西弁」を話すイメージを持つかもしれません。しかし、南北に長い兵庫県では、地域によって言葉が大きく異なることを知っていますか?
この記事では、「兵庫県方言一覧」や「兵庫弁」というキーワードで情報を探している方のために、奥深い兵庫の方言の世界をやさしく解説します。神戸のおしゃれな響きから、播州の力強い言葉、但馬や丹波の少し懐かしい響きまで、実に多様な顔を持っています。それぞれの地域でどのような言葉が話され、どんな特徴があるのか、具体的な例文を交えながらご紹介します。この記事を読めば、あなたもきっと兵庫弁の虜になるはずです。
兵庫県方言一覧の前に知るべき基本!兵庫弁とは?

兵庫県は、摂津、播磨、但馬、丹波、淡路という旧五国から成り立っており、その歴史的背景から地域ごとに独自の文化や言葉が育まれてきました。そのため、「兵庫弁」と一括りにすることは難しく、地域によって方言が大きく異なります。この記事では、それぞれの地域の方言を詳しく見ていく前に、まずは兵庫弁全体の基本的な特徴について解説します。
兵庫弁は1つじゃない?5つの地域で言葉が違う!
兵庫県の方言は、大きく分けて「摂津弁」「播州弁」「但馬弁」「丹波弁」「淡路弁」の5つ、細かく分けると6つに分類されます。
・摂津弁(神戸弁含む):神戸市や尼崎市、西宮市などの阪神間で話される言葉です。大阪弁に近いですが、神戸周辺では「~しとぉ?」といった独特の言い回しがあり、「神戸弁」として区別されることもあります。
・播州弁:姫路市や加古川市など播磨地方で使われます。力強い言い回しが特徴で、「日本一汚い方言」と冗談で言われることもあります。
・但馬弁:県北部の但馬地方で話されます。日本海に面し、鳥取県に近いため、関西弁とは異なる中国方言の影響を受けています。
・丹波弁:丹波篠山市など丹波地方の言葉です。京都府に隣接しているため、京ことばの影響が見られます。
・淡路弁:淡路島で話される方言で、徳島県の阿波弁の影響を強く受けているのが特徴です。
このように、兵庫県内では地域によって全く異なる方言が話されており、同じ兵庫県民でも出身地が違うと話が通じないことがあるほど、多様性に富んでいます。
関西弁とどう違う?兵庫弁のアクセントとイントネーション
兵庫県の方言は、大枠では「関西弁」の一部とされますが、地域によってアクセントに違いがあります。神戸市や姫路市などを含む阪神間や播磨地域は、大阪や京都と同じ「京阪式アクセント」です。 これは、標準語の「東京式アクセント」とは異なり、例えば「橋」を「は」を高く発音するなどの特徴があります。
しかし、同じ兵庫県内でも、北部の但馬地方は「東京式アクセント」に分類されます。 これは、隣接する鳥取県など中国地方の方言が東京式アクセントである影響です。 そのため、但馬地方の人が話す言葉は、他の兵庫県の地域の人からすると標準語に近いイントネーションに聞こえることがあります。
また、神戸弁はゆったりとしたイントネーションで話されることが多く、大阪弁の早口なイメージとは対照的です。 このように、兵庫県内でも地域によってアクセントが異なり、それが各方言の独特の響きを生み出しています。
兵庫弁の歴史的背景と成り立ち
兵庫県の方言がこれほど多様なのは、県の成り立ちが大きく関係しています。現在の兵庫県は、明治時代に摂津国(西部)、播磨国、但馬国、丹波国(東部)、淡路国の旧五国が合併して誕生しました。
それぞれの国は、江戸時代まで異なる藩が治めており、文化や人々の気質も異なっていました。例えば、瀬戸内海に面した摂津や播磨は商業や海運で栄え、上方(京・大坂)との交流が盛んでした。一方、日本海側の但馬は山陰地方との、南の淡路島は四国とのつながりが深い地域でした。
このような地理的・歴史的背景から、それぞれの地域が独自の方言を育んできました。摂津弁は大阪弁と、播州弁は岡山弁と、但馬弁は鳥取弁と、丹波弁は京ことばと、淡路弁は徳島弁と、それぞれ隣接する地域の方言と似た特徴を持っています。 このように、旧五国の文化がモザイク状に組み合わさっていることが、兵庫弁の多様性の源泉となっているのです。
【地域別】兵庫県方言一覧 – 摂津・播磨編

兵庫県の南部、瀬戸内海に面した摂津・播磨地域は、県内で最も人口が多く、経済的な中心地です。大阪や神戸といった大都市の影響を受けつつも、それぞれに個性的な方言が育まれてきました。ここでは、都会的でおしゃれな響きを持つ摂津弁(神戸弁)と、力強く独特な魅力を持つ播州弁について、具体的な表現を交えながら詳しく見ていきましょう。
神戸市・阪神間で使われる「摂津弁(神戸弁)」の特徴的な表現
摂津弁は、主に神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市などで話される方言です。 大阪に隣接しているため大阪弁とよく似ていますが、特に神戸市周辺で使われる言葉は「神戸弁」と呼ばれ、より柔らかくおしゃれな響きを持つのが特徴です。
神戸弁の最も代表的な特徴は、進行形を表す「~しとぉ」と、完了形を表す「~しとう」の使い分けです。 例えば、「今、向かっとぉよ」(今、向かっている最中だよ)は進行形、「もう着いとうよ」(もう着いているよ)は完了形となります。 この使い分けは播州弁とも共通しますが、大阪弁では一般的にどちらも「~してる」と言うため、これを聞くと神戸やその周辺の出身者だとわかります。
他にも、「すごく」を意味する「ばり」や「ごっつー」、「~なの?」と尋ねる「~とん?」など、特徴的な表現があります。 例えば、「このケーキ、ばり美味しいやん!」(このケーキ、すごく美味しいじゃない!)のように使います。 また、「山側(北)」「海側(南)」という言葉で方角を示すのも、六甲山と海に挟まれた神戸ならではの表現です。
姫路市・加古川市周辺の「播州弁」 – ちょっと強面?な魅力
播州弁は、姫路市、加古川市、明石市などを含む播磨地方で話される方言です。 その語感の強さから「怖い」「汚い」と言われることもあり、「日本一ガラの悪い方言」と自虐的に語られることさえあります。 しかし、その裏には飾らない人情味あふれる魅力が隠されています。
播州弁を代表する言葉に「なんどいや」があります。 標準語では「なんですか?」という意味ですが、その強い響きから、知らない人が聞くと喧嘩を売られているように感じてしまうかもしれません。 また、「大丈夫」を意味する「べっちょない」も有名な播州弁です。 「これくらい、べっちょない、べっちょない」といったように、困難な状況でも前向きな気質が表れています。
語尾に「~けぇ」「~どぉ」が付くのも特徴です。「何しとんけぇ?」(何してるの?)、「そら、あかんどぉ」(それはダメだよ)のように使われ、言葉に力強さを与えます。 他にも、「めちゃくちゃ」を「ごじゃ」と言ったり、「腹が立つ」を「ごうわく」と言ったり、独特の語彙が豊富にあります。最初は少し怖く感じるかもしれませんが、慣れると親しみやすく、味のある方言です。
摂津弁と播州弁で意味が変わる言葉
摂津弁(神戸弁)と播州弁は隣接しているため共通の言葉も多いですが、中には同じ言葉でもニュアンスや意味合いが異なるものがあり、注意が必要です。
代表的なのが「だぼ」という言葉です。 これは「どあほ(度阿呆)」が語源とされ、相手を罵る言葉ですが、使われる地域や状況によって深刻度が変わります。神戸などの摂津地域では、親しい友人同士で「アホやなぁ」という軽いニュアンスで「だぼ!」と使うことがあります。 しかし、播州地域、特に姫路周辺では、より強い侮蔑の意味を込めて使われることがあり、喧嘩の場面などで聞かれることもあります。
また、「めげる」という言葉も面白い例です。標準語では「気力がなくなる」といった意味ですが、播州弁では「壊れる」という意味で使われます。 「このテレビ、めげとーわ」(このテレビ、壊れているよ)のように使います。神戸でも通じることはありますが、主に播州地域で使われる表現です。さらに、これを「壊した」と言う場合、神戸では「めんだ」、姫路では「めいだ」となることもあり、微妙な地域差が見られます。 このように、すぐ近くの地域でも言葉の使い方が少しずつ違うのが、兵庫弁の面白いところです。
日常会話で使える摂津・播磨の兵庫弁フレーズ
ここでは、摂津弁(神戸弁)と播州弁の日常会話で使える便利なフレーズをいくつかご紹介します。旅行や知人との会話で使ってみると、ぐっと距離が縮まるかもしれません。
・「これ、なんぼ?」(これ、いくらですか?)
値段を尋ねる際の定番フレーズです。摂津・播磨地域だけでなく、関西一円で通じます。
・「えらいわー」(疲れたー、大変だー)
「えらい」は「偉い」という意味ではなく、「しんどい」「疲れた」という意味で使われます。 「今日の仕事はえらかったわー」のように言います。
・「かなんなぁ」(困ったなぁ、嫌だなぁ)
思い通りにいかない時や、困った時に使う言葉です。 「雨降ってきて、かなんなぁ」といった具合です。
・「ほかす」(捨てる)
「このゴミ、ほかしといて」のように使います。 関西地方で広く使われる言葉ですが、知らないと意味が分かりにくいかもしれません。
・「さらぴん」(新品)
「この服、さらぴんやで」のように、新品のものを指して使います。
・「はりこむ」(おごる)
「今日のランチは俺がはりこむわ!」と言えば、「今日のランチは私がおごるよ!」という意味になります。
これらのフレーズを覚えておくと、地元の人とのコミュニケーションがより一層楽しくなるでしょう。
【地域別】兵庫県方言一覧 – 丹波・但馬・淡路編

兵庫県の魅力は、神戸や姫路といった南部の都市だけではありません。北には日本海に面した但馬、東には京都府と接する丹波、そして南には瀬戸内海に浮かぶ淡路と、豊かな自然に囲まれた地域が広がっています。これらの地域では、南部の摂津・播磨とはまた違った、個性的で味わい深い方言が話されています。ここでは、その3つの地域の方言について、それぞれの特徴と代表的な表現をご紹介します。
京都の影響を受ける「丹波弁」の奥ゆかしい響き
丹波地方は、兵庫県の中東部に位置し、丹波篠山市や丹波市が中心です。古くから京都との文化的な交流が深く、その影響は言葉にも色濃く表れています。 そのため、丹波弁は播州弁のような力強さよりも、京ことばに通じるような、やや柔らかく奥ゆかしい響きを持つのが特徴です。
丹波弁の代表的な表現の一つに、「~ちゃった」があります。これは標準語の「~てしまった」という意味ですが、失敗した時だけでなく、「雨が降ってきちゃった」(雨が降ってきた)のように、単なる完了を表す際にも使われます。 この表現は丹波地方の広い範囲で聞かれます。
また、言葉の端々に京都弁や大阪弁、そして西隣の播州弁の影響が混在しており、話者や地域によって微妙なバリエーションが見られるのも丹波弁の面白いところです。 例えば、敬語表現においては、大阪で使われる「~はる」と、神戸や播磨で使われる「~てや」のような敬語が混在することもあります。こうした様々な方言が混じり合った混沌とした側面も、丹波弁のユニークな魅力と言えるでしょう。
山陰地方との繋がりが見える「但馬弁」のユニークな言葉
但馬地方は、豊岡市や香美町、新温泉町などを含む兵庫県北部の地域です。日本海に面し、鳥取県と隣接しているため、同じ兵庫県内の他の方言とは大きく異なる特徴を持っています。 但馬弁は、近畿方言ではなく、鳥取弁などと同じ「中国方言」に分類され、アクセントも標準語に近い「東京式アクセント」です。 そのため、但馬地方の人が話すのを聞くと、関西人以外の人にとっては比較的聞き取りやすいかもしれません。
但馬弁には、他の地域ではあまり聞かれないユニークな単語がたくさんあります。例えば、「たくさん」「すごい」という意味で「がっせぇ」という言葉を使います。 「がっせぇ雪が降っとる」(すごく雪が降っている)のように使います。また、「大丈夫」という意味の「だんない」も特徴的です。 これは播州弁の「べっちょない」とはまた違った響きがあります。
さらに、断定の助動詞として「~だ」を使うことがあります。 関西のほとんどの地域では「~や」を使うため、これは但馬弁の大きな特徴と言えます。「あれは田中さんの車だ」(あれは田中さんの車や)のようになります。このように、但馬弁は兵庫県の中でも特に独自性が強く、その言葉からは山陰地方との深いつながりが感じられます。
四国との交流が育んだ「淡路弁」ののんびりした表現
淡路島で話されている「淡路弁」は、地理的に近い四国、特に徳島県(旧阿波国)の方言の影響を強く受けているのが最大の特徴です。 江戸時代には淡路島が徳島藩の統治下にあった歴史的背景もあり、言葉の面でも深いつながりが生まれました。 そのため、神戸や大阪の言葉とは一線を画し、ゆったりとした独特の響きを持っています。
淡路弁の面白い表現の一つに、「いぬ」があります。これは動物の「犬」ではなく、「帰る」という意味の動詞です。 「もういぬわ」(もう帰るね)というように使われ、これを知らないと少し驚いてしまうかもしれません。
また、語尾に特徴があり、相槌を求める際に「~だぁ?」という表現が使われます。 例えば、「これ、美味しいやろ?」が淡路弁では「これ、美味しいんだぁ?」といった響きになります。否定の表現では、「できへん」が「できらん」のように、「~らん」という形になるのも特徴的です。 同じ島内でも、南部の由良地区などではさらに難解な方言が話されていると言われ、淡路弁の奥深さを物語っています。
これだけは覚えたい!丹波・但馬・淡路の代表的な兵庫弁
ここでは、丹波・但馬・淡路の各地域を代表する特徴的な方言をいくつかピックアップしてご紹介します。これらの言葉を知っていると、各地域への理解がより一層深まるでしょう。
・「ごーがわく」(丹波・播磨など)
「腹が立つ」という意味です。 「あいつの言い方にはごーがわいたわ」のように使います。
・「なんぎ」(丹波・但馬など)
「疲れた」「しんどい」といった意味で使われる言葉です。元々は「難儀」から来ています。
・「おせらしい」(丹波など)
「大人びている」という意味です。 子供が生意気なことを言った時などに「おせらしいこと言うなぁ」と使います。
・「けったいな」(但馬・丹波など)
「奇妙な」「変な」という意味です。 「けったいな格好しとるな」のように言います。
・「わや」(但馬・播磨など)
「めちゃくちゃ」「台無し」といった意味で、広い範囲で使われます。 「部屋がわやになっとる」は「部屋がめちゃくちゃになっている」という意味です。
・「自分」(兵庫県全域、特に関西広域)
「あなた」という意味で相手を指す時に使います。 親しい間柄で「自分、何しとん?」のように使いますが、慣れないと少し戸惑うかもしれません。
これらの言葉は、それぞれの地域の暮らしや文化の中から生まれてきたものばかりです。その響きや意味を知ることで、兵庫県の多様な魅力を感じてみてください。
シーン別で見る!兵庫弁の使い方とコミュニケーション

兵庫県の方言は、地域によって様々ですが、日常のコミュニケーションの中でどのように使われているのでしょうか。ここでは、挨拶や自己紹介、買い物、感情表現といった具体的なシーンを想定し、兵庫弁がどのように活かされているかをご紹介します。また、他県の人に誤解されやすい表現についても触れていきます。
初対面でも大丈夫?兵庫弁での自己紹介と挨拶
初対面の場面では、多くの人が標準語に近い丁寧な言葉遣いを心がけますが、打ち解けてくると自然と方言が出てくるのが一般的です。
例えば、自己紹介で「姫路から来ました。播州弁なんで、ちょっと言葉がきつく聞こえるかもしれんけど、かんにんしてくださいね」のように、自分の方言について一言添える人もいます。これは、播州弁が持つ「怖い」というイメージを和らげるための、一種の気遣いと言えるでしょう。
挨拶では、親しい間柄になると「おはようさん」「まいど」といった関西共通の表現が使われます。別れ際の挨拶では、神戸弁の「ほなね」 や、より丁寧な「さいなら」 などが使われます。「ほな、また」は「じゃあ、またね」という意味で、気軽な別れの挨拶として頻繁に耳にします。初対面の人にいきなり方言で話しかけることは少ないですが、こうした表現を知っておくと、地元の人との距離が縮まりやすくなります。
買い物や食事で使える便利な兵庫弁
旅行先での買い物や食事の際に、地元の方が使う言葉を知っていると、コミュニケーションがより楽しくなります。
飲食店で鶏肉料理を頼む際、「かしわ」という言葉が使われることがあります。 これは鶏肉を指す方言で、関西地方で広く使われています。「かしわの唐揚げ」のようにメニューに書かれていることもあります。
また、お店で何かを勧めてもらい、断る際には「ええわ、ええわ」と言ったりします。これは「結構です」というニュアンスですが、イントネーションによっては「いいね!」という肯定的な意味にも取られかねないため、表情やジェスチャーと合わせて使うのが良いでしょう。
さらに、食事をご馳走になったり、何かをもらったりした際には、「おおきに」という感謝の言葉が自然と出てきます。 これは「ありがとう」を意味する代表的な関西弁で、兵庫県でも広く使われています。心を込めて「おおきに」と伝えると、相手にも温かい気持ちが伝わるはずです。
感情を豊かに表現する兵庫弁(嬉しい・怒る・悲しい)
兵庫弁には、感情をストレートに、そして豊かに表現する言葉がたくさんあります。
嬉しい時や感動した時には、「めっちゃええやん!」「ごっついええ感じ!」のように、「めっちゃ」「ごっつい」「ばり」といった強調の言葉を使って表現します。神戸弁の「何しとぉ?」のように、語尾を伸ばすことで、親しみや嬉しさを表現することもあります。
一方で、怒りの感情は非常にダイレクトに表現されます。播州弁の「ごうわくわ!」(腹が立つ!) や「なんどいや!」(なんだよ!) は、その代表例です。摂津弁や神戸弁では「ほんま、かなんなー」(本当に困るよ)や「あかんて、それは!」のように、少し柔らかいながらもはっきりと不満を示す表現が使われます。
悲しい時やがっかりした時には、「しょーもないわ…」 や「わやや…」 といった言葉が使われます。「しょーもない」は「つまらない」「くだらない」という意味ですが、どうしようもない状況に対する諦めの気持ちを表す際にも使われます。「わや」は「台無し」「めちゃくちゃ」という意味で、計画がうまくいかなかった時などに「今日の予定、雨でわやになったわ」のように使われます。
勘違いされやすい?注意が必要な兵庫弁の表現
兵庫弁、特に関西弁に馴染みのない人が聞くと、意図せず誤解してしまう可能性のある表現もいくつか存在します。
その代表格が、二人称の「自分」です。 関西地方では、相手を指して「あなた」という意味で「自分」と言うことがあります。 例えば、「自分、どっから来たん?」と聞かれた場合、話している相手が自分のことを尋ねているのであり、決して独り言を言っているわけではありません。
また、「なおす」という言葉も注意が必要です。標準語では「修理する」という意味ですが、兵庫弁を含む関西弁では「片付ける」「元の場所に戻す」という意味で使われます。 「この本、なおしといて」と言われたら、本を修理するのではなく、本棚に戻してほしいという意味になります。
さらに、「モータープール」という言葉を耳にしたら、それは「駐車場」のことです。これは関西特有の和製英語で、他の地域ではほとんど通じません。これらの表現を知っておくと、コミュニケーションの際のすれ違いを防ぐことができます。
もっと知りたい!兵庫弁の豆知識

兵庫弁の地域差や具体的な使い方を知ると、さらにその背景にある文化にも興味が湧いてくるのではないでしょうか。ここでは、兵庫弁がどのようにメディアで描かれているか、また、兵庫県出身の有名人の話し方など、より深く兵庫弁を楽しむための豆知識をご紹介します。
兵庫弁が登場する有名なアニメやドラマ
兵庫県を舞台にしたアニメやドラマは数多くありますが、作中で話される言葉は必ずしも方言に忠実とは限りません。全国放送を意識して、視聴者が理解しやすいように標準語の設定になっている作品も少なくありません。
しかし、中には兵庫弁、特に関西弁の雰囲気を効果的に取り入れた作品もあります。例えば、西宮市が舞台のモデルとされるアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』では、登場人物たちの会話に関西弁のイントネーションや語彙が時折見られます。
また、戦時中の神戸を舞台にしたアニメ映画『火垂るの墓』では、登場人物が話す言葉に当時の神戸の雰囲気が反映されており、物語のリアリティを高めています。 こうした作品を見る際に、キャラクターの言葉遣いに注目してみると、標準語で描かれるのとはまた違った、その土地ならではの空気感や生活感を感じ取ることができるでしょう。
兵庫県出身の有名人とその話し方
兵庫県出身の有名人は数多く、彼らの話し方から兵庫弁の特徴を知ることもできます。
例えば、神戸市出身の女優・戸田恵梨香さんや北川景子さんのインタビューなどでは、時折、神戸弁特有の柔らかいイントネーションが感じられることがあります。
また、お笑い芸人では、ダウンタウンの浜田雅功さん(尼崎市出身)の言葉は、大阪弁に近い摂津弁の特徴をよく表しています。一方で、同じお笑い芸人でも、陣内智則さん(加古川市出身)の話し方には、播州弁のニュアンスが含まれていることがあります。
TikTokで「熊本の彼氏」として人気の杉本琢弥さんは、実は熊本県出身ですが、SNSで人気の小山銀次郎さん(兵庫県出身)は、「日本一有名な背中」として知られ、彼の動画の中での話し方にも注目が集まります。
彼らのメディアでの発言に耳を傾けてみると、出身地域による言葉の微妙な違いが分かり、兵庫弁をより身近に感じられるかもしれません。
兵庫弁を学べる書籍やツール
兵庫弁の多様性や面白さに触れ、もっと深く知りたいと思った方のために、学習に役立つ書籍やツールも存在します。
方言に関する研究書や辞典は、各地域の言葉の成り立ちや文法、語彙などを体系的に学ぶのに適しています。大学の図書館や地域の大きな書店で探してみると、専門的な資料が見つかるかもしれません。
また、より気軽に楽しみたい方には、方言をテーマにしたエッセイや漫画もおすすめです。地元出身の作家が書いた作品には、生き生きとした方言の用例が豊富に登場し、言葉の背景にある文化や人々の暮らしぶりも感じ取ることができます。
最近では、インターネット上にも方言を紹介するウェブサイトやブログ、動画コンテンツなどが数多く存在します。 「兵庫県方言一覧」や「播州弁講座」といったキーワードで検索すれば、ネイティブの発音を聞くことができる動画や、具体的な例文をまとめたサイトを見つけることができるでしょう。こうしたツールを活用して、奥深い兵庫弁の世界をさらに探求してみてはいかがでしょうか。
兵庫県方言一覧でわかる兵庫弁の奥深い世界

この記事では、「兵庫県方言一覧」と「兵庫弁」をテーマに、兵庫県の多様な方言について解説してきました。摂津・播磨・丹波・但馬・淡路という5つの地域で、それぞれ異なる歴史と文化を背景に、個性豊かな言葉が育まれてきたことがお分かりいただけたと思います。
神戸のおしゃれな響きの「神戸弁」、力強い「播州弁」、京都に近い「丹波弁」、山陰地方と繋がる「但馬弁」、そして四国の影響を受けた「淡路弁」など、その魅力は一言では語り尽くせません。 方言は、単なる言葉の違いだけでなく、その土地に住む人々の気質や暮らしを映す鏡でもあります。この一覧を通じて、兵庫県の知られざる奥深い魅力に触れるきっかけとなれば幸いです。