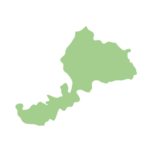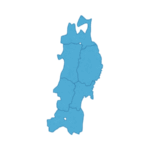福岡と聞くと、多くの人が「博多弁」を思い浮かべるかもしれません。テレビや映画などで耳にする機会も多く、「〜と?」「〜ばい」といった独特の語尾が可愛いと人気ですよね。しかし、実は福岡県内で話されている方言は、博観弁だけではないことをご存知でしょうか? 福岡県は広く、地域によって歴史や文化が異なるため、言葉にもそれぞれ特色があるのです。
この記事では、「福岡の方言一覧」というキーワードで検索してくださったあなたのために、福岡の豊かな方言の世界をわかりやすくご紹介します。有名な博多弁はもちろん、県民でも「え、そんな言葉があるの?」と驚くような地域ごとの方言まで、具体的な使い方やニュアンスを交えながら詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたもきっと福岡の方言博士になれるはず。福岡の知られざる言葉の魅力を、一緒に探っていきましょう。
福岡の方言一覧!地域ごとの特徴を知ろう

福岡県内で話されている方言は、決して一つではありません。県外の人からすると同じように聞こえるかもしれませんが、イントネーションや語感は地域によって全く異なり、福岡県民同士なら出身地が分かるほどです。 一般的に、福岡の方言は大きく4つのエリアに分けられます。
県内でもこんなに違う?福岡の4大方言
福岡県の方言は、主に以下の4つに分類されます。
・博多弁(はかたべん):福岡市を中心に使われる方言
・北九州弁(きたきゅうしゅうべん):北九州市を中心に使われる方言
・筑後弁(ちくごべん):久留米市など県南部で使われる方言
・筑豊弁(ちくほうべん):飯塚市など県中央部で使われる方言
これらの4つの地域は、それぞれ独自の歴史や文化を背景に発展してきたため、方言にも違いが生まれたと考えられています。 例えば、福岡市周辺の博多弁は商業の町として栄えた歴史から親しみやすい響きを持ち、一方でかつて炭鉱で栄えた筑豊地方の筑豊弁は力強い表現が特徴的です。 次の項目から、それぞれの地域の方言について、さらに詳しく見ていきましょう。
福岡市中心部の「博多弁」
博多弁は、福岡市博多区を中心に、現在では福岡市内全域やその周辺地域で広く使われている方言です。 全国的に最も知名度が高く、親しみやすく柔らかい響きが特徴とされています。 語尾に感情を込めやすいイントネーションも特徴の一つで、独特のリズム感が生まれます。
代表的な博多弁には、「なんしようと?」(何をしているの?)、「ばり〜」(とても〜)、「好いとーよ(すいとーよ)」(好きだよ)などがあります。 「なんしようと?」は、単に何をしているか尋ねるだけでなく、久しぶりに会った時の挨拶や、相手の行動に驚いた時など、様々な場面で使われる便利な言葉です。 また、強調を表す「ばり」は、英語の「very」が由来という説もあります。 物を片付けることを「なおす」と言うのも、標準語と意味が異なる特徴的な例です。
語尾も多彩で、「〜たい」「〜ばい」は断定や強調を表し、「〜やけん」は理由を説明する際に使われます。 「〜と?」は疑問を表す可愛らしい語尾として有名ですね。 これらの言葉が、博多弁の温かく、人間味あふれる雰囲気を形作っています。
北九州市周辺の「北九州弁(小倉弁)」
北九州弁は、北九州市を中心に、行橋市や豊前市などの周辺地域で話されている方言です。 「北九弁(きたきゅうべん)」や「小倉弁」とも呼ばれます。 関門海峡を挟んで山口県と隣接しているため、その影響も受けていると言われています。 博多弁に比べると、少し力強い響きが特徴で、地元の人にとっては親しみ深い言葉ですが、他の地域の人には少し荒々しい印象を与えることもあるようです。
北九州弁の最大の特徴は、語尾に「〜ちゃ」や「〜ち」が使われることです。 例えば、「そうだよ」は「そうっちゃ」となり、「好きだよ」は「好きっちゃ」というように、まるでアニメ『うる星やつら』のラムちゃんのような話し方になります。 ちなみに、ラムちゃんの「〜だっちゃ」は富山弁だそうです。 疑問文の語尾は、博多弁の「〜と?」に対して「〜ん?」となるのも違いの一つです。
他にも、「何て言った?」を「なんち?」と言ったり、ほうきで「掃く」ことを「はわく」と言ったりします。 また、腹が立ったり、ふてくされたりすることを「はぶてる」と言うなど、ユニークな表現も多く存在します。
筑後地方の「筑後弁」
筑後弁は、久留米市を中心とした福岡県南部の筑後地方で話されている方言です。 佐賀県や熊本県と隣接しているため、そちらの方言の影響も受けています。 同じ福岡県内でも、博多弁や北九州弁を使う人には意味が分からない言葉も多く、訛りが強いと感じられることもあります。
特徴的な言葉としては、「犬」を「いん」、「これだけ」を「こがしこ」と言うなど、短い単語に独特なものが見られます。 また、「とても、たくさん」を意味する「ばさらか」や、殴るという意味の「くらす」といった言葉もあります。 「くらす」は少し怖い言葉に聞こえますが、「こがしこ ばさらか すらごつゆうて にやがりよると くらすぞ」(これだけ たくさん 嘘をついて にやにやしていると 殴るぞ)といったように、冗談めかして使われることもあります。
アクセントは型がなく、いわゆる無アクセントに分類されるのが大きな特徴です。 語尾には「〜ばい」「〜たい」「〜けん」をよく使い、これらは博多弁とも共通しますが、イントネーションが異なるため、受ける印象はかなり違います。
筑豊地方の「筑豊弁(嘉飯弁)」
筑豊弁は、飯塚市や田川市を中心とする筑豊地方で話されている方言です。 かつて炭鉱地帯として栄え、全国から多くの労働者が集まった歴史的背景から、力強く簡潔な表現が特徴となっています。 そのため、特に男性が使うと、博多弁や北九州弁よりもさらに迫力のある方言に感じられることがあります。
筑豊弁では、理由を表す接続助詞として「〜き」を使います。博多弁の「〜けん」や北九州弁の「〜け」にあたる言葉です。 例えば、「分からないから教えて」は「分からんき、教えて」となります。 また、調子に乗る、ふざけるといった意味で「とんぴんつく」というユニークな言葉もあります。
筑豊地方は旧筑前国と旧豊前国にまたがっているため、地域によって方言に違いが見られます。 飯塚市周辺の「飯塚弁」と、田川市周辺の「田川弁」に大きく分けられ、田川弁は北九州弁に近い豊日方言の要素が強いとされています。 一方で、直方市周辺は、筑豊弁の中でも特に博多弁などに近い肥筑方言の要素が強い地域です。 このように、同じ筑豊エリア内でも多様な言葉が話されています。
【場面別】福岡の方言一覧【日常会話で使えるフレーズ】

福岡の方言は、地域ごとの違いだけでなく、日常のさまざまな場面で使われることで、より生き生きとした表情を見せます。ここでは、挨拶や気持ちを伝えるときなど、具体的なシチュエーションで使える福岡の方言を一覧でご紹介します。これらのフレーズを知っていれば、福岡の人々とのコミュニケーションがもっと楽しくなるかもしれません。
挨拶で使える福岡の方言
福岡では、標準語の「こんにちは」にあたる直接的な挨拶言葉はあまり使われず、代わりに相手の状況を尋ねるような声かけが挨拶として機能します。
その代表格が「なんしようと?」です。 これは「何をしているの?」という意味ですが、道端でばったり会った知人に対して「やあ、元気?」といったニュアンスで使われます。 同様に、「どげんしたと?」という言葉も「どうしたの?」という意味合いで、挨拶代わりに使われることがあります。
また、丁寧な挨拶としては、「おはようございますばい」のように語尾に「ばい」を付けることがあります。 人の家を訪ねた際には、「ごめんください」の意味で「ごめん」と言ったりします。別れ際には「またね」の意味で「またねー」や「じゃあね」が一般的です。感謝を伝える「ありがとう」は、「ありがとねー」や「いつもありがとう」のように、少し親しみを込めた言い方をすることが多いです。丁寧な場面では標準語と同じく「ありがとうございます」が使われます。
気持ちを伝える福岡の方言
感情を表現する言葉にも、福岡ならではの言い回しがたくさんあります。嬉しい時、楽しい時、悲しい時、さまざまな気持ちを表す方言を見ていきましょう。
嬉しい気持ちや肯定的な感情を表す際には、「よかよ」がよく使われます。 これは「良いよ」という意味で、快く承諾する場面などで活躍する言葉です。 誰かに褒められた時には、「そんなことないよ」と謙遜しつつも嬉しい気持ちを込めて「そげんことなかよ〜」と言ったりします。
愛情を伝える言葉としては、「好いとーよ(すいとーよ)」が非常に有名です。 標準語の「好きだよ」にあたります。告白の場面では「好きっちゃん」や「好きやけん、付き合ってくれん?」といった表現も使われます。
一方で、面倒くさい、うるさいといったネガティブな気持ちを表す時には「しゃーしい」や「せからしか」という言葉が使われます。 「せからしか」の方がより強い表現です。 驚いた時には「わいたー!」や「あいたー!」といった感嘆詞が咄嗟に出ることもあります。 これらの言葉は、感情をストレートに表現する福岡県民の気質を表しているのかもしれません。
質問するときに便利な福岡の方言
何かを尋ねたいとき、福岡の方言には特徴的な疑問の表現があります。特に語尾の変化に注目です。
最もポピュラーなのは、博多弁で使われる「〜と?」という語尾でしょう。 「何してるの?」は「なんしようと?」、「これは何?」は「これなんと?」という具合です。この柔らかい響きが、尋ねる口調を優しく聞かせます。
一方で、北九州弁では「〜ん?」という語尾が使われます。 例えば、「何してるの?」は「なんしよーん?」となります。 また、「何て言った?」と聞き返す際には「なんち?」という短いフレーズが便利です。
筑後弁では、準体助詞(〜のもの、〜のこと、の意)に「つ」を使う特徴があり、「何ばしよっとか?」のように質問することがあります。 相手の意向を尋ねる際には、「来るの?」を「来るとね?」や「こんね?」と言ったり、「どうですか?」を「どうね?」と聞いたりすることもあります。 また、「〜かな?」という意味で「〜かいな?」という語尾も使われます。 これらの疑問表現を使いこなせると、より地元の人らしい会話ができるようになります。
相づちで使える福岡の方言
会話を弾ませる上で欠かせないのが相づちです。福岡の方言には、会話のリズムを良くするユニークな相づちがたくさんあります。
同意や納得を示す相づちとして、「そうっちゃんね〜」や「なるほどですね」があります。 「そうっちゃんね〜」は「そうなんだね〜」という意味で、相手の話に共感していることを示します。 「なるほどですね」は、標準語の「なるほど」と同じ意味ですが、丁寧な印象を与えようとする福岡県民の気質から生まれた表現と言われています。
相手の話を促す時には、「で?」や「そいで?」のように使います。「それで?」という意味です。驚きを表す相づちとしては、「ほんなこつ?」(本当に?)や、感心した時に使う「へぇー、すごかー」などがあります。
また、博多弁では「そうたい」「そうばい」といった言い方もされます。これは「そうだよ」という意味で、相手の言ったことを肯定する際に使われます。これらの相づちを会話の中に挟むことで、ぐっと福岡らしいやり取りになるでしょう。
かわいい響きが魅力!女の子が使うと可愛い福岡の方言一覧

福岡の方言、特に博多弁は「女性が話すとかわいい方言」として全国的に人気があります。 独特の語尾や柔らかいイントネーションが、聞く人に親しみやすく、愛らしい印象を与えるようです。 ここでは、特に女の子が使うと魅力が増すと言われる、かわいい福岡の方言をいくつかピックアップしてご紹介します。
女の子らしい語尾「〜と?」「〜っちゃん」
福岡の方言がかわいいと言われる大きな理由の一つに、その特徴的な語尾が挙げられます。 中でも「〜と?」と「〜っちゃん」は、その代表格と言えるでしょう。
「〜と?」は、博多弁で質問する際に使われる語尾です。 「なにしてるの?」が「なんしようと?」、「元気?」が「元気と?」というように、語尾につけるだけで、尋ねる言葉が一気に柔らかく、可愛らしい響きになります。甘えているような、少し首をかしげながら聞いているような、そんな情景が目に浮かぶようです。
一方、「〜っちゃん」は「〜だよ」「〜だよね」という意味で使われる語尾です。 例えば、「今日ね、美味しいケーキ食べたっちゃん!」(今日、美味しいケーキ食べたんだよ!)のように使います。 自分の話を聞いてほしい、同意してほしいというニュアンスが含まれており、親しみを込めて話している感じが伝わります。語尾が「ん」で終わる優しい響きも、可愛らしさを引き立てるポイントです。
甘えた響きの「すいとーよ」
福岡の方言で愛情を伝える言葉といえば、「すいとーよ」が有名です。 これは標準語の「好きだよ」にあたる言葉で、その甘く優しい響きから、告白のセリフとして絶大な人気を誇ります。実際に気になる相手からこんな風に言われたら、思わずドキッとしてしまう人も多いのではないでしょうか。
ただし、地元の若い世代の日常会話、特に改まった告白の場面で「すいとーよ」が頻繁に使われるかというと、実はそうでもないようです。 むしろ「好きっちゃん」や「好きやけん」といった表現の方が一般的かもしれません。
それでも「すいとーよ」という言葉が持つ特別な響きは、多くの人の心を掴んで離しません。直接的すぎず、それでいて温かい愛情が伝わるこの言葉は、福岡の方言の魅力を象徴するフレーズの一つと言えるでしょう。
頼るときに可愛い「〜してくれん?」
誰かにお願いごとをするとき、福岡の方言では「〜してくれん?」という表現がよく使われます。これは標準語の「〜してくれない?」にあたる言葉です。
例えば、「ちょっと手伝ってくれん?」や「これ、持っててくれん?」といった形で使います。命令形ではなく、相手に優しく問いかけるような形なので、言われた側も嫌な気持ちがせず、つい「よかよ(いいよ)」と引き受けたくなってしまうような魅力があります。
この「〜くれん?」という言い方は、少し甘えたような、相手を頼りにしているようなニュアンスを含んでいます。そのため、特に女性が使うと、控えめで可愛らしい印象を与えるようです。このフレーズを上手に使うことで、お願いごともスムーズに、そして和やかな雰囲気で伝えることができるでしょう。福岡の人々の円滑なコミュニケーションを支える、便利な表現の一つです。
知っていると面白い!特徴的な福岡の方言一覧

福岡の方言には、かわいい響きの言葉だけでなく、標準語話者が聞くと意味を誤解してしまいそうな言葉や、独特のイントネーションを持つ面白い言葉もたくさん存在します。ここでは、知っていると福岡通になれる、そんな特徴的な方言をいくつかご紹介します。これらの言葉を知れば、福岡の文化への理解がさらに深まるはずです。
イントネーションが独特な言葉
福岡の方言、特に博多弁は、言葉そのものだけでなく、その独特なイントネーション(言葉の抑揚やリズム)も大きな特徴です。 県外の人が真似をしようとしても、なかなか上手くいかないと言われるほどです。
その代表例が、博多弁の有名な早口言葉「おっとっととっとってっていっとったとになんでとっとってくれんかったとっていっとーと」です。 これは「(お菓子の)おっとっとを取っておいてって言ったのに、なんで取っておいてくれなかったのって言ってるの」という意味です。 文字で見ると暗号のようですが、地元の人が話すと、流れるようなリズムと独特の抑揚で、意味がすっと通じるから不思議です。
また、「そげんあるとね」という相づちも、イントネーションによって意味合いが変わります。 フラットな抑揚なら「へぇ、そうなんだ」という軽い相づちですが、語尾を上げて言うと「本当にそうなの?」という驚きや疑いのニュアンスが含まれます。このように、同じ言葉でもイントネーション一つで感情の機微を表現するのが、福岡の方言の面白いところです。
意味が標準語と少し違う言葉
福岡の方言には、標準語と同じ言葉なのに、全く違う意味で使われる単語がいくつか存在します。これを知らないと、会話が噛み合わなくなってしまうかもしれません。
代表的なのが「なおす」です。 標準語では「修理する」という意味ですが、福岡では「片付ける」「元の場所に戻す」という意味で使われます。 ですから、福岡の家庭で「このおもちゃ、なおしといてね」と言われたら、壊れているわけではなく「片付けなさい」という意味なので注意が必要です。
また、「はわく」は標準語の「掃く」と同じ意味ですが、一文字違うだけで方言だと気づかずに使っている県民も多い言葉です。 さらに、リュックサックなどを「背負う」ことを「からう」と言います。 これは福岡だけでなく、九州の広い地域で使われる方言です。 食べ物に関する言葉では、唐辛子のことを「こしょう」と呼ぶ地域(特に筑後地方)もあります。 初めて聞くと、何を指しているのか戸惑ってしまうかもしれませんね。
博多祇園山笠で使われる特別な言葉
福岡の夏を代表する祭り「博多祇園山笠」では、この祭りの期間中だけに使われる独特な言葉があります。その一つが「きゅうり断ち」です。
祭りに参加する男衆は、約2週間の山笠の期間中、きゅうりを食べることを禁じられています。その理由は、きゅうりを輪切りにした時の断面が、博多の総鎮守である櫛田神社の御神紋(祇園守紋)に似ているため、口にするのは恐れ多い、というものです。この風習は今でも固く守られており、山笠関係者の家庭では、この期間中、食卓にきゅうりが出ることはありません。
また、山笠の舁き手(かきて)のことを「おいしゃん」と呼ぶことがあります。これは本来「おじさん」を意味する博多弁ですが、山笠においては、親しみと敬意を込めて、経験豊富な先輩の舁き手などを指して使われます。 このような特別な言葉からも、祭りが地域に深く根付いていることがうかがえます。
福岡の方言一覧【品詞別で学ぶ】

福岡の方言をより深く理解するために、ここでは品詞(言葉の種類)ごとに特徴的なものをいくつか見ていきましょう。助詞や助動詞といった文法的な要素から、日常的によく使う動詞や形容詞まで、具体的な例を挙げて解説します。言葉の仕組みを知ることで、方言の面白さがさらに増すはずです。
特徴的な助詞・助動詞
助詞や助動詞は、文の骨格を作る重要な要素です。福岡の方言には、会話のニュアンスを豊かにする独特な助詞・助動詞がたくさんあります。
・〜ばい、〜たい:断定や強調を表す終助詞。 「〜だよ」という意味で使われます。若者言葉では「〜ちゃん」が使われることも多いです。
・〜けん、〜き:理由や原因を表す接続助詞。「〜だから」という意味です。 博多弁では「〜けん」、筑豊弁では「〜き」が主に使われます。
・〜と?:疑問を表す終助詞。「〜なの?」という意味で、博多弁でよく使われます。
・〜くさ:強調を表す間投助詞。「〜だよ」という意味で、少しぞんざいな印象を与えることもあります。博多弁で使われますが、最近の若者はあまり使いません。
・〜ばってん:逆接の接続助詞。「〜だけれども」という意味です。
・〜ごつ、〜ごと:比況の助動詞。「〜のように」という意味です。筑後弁で「すらごつゆうて(嘘を言って)」のように使われます。
これらの助詞や助動詞が、福岡の方言独特のリズムと響きを生み出しています。
よく使われる動詞
日常の動作を表す動詞にも、福岡ならではの面白い言葉がたくさんあります。標準語とは異なるユニークな表現を見ていきましょう。
・からう:標準語の「背負う」にあたります。 ランドセルやリュックを背負うときに使います。
・なおす:標準語の「片付ける」「元に戻す」という意味です。
・はわく:標準語の「掃く」です。 ほうきで床などをきれいにします。
・かたす:仲間に入れる、参加させるという意味です。「かてて」と頼む形でよく使われます。
・くらす:筑後弁や筑豊弁で使われる言葉で、「殴る」という意味です。 「食らわす」が変化した言葉とされています。
・いもる:筑豊弁で「びびる」「怖気付く」という意味です。
・なんかかる:北九州弁で「寄りかかる」「もたれかかる」という意味です。
・はぶてる:北九州弁で「ふてくされる」「すねる」という意味です。
これらの動詞を知っていると、福岡の人々の日常会話がより具体的にイメージできるのではないでしょうか。
感情を表す形容詞
感情や状態を表す形容詞にも、福岡の方言ならではの言葉があります。豊かでストレートな感情表現が特徴です。
・よか:標準語の「良い」にあたります。 許可や肯定を示す「よかよ」という形でよく使われます。
・しゃーしい:うるさい、やかましい、面倒くさい、といった意味で使われます。
・せからしか:「しゃーしい」と似た意味ですが、より強い苛立ちを表します。
・きない:筑豊弁で「黄色い」を意味する言葉です。
・ふうたんぬるい:筑豊弁で「生ぬるい」「ぼんやりしている」といった意味で使われます。人の性格を指して言うこともあります。
・はがいい:北九州弁で「はがゆい」「もどかしい」という意味です。
・すごか:標準語の「すごい」にあたります。形容詞の語尾が「〜い」ではなく「〜か」になるのは、古い日本語の形を残しているもので、「カ語尾」と呼ばれます。 ただ、現在では「よか」以外はあまり使われなくなっています。
これらの形容詞は、話し手の感情を生き生きと伝え、会話に彩りを添えます。
便利な副詞
言葉を修飾し、意味をより豊かにする副詞にも、福岡の方言らしい表現が見られます。会話の中で強調したいときなどに使われる便利な言葉です。
・ばり:標準語の「とても」「すごく」にあたる言葉で、博多弁でよく使われます。 「ばりすごい」「ばりかわいい」のように、形容詞や動詞を強調します。
・ちかっぱ:「ばり」と似た意味ですが、さらに強調したいときに使われます。 「力いっぱい」が語源とされています。
・そーとー:北九州弁で「とても」「かなり」という意味で使われます。
・ばさらか:筑後弁で「たくさん」「ものすごく」といった意味です。量が多いことや程度が甚だしいことを表します。
・いっちょん:北九州弁などで使われ、後に否定の言葉を伴って「全く〜ない」「全然〜ない」という意味になります。
・ほんなこつ:標準語の「本当に」にあたります。 相づちとしてもよく使われます。
これらの副詞を使いこなせると、表現の幅が広がり、よりネイティブに近い福岡の方言を話せるようになるでしょう。
まとめ:福岡の方言一覧から見えてくる言葉の多様性と魅力

この記事では、福岡県内で話されている多様な方言を「福岡の方言一覧」として、地域別、場面別、品詞別にご紹介してきました。一般的に知られている博多弁だけでなく、北九州弁、筑後弁、筑豊弁といった、それぞれに個性豊かな方言が存在することをお分かりいただけたかと思います。
語尾に「〜ちゃ」がつく北九州弁や、無アクセントが特徴の筑後弁、力強い響きの筑豊弁など、同じ福岡県内でも言葉に大きな違いがあるのは、それぞれの地域が育んできた歴史や文化が深く関係しています。 また、「なおす」が「片付ける」という意味であったり、「からう」が「背負う」を意味したりと、標準語との違いを知るのも方言の面白い点です。
方言は、単なる言葉の違いだけでなく、その土地に暮らす人々のアイデンティティや気質、コミュニケーションのあり方を映し出す鏡のようなものです。 この記事を通じて、福岡の方言が持つ温かさや面白さ、そしてその奥深さに触れ、福岡という土地への興味をさらに深めていただけたなら幸いです。