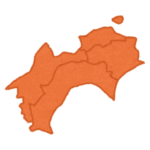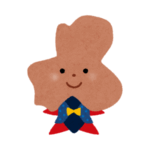「やっとかめ(お久しぶり)!」「どえらい(すごい)ええ記事だがや(ですね)!」なんて、街で聞こえてきたら、そこはもう名古屋かもしれません。
愛知県西部、かつての尾張国で話される「尾張弁」は、一般的に「名古屋弁」として知られています。独特の語尾やイントネーションが特徴で、ちょっぴり無骨ながらも、どこか温かみと親しみやすさを感じさせる方言です。この記事では、そんな尾張弁の魅力を余すところなくお伝えするため、「尾張弁一覧」として基本的な単語から日常会話で使えるフレーズまで、分かりやすくまとめました。尾張弁の歴史や三河弁との違いも解説しますので、この記事を読めば、あなたも尾張弁マスターになれること間違いなしです!
尾張弁一覧の前に知っておきたい!尾張弁の基本情報

尾張弁を深く理解するためには、その背景にある基本的な情報を知っておくことが大切です。ここでは、尾張弁がどのような方言で、どこで話され、どのような歴史を歩んできたのかを解説します。また、同じ愛知県内で話される三河弁との違いにも触れ、愛知県の方言の全体像を明らかにしていきます。
尾張弁ってどんな方言?話されている地域はどこ?
尾張弁とは、現在の愛知県西部にあたる旧尾張国で話されている日本語の方言です。 一般的には「名古屋弁」という呼び名で広く知られており、名古屋市を中心にその周辺地域で使われています。 厳密には、名古屋市中心部の方言を「狭義の名古屋弁」、一宮市などの北尾張地域や知多半島などを含む尾張地方全体の方言を「尾張弁」として区別することもありますが、この記事では尾張地方全体の方言として扱います。
尾張弁の大きな特徴として、語尾に「~だがや」「~だがね」といった濁音を用いたり、「~みゃあ」といった独特の言い回しをしたりする点が挙げられます。 また、2つの母音が連続する場合に、1つの母音を伸ばして発音する傾向もあります。 例えば、「無い」が「にゃー」に近い発音になるのは、この特徴の表れです。 アクセントは東京式アクセントに分類されますが、文法的には関西弁のような西日本方言の要素を多く含んでいるのも面白い点です。 これは、尾張が日本の東西を結ぶ交通の要衝であった歴史的背景が関係していると考えられます。
尾張弁の歴史と文化的背景
尾張弁のルーツは、江戸時代にまで遡ると言われています。 当時の名古屋は、徳川御三家の一つである尾張藩の城下町として、また、交通の要衝として大いに栄えました。織田信長が推し進めた「楽市楽座」によって多くの商人が尾張に集まり、全国の方言が混ざり合って現在の名古屋弁の基礎が形成されたと考えられています。
名古屋の言葉は、大きく分けて2つの種類があったとされています。 一つは、名古屋城下の武士たちが使っていた、丁寧で上品な「上町(うわまち)言葉」。 これは「~なも」「~なもし」といった柔らかな語尾が特徴です。 もう一つは、商人や職人たちが使っていた、活気のある「下町言葉」で、「~がや」「~がね」といった歯切れの良い言い方が特徴です。 戦後の都市化などにより、かつての上品な上町言葉は少しずつ使われなくなり、下町言葉が現代の名古屋弁の主流となっていきました。 このように、尾張弁は城下町としての歴史の中で、様々な階級の人々の言葉が交じり合いながら、独自の発展を遂げてきたのです。
三河弁との違いは?愛知県の方言事情
愛知県は、かつて西側の「尾張国」と東側の「三河国」に分かれていました。 この歴史的な背景から、現在でも方言は大きく「尾張弁(名古屋弁)」と「三河弁」の2つに大別されます。
両者の違いは明確で、まず語尾が大きく異なります。尾張弁が「~だがや」「~なも」などを使うのに対し、三河弁では「~じゃん」「~だら」「~りん」といった表現が使われます。 例えば、何かを勧めるとき、尾張弁では「食べやあ(食べなさい)」となりますが、三河弁では「食べりん(食べなさいよ)」のようになります。
また、発音やアクセントにも違いが見られます。尾張弁では「無い (nai)」が「にゃー (nyā)」のように母音が融合する連母音の変化が起こりますが、三河弁ではこの変化はあまり見られません。 形容詞のアクセントも異なり、例えば「赤い」は尾張弁では真ん中の「か」を高く発音しますが、三河弁では平坦に発音します。
このように、同じ愛知県内でも尾張と三河では言葉に大きな違いがあり、それぞれが独自の文化を育んできたことが分かります。 ちなみに、旧尾張国に属する知多半島の方言は、三河弁に近い特徴を持つため、西三河方言に分類されることもあります。
【保存版】日常で使える尾張弁一覧!基本の単語とフレーズ

ここからは、いよいよ実践編です。日常会話で頻繁に使われる尾張弁の単語やフレーズを一覧でご紹介します。独特の語尾から、感情を豊かに表現する言葉まで、これを覚えればあなたも名古屋の街に溶け込めるはずです。例文を参考に、使い方をマスターしてみましょう。
名古屋弁の代名詞!「~だがや」「~みゃあ」の使い方
尾張弁と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、「~だがや」や「~みゃあ」といった特徴的な語尾ではないでしょうか。これらは名古屋弁の代名詞とも言える表現ですが、実は使われる場面やニュアンスが異なります。
「~だがや」「~だがね」は、主に断定や同意を求める際に使われる下町言葉由来の表現です。 「そうだ」という意味の「だ」に、強調の「が」と終助詞の「や」「ね」が付いた形で、「~だよ」「~だよね」といったニュアンスになります。
・例文:「このひつまぶし、でらうみゃあだがや!(このひつまぶし、すごく美味しいですね!)」
・例文:「明日の飲み会、来るんだがね?(明日の飲み会、来るんだよね?)」
一方、「~みゃあ」は、動詞の命令形や勧誘の表現で使われます。「~しなさい」「~しようよ」という意味合いです。「見なさい」が「見やあ」、「食べなさい」が「食べやあ」というように変化します。
・例文:「はよ、こっちへ来やあ。(早く、こっちへ来なさい。)」
・例文:「映画でも見に行こみゃあ。(映画でも見に行こうよ。)」
最近の若い世代ではあまり使われなくなってきたとも言われますが、これらの表現は尾張弁の個性を象徴する大切な言葉です。
感情を豊かに表現する形容詞・副詞(「どえらい」「でら」など)
尾張弁には、感情を豊かに、そして強調して伝えるための形容詞や副詞がたくさんあります。これらを使いこなせると、会話がより生き生きとしたものになります。
・どえらい、でら:「とても」「すごく」という意味の強調表現です。「どえらい」は少し古い言い方で、年配の方が使うことが多いかもしれません。「でら」は若者言葉として広まり、現在では世代を問わず使われています。
・例文:「今日の祭りは、どえらい人だがね。(今日のお祭りは、すごい人出だね。)」
・例文:「この味噌カツ、でらうまい!(この味噌カツ、すごく美味しい!)」
・えらい:「疲れた」「しんどい」という意味で使われます。 標準語の「偉い」とは全く意味が異なるので注意が必要です。
・例文:「一日中歩き回っとったで、えらいわ。(一日中歩き回っていたから、疲れたよ。)」
・あんばよう:「うまく」「具合よく」という意味の言葉です。 何かを慎重に行うよう促すときなどに使われます。
・例文:「このプラモデル、あんばように組み立てなあかんで。(このプラモデル、うまく組み立てないといけないよ。)」
これらの言葉は、名古屋の人々の感情の機微を表現するのに欠かせないものばかりです。
日常会話で頻出する動詞・名詞(「かう」「放課」など)
尾張弁には、標準語とは異なる意味で使われる動詞や、独特の名詞が存在します。これらを知っていると、地元の人との会話がよりスムーズになります。
・かう:「(鍵を)かける」という意味で使われます。「買う」と同じ発音ですが、文脈で判断します。
・例文:「出かける前に、ちゃんと鍵かっといてよ。(出かける前に、ちゃんと鍵をかけておいてよ。)」
・つる:「(机などを)運ぶ」という意味です。標準語の「吊る」とは違い、水平方向の移動にも使われます。 学校の掃除の時間などで「机をつる」という指示がよく聞かれます。
・例文:「掃除するで、机を後ろへつってちょうだい。(掃除するから、机を後ろへ運んでください。)」
・放課(ほうか):「授業と授業の間の休み時間」を指します。標準語の「放課後」とは意味が異なるため、注意が必要です。名古屋の学校では「今日の2限の放課に…」といった使い方がされます。
・ケッタ:「自転車」のことです。 「ケッタマシーン」とも言います。 比較的広い世代で使われる言葉ですが、最近の若者は「チャリ」と言うことも増えています。
・例文:「駅まで遠いもんで、ケッタで行くわ。(駅まで遠いから、自転車で行くよ。)」
これらの言葉は、名古屋の日常生活に深く根付いています。
驚きや感動を伝える感嘆詞(「まあ、いかんわ」など)
感情が動いたときに思わず口から出てしまう感嘆詞にも、尾張弁ならではの表現があります。驚きや落胆、感動など、様々な場面で使われる言葉を知っておくと、よりネイティブらしい会話ができます。
・まあ、いかんわ:「まあ、だめだ」「なんてことだ」といった、驚きや落胆、あきれた気持ちを表す言葉です。「いかん」は「だめ」という意味で、非常によく使われます。
・例文:「終電、行っちゃったわ。まあ、いかんわ。(終電、行ってしまった。ああ、だめだ。)」
・うそだがね!:「うそでしょ!」という驚きを表す言葉です。信じられないような話を聞いたときに使います。
・例文:「宝くじで100万円当たったの!?うそだがね!」
・やっとかめ:「お久しぶり」という意味の挨拶言葉です。 「八十日目」が語源とされ、長い間会っていなかった相手に対して使います。 日常会話で頻繁に使われるわけではありませんが、尾張弁を象徴する言葉として知られています。
・例文:「鈴木さん、やっとかめだなも!(鈴木さん、お久しぶりですね!)」
これらの感嘆詞を使いこなせれば、あなたの感情表現もより豊かになり、名古屋の人々との心の距離もぐっと縮まるでしょう。
シーン別・尾張弁一覧!会話で使ってみよう

覚えた尾張弁を実際に使ってみたくなりますよね。ここでは、具体的な会話シーンを想定して、すぐに使える尾張弁のフレーズを一覧で紹介します。挨拶から買い物、友人との会話まで、様々な場面で役立つ表現を学び、自然な尾張弁でのコミュニケーションを目指しましょう。
挨拶で使う尾張弁(「やっとかめ」など)
人との交流は挨拶から始まります。尾張弁には、温かみのある挨拶表現がいくつかあります。
・やっとかめ:前述の通り、「お久しぶり」という意味の、最も有名な尾張弁の挨拶の一つです。 しばらく会っていなかった友人や知人に再会した際に使うと、相手もきっと喜んでくれるでしょう。
・会話例:「田中さん、やっとかめだなも!元気しとった?(田中さん、お久しぶりです!お元気でしたか?)」
・ようこそおいでんさった:丁寧な「いらっしゃいませ」です。「ようこそおいでくださいました」という意味で、お客様を歓迎する気持ちが伝わります。
・会話例:「まあ、山田さん!ようこそおいでんさった。ささ、上がってちょうだい。(まあ、山田さん!よくいらっしゃいました。さあさあ、お上がりください。)」
・おはようさん、こんにちはさん、こんばんはさん:「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」を少し丁寧にした言い方です。「~さん」を付けることで、親しみを込めつつも丁寧な響きになります。
・会話例:「おはようさん。今日はええ天気だがね。(おはようございます。今日はいい天気ですね。)」
これらの挨拶を使うことで、初対面の人とも和やかな雰囲気を作ることができるでしょう。
買い物や食事の場面で役立つ尾張弁
名古屋の商店街や飲食店では、今でも活気のある尾張弁が飛び交っています。買い物や食事の際に使えるフレーズを知っておくと、地元の人との交流がもっと楽しくなります。
・お値打ち(おねうち):「お買い得」という意味で使われます。 価格が安いことを表す際に使われる言葉で、スーパーのポップなどでもよく見かけます。
・会話例:(店員)「この味噌、今日はお値打ちだがや!」(お客)「じゃあ、これいただこかな。(じゃあ、これをいただこうかな。)」
・まける:「値引きする」という意味の動詞です。商店街などでの値段交渉の際に使われることがあります。
・会話例:「お母さん、これもうちょっとまからん?(奥さん、これもう少し値引きできませんか?)」
・ひきずり:すき焼きのことです。鍋の中で肉を引きずるようにして食べたことから、この名で呼ばれるようになったと言われています。鶏肉を使ったすき焼きを指すことが多いです。
・会話例:「今晩のおかずは、ひきずりにしょまいか。(今晩のおかずは、すき焼きにしようか。)」
・しゃびしゃび:料理などの水分が多くて薄い状態を指します。 例えば、カレーのルーが水っぽいときなどに使います。
・会話例:「この味噌汁、ちょっとしゃびしゃびだで、もう少し味噌足そか。(この味噌汁、少し薄いから、もう少し味噌を足そうか。)」
これらの言葉を使えば、あなたも名古屋の食文化や商人の文化に一歩踏み込むことができるでしょう。
友達や家族との親しい会話で使う尾張弁
気心の知れた友人や家族との会話では、よりくだけた、親しみやすい尾張弁が使われます。リラックスした雰囲気の中で使われる自然な表現をいくつかご紹介します。
・~だがね/~だがや:「~だよね」という同意を求めたり、念を押したりする際に頻繁に使われます。会話にリズムを生み出す重要な役割を果たします。
・会話例:「昨日のドラマ、でらおもろかっただがね!(昨日のドラマ、すごく面白かったよね!)」
・~やん/~やて:「~じゃん」や「~だって」という伝聞や確認の意味で使われます。関西弁の影響も感じられる表現です。
・会話例:「来週、駅前に新しいカフェができるんだって。」「へえ、そうやん。(へえ、そうなんだ。)」
・机をつる:前述の通り、「机を運ぶ」という意味です。 家族に部屋の片付けをお願いする時などに使えます。
・会話例:「ちょっと悪いけど、その机こっちへつってくれん?(ちょっと申し訳ないけど、その机をこっちへ運んでくれない?)」
・はよして:「早くして」という意味です。急いでいるときや、相手を急かす場面で使われます。
・会話例:「もう出かける時間だで、はよしてちょうだい!(もう出かける時間だから、早くしてください!)」
これらの表現を会話に取り入れることで、友人や家族とのコミュニケーションがより円滑で楽しいものになるはずです。
尾張弁一覧から探る!文法的な特徴と発音のコツ

尾張弁をより深く理解し、自然に使いこなすためには、単語だけでなく文法や発音のルールを知ることが役立ちます。ここでは、尾張弁独特の語尾の変化やアクセントのポイント、そしてネイティブに近づくための発音のコツについて、一覧で分かりやすく解説します。
独特の語尾変化!助詞・助動詞の世界
尾張弁の最も特徴的な部分の一つが、文の終わりに来る助詞や助動詞の使い方です。これらが変わるだけで、文章のニュアンスが大きく変わります。
・断定の「だ」+強調の「が」+終助詞「や・ね」:これが「だがや」「だがね」の正体です。 下町言葉に由来し、力強く断定したり、相手に同意を求めたりする際に使われます。
・敬語の助動詞「~す」「~やす」「~なさる」「~ゃーす」:尾張弁には丁寧な表現も豊富にあります。「来る」を例にとると、「来ます」→「来やーす」、「いらっしゃる」→「いりゃあす」、「来てください」→「来てちょーだゃあ」のように変化します。これらは、かつての上町言葉の名残を感じさせます。
・否定の助動詞「ん」「せん」「へん」:否定を表す際には「~ない」の代わりに「~ん」や「~せん(へん)」が使われます。 例えば、「行かない」は「行かん」、「しない」は「せん(or せへん)」となります。これは西日本の方言と共通する特徴です。
・勧誘・意志の「~まい」「~(し)よまい」:「~しよう」という意味で、「行こう」は「行こまい」、「食べよう」は「食べよまい」となります。
これらの語尾を使い分けることで、表現の幅がぐっと広がります。
アクセントとイントネーションのポイント
尾張弁のアクセントは、基本的には東京式アクセントに分類されますが、独特のイントネーションがあります。 これが、尾張弁らしい響きを生み出す重要な要素です。
・語尾が上がるイントネーション:疑問文でなくても、文の終わりや助詞「ね」「さ」などが少し上がる傾向があります。 これが、聞く人によっては親しみやすく、あるいは少しぶっきらぼうに聞こえる要因の一つかもしれません。例えば、「そうだよね」は「そうだだがね⤴」のように、語尾が少し上がり気味に発音されます。
・形容詞のアクセント:一部の形容詞では、東京式アクセントとは異なる位置にアクセントが来ます。例えば、「赤い」「白い」などの色は、東京では「あかい」「しろい」と平坦ですが、名古屋では「あかい」「しろい」のように真ん中の音が高くなります。
・地名のアクセント:名古屋では地名のアクセントも独特です。「名古屋」は「なごや」、「熱田」は「あった」と、頭にアクセントが来るのが地元流です。
これらのイントネーションを意識するだけで、より自然な尾張弁に近づくことができます。
母音の無声化とは?ネイティブに近づく発音テクニック
よりネイティブに近い尾張弁を話すための、少し上級者向けのテクニックが「母音の無声化」と「連母音の変化」です。
・母音の無声化:「~です」「~ます」などの「す」や、「~して」の「し」の母音「u」や「i」が、ほとんど発音されない現象です。息の音だけが聞こえるようなイメージで、「です」は「dess」、「して」は「shte」のように聞こえます。これにより、スピーディーで歯切れの良い印象が生まれます。
・連母音の変化:尾張弁の発音の最大の特徴ともいえるのが、母音が連続したときの融合です。
- 「ai」→「ゃー」:「無い」が「にゃー」、「うまい」が「うみゃー」、「大根」が「でゃーこん」になるのはこのためです。発音のコツは、「エ」の口の形で「ア」と発音するようなイメージです。
- 「oi」→「えー」:「遅い」が「おせー」、「黒い」が「くれー」のように変化します。
- 「ui」→「いー」:「熱い」が「あつぃー」のように聞こえます。
これらの発音ルールは少し難しいかもしれませんが、意識して聞いて、真似てみることで、あなたの尾張弁は格段にレベルアップするでしょう。
もっと知りたい!尾張弁一覧にまつわる豆知識

尾張弁の基本的な使い方をマスターしたら、次はもう少しディープな世界を覗いてみませんか。ここでは、尾張弁を話す有名人や、意味を勘違いされやすい言葉、そしてさらに学習を深めたい人のための情報など、知っているとちょっと自慢できる豆知識を集めました。
尾張弁を話す有名人やアニメキャラクター
テレビやアニメで活躍する有名人の中にも、尾張弁を話す人はたくさんいます。彼らの話し方に注目すると、生きた尾張弁のイントネーションや言い回しを学ぶ良い参考になります。
例えば、フィギュアスケートの浅田真央さんや、俳優の竹下景子さん、佐藤二朗さんなどは愛知県の出身で、時折見せる方言に親しみを感じる人も多いでしょう。また、お笑い芸人のスピードワゴンのお二人のトークでは、軽快な尾張弁の掛け合いを楽しむことができます。
アニメの世界では、『八十亀ちゃんかんさつにっき』が有名です。この作品は名古屋を舞台にしており、主人公の八十亀最中をはじめとするキャラクターたちが、生き生きとした尾張弁(や三河弁)を話します。 尾張弁の様々な表現が解説付きで登場するため、楽しみながら方言を学ぶのに最適な作品です。これらの作品や有名人の話し方を参考に、リアルな尾張弁のニュアンスを感じ取ってみてください。
勘違いされやすい尾張弁とその意味
尾張弁には、標準語と同じ言葉なのに全く違う意味で使われる単語がいくつか存在します。これを知らないと、会話が噛み合わなくなってしまうこともあるかもしれません。代表的なものをいくつかご紹介します。
・えらい:標準語では「偉い」「立派だ」という意味ですが、尾張弁では「疲れた」「しんどい」という意味で使われます。 「昨日は残業でえらかったわ」と言われたら、「大変だったね」と労ってあげるのが正解です。
・かまう:標準語では「気にする」「関わる」といった意味ですが、尾張弁では「(人の)世話をする」「面倒を見る」といった意味合いで使われることがあります。 例えば、「あの子のこと、ちゃんとかまってやらんと」は、「あの子のこと、ちゃんと面倒を見てあげないと」という意味になります。
・たわけ:「馬鹿者」「阿呆」という意味の、相手を罵る言葉です。 語源は「田を分ける」から来ており、田畑を細かく分割相続することを禁じた昔の法律に由来すると言われています。 非常に強い言葉なので、使う場面には注意が必要ですが、尾張の歴史を感じさせる言葉の一つです。
これらの言葉の意味を知っておくことで、コミュニケーションのすれ違いを防ぐことができます。
尾張弁を学べる書籍やコンテンツ
この記事を読んで、さらに尾張弁に興味が湧いた方もいるかもしれません。幸いなことに、尾張弁をより深く学ぶための書籍やオンラインコンテンツも存在します。
地域の書店では、名古屋弁の単語やフレーズを集めた辞典や解説書が見つかることがあります。 こうした書籍は、方言の歴史的背景や語源まで詳しく解説していることが多く、知識を深めるのに役立ちます。
また、インターネット上にも名古屋弁の辞典サイトや解説ブログが多数存在します。 YouTubeなどの動画サイトで「名古屋弁」と検索すれば、地元の人による講座動画や、方言を使ったコントなどが見つかるでしょう。LINEスタンプにも、かわいいイラストと共に尾張弁のフレーズが学べるものがたくさんあります。
これらのコンテンツを活用すれば、机上の学習だけでなく、耳で聞いて、目で見て、楽しみながら尾張弁を身につけていくことができるでしょう。
まとめ:尾張弁一覧で知る名古屋ことばの奥深さ

この記事では、「尾張弁一覧」をテーマに、その基本的な情報から日常で使える具体的なフレーズ、さらには文法や発音のコツ、豆知識に至るまで、幅広くご紹介してきました。
尾張弁は、単なる地方の方言というだけではありません。城下町として栄えた歴史の中で、武士の上品な「上町言葉」と商人の活気ある「下町言葉」が混ざり合い、独自の発展を遂げてきた文化そのものです。 「~だがや」といった力強い語尾や、「えらい(疲れた)」、「かう(鍵をかける)」 のような独特の単語には、名古屋の人々の気質や生活が色濃く反映されています。
また、同じ愛知県内でも三河弁とは明確な違いがあり、その多様性もまた魅力の一つです。最初は少し無骨に聞こえるかもしれませんが、知れば知るほど、その裏にある温かみや合理性、そして歴史の奥深さに気づかされるはずです。
この一覧を参考に、ぜひ名古屋の街で実際に尾張弁に触れてみてください。地元の人との会話が、きっと何倍も楽しく、味わい深いものになることでしょう。