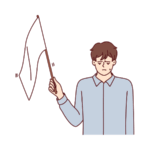石川県北部に位置する能登半島。豊かな自然と独自の文化が息づくこの地で話されているのが「能登方言」です。どこか温かく、そして時には力強い響きを持つ能登方言は、この地域の暮らしや人々の気質を映し出す鏡のような存在と言えるでしょう。「能登方言一覧」と検索されたあなたは、きっとその奥深い世界に興味をお持ちのはずです。
この記事では、日常の挨拶から、感情を表す言葉、そして知っていると地元の人との距離がぐっと縮まるユニークな表現まで、さまざまな能登方言を一覧形式でご紹介します。単語の意味だけでなく、実際の会話でどのように使われるのか、具体的な例文も交えてやさしく解説していきます。能登の言葉を知ることは、この土地の文化や人々の心をより深く理解する第一歩です。さあ、一緒に能登方言の魅力に触れてみましょう。
能登方言一覧【基本のあいさつ・返事編】

人と人とのコミュニケーションの基本は、やはり挨拶です。能登地方で使われる挨拶や返事の言葉には、相手を思いやる温かい心が込められています。基本的な表現を覚えて、能登の人々と心を通わせてみませんか。
「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」
一日の中で何度も交わされる基本的な挨拶。能登方言では、標準語と似ているものもありますが、独特のイントネーションや言い回しが加わることで、ぐっと親しみやすい響きになります。
朝の挨拶「おはようございます」は、能登でも同じように使われますが、親しい間柄では「おはよう」と短く言うのが一般的です。昼の挨拶「こんにちは」も同様に使われます。
特徴的なのは夜の挨拶です。能登地方では「こんばんは」を「よさり」と言うことがあります。 「よさりになったぞいね(夜になりましたね)」のように使われ、日が暮れて夜になった時間帯を指す言葉として生活に根付いています。 親しい人に対して「よさりです」や「よさりになりました」といった形で使われることもあり、どこか風情を感じさせる表現です。
これらの挨拶は、言葉そのものよりも、交わす際の表情や声のトーンが大切です。温かい心で挨拶を交わせば、きっと能登の人々も笑顔で応えてくれるでしょう。
「ありがとう」「ごめんなさい」
感謝と謝罪の気持ちを伝える言葉は、円滑な人間関係を築く上で欠かせません。能登方言には、この大切な気持ちを表現するための、心温まる言い回しがあります。
感謝を伝える「ありがとう」は、能登地方では「きのどくな」や「おきのどくな」という言葉で表現されることがあります。 標準語の「お気の毒に」と同じ言葉ですが、能登では「わざわざすみません、ありがとうございます」という恐縮や感謝の気持ちを込めて使われるのが特徴です。 例えば、何かをしてもらった時に「きのどくな、助かったわ」のように言います。また、より丁寧に伝えたい場合は「おきのどくな」が使われます。
一方、「ごめんなさい」という謝罪の言葉は、状況に応じて「すまん」「すんません」などが使われますが、軽い謝罪や恐縮の意を示す際には、やはり「きのどくな」が使われることもあります。
「どういたしまして」にあたる言葉としては「なんも、なんもいね」や「なんもなんも」といった表現があります。 これは「何でもありませんよ」というニュアンスで、相手の感謝に対して謙遜の気持ちを示す優しい言葉です。
「はい」「いいえ」などの返事
会話の中で頻繁に使われる肯定と否定の返事。能登方言では、短い言葉の中に様々なニュアンスが込められています。
肯定の「はい」や「そうです」は、「おいね」や「おーとる」と言います。 また、「ほんなが」や「ほんなんげ」も「そうなんです」という意味で使われます。 例えば、「これ、あんたのか?(これ、あなたのですか?)」と聞かれた際に、「おいね、わし(私)のげん」のように答えます。同意を求める際には語尾に「のきゃ」や「のけ」が付き、「ほんながのきゃ?(そうなんですよね?)」のようになります。
否定の「いいえ」や「違います」は、「なんも」や「ちごう」と言います。 よりはっきりと否定する際には「びっちゃ」という特徴的な言葉も使われます。 「それ、びっちゃ(それは違うよ)」のように、間違いを指摘する際などに用いられます。
さらに、「大丈夫です」「構いません」といった意味合いでは、「だんない」や「だんねわー」、「じゃまない」といった言葉が使われます。 何か申し出を断る際や、相手の気遣いに対して「気にしないでください」と伝えたい時に便利な表現です。
能登方言一覧【日常でよく使う言葉編】

ここでは、毎日の生活の中で自然と口から出てくるような、より身近な能登方言をご紹介します。これらの言葉を覚えておくと、能登での暮らしや人々との会話がさらに楽しくなるはずです。
気持ちや状態を表す言葉
嬉しい、悲しい、疲れた、大きい、小さいなど、自分の感情や物事の状態を伝える言葉はコミュニケーションの基本です。能登方言には、こうした気持ちや状態を豊かに表現する言葉がたくさんあります。
例えば、「つらい」「しんどい」といった体調の悪さを表す言葉として「ちきない」があります。 「風邪ひいてちきないわ(風邪をひいてつらいよ)」のように使います。 また、「疲れた」は「たいそな(たいそない)」と言い、体がだるい状態を「えらい」や「えれー」と表現することもあります。
感情を表す言葉では、「悔しい」を「はがやしい」と言います。 また、「うるさい」「わずらわしい」と感じる状態を「いじくらしい」と表現します。 例えば、子供が騒いでいる時に「朝からぎゃあぎゃあといじくらしいわぁ」のように使われます。
物の状態を表す言葉としては、「小さい」を意味する「ちょんこい」があります。 「きのこ」を指す「こけ」と合わせて、「ちょんこいこけ(小さいきのこ)」のように使われます。 これらの言葉は、標準語にはない独特の響きと温かみを持っており、能登の人々の感情の機微を伝えてくれます。
動作を表す言葉
「行く」「来る」「食べる」「寝る」など、日常の動作を表す言葉にも能登ならではの表現があります。これらの言葉は会話の中で頻繁に登場するため、覚えておくと非常に役立ちます。
例えば、「いる」「来る」といった存在や移動を表す言葉として「おる」「おいでる」が使われます。 尊敬語としても用いられ、「先生、おいでるけ?(先生、いらっしゃいますか?)」のように言うことができます。
また、軽い命令や勧誘を表す際に、語尾に「〜まっし」を付けるのが能登方言の大きな特徴です。 「食べまっし(食べなさい、食べなよ)」「こっち来まっし(こっちに来なさい、おいでよ)」のように使われ、柔らかく親しみやすい印象を与えます。
他にも、物を「捨てる」ことを「ほおる」「ほーかす」と言ったりします。 奥能登地方では、「捨てる」を「紛失する」という意味で使うこともあるため、文脈に注意が必要です。 「借りる」は「かった」となり、「買う」の「こーた」とは区別されます。 このように、日常的な動作を表す言葉一つひとつに、能登地方の文化や習慣が反映されているのが興味深い点です。
人や物を指す言葉
「私」「あなた」「これ」「あれ」といった、人や物を指し示す代名詞は、会話の基本となる言葉です。能登方言にも、地域ならではの言い方があり、親しい間柄でよく使われます。
一人称の「私」は、男性が使う「わし」のほかに、女性も使う「わて」という言い方があります。 また、「私たち」は「おらっちゃ」と言い、「おらっちゃ、先に帰るじゃ(私たちは先に帰りますよ)」のように使われます。
二人称の「あなた」は「われ」や「あんた」が使われますが、少しぞんざいな響きに聞こえることもあるため、使い方には注意が必要です。「あなたたち」は「わっちゃ」と言います。
能登地方では、家族の呼び方にも特徴があります。「長男」を「あんま」や「あんさま」、「次男」を「おっさま」と呼びます。 これは、家督相続などの慣習が言葉に残っている例と言えるでしょう。
これらの言葉は、特に地域コミュニティの中での結びつきが強い能登ならではの表現であり、人と人との関係性の近さを示しています。観光などで訪れた際に耳にすることがあれば、その背景にある文化にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
能登方言一覧【知っていると面白い!特徴的な言葉編】

能登方言の中には、標準語とは全く異なるユニークな単語や、聞いただけでは意味の想像がつきにくい面白い表現がたくさんあります。ここでは、そんな能登方言の奥深さを感じられる言葉をいくつかピックアップしてご紹介します。
食べ物に関するユニークな表現
食文化が豊かな能登半島では、食べ物に関する独特な方言も存在します。「おいしい」は「まい」「まいもん」と言い、「ごちそう」は「ごっつぉ」と表現されます。 「このじょにまいもんあたって、ごっつぉやわ(こんなにおいしいものにありつけて、ごちそうだね)」といった形で使われます。
また、標準語と同じ言葉でも、指すものが異なる場合があります。例えば、「なんば」は関西地方では「とうもろこし」を指しますが、能登では「唐辛子」のことです。 きのこ全般を「こけ」と呼ぶのも特徴的で、奥能登では「みみ」と言うこともあります。
さらに、魚の鮮度が落ちて傷んでしまうことを「なまる」と表現します。 新鮮な海の幸が豊富な能登ならではの言葉と言えるでしょう。塩味が足りない味噌汁を「しょーむない味噌汁」と言いますが、これは決してけなしているわけではなく、味の薄さを客観的に述べているだけです。 このように、食にまつわる方言を知ることで、能登の豊かな食文化をより深く味わうことができます。
天気や自然に関する言葉
三方を海に囲まれ、里山が広がる能登半島では、天気や自然に関する言葉も生活に密着しています。季節の移り変わりや日々の天候を、肌で感じながら暮らしてきた人々の知恵が詰まっています。
例えば、「お湯」を「およ」、「冬」を「ふよ」、「雪」を「よき」と発音することがあります。 ユの音がヨに近くなるという、能登方言の発音の特徴が表れています。
また、自然の中にいる生き物の呼び名もユニークです。「カニ」を「がんちょ」、「カエル」を「がっと」と呼びます。 子供たちが野山を駆け巡りながら、「おっきいがっと捕まえてんよ!(大きなカエルを捕まえたよ!)」と自慢げに話す姿が目に浮かぶようです。
これらの言葉は、単なる呼び名というだけでなく、能登の自然環境と人々の暮らしがいかに密接に関わっているかを示しています。豊かな自然と共に生きてきたからこそ生まれた、温かみのある表現と言えるでしょう。
思わず笑ってしまう面白い方言
能登方言には、その響きや意味合いから、思わずクスッとしてしまうような面白い言葉もあります。地元の人にとっては当たり前の表現でも、初めて聞く人にとっては新鮮で、心に残るものばかりです。
例えば、「だら」や「だらぼち」という言葉があります。 これは「馬鹿」や「阿呆」といった意味ですが、親しい間柄で愛情を込めて使われることも多く、必ずしも強い非難の言葉ではありません。 「われ、だらびちか?(あんた、馬鹿じゃないの?)」といった具合です。
また、「落ち着きがない」様子を「しゃわしきない」と表現します。 「うちの子供、ほんとにしゃわしきないげんて(うちの子は本当に落ち着きがなくて)」のように、少し困ったような、でもどこか微笑ましいニュアンスで使われます。
さらに、「ビリ」や「最下位」のことを「げっと」や「げっとクソ」と言います。 「走り競争でげっとやったわ(かけっこでビリだったよ)」と聞くと、そのユニークな響きに思わず笑みがこぼれてしまうかもしれません。 これらの言葉は、能登の人々の飾らない人柄やユーモアのセンスを感じさせてくれます。
能登方言の文法的な特徴と発音

能登方言の魅力をさらに深く知るためには、単語だけでなく、文法や発音のルールにも目を向けてみましょう。特徴的な語尾やイントネーションが、能登方言ならではの温かい響きを生み出しています。
特徴的な語尾「〜げん」「〜まっし」
能登方言を最も特徴づけているのが、文末に使われる語尾です。中でも「〜げん」と「〜まっし」は、能登らしさを感じさせる代表的な表現と言えるでしょう。
「〜げん」は、「〜のだ」「〜んだ」という意味合いで、断定や説明の際に使われます。 例えば、「珠洲に行くげん」は「珠洲に行くんだ」という意味になります。 石川県内で広く使われる「〜がん」と似ていますが、能登地方では「〜げん」がより一般的です。
一方、「〜まっし」は、軽い命令や丁寧な勧誘を表す際に用いられます。 「食べまっし(食べなさい、どうぞ召し上がれ)」「はよ起きまっし(早く起きなさい)」のように使われ、相手への配慮が感じられる柔らかい表現です。 能登を訪れた際には、「こっち来まっし」と優しく声をかけられることがあるかもしれません。
これらの語尾は、能登の人々のコミュニケーションに欠かせない要素であり、言葉に温かみと親しみを加えています。
疑問形の作り方「〜け?」
相手に質問を投げかける疑問文にも、能登方言ならではの作り方があります。標準語の「〜ですか?」にあたる表現として、文末に「〜け?」を付けるのが一般的です。
例えば、「これで合っていますか?」と尋ねたい時は、「これで合っとるけ?」となります。 「け」を付けなくても疑問の意味は通じますが、「け」を付けることで、質問であるこをより明確に示すことができます。
また、同意を求める「〜ですよね?」という意味では、「〜のきゃ?」という表現も使われます。 「あの人、いじくらしいのきゃ(あの人、うるさいですよね)」のように、相手の共感を得たい時に用いられます。
さらに、「どうですか?」と意見を求める際には「どいね?」という便利な言葉があります。 何かを見せたり、提案したりした後に「どいね?」と付け加えるだけで、相手の感想を促すことができます。これらの疑問表現を使いこなせれば、能登の人々との会話も一層弾むことでしょう。
発音のイントネーション
能登方言の響きを特徴づけるもう一つの重要な要素が、独特の発音とイントネーションです。京阪式アクセントと東京式アクセントの中間的な特徴を持つとされ、地域によっても微妙な違いがあります。
音声的な特徴としては、イとエの区別が曖昧になる傾向が見られます。 例えば、「息(いき)」と「駅(えき)」の発音が近くなることがあります。 また、「シ・チ・ジ」の音が「ス・ツ・ズ」に近くなる、いわゆる「ズーズー弁」の特徴も見られることがあります。 そのため、「梨(なし)」が「茄子(なす)」のように聞こえたり、「口(くち)」が「靴(くつ)」のように聞こえたりすることがあるかもしれません。
さらに、ユの音がヨに近くなるのも特徴で、「お湯(ゆ)」が「およ」、「雪(ゆき)」が「よき」と発音されることがあります。 これらの発音は、聞き慣れないうちは少し戸惑うかもしれませんが、能登方言の素朴で温かい魅力を構成する大切な要素です。言葉の響きそのものを楽しむことで、能登の文化をより深く体感できるでしょう。
能登方言が聞ける場所・作品

能登方言の響きに実際に触れてみたい、もっと深く知りたいと思った方もいるのではないでしょうか。ここでは、能登方言が話されている地域や、能登方言が登場する作品、そして学習に役立つ資料についてご紹介します。
能登地方の地域
能登方言は、石川県北部の能登半島一帯で話されています。 ただし、「能登」と一括りにいっても、地域によって言葉には少しずつ違いがあります。大きくは、南部の「口能登(くちのと)」、北部の「奥能登(おくのと)」に分けられます。
口能登は、七尾市や羽咋市、中能登町などが含まれる地域です。金沢に近いこともあり、加賀地方の方言の影響も受けています。
一方、奥能登は、輪島市や珠洲市、能登町、穴水町などが含まれる地域です。 より昔ながらの能登方言が色濃く残っているとされています。同じ奥能登でも、富山湾に面した「内浦(うちうら)」と、日本海に面した「外浦(そとうら)」で言葉が異なるとも言われています。
また、能登島や輪島市海士町などは、周囲とは異なる独自の方言が話される「言語島」として知られています。 これらの地域を旅する際には、土地ごとの言葉の違いに耳を澄ませてみるのも面白いかもしれません。
能登方言が登場する映画やドラマ
能登地方を舞台にした映画やドラマでは、登場人物たちが生き生きとした能登方言を話すのを聞くことができます。映像作品を通じて、実際の会話の中でのイントネーションや言葉のニュアンスを感じ取ることができるでしょう。
例えば、能登を舞台にした有名な作品として、NHKの連続テレビ小説「まれ」が挙げられます。 パティシエを目指すヒロインが能登で成長していく物語で、作中では多くの能登方言が使われました。
また、近年の人気漫画でアニメ化もされた「スキップとローファー」も、能登の先端にある珠洲市出身のヒロインが主人公です。 故郷の家族や友人と話すシーンなどで、自然な能登方言を聞くことができます。
これらの作品を観ることで、この記事で紹介した方言が、実際にどのような場面で、どのような感情を込めて使われるのかを具体的に知ることができます。物語を楽しみながら、能登の言葉の魅力に触れてみてください。
能登方言を学ぶための資料
能登方言について、さらに体系的に学びたい、もっと多くの言葉を知りたいという方のために、参考になる資料も存在します。
各自治体のウェブサイトで、方言が紹介されていることがあります。例えば、珠洲市のホームページでは、方言と標準語の対照表や使用例が掲載されており、非常に参考になります。
また、研究者や地域の有志によってまとめられた方言集やパンフレットなども貴重な資料です。東北大学方言研究センターが作成した「支援者のための知っておきたい能登方言」は、医療や介護の場面で誤解が生じないように、発音の注意点や意味を取り違えやすい言葉などを分かりやすく解説しています。
さらに、個人のブログやウェブサイトでも、愛情を込めて能登方言を紹介しているものが見つかります。 こうした資料を活用することで、能登方言への理解を一層深めることができるでしょう。言葉を知ることは、その土地の文化や人々を知るための素晴らしいきっかけとなります。
まとめ:能登方言一覧で知る言葉の魅力

この記事では、「能登方言一覧」をテーマに、石川県能登地方で話される温かく魅力的な言葉の数々をご紹介してきました。基本的な挨拶から日常会話でよく使われる表現、そして思わず笑みがこぼれるようなユニークな方言まで、その豊かさを感じていただけたのではないでしょうか。
能登方言は、単なる言葉のバリエーションにとどまりません。「きのどくな」という感謝の言葉に込められた相手への気遣いや、「〜まっし」という柔らかい勧誘の響きには、能登の人々の温かい人柄が表れています。また、「だら」や「いじくらしい」といった言葉の裏には、親しい間柄だからこその愛情やユーモアが感じられます。
「〜げん」や「〜け?」といった特徴的な語尾や、独特のイントネーションは、能登の風土と歴史の中で育まれてきた文化そのものです。この記事で紹介した能登方言一覧が、あなたにとって能登という地域への興味を深め、いつか訪れる際のコミュニケーションの一助となれば幸いです。言葉を知ることで、旅はもっと豊かで味わい深いものになるはずです。