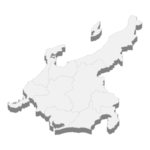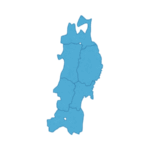鳥取県への旅行や移住を考えている方、あるいはアニメや漫画で鳥取弁に興味を持った方はいらっしゃいませんか。どこか懐かしく、親しみやすい響きが魅力の鳥取弁ですが、実は地域によって少しずつ言葉が違うことをご存じでしょうか。
この記事では、日常会話でよく使われる鳥取弁の単語やフレーズを一覧で分かりやすくご紹介します。面白い表現やかわいらしい語尾、そして鳥取県東部・中部・西部それぞれの地域ごとの方言の特徴まで、鳥取弁の魅力を余すことなく解説していきます。この記事を読めば、あなたも鳥取弁の面白さに触れ、もっと鳥取県が好きになるはずです。ぜひ、最後までご覧になって、鳥取弁の世界に浸ってみてください。
これだけは押さえたい!鳥取弁一覧【基本のあいさつ・返事編】

鳥取県の人々とコミュニケーションをとる第一歩は、やはりあいさつです。日常的によく使うあいさつや返事の言葉を知っておくと、ぐっと距離が縮まります。ここでは、基本的な鳥取弁のフレーズを一覧にしてご紹介します。
日常のあいさつで使われる鳥取弁
鳥取での朝のあいさつは、標準語と同じく「おはよう」が一般的です。しかし、感謝やお礼を伝える場面では、鳥取弁ならではの表現が登場します。「ありがとう」という感謝の気持ちは、「だんだん」という言葉で表されることがあります。また、何かをしてもらった際には「ようこそ」と言うこともあり、これは標準語の「ようこそ」とは意味が異なり、感謝の意を伝える際に使われます。
その他、別れ際の「さようなら」は「さいなら」や「またな」などが使われ、家に帰ることを「いぬる」と言うこともあります。 例えば、「そろそろ帰ります」は「そろそろいぬるわ」といった具合です。 こうした言葉を自然に使えると、地元の人との会話がより一層楽しくなるでしょう。
相づちや返事で使われる鳥取弁
会話を弾ませるには、上手な相づちが欠かせません。鳥取弁には、特徴的な相づちの言葉がいくつかあります。肯定する際の「そうだ」は「そうだわ」「そげだ」などと言い、驚いたときには「わったいな」という感嘆詞が使われることもあります。
相手に何かを尋ねるとき、「どうしたの?」は「なんだいや?」という温かみのある表現になります。 また、相手の言うことに同意したり、相づちを打ったりする際に「ですです」と繰り返すことがあります。標準語ではあまり使われませんが、鳥取弁ではごく自然な表現です。
否定の「違う」や「だめ」は、「いけん」とはっきりした言葉で表現されることが多いです。 例えば、「それはだめだよ」は「そりゃいけんわ」のようになります。
ありがとう・ごめんなさいの伝え方
感謝の気持ちを伝える「ありがとう」には、「だんだん」という言葉がよく使われます。 年配の方などは、より丁寧に「ありがとうござんして」や「ようごしなってなあ」といった表現を使うこともあります。
謝罪の言葉である「ごめんなさい」は、「こらえてごしない」という独特の言い方があります。 「こらえて」は「我慢して」という意味ではなく、「許して」というニュアンスで使われます。また、「申し訳ない」という気持ちは「いぎちない」と表現されることもあります。 これらの言葉は、知らないと意味を推測するのが難しいかもしれませんが、覚えておくとコミュニケーションの幅が広がります。
つい使ってみたくなる!面白い鳥取弁一覧

鳥取弁には、標準語に訳すと少し変わっていたり、ユニークな響きを持っていたりする言葉がたくさんあります。知っていると会話がもっと面白くなる、そんな鳥取弁の数々をご紹介します。
食べ物や休憩に関するユニークな表現
鳥取弁で特に面白いのが、「たばこ」という言葉です。これは喫煙のことではなく、「休憩」や「一休み」を意味します。 農作業の合間などに「ちょっとたばこしょうか」と言われたら、それは「少し休憩しよう」という合図です。 喫煙者でなくても使う言葉なので、知らずに聞くと驚くかもしれません。
また、お雑煮に関する文化もユニークです。鳥取県の一部地域では、お正月に甘い小豆のお汁粉のような「小豆雑煮」を食べる習慣があります。 他県の人から見れば甘いスイーツのようですが、鳥取ではこれが立派なお雑煮なのです。 このように、食文化に根差した言葉や習慣の違いも方言の面白さの一つです。
人の様子や状態を表す言葉
人の性格や状態を表す言葉にも、鳥取弁ならではの表現があります。例えば、「愚か者」や「憎めない人」といったニュアンスで使われるのが「だらず」という言葉です。 これは地元のFM局の名前にも使われるなど、県民に親しまれている言葉です。
また、「疲れた」「しんどい」という意味で「えらい」という言葉が頻繁に使われます。 「今日はよく歩いてえらいわー」と言えば、それは「偉い」と褒めているのではなく、「疲れた」と表現しているのです。 同様に、「苦しがる・つらがる」ことを「えらがる」と言います。
他にも、「手が付けられないほど散らかっている」状態を「さんだがない」と言ったり、いたずらっ子のことを「しょーから」と呼んだりします。 これらの言葉は、情景が目に浮かぶような、生き生きとした表現が特徴です。
ちょっと変わった動詞・形容詞
動詞や形容詞にも、耳慣れない面白い言葉があります。例えば、「怒る」ことを「ごーがわく」と表現します。 「てわやく(手遊び)ばかりしとると、ごーがわくで!」は「手遊びばかりしていると、怒るよ!」という意味になります。
また、「頑張る」は「がんじょする」、「ください」は「ごしない」と言います。 「見てごしない」は「見てください」という意味で、様々な場面で使える便利な言葉です。
驚いたときや感心したときには「しぇたもんだ」という言葉も使われます。これは「信じられない」「大したものだ」といった意味合いで、良い意味でも悪い意味でも使われる表現です。 このように、標準語とは全く異なる響きの言葉が、鳥取弁の面白さを引き立てています。
かわいい響きが魅力!鳥取弁の語尾一覧

方言の印象を大きく左右するのが、文末に使われる「語尾」です。鳥取弁には、柔らかくかわいらしい響きを持つ語尾がたくさんあります。ここでは、代表的な鳥取弁の語尾を一覧でご紹介します。
親しみを込めた「〜だで」「〜だに」
鳥取弁の語尾として有名なのが、「〜だで」「〜だに」です。 これらは標準語の「〜だよ」にあたる表現で、親しみを込めて使われます。 例えば、「これは私の本だよ」は「これはうちの本だで」となります。「〜だに」も同様に「〜なんだ」という意味で使われ、「好きだに」と言えば「好きなんだ」という気持ちを伝えることができます。
鳥取県内でも地域によって微妙な違いがあり、東部では「〜だ」、中部では「〜だで」「〜だや」、西部では「〜だら」が使われる傾向があります。 これらの語尾が付くことで、言葉全体が柔らかく、親しみやすい印象になります。
理由を説明する「〜けぇ」「〜けん」
理由や原因を説明するときには、「〜けぇ」や「〜けん」という語尾が使われます。 これは標準語の「〜から」「〜だから」に相当します。 例えば、「時間がないから急ごう」は「時間がないけぇ急ごう」となります。「幸せにするけぇ」と言えば、「幸せにするからね」という強い意志と温かさが伝わる告白の言葉になります。
この「〜けぇ」も鳥取県内で広く使われる語尾ですが、特に東部や中部でよく耳にします。 西部では島根県の影響もあり、「〜けん」が使われることも多いです。 会話の中で理由を述べるときに自然と出てくる、非常に便利な表現です。
柔らかな疑問の「〜かえ?」「〜だら?」
相手に質問を投げかける疑問の語尾も特徴的です。倉吉市などの中部では「〜かえ?」という表現が使われます。 「元気ですか?」を「元気だかえ?」と言うと、どこかおっとりとした優しい尋ね方になります。
一方、米子市などの西部では「〜だら?」という語尾がよく使われます。 これは標準語の「〜でしょ?」にあたり、相手に同意を求めたり、確認したりする際に用いられます。「明日は晴れるでしょ?」は「明日は晴れるだら?」となります。この語尾も、断定を避けた柔らかな響きを持っています。
強調や呼びかけで使う「〜がな」「〜な」
自分の意見を強調したり、相手に念を押したりする際には「〜がな」という語尾が使われることがあります。また、呼びかけや同意を求める際には文末に「〜な」が付きます。 「頑張るからね」は「がんじょするけぇなぁ」といった具合で、語尾のイントネーションが少し上がるのが特徴です。
こうした語尾は、特に親しい間柄での会話で頻繁に登場します。何気ない会話の中にこれらの語尾が加わることで、鳥取弁らしいリズムと温かみが生まれるのです。
【地域別】鳥取弁一覧!東部・中部・西部の違いとは?

鳥取県は東西に長い地形で、一括りに「鳥取弁」と言っても、実は地域ごとに言葉やイントネーションに違いがあります。 大きく分けて、鳥取市を中心とする「東部(因州弁)」、倉吉市を中心とする「中部(倉吉弁)」、そして米子市を中心とする「西部(雲伯方言)」の3つの方言に分類されます。 ここでは、それぞれの地域の方言の特徴を詳しく見ていきましょう。
因州弁(鳥取市など東部)の特徴
鳥取県東部で話される「因州弁(いんしゅうべん)」は、鳥取弁と聞いて多くの人がイメージする方言です。 3つの中では最も標準語に近いと言われており、兵庫県や岡山県の方言の影響も受けています。
発音の面では、アクセントが東京式で、母音をはっきりと発音するのが特徴です。 文法的には、断定の助動詞に「〜じゃ」ではなく「〜だ」を用いるのが山陰地方共通の特徴です。
語彙では、「ありがとう」を意味する「だんだん」や、「疲れた」を意味する「えらい」などが使われます。語尾には理由を示す「〜けぇ」や、断定の「〜だ」がよく用いられます。 全体的に穏やかで聞き取りやすい方言ですが、「はやくしろ」を「早よせーや」と言うなど、少しきつく聞こえる表現もあります。
倉吉弁(倉吉市など中部)の特徴
倉吉市を中心とする鳥取県中部で話されるのが「倉吉弁(くらよしべん)」または「東伯耆弁(ひがしほうきべん)」です。 基本的には東部の因州弁と非常に似ており、標準語に近い方言とされています。
しかし、語尾に独自の特徴が見られます。「〜かえ?」という疑問の表現や、「〜だで」「〜だや」といった断定の語尾が使われ、因州弁よりもさらに柔らかく、おっとりとした印象を与えることがあります。
また、母音が融合して「高い」を「たきゃあ」のように発音する現象も見られます。 東部と西部の中間に位置するため、両方の特徴を併せ持った興味深い方言です。
雲伯方言(米子市など西部)の特徴
米子市や境港市など、鳥取県西部で話される方言は「雲伯方言(うんぱくほうげん)」と呼ばれ、東部や中部の方言とは大きく異なります。 この方言は、隣接する島根県東部(出雲地方)と共通の特徴を多く持ち、「米子弁」とも呼ばれます。
最大の特徴は、東北地方の方言(ズーズー弁)と共通する発音です。 イ段とウ段の母音が区別されにくく、中舌母音で発音されるため、他の地域の日本人には聞き取りにくい場合があります。
語彙や語尾も独特で、肯定の「そうだ」を「そげだ」と言ったり、「〜だろう」を「〜だらあ」と表現したりします。 また、疑問の「〜か?」を「〜かえ?」、同意を求める「〜でしょ?」を「〜だら?」と言うなど、特徴的な語尾が使われます。 東部・中部の鳥取弁とは一線を画す、個性豊かな方言です。
まとめ:鳥取弁一覧で知る方言の奥深い魅力

この記事では、日常会話で使える鳥取弁の一覧から、面白い表現、かわいい語尾、そして東部・中部・西部の地域差に至るまで、鳥取弁の魅力を多角的にご紹介してきました。
鳥取弁は、「だんだん(ありがとう)」や「えらい(疲れた)」といった温かみのある単語や、「〜だで」「〜けぇ」といった親しみやすい語尾が特徴です。一方で、同じ県内でも東部の「因州弁」、中部の「倉吉弁」、西部の「雲伯方言」と、地域によって言葉や響きに違いがあることもお分かりいただけたかと思います。
特に、東部・中部の方言が比較的標準語に近いのに対し、西部の雲伯方言は発音などに独自の特徴を持っている点は、鳥取弁の多様性を示す興味深いポイントです。 このような方言のバリエーションは、その土地の歴史や文化、人々との交流の中で育まれてきたものです。
今回ご紹介した鳥取弁の一覧を参考に、ぜひ現地の人との会話を楽しんでみてください。言葉を知ることは、その土地をより深く理解することにつながります。鳥取弁の持つ独特のリズムと温かさに触れることで、あなたの鳥取への関心がさらに深まることを願っています。