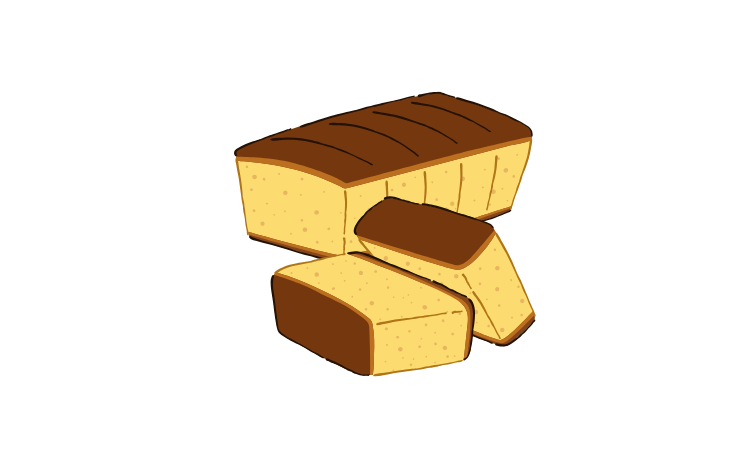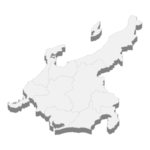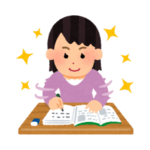長崎と聞いて、何を思い浮かべますか?美しい夜景、異国情緒あふれる街並み、そして美味しいちゃんぽん。しかし、長崎の魅力はそれだけではありません。独特でどこか温かみのある「長崎弁」も、多くの人々を惹きつけてやみません。
この記事では、そんな魅力あふれる「長崎の方言一覧」をテーマに、言葉の持つ意味や使い方を、具体的な例文を交えながらやさしく解説します。歴史的背景から生まれたユニークな言葉、日常でよく使われるフレーズ、そして思わず「みじょか(可愛い)」と言いたくなるような表現まで、幅広くご紹介。この記事を読めば、あなたも長崎の言葉の面白さや奥深さに触れ、もっと長崎が好きになるはずです。長崎出身の方も、そうでない方も、一緒に長崎弁の豊かな世界を覗いてみませんか?
長崎の方言一覧【基本編】まずはここから!日常でよく使う言葉

長崎の日常会話では、特徴的な方言がごく自然に使われています。まずは、地元の人々のコミュニケーションに欠かせない基本的な言葉から見ていきましょう。あいさつや返事、感情を表す言葉など、これらを覚えておくと、長崎の人々との距離がぐっと縮まるかもしれません。
あいさつや返事で使う長崎の方言
日々のコミュニケーションの始まりと終わりには、あいさつが欠かせません。長崎では、標準語とは少し違う、親しみを込めた言い方がよく使われます。例えば、「おはよう」は「おはようさん」、「ありがとう」はよりフランクに「どーも」と言うことがあります。 また、何かを承諾するときの「いいよ」は、「よかよ」という柔らかい響きの言葉になります。 例えば、「このお菓子、食べていい?」と聞かれたら、「よかよ」と返します。 この「よか」は、「良い」という意味で、九州地方で広く使われる表現です。
さらに、別れ際の「またね」は「あいばね〜」と言ったりします。 日常の何気ない場面で、こうした方言が自然に出てくるのが長崎の魅力です。少し意識して耳を傾けてみると、街のあちこちで温かい言葉のやり取りが聞こえてくるでしょう。
感情を表す豊かな長崎の方言
長崎弁には、人の気持ちを豊かに表現する言葉がたくさんあります。驚いた時には「うったまぐる」、すねている様子は「はぶてる」と言います。 例えば、友達が急に驚くようなことをしたら、「うったまぐったー!(すごくびっくりした!)」のように使います。また、子供が言うことを聞かずにプイッと横を向いてしまったら、「また、はぶてとる(また、すねてる)」といった具合です。
恐ろしいものや怖いものに対しては、「おとろしか」という言葉が使われます。 例えば、怖い話を聞いた後には「今夜はトイレに行かれんごつ、おとろしかー(今夜はトイレに行けないくらい、恐ろしい)」と表現できます。嬉しい時や楽しい時だけでなく、こうした様々な感情を表す言葉が、日々の会話に彩りを与えています。
標準語と間違えやすい?長崎でよく使う動詞・名詞
長崎弁の中には、標準語と同じ言葉なのに全く違う意味で使われるものや、長崎県民が方言だと気づかずに使っている言葉があります。その代表格が「なおす」と「からう」です。標準語で「なおす」は修理するという意味ですが、長崎では「片付ける」「しまう」という意味で使われます。 例えば、「その本、なおしとって」と言われたら、本を元の場所に戻すことを指します。
また、「からう」は「背負う」という意味です。 子供がランドセルを背負う姿を見て、「ランドセルからって、いってらっしゃい」と声をかけるのは、長崎ではごく普通の光景です。 他にも、靴下に穴があくことを「じゃがいもができた」とユニークな表現をしたり、かさぶたのことを「つ」と一文字で言ったりします。 このように、知らず知らずのうちに使っている言葉が、実は地域に根ざした大切な方言なのです。
長崎の方言一覧【特徴編】文法や語尾のユニークなルール

長崎弁の面白さは、単語一つひとつだけにとどまりません。会話の最後につく「語尾」や、文の組み立て方にも独特のルールがあります。ここでは、長崎弁をより深く理解するために、特徴的な文法や語尾の使い方について解説します。これらをマスターすれば、あなたも長崎弁ネイティブに一歩近づけるでしょう。
「〜ばい」「〜たい」はどう違う?定番の語尾
九州の方言と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、「〜ばい」や「〜たい」といった語尾ではないでしょうか。 もちろん長崎でもよく使われますが、この二つにはニュアンスの違いがあります。簡単に言うと、「〜ばい」は、相手が知らないであろう情報を教える時や、自分の意見を主張する時に使われることが多いです。例えば、「今日は暑かばい(今日は暑いね)」のように、相手に同意を求めたり、状況を伝えたりする際に用います。
一方で、「〜たい」は、すでに相手も知っているであろう事柄について、確認したり念を押したりする時に使います。また、独り言のような場面でも登場します。例えば、約束の時間を過ぎても友達が来ない時に、「遅かたい(遅いなあ)」と呟くようなイメージです。微妙な使い分けですが、この違いを理解すると、会話の意図がより正確に伝わるようになります。
「〜けん」「〜と?」で会話がスムーズに!
長崎弁の会話をスムーズに進める上で欠かせないのが、「〜けん」と「〜と?」という語尾です。「〜けん」は、理由や原因を表す「〜だから」という意味で、接続詞としても文末の語尾としても使われます。 例えば、「雨が降りよるけん、傘ば持っていかんね(雨が降っているから、傘を持っていきなさい)」のように使います。 相手に何かを勧めたり、行動を促したりする際に、その理由を優しく伝える便利な言葉です。
一方、「〜と?」は、質問する時に使う「〜なの?」という意味の語尾です。 例えば、「明日、暇しとると?(明日、暇してるの?)」と尋ねる際に使います。博多弁では「とっとーと?」のように「と」が重なることもありますが、長崎ではシンプルに「〜と?」と使うことが多いです。 この二つの語尾を使いこなせるようになると、長崎の人々との会話がより自然でテンポ良く進むでしょう。
外国語がルーツ?歴史を感じる長崎の言葉
かつて日本で唯一の海外との貿易港として栄えた長崎は、その歴史的背景からポルトガル語やオランダ語、中国語などの影響を受けた言葉が方言として残っています。 例えば、ガラスを意味する「ビードロ」や、石鹸を意味する「シャボン」はポルトガル語が語源とされています。
また、お祭りで使われる「もってこーい!」という掛け声は、実はアンコールの意味で使われる長崎弁です。 一説には、ポルトガル語に由来するという話もあります。さらに、町をぶらぶら歩くことを「さるく」と言いますが、これも長崎ならではの表現です。 この言葉を使ったイベント「長崎さるく博」が開催されたことで、全国的にも知られるようになりました。これらの言葉に触れると、異文化交流の玄関口であった長崎の歴史に思いを馳せることができます。
長崎の方言一覧【地域差編】場所によってこんなに違う!

一口に「長崎弁」と言っても、実は地域によって言葉のアクセントや言い回しが異なります。 長崎県は地理的に広く、半島や多くの島々から成り立っているため、それぞれの地域で独自の言葉が育まれてきました。 ここでは、代表的な地域の言葉の違いをいくつかご紹介します。
長崎市周辺の中南部方言
長崎市を中心とした県の中南部で話されている方言は、一般的に「長崎弁」としてイメージされることが多い言葉です。 この地域の方言は、鹿児島などと同じ種類の二型アクセント(九州西南部式アクセント)を持つのが特徴です。 また、江戸時代に幕府の直轄地(天領)として栄え、様々な地域の人々が行き交った歴史から、他の地域の方言や外国語の影響を受けている点も特徴と言えるでしょう。
例えば、「〜ばい」「〜たい」といった肥筑方言に共通する特徴を持ちながらも、「ぶらぶら歩く」を意味する「さるく」や、「元気な人」を指す「ばらかもん」といった長崎市周辺で特によく使われる言葉があります。 イントネーションも比較的穏やかで、温かみのある響きが感じられるのが、この地域の方言の魅力です。
佐世保市などの北部方言
佐世保市や平戸市など、県の北部で話される方言は「佐世保弁」とも呼ばれ、中南部の方言とは異なる特徴を持っています。 最も大きな違いはアクセントで、北部方言はアクセントによる意味の区別がない「無アクセント」地域です。 そのため、中南部の人が聞くと、少し平坦な口調に聞こえるかもしれません。
文法面では、お隣の佐賀県西部の方言と似ている点も見られます。 例えば、佐世保が舞台となった人気漫画・アニメ『坂道のアポロン』では、登場人物たちが話す言葉を通じて、この地域独特のイントネーションや言い回しに触れることができます。 同じ長崎県内でも、北部と中南部では言葉の響きやリズムが異なり、その違いを知るのも方言の面白いところです。
五島や対馬、壱岐の離島の方言
長崎県は多くの離島を抱えており、それぞれの島でさらに独特な方言が話されています。五島列島で話される「五島弁」、対馬の「対馬弁」、壱岐の「壱岐弁」は、本土の方言とはまた違った発展を遂げてきました。
例えば、五島が舞台となった漫画・アニメ『ばらかもん』では、主人公が都会の言葉との違いに戸惑うシーンが描かれています。「元気」を意味する「ばらか」という言葉は本土でも使いますが、島ならではのイントネーションや他の言葉との組み合わせが、独特の響きを生み出しています。 海を隔てていることで、古い言葉が残っていたり、独自の進化を遂げたりと、離島の方言は言語学的にも非常に興味深い存在です。
長崎の方言一覧【応用編】使ってみたくなる表現集

基本的な言葉や特徴がわかったところで、次はもう少し踏み込んだ応用編です。実際の会話で使える面白いフレーズや、その響きから「かわいい」と感じられる言葉、そしてあの有名な早口言葉まで、知っているとより長崎弁を楽しめる表現を集めてみました。
思わず笑っちゃう?面白い長崎の方言
長崎弁には、意味を知るとクスッと笑ってしまうようなユニークな表現があります。例えば、カエルのことを「どんく」と呼びます。 標準語の「カエル」という音とは全く違うため、初めて聞くと何のことか分からないかもしれません。また、おばけのことを「あもじょ」や「あもよ」と言ったりします。 子供に「早く寝ないと『あもじょ』が出るよ」と言い聞かせる際に使うそうです。
さらに、どうしようもない状況や、呆れた気持ちを表す時に使われるのが、「どがんもこがんも」という言葉です。 「どがん(どうにも)も、こがん(こうにも)もならん」といったニュアンスで、リズミカルな響きが面白い表現です。これらの言葉は、日常の会話にユーモアを添えてくれます。
「みじょか〜」響きがかわいい長崎の方言
方言女子が可愛いと話題になることがありますが、長崎弁にも「みじょか(かわいい、愛らしい)」と感じる言葉がたくさんあります。 その代表格が、座ることを意味する「ちょんちょん」です。 「ここにちょんちょんしときなさい(ここに座っておきなさい)」と言われたら、その響きのかわいらしさに、思わずにっこりしてしまいそうです。
また、くすぐったいことを「こちょばい」と言います。 これもどこか微笑ましい響きを持つ言葉です。告白のシーンで使われる「ずっと好いとったとよ」というフレーズも、ストレートな愛情が伝わってくる、温かくてかわいい表現です。 このように、長崎弁には人の心を和ませるような、優しくて愛らしい言葉が溢れています。
あなたは言える?有名な早口言葉「とっとっと」
長崎弁、ひいては九州地方の方言の面白さを象徴するのが「とっとっと」というフレーズです。これは、標準語にすると「(席を)取っているの?」という意味になります。動詞「取る」の進行形「取っとる」に、疑問の終助詞「と」がくっついた形です。
この「とっとっと」を使った有名な早口言葉があります。
「おっとっと、とっとってっていっとったとに、なんでとっとってくれんかったと?」(意味:おっとっと(お菓子)を取っておいてって言ってたのに、どうして取っておいてくれなかったの?)
一見すると暗号のようですが、意味が分かると納得できるはずです。長崎を訪れた際には、この早口言葉に挑戦してみてはいかがでしょうか。うまく言えれば、地元の人から一目置かれるかもしれません。
まとめ:長崎の方言一覧から知る、言葉の魅力と多様性

この記事では、「長崎の方言一覧」をテーマに、日常で使われる基本的な言葉から、地域による違い、そしてユニークで可愛らしい表現まで幅広くご紹介しました。長崎弁は、単なる言葉のバリエーションにとどまらず、その土地の歴史や文化、人々の気質を色濃く反映しています。 語尾につく「〜ばい」や「〜けん」といった特徴的な言い回し、外国語に由来する単語、そして「なおす」や「からう」のように標準語とは異なる意味で使われる言葉など、知れば知るほど奥深い魅力に気づかされます。
同じ県内でも、長崎市、佐世保市、そして五島などの離島では、アクセントや語彙に違いがあり、その多様性もまた長崎弁の面白さです。 「みじょか(かわいい)」 や「すいとー(好きだよ)」といった心温まる言葉に触れることで、長崎という土地や人々への親しみが一層増すことでしょう。方言は、その地域に生きる人々の大切な宝物です。この記事が、長崎の言葉の豊かさに触れるきっかけとなれば幸いです。