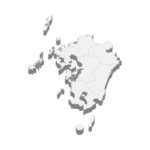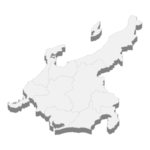「~じゃけぇ」「~だに」「~っちゃ」。これらが、どこの方言かご存知ですか。これらはすべて中国地方で使われている言葉です。中国地方と一括りにいっても、鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県の5県それぞれに、個性豊かな方言が根付いています。同じ県内でも地域によって言葉が違うこともあり、その多様性は非常に興味深いものです。
この記事では、そんな奥深い中国地方の方言について、その全体像から各県ごとの詳しい特徴、さらには日常で使ってみたくなる面白いフレーズまで、分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、中国地方の方言の魅力にきっと気づくはずです。
中国地方の方言とは?その全体像に迫る

中国地方の方言は、専門的には「中国方言」と呼ばれ、西日本方言の一部に分類されます。 しかし、一枚岩というわけではなく、日本海側の山陰(鳥取・島根)と瀬戸内海側の山陽(岡山・広島・山口)とでは、言葉に大きな違いが見られます。 ここでは、まず中国地方全体の方言に見られる共通点や、どのように分類されているのかを見ていきましょう。
中国地方の方言の区分:山陰と山陽の違い
中国地方の方言は、大きく「山陰方言」と「山陽方言」の2つに分けられます。 この分類で最も分かりやすい違いが、断定の助動詞、つまり「~だ」にあたる言葉です。山陽地方の岡山県、広島県、山口県では主に「~じゃ」が使われるのに対し、山陰地方の鳥取県や島根県石見地方では「~だ」が用いられます。
さらに細かく見ると、鳥取県の因州弁や倉吉弁は「東山陰方言」、広島県の安芸弁や山口弁、島根県の石見弁は「西中国方言」、岡山弁や広島県の備後弁は「東山陽方言」といったグループに分けられます。 ただし、島根県東部の出雲弁や鳥取県西部の米子弁などは「雲伯方言」と呼ばれ、その音韻体系が他の中国方言と大きく異なるため、区別して扱われるのが一般的です。
文法的な共通点:「~よる」と「~とる」の使い分け
中国地方の方言には、地域ごとの違いだけでなく、西日本の他の方言とも共通する特徴があります。その代表的なものが、動作の状況を表現する「アスペクト」の区別です。具体的には、動作が進行中であることを示す「~よる」と、動作が完了・結果が残っていることを示す「~とる(ちょる)」を使い分けます。
例えば、「雨が降りよる」と言えば、今まさに雨が降っている最中であることを意味します。一方で、「雨が降っとる」と言った場合、雨が降った結果として地面が濡れている状態を表すことが多いです。この使い分けは、九州や四国地方の方言にも見られるもので、西日本方言の大きな特徴の一つと言えるでしょう。標準語ではどちらも「~ている」で表現されるため、この細やかな表現の違いは、中国地方の方言の豊かさを示しています。
アクセントと発音の特徴:実は標準語に近い?
中国地方の方言のアクセントは、そのほとんどの地域で標準語と同じ「東京式アクセント」が用いられています。 東京式アクセントとは、単語ごとに音の高低のパターンが決まっているアクセントのことです。そのため、他地域の人からすると、イントネーションは比較的聞き取りやすいと感じるかもしれません。
一方で、発音には独特の特徴が見られます。「連母音の融合」と呼ばれる現象が盛んで、母音が連続すると発音が変化します。 例えば、「赤い(akai)」という単語が、岡山などでは「あけー」や「あきゃー」に、広島や山口では「あかー」に聞こえることがあります。 このような音の変化が、各地域の方言に独特の響きを与えているのです。また、ガ行の音は、鼻に抜ける鼻濁音を使わず、破裂音の[g]でハッキリと発音されるのも共通した特徴です。
【山陰編】鳥取・島根の中国地方方言
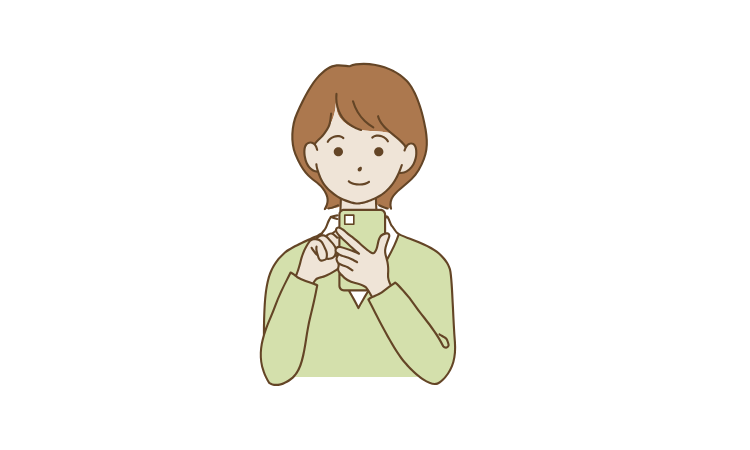
日本海に面し、豊かな自然と神話が息づく山陰地方。この地域の鳥取県と島根県の方言は、山陽地方とはまた違った趣を持っています。特に島根県東部から鳥取県西部にかけて話される「雲伯方言」は、他の西日本方言とは一線を画す古代の言葉の響きを残していると言われています。ここでは、鳥取県と島根県の個性的な方言の世界を見ていきましょう。
鳥取県の方言:因州弁・倉吉弁・西伯耆弁
鳥取県の方言は、主に東部の「因州弁(いんしゅうべん)」、中部の「倉吉弁(くらよしべん)」、西部の「西伯耆弁(にしほうきべん)」の3つに大きく分けられます。 県庁所在地である鳥取市周辺で話される因州弁は「鳥取弁」とも呼ばれ、比較的標準語に近いと言われることもありますが、岡山弁や兵庫県の但馬弁と共通する部分もあります。
倉吉市周辺の倉吉弁は、「さしすせそ」が「しゃししゅしぇしょ」のように発音される特徴があると言われています。 そして、米子市や境港市を中心とする西伯耆弁は、お隣の島根県東部の出雲弁とともに「雲伯方言」に分類され、独特のイントネーションや語彙を持っています。 例えば「だんだん」は「ありがとう」を意味する有名な方言ですが、これは鳥取県や島根県で広く使われる言葉です。 他にも、「だらず(馬鹿者)」や「よだきい(面倒だ、疲れる)」 など、一度聞いたら忘れられないようなユニークな言葉がたくさんあります。
島根県の方言:出雲弁・石見弁・隠岐弁
東西に長い島根県の言葉は、東部の「出雲弁(いずもべん)」、西部の「石見弁(いわみべん)」、そして日本海の離島で話される「隠岐弁(おきべん)」の3つに大別されます。 出雲大社で知られる出雲地方の出雲弁は、東北地方の方言で聞かれる「ズーズー弁」に似たイントネーションを持つのが最大の特徴で、雲伯方言の代表格です。
一方で、広島県や山口県と隣接する石見地方の石見弁は、山陽地方の方言に近い特徴を持ち、「~じゃ」という言い方が聞かれることもあります。 隠岐諸島の隠岐弁は、島という地理的な条件から本土とは異なる独自の発展を遂げた方言です。 島根県の方言で有名なものに、「ありがとう」を意味する「だんだん」や、「そうだそうだ」と相づちを打つ際に使う「そげそげ」 などがあります。また、「休憩する」という意味で「たばこする」という面白い言い方もあり、これを知らないと少し驚いてしまうかもしれません。
山陰に共通する言葉と「雲伯方言」の謎
鳥取県西部から島根県東部にかけての「雲伯(うんぱく)地方」で話される雲伯方言は、なぜ東北方言に似た特徴を持つのでしょうか。その理由ははっきりとは解明されていませんが、一説には、古代に出雲地方が日本の政治・文化の中心地の一つであった時代の言葉遣いが、そのまま現代まで残ったのではないかと考えられています。
例えば、出雲弁では「火事」を「くぁじ」と発音するなど、古い時代の発音が残っているのが特徴です。 また、雲伯方言と東山陰方言(鳥取県東部・中部など)には、「行こう」を「いかー」、「だろう」を「だらー」と発音する共通点があります。 これは「行かむ」「であらむ」といった古い言葉の形が変化して残ったもので、他の西日本方言では「いこー」「じゃろー」となっているのとは対照的です。 このように、山陰地方の方言、特に雲伯方言は、日本語の歴史を解き明かす上で非常に興味深い要素を多く含んでいるのです。
【山陽編】岡山・広島の中国地方方言
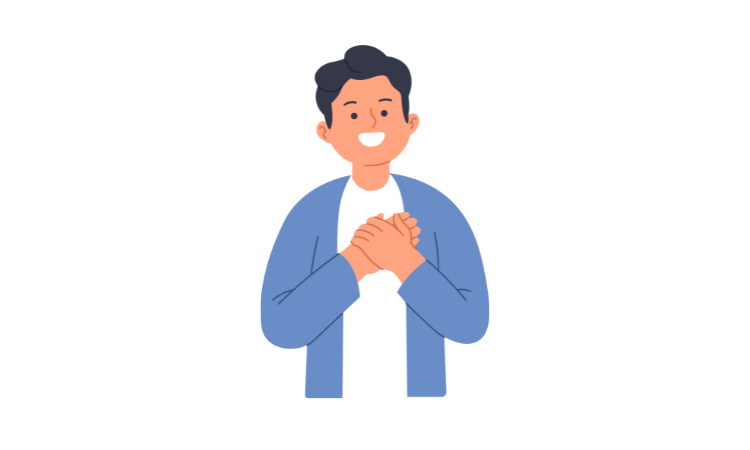
温暖な気候の瀬戸内海に面した山陽地方の中部、岡山県と広島県。この地域の方言は、映画や漫才などを通して全国的にもよく知られています。特に「~じゃ」「~けぇ」といった力強い語尾は、多くの人が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。ここでは、岡山弁と広島弁が持つ、親しみやすくも奥深い世界を探っていきます。
岡山県の方言:備前弁・備中弁・美作弁
岡山県の方言は、旧国名に由来する「備前弁(びぜんべん)」「備中弁(びっちゅうべん)」「美作弁(みまさかべん)」の3つに区分されますが、現在では地域による言葉の違いはそれほど大きくありません。 岡山弁は広島県東部の備後弁とともに「東山陽方言」というグループに属し、アクセントは標準語に近い東京式です。
岡山弁の大きな特徴は、母音が2つ続くときに音が融合して伸びることです。 例えば、「赤い(akai)」は「あけー」、「長い(nagai)」は「なげー」といった具合に変化します。 また、理由を説明するときの「~だから」は「~じゃけぇ」となり、これも岡山弁を象徴する表現です。 そして何と言っても有名なのが、「とても」「すごく」を意味する強調表現でしょう。「でぇれぇ」「ぼっけぇ」といった言葉があり、少し前には「もんげぇ」もアニメの影響で話題になりました。 これらの言葉は、感情を豊かに表現するために使い分けられています。
広島県の方言:安芸弁と備後弁の違い
広島県の方言は、県西部(広島市など)の「安芸弁(あきべん)」と、県東部(福山市・尾道市など)の「備後弁(びんごべん)」の2種類に大きく分けられます。 一般的に「広島弁」としてメディアなどでイメージされるのは、安芸弁の方です。 備後弁は、お隣の岡山弁と非常に近く、同じ東山陽方言に分類されることがあります。
安芸弁と備後弁の分かりやすい違いとしては、例えば「~ばかり」という言葉が、安芸弁では「~ばっかり」となるのに対し、備後弁では「~ばあ」となるといった点が挙げられます。 また、昔ながらの表現では、「~でございます」にあたる言葉が安芸では「~がんす」、備後では「~やんす」となり、地域差が見られました。 とはいえ、両地域に共通する特徴も多く、代表的なのが「~じゃけぇ(~だから)」や、命令形の「~しんさい(~しなさい)」、「来て」を意味する「来んさい」などです。
山陽中部を代表する表現:「じゃけぇ」「たいぎい」「ぶち」
岡山弁や広島弁には、地域を象徴するような有名な言葉が数多く存在します。中でも「~じゃけぇ」「~じゃけん」は、理由や原因を示す接続助詞で、「~だから」という意味で広く使われます。 これはもともと「故(ゆえ)に」という古い言葉が変化したものとされています。
また、「たいぎい」という言葉も広島県を中心によく使われます。これは「億劫だ」「面倒くさい」という意味で、体がだるい時や、何かをするのが億劫な時に口にされる言葉です。 そして、広島や山口でよく聞かれるのが「ぶち」という言葉。 これは「とても」「すごく」という意味の強調表現で、「ぶちすごい」「ぶちうまい」のように使われます。人によっては「ぶり」「ばり」と言うこともあり、若者を中心に日常的に使われる、活気のある方言です。
【西の玄関口】山口の中国地方方言

本州の最西端に位置する山口県は、古くから九州や大陸との交流の窓口としての役割を担ってきました。その地理的な条件を反映し、山口県の方言は、中国地方の言葉としての特徴を持ちながらも、九州地方の方言と多くの共通点が見られる、まさに「境界域」の方言と言えます。ここでは、そんな山口弁のユニークな特徴に迫ります。
山口県の方言の特徴:中国方言と九州方言の交差点
山口県の方言(山口弁)は、広島弁や石見弁とともに「西中国方言」に分類されます。 アクセントは東京式で、江戸時代に県内のほとんどを長州藩が治めていた影響から、県内での方言差が比較的小さいとされています。
山口弁の最も大きな特徴は、西日本方言の西の端に位置しながら、関門海峡を挟んだ九州の方言、特に北九州弁との共通点が非常に多いことです。 例えば、動詞の活用の一部(バ行・マ行のウ音便化)や、語彙の面で多くの類似点が見られます。そのため、山口県の西部で話される言葉は、中国方言と九州方言の「境界域方言」とも言われることがあります。 このように、中国地方と九州地方、二つの文化が交わる場所だからこそ生まれたハイブリッドな方言が山口弁なのです。
「~ちゃ」「~ちょる」に代表される独特の語尾
山口弁と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、「~ちゃ」や「~ちょる」という可愛らしい響きの語尾ではないでしょうか。 「~ちゃ」は、「~だよ」という主張や念押しを表す終助詞で、「これ、おいしいっちゃ(これ、おいしいんだよ)」のように使われます。また、「~ちょる」は、「~している」という動作の継続や状態を表し、「今、テレビ見ちょる(今、テレビを見ている)」という風に使います。
これらの語尾は、山口県民のアイデンティティとも言えるほど広く浸透しており、県のPRキャラクター「ちょるる」の名前の由来にもなっています。 ちなみに、同じ「~ちゃ」でも、福岡県の博多弁などにも見られますが、使われる文脈やイントネーションには微妙な違いがあります。この語尾があることで、山口弁の会話は親しみやすく、柔らかな印象を与えます。
他県民が驚く山口県の言い回し
山口弁には、他の地域の人々が聞くと意味を誤解してしまったり、驚いたりするようなユニークな言葉が存在します。例えば、「この問題はみやすい」と言われたら、どういう意味だと思いますか。これは「問題が見やすい」という意味ではなく、「この問題は簡単だ・たやすい」という意味で使われる方言です。
また、疲れたり、しんどい状態を表す時に「せんない」という言葉を使います。 「ああ、せんないわあ」と言っていたら、それは「つらい、大変だ」と訴えているサインです。同じく疲れた様子を表す言葉に「えらい」がありますが、これも標準語の「偉い」とは全く意味が異なり、「疲れた、しんどい」という意味で使われます。 他にも、すねることを「はぶてる」、物を元の場所に戻すことを「なおす」と言うなど、知っていると山口県民とのコミュニケーションがもっと楽しくなる言葉がたくさんあります。
まとめ:多様性が魅力の中国地方の方言

この記事では、中国地方5県の方言について、その全体像から各県ごとの細かな特徴までを掘り下げてきました。中国地方の方言は、山陰と山陽で「だ」と「じゃ」の使い分けがあるなど、地域によって大きな違いがあります。 また、鳥取・島根の雲伯方言のように古代の響きを残す言葉、岡山・広島の力強くも親しみやすい表現、そして山口の九州方言とのつながりを感じさせる言葉など、そのバリエーションは非常に豊かです。
それぞれの土地の歴史や風土が、言葉を少しずつ形作り、現在に伝わってきました。 方言は、単なる言葉のバリエーションではなく、その土地の文化そのものです。中国地方を訪れる機会があれば、ぜひ現地の人の温かい言葉に耳を傾けて、その魅力を肌で感じてみてください。