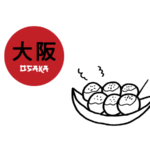杜の都、仙台。旅行や出張、あるいはアニメやドラマをきっかけに、独特の響きを持つ「仙台弁」に興味を持った方も多いのではないでしょうか。仙台弁は、江戸時代の仙台藩で話されていた言葉がルーツとされ、宮城県全域でその名残を聞くことができます。 一見すると少し無愛想に聞こえるかもしれませんが、実はとても温かみがあり、親しみやすい魅力にあふれています。
この記事では、そんな仙台弁の基本的な特徴から、日常会話で使える便利なフレーズ、そして標準語とは少し違う面白い表現まで、豊富な「仙台の方言一覧」を交えながら、やさしく分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたも仙台弁の虜になること間違いなし。さあ、一緒に仙台弁の奥深い世界を探検してみましょう。
そもそも仙台弁とは?その特徴を解説

仙台弁と一言で言っても、その背景には長い歴史と独特の文化が息づいています。ここでは、仙台弁がどのようにして生まれ、どのような音声的・文法的な特徴を持っているのかを紐解いていきます。これらの基本を知ることで、方言一覧をより深く理解することができるでしょう。
仙台弁の歴史と成り立ち
現在の仙台弁の基礎は、江戸時代に広大な領地を誇った仙台藩で使われていた言葉にあります。 当時の侍言葉や町人言葉、そして土着の言葉が混じり合い、独自の発展を遂げたとされています。 興味深いことに、仙台藩はその広大な領土にもかかわらず、地域による方言の差が比較的少ないとされています。
これは、藩の中心であった仙台の言葉が、領内全域に影響を与えていたためと考えられます。ただし、厳密には県北、県南、沿岸部、内陸部で少しずつ言葉の違いが見られ、それぞれが独自のニュアンスを持っています。 例えば、三陸地方では岩手県沿岸部と共通する語彙が見られるなど、隣接する地域との繋がりも感じられます。
発音やイントネーションの特徴
仙台弁、そして広く東北地方の方言の大きな特徴として「ズーズー弁」が挙げられます。 これは、特定の音が濁って発音される現象のことで、例えば「し」が「す」に、「じ」が「ず」に近い音になることがあります(例:「寿司」→「すす」)。 また、「カ行」が「ガ行」に(例:「書く」→「書ぐ」)、「タ行」が「ダ行」に(例:「頭」→「あだま」)なりやすいのも特徴です。
さらに、言葉の間に小さい「っ」が入る「促音便」や、言葉の終わりが「ん」になる「撥音便」が多用されることも、仙台弁の独特なリズムを生み出しています。 このような発音の特徴が、仙台弁に温かみや柔らかさを与えているのかもしれません。
文法的な特徴(語尾など)
仙台弁の文法で最も特徴的なのは、文末に使われる多彩な語尾です。おそらく最も有名なのは「〜だっちゃ」でしょう。 これは「〜だよ」「〜だよね」といった意味で、同意を求めたり、念を押したりする際に使われます。 有名なアニメキャラクターの影響で知られていますが、実際の仙台弁のイントネーションは少し異なります。
他にも、勧誘を表す「〜べ」や「〜ぺ」(例:「行こう」→「行ぐべ」)、丁寧な依頼を表す「〜けさいん」(例:「来てください」→「来てけさいん」)など、状況に応じて様々な語尾が使い分けられます。 これらの語尾を覚えるだけで、ぐっと仙台らしい会話に近づくことができます。
【場面別】仙台の方言一覧(日常会話編)

ここでは、実際の生活シーンで役立つ仙台弁を場面ごとにご紹介します。挨拶から感情表現、さらには買い物や食事の際に使える便利なフレーズまで、すぐに使えるものばかりです。これらの言葉を使えば、地元の人々との距離もぐっと縮まるはずです。
あいさつで使う仙台弁
仙台でのコミュニケーションは、まず挨拶から。朝の挨拶「おはようございます」は「おはよがす」となります。 そして、夕方以降の「こんばんは」にあたるのが「おばんです」または「おばんでがす」です。 これは仙台だけでなく、東北や北海道の広い地域で使われる挨拶で、地元の人々の間では非常に馴染み深い言葉です。
また、感謝を伝える「ありがとう」は「どうもね」や、より丁寧に「ありがとうござりす」と言います。 別れ際の「さようなら」は、親しい間柄なら「んでね」と軽く言ったりします。 これらの挨拶を自然に使えるようになれば、あなたも仙台コミュニティの一員です。
感情を表現する仙台弁
感情を豊かに表現する言葉も仙台弁にはたくさんあります。「うれしい」「すごい」といったポジティブな感情は、「いぎなりうれしい!」(とてもうれしい)のように表現します。 驚いたときには思わず「なんだべ!」や「たまげた!」という言葉が飛び出します。 「なんだべ」は「あらまあ!」というようなニュアンスです。
一方で、疲れた時は「こわい」や「がおった」と言います。 標準語の「怖い」とは意味が違うので注意が必要です。「こわい」は身体的な疲れを、「がおった」はもう少しぐったりしてしまった、気が滅入ったというような状態を表します。 また、腹が立った時には「ごしゃぐぞ!」(怒るぞ!)なんていう少し強めの表現もあります。
買い物や食事で使える仙台弁
市場やお店でのやり取り、食堂での注文など、旅先でのコミュニケーションに方言は欠かせません。「これ、ください」は「これ、けさいん」。「食べてください」は「あがいん」や「け」と言ったりします。 「け」一文字で「食べなさい」という意味になるのは、面白い特徴です。
美味しいものを食べた時には、「んめぇ!」(うまい!)や「いぎなりうまい!」(とてもおいしい!)と感想を伝えてみましょう。お店の人もきっと喜んでくれるはずです。また、会計の際に「お会計お願いします」を「お勘定してけさいん」と言うと、より地元らしい表現になります。
驚いたときに使う仙台弁
予期せぬ出来事に遭遇したとき、仙台の人々は様々な言葉で驚きを表現します。「あらまあ!」という意味合いで使われるのが「あいや!」や「なんだべ!」です。 「あいや!」は、しまった、というニュアンスを含むこともあります。
さらに強い驚きや、信じられないという気持ちを表すときには「たまげた!」という言葉が使われます。 これは「びっくりした」の最上級のような表現です。「なにすや!?」(なんだって!?)というのも、驚きを表現する際に使われる言葉です。 これらのフレーズは、会話の中で相槌として使うと、感情がより豊かに伝わります。
【品詞別】仙台の方言一覧(単語編)

仙台弁の魅力をさらに深く知るために、ここでは名詞、動詞、形容詞・副詞といった品詞別に具体的な単語を一覧で見ていきましょう。聞き慣れない単語も多いかもしれませんが、意味を知ると日常の風景が少し違って見えてくるかもしれません。
名詞を表す仙台弁
日常的に使われる物や体の部位にも、仙台弁ならではの呼び名があります。例えば、体の部位では「目」のことを「まなぐ」、「おでこ」を「なづぎ」と言います。お金のことは「じぇんこ」や「じぬ」、子供たちのことは「わらすこ」と呼びます。
食べ物に関しても、ジャガイモを「ごしょいも」、とうもろこしを「きみ」と言ったりします。また、意外なところでは「ジャージ」のことを「ジャス」と呼ぶことがあります。これは特に学生を中心に使われることがある言葉です。靴下に穴が開いて指が出ている状態を「おはよう靴下」と呼ぶユーモラスな表現もあります。
動詞を表す仙台弁
動詞にも、標準語とは異なるユニークなものがたくさんあります。「捨てる」ことを「なげる」と言うのは、仙台を含む東北・北海道地方で広く使われる有名な方言です。 ゴミを捨てることを「ゴミをなげる」と言うので、他県から来た人は「投げていいの?」と驚くことがあります。
他にも、「触る」「いじる」ことを「ちょす」、「交換する」ことを「ばくる」、「(液体を)こぼす」ことを「まかす」と言います。「怒られる」は「ごしゃがれる」という特徴的な言い方をします。 また、「頑張れ」と応援するときには「けっぱれ!」という温かい言葉が使われます。
形容詞・副詞を表す仙台弁
感情や状態を表す形容詞や副詞には、仙台弁のニュアンスが色濃く現れます。「小さい」ことを「ちっちゃい」がさらに訛って「ちゃんこい」と言ったり、「かっこいい」ことを「まぼい」と言ったりします。
「とても」「すごく」という強調を表す副詞「いきなり(いぎなり)」は非常に重要です。 また、物事がうまくいかずちぐはぐな様子を「あぺとぺ」と表現します。 「しょっぱい」ことは「しょっぺ」、「味が薄い」ことは「あんばい」と言います。 このように、感覚的な表現にこそ、方言の面白さが詰まっています。
これを知ればあなたも仙台通!仙台弁の面白い表現

仙台弁には、標準語に一言では訳しにくい、独特のニュアンスを持つ言葉が存在します。これらの言葉を理解することは、仙台の人々の考え方や文化に触れることにも繋がります。ここでは、特に代表的で面白い表現をいくつか掘り下げてみましょう。
「いずい」- 仙台弁を代表する独特の感覚
「いずい」は、仙台弁、ひいては東北地方を代表する言葉の一つで、標準語にぴったりと当てはまる訳語がないことで有名です。 これは「しっくりこない」「フィットしない」「居心地が悪い」「もどかしい」といった、身体的または精神的な違和感を総合したような感覚を表します。
例えば、目にゴミが入ってゴロゴロする感じ、服のタグが首に当たってチクチクする不快感、歯に何かが挟まったような感じ、あるいは自分だけ場違いな場所にいるような気まずさなど、多岐にわたる状況で「いずい」が使われます。 この言葉の起源は、室町時代の京都で使われていた「えずい」(恐ろしくてぞっとするような)という言葉にあるとされています。 この言葉が東北に伝わり、現在の意味に変化していったと考えられています。
「だから」- 同意を示す相槌の言葉
標準語での「だから」は、理由や原因を示す接続詞として使われます。 しかし仙台弁では、これが相手への強い同意や共感を示す相槌として使われるのが大きな特徴です。
会話の中で相手が言ったことに対して「だから!」や「だからねー」と返された場合、それは「本当にその通り!」「そうそう、そうなのよ!」といった意味になります。 初めて聞くと、話を遮られたように感じたり、理由を問われているように聞こえたりして戸惑うかもしれませんが、これは相手があなたの話に深く共感しているサインなのです。 この使い方を覚えておくと、仙台の人との会話がよりスムーズで楽しくなるでしょう。
「いきなり」- 「とても」を意味する強調表現
標準語の「いきなり」は「突然に」「急に」という意味で使われます。 もちろん仙台弁でもその意味で使われることがありますが、若者を中心に「とても」「すごく」という強調の意味で使われることが非常に多いです。
「このラーメン、いきなりうまい!」(このラーメン、とてもうまい!)、「昨日はいきなり疲れた」(昨日はすごく疲れた)のように、形容詞や動詞を強調する形で使われます。 元々は標準語の「いきなり」が持つ「突然で激しい」というニュアンスから、程度の大きさを表す部分だけが独立して使われるようになったと考えられています。 関西地方の「めっちゃ」や「ばり」に近い使い方だとイメージすると分かりやすいかもしれません。
「んだ」 – バリエーション豊かな万能相槌
「んだ」は、「そうだ」という意味を表す、仙台弁を含む東北地方で広く使われる基本的な相槌です。 親しい間柄で頻繁に使われ、これ一つで会話が成立することも少なくありません。
この「んだ」は、語尾が変化することで様々なニュアンスを表現できるのが特徴です。「んだべ?」「んだっちゃ?」(そうだよね?)と同意を求めたり、「んだげっと」(そうだけど)と話を続けたり、「んだから」(そうなんだよ、だから言ったじゃないか)と強調したりと、バリエーションは非常に豊かです。 地元の人々の会話に耳をすませば、様々な「んだ」が飛び交っているのが聞こえるはずです。この万能な相槌を使いこなせれば、あなたも仙台弁マスターに一歩近づけます。
仙台弁を使う上での注意点と他の東北方言との違い

方言はその土地の文化であり、温かみのあるコミュニケーションツールですが、使い方を間違えると誤解を生む可能性もあります。また、仙台弁と一括りにされがちですが、近隣の他県の方言とはもちろん、宮城県内でも地域によって違いがあります。
使う相手や場面に気をつけよう
仙台弁には親しみやすい表現が多いですが、やはり方言ですので、ビジネスシーンや初対面の人、目上の人に対して使う際は注意が必要です。 例えば、親しい同僚に「けっぱれ!」(頑張って!)と声をかけるのは励ましになりますが、フォーマルな場では「頑張ってください」と言うのが適切です。
また、「だから」という相槌も、意味を知らない相手には「だから何なのですか?」と詰問しているように聞こえてしまう可能性があります。 方言の面白さに惹かれて使ってみたくなる気持ちは分かりますが、まずは相手との関係性や場面をよく考えて、少しずつ使ってみるのが良いでしょう。
宮城県内の他地域の方言との違い
「仙台弁」という言葉は、広く宮城県全域の方言を指して使われることが多いですが、厳密には地域ごとに違いがあります。 大きく分けると、仙台市周辺の「仙台方言」、県北内陸部の「仙北内陸方言」、県南の「仙南方言」、そして沿岸部の「三陸方言」の4つに区分されることがあります。
例えば、仙南地方では福島県でよく使われる「さすけね」(問題ない、気にするな)という言葉が聞かれたりします。 沿岸部の石巻などでは、漁師町らしい少し荒々しくも気風の良い言葉遣いが特徴的です。 このように、同じ宮城県内でも地域によって少しずつ言葉の特色が異なることを知っておくと、地元の人との交流がさらに楽しくなるでしょう。
山形弁や福島弁など近隣の方言との比較
仙台弁が属する南奥羽方言は、奥羽山脈を隔てた山形県内陸部の方言(村山弁や置賜弁など)や、福島県の方言と多くの共通点を持っています。 例えば、同意の「んだ」や勧誘の「〜べ」などは、これらの地域で広く使われています。
しかし、もちろん違いもあります。例えば、山形弁では文末に「〜っす」を多用する傾向があったり、福島県の浜通り地方ではまた違ったイントネーションや語彙があったりします。細かい語尾の使い方や特定の単語は、それぞれの地域で独自に発展してきました。東北地方を旅する際には、それぞれの土地の言葉の微妙な違いに耳を傾けてみるのも一興です。
まとめ:仙台の方言一覧で知る仙台弁の奥深い魅力

この記事では、「仙台の方言一覧」というキーワードを軸に、仙台弁の様々な側面を掘り下げてきました。仙台弁は、単なる言葉のバリエーションではなく、その土地の歴史や文化、そして人々の気質が色濃く反映されたコミュニケーションの形です。 発音の濁りや独特の語尾が作る温かい響き、そして「いずい」や「だから」といった標準語にはないユニークな表現は、仙台弁の大きな魅力と言えるでしょう。
はじめは聞き慣れない言葉に戸惑うかもしれませんが、一覧で紹介したフレーズの意味を知り、実際の会話で耳にすることで、その奥深さや面白さに気づくはずです。仙台を訪れる機会があれば、ぜひこの記事を参考に、地元の人々との会話を楽しんでみてください。きっと、あなたの旅がより一層豊かなものになることでしょう。