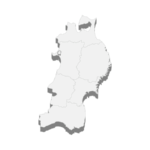静岡県と聞くと、富士山やお茶、うなぎなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、静岡の魅力はそれだけではありません。実は、静岡県内で話される「静岡弁」も、とても個性的で奥深い魅力を持っているのです。東西に長い静岡県では、地域によって言葉に違いがあるのが大きな特徴です。
この記事では、そんな静岡の方言一覧をご紹介します。日常的によく使われる「だら」や「しょんない」といった言葉から、思わず「どういう意味?」と聞き返したくなる面白い表現まで、例文を交えながらやさしく解説していきます。この記事を読めば、あなたも静岡弁の虜になること間違いなし。静岡への旅行や、静岡出身の方との会話がもっと楽しくなるはずです。
静岡の方言一覧!まずは知っておきたい代表的な言葉

静岡県には、県民が日常的に使う特徴的な方言がいくつもあります。標準語に近いと言われることもありますが、語尾や特定の単語に静岡らしさが表れます。 まずは、静岡弁を語る上で欠かせない、基本的な言葉をいくつか見ていきましょう。これらを知っているだけで、静岡県民との距離がぐっと縮まるかもしれません。
「〜だら」「〜ら」:親しみやすい同意と推量の表現
「〜だら」や「〜ら」は、静岡弁を代表する語尾の一つです。 主に「〜でしょ?」や「〜だよね?」といった、相手に同意を求めたり、確認したりする意味で使われます。 例えば、「このお菓子、おいしいだら?」と言えば、「このお菓子、おいしいでしょ?」というニュアンスになります。
また、「〜だろう」という推量を表す場合にも使われ、「明日は晴れるだら」は「明日は晴れるだろう」という意味です。 この「だら」「ら」は、言葉の響きを和らげ、親しみやすい雰囲気を作り出す効果があります。静岡県民同士の会話では非常によく登場する表現で、特に中西部で頻繁に耳にします。 例えば、「行くだら?」は「行くだろう?」と相手の意向を伺うような、柔らかい誘い方になります。 静岡出身の人と話す機会があれば、ぜひこの「だら」の使い方に注目してみてください。
「だもんで」:理由を伝える便利な接続詞
「だもんで」は、「〜だから」「〜なので」という意味で使われる接続詞で、静岡県民の会話に頻繁に登場する言葉です。 標準語の「だから」よりも、少し柔らかく、丁寧な印象を与えるのが特徴です。 例えば、「今日は雨が降っているだもんで、傘を持っていったほうがいいよ」というように、理由や原因を説明する際に使われます。
この「だもんで」は、文の途中だけでなく、文頭で使われることもあります。 「だもんで、今日はやめにしたよ」のように、前の会話を受けて「だから、〜」と話を続ける際にも便利です。静岡県内の広い地域で、年齢を問わず使われている方言なので、静岡を訪れると耳にする機会が非常に多いでしょう。 この言葉を使いこなせれば、あなたも静岡弁のネイティブに一歩近づけるかもしれません。
「しょんない」:諦めと共感の万能フレーズ
「しょんない」は、「仕方がない」「しょうがない」という意味を持つ、静岡県で広く使われる方言です。 何かうまくいかなかった時や、どうしようもない状況に陥った時に、「まあ、しょんないね」といった形で使われます。この言葉には、単なる諦めだけでなく、相手への共感や慰めのニュアンスが含まれているのが特徴です。
例えば、楽しみにしていたイベントが雨で中止になった時に、友人が「しょんないよ、また今度行こう」と声をかけてくれるような場面で使われます。静岡が舞台のローカルテレビ番組のタイトルにも使われたことがあるほど、県民に親しまれている言葉です。 残念なことがあった時に「しょんない!」と口にすることで、気持ちを切り替えるきっかけにもなる、静岡県民の生活に根付いた便利なフレーズと言えるでしょう。
【地域別】静岡の方言一覧(東部・中部・西部)

東西に約155kmと細長い地形の静岡県では、地域によって方言に大きな違いが見られます。 これは、東は関東、西は愛知県と隣接している地理的な要因が大きく影響しています。 ここでは、静岡県を大きく「東部(伊豆・駿東)」「中部(駿河)」「西部(遠州)」の3つのエリアに分けて、それぞれの地域で話される方言の特徴を一覧でご紹介します。
東部(伊豆・駿東)の方言:関東地方の影響が色濃い言葉
富士川以東に位置する東部地域、特に伊豆半島や沼津市、三島市周辺で話される方言は、西関東方言の影響を受けているのが特徴です。 そのため、首都圏の言葉に近い部分もありますが、伊豆ならではの独特な表現も存在します。
語尾には「〜さー」がよく使われます。 これは「〜だよね」といったニュアンスで、親しい友人との会話で頻繁に登場します。 例えば、「昨日、あの店行ったさー」は「昨日、あの店に行ったんだよね」という意味になります。 また、意志や勧誘を表す際には「〜べー」が使われることもあり、「そろそろ行くだべー(そろそろ行こうよ)」といった言い方をします。
単語では、標準語の「大きい」を「いかい」と言ったり、ごみを「捨てる」ことを「うっちゃる」と言ったりします。 この「うっちゃる」は静岡県全域で使われることもありますが、関東の一部でも使われる表現です。 このように、東部の方言は関東地方との言葉の近さを感じさせつつも、独自の進化を遂げた興味深い方言と言えるでしょう。
中部(駿河)の方言:東西の特徴が混じるエリア
静岡市を中心とし、富士川と大井川に挟まれた中部地域は、駿河方言が話されるエリアです。 この地域の方言は、東部と西部の特徴が混じり合っているのが面白い点です。
代表的な表現としては、勧誘の「〜ざあ」や「〜ず」があります。 「一緒に行かざあ(一緒に行こうよ)」のように使い、西部で使われる「〜まいか」とは異なります。 また、静岡市周辺では、過去を表すのに「〜け」という珍しい語法が残っています。 例えば、「昨日、映画を見たけ」は「昨日、映画を見たよ」という意味になります。これは全国的に見ても珍しい表現です。
中部地方でも、「しょんない(仕方ない)」や「だもんで(だから)」は広く使われます。 さらに、「おぞい」という言葉も特徴的です。これは「品質が悪い」や「粗末な」といった意味で、「この服、おぞいね」のように使います。 東と西の言葉が行き交う中部の方言は、まさに静岡の多様性を象徴していると言えます。
西部(遠州)の方言:愛知県との深いつながり
大井川より西側の浜松市や掛川市を中心とする西部地域は、遠州(えんしゅう)と呼ばれ、「遠州弁」が話されています。 この地域は愛知県と隣接しているため、三河弁など西日本の言葉の影響が強く見られるのが特徴です。
語尾には「〜だに」や「〜りん」が使われます。「〜だに」は「〜だよ」と念を押すようなニュアンスで、「時間過ぎてるだに(時間は過ぎてるよ)」のように使います。 一方、「〜りん」は「〜しなさい」と優しく促す表現で、浜名湖周辺で聞かれます。 「まあ、食べりん(まあ、食べなさいよ)」といった具合です。
また、強調表現として「ど」や「でら」が使われることもあり、これは名古屋弁とも共通しています。単語では、「頭のてっぺん」を「てんこちょ」と言ったり、暖かいことを「ぬくとい」と言ったりするなど、ユニークな言葉が多く存在します。 遠州弁の持つ独特のリズムと響きは、多くの人に親しまれています。
静岡の方言一覧から見る面白い・かわいい表現

静岡県の方言には、標準語と同じ言葉なのに意味が全く違うものや、響きがユニークで思わず微笑んでしまうような面白い・かわいい表現がたくさんあります。これらの方言を知ることで、静岡県民の気質や文化に触れることができるかもしれません。ここでは、そんな静岡弁の中から、特に興味深いものをいくつかピックアップしてご紹介します。
「こわい」:固い、または疲れたという意味の方言
標準語で「こわい」と聞くと、恐怖を感じるという意味を思い浮かべますが、静岡の方言では全く違う意味で使われることがあります。一つは「固い」という意味です。例えば、ご飯が固めに炊けてしまった時に「このご飯、ちょっとこわいね」と言ったりします。
もう一つ、特に遠州地方で使われるのが「疲れた、しんどい」という意味です。 長時間歩いた後などに「ああ、こわい」と言えば、それは「ああ、疲れた」という意味になります。 このように、文脈によって意味が変わるため、初めて聞く人は驚くかもしれません。恐怖とは無関係の「こわい」は、静岡弁の面白さを代表する言葉の一つです。静岡を訪れた際に、誰かが「こわい」と言っていても、必ずしも怖い話をしているわけではないことを覚えておくと良いでしょう。
「みるい」:若い・未熟なことを指すお茶処ならではの言葉
「みるい」は、静岡県、特に中部のお茶の産地でよく使われる方言で、「若い」「未熟な」「柔らかい」といった意味を持ちます。 もともとは、お茶の新芽の柔らかい状態を指す言葉として使われていました。 そこから転じて、果物がまだ熟していない状態や、人の性格が未熟であることなど、幅広い対象に使われるようになりました。
例えば、まだ青いメロンを見て「このメロンはまだみるいね」と言ったり、経験の浅い若者に対して「彼はまだみるいなあ」と評したりします。お茶の文化が深く根付いている静岡ならではの、みずみずしさを感じさせる表現です。響きも柔らかく、どこか可愛らしさを感じさせるため、静岡県民に愛されている方言の一つです。この一言から、静岡の豊かな食文化や人々の暮らしを垣間見ることができます。
「ぶしょったい」:だらしなさや不潔さを表す言葉
「ぶしょったい」は、「だらしない」「みっともない」「汚い」といった意味で使われる方言です。 「無精(ぶしょう)」という言葉が変化したものと考えられており、身だしなみが整っていない様子や、部屋が散らかっている状態などを指して使います。
例えば、「そんなぶしょったい格好で出かけるのかい?」と母親が子供に注意するような場面で登場します。 少し厳しい響きにも聞こえますが、そこには相手を思う親しみや愛情が込められていることも少なくありません。現在では主に年配の方が使うことが多くなりましたが、静岡の中部や西部では今でも耳にすることがあります。 標準語にはない独特の語感が、この言葉の面白さと言えるでしょう。この言葉が自然に出てきたら、あなたも立派な静岡通です。
静岡の方言一覧で学ぶ!日常会話で使えるフレーズ

静岡の方言の基本的な単語や地域ごとの特徴を知ったところで、次は実際に日常会話で使えるフレーズを見ていきましょう。挨拶から感情表現、さらには買い物や食事の場面まで、具体的なシチュエーションで使える静岡弁をマスターすれば、地元の人々とのコミュニケーションがより一層楽しくなるはずです。これらのフレーズを覚えて、静岡を訪れた際にぜひ使ってみてください。
挨拶や呼びかけで使える静岡弁
日常の挨拶にも、静岡らしい表現が隠されています。例えば、親しい間柄での「元気?」という問いかけは、「まめったいかい?」やシンプルに「まめか?」と言ったりします。 また、家に帰ることを「けえる」と言う人もいます。 友人との別れ際に「じゃあ、そろそろけえるわ」と言えば、「それじゃあ、そろそろ帰るね」という自然な挨拶になります。
人や物を指す時には、「〜っち」という接尾語が使われることがあります。例えば、「私たち」は「うちっち」、「あなたたち」は「おまんっち」のように言います。 「うちっち来る?(私の家に来る?)」といった誘い方は、とても親密でかわいらしい響きがあります。 こうした小さな表現に気づくだけで、会話の中に温かみが生まれるのを感じられるでしょう。
感情を表現する静岡弁
感情を表現する言葉にも、静岡ならではのユニークな方言があります。とても嬉しい時や、何かが素晴らしいと感じた時、静岡では「ばか」という言葉を使って強調することがあります。 「このケーキ、ばかおいしい!」と言えば、「このケーキ、すごくおいしい!」という称賛の意味になります。 初めて聞くと驚くかもしれませんが、静岡ではポジティブな意味で頻繁に使われる表現です。
一方で、腹が立ったりがっかりしたりした時には「やっきりする」という言葉が使われます。 「何度も同じミスをして、やっきりしちゃうよ」といった具合です。 激しい怒りというよりは、呆れやうんざりした気持ちに近いニュアンスです。 また、少し拗ねてしまった様子を「ちんぷりかえる」と表現することもあります。 どれも標準語にはない、感情の機微を巧みに表す面白い言葉たちです。
買い物や食事で使える静岡弁
買い物や食事のシーンでも、静岡弁は活躍します。例えば、急いでいる時に「ちゃっと行ってくる!」と言えば、「急いで行ってくるね!」という意味になります。 この「ちゃっと」は「素早く」という意味で、様々な場面で使える便利な言葉です。
また、静岡では「走る」ことを「とぶ」と言うことがあります。 ですから、もしお店の人に「危ないからとばないで!」と言われても、ジャンプしろという意味ではなく「走らないで」という注意なので間違えないようにしましょう。 さらに、食べ物や飲み物が温かい時には「このお茶、ぬくといね」と言います。 この「ぬくとい」という言葉は、じんわりとした温かさを感じさせる、響きの良い方言です。 こうした方言を自然に使えるようになれば、旅先での食事や買い物がもっと楽しくなることでしょう。
まとめ:静岡の方言一覧からわかる多様な言葉の魅力

この記事では、静岡県で話される方言について、代表的な言葉から地域ごとの特徴、そして日常で使える面白い表現まで、幅広く一覧でご紹介しました。東西に長い静岡県は、東部が関東、西部が中京圏の影響を受け、それぞれに異なる方言が育まれてきたことがお分かりいただけたかと思います。
「〜だら」や「しょんない」のような県内で広く使われる言葉から、「みるい」や「ぶしょったい」といった標準語とは意味が異なるユニークな単語まで、静岡弁は知れば知るほど奥深い魅力にあふれています。 これらの言葉は、単なるコミュニケーションの道具ではなく、静岡の文化や歴史、そして人々の温かい人柄を映し出す鏡のような存在です。
もし静岡を訪れる機会があれば、ぜひ耳を澄まして、地元の人々が話す言葉に触れてみてください。そして、勇気を出して一つでも方言を使ってみれば、きっと地元の人々との距離が縮まり、旅がより一層思い出深いものになるはずです。