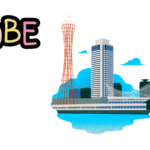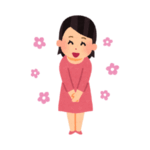「神奈川県の方言」と聞くと、「標準語とあまり変わらないのでは?」と思う方も多いかもしれません。しかし、実は神奈川県には地域ごとに特色のある様々な方言が存在します。有名な「〜じゃん」や「〜だべ」といった言葉は、神奈川県が発祥とされていることをご存知でしたか? これらの言葉は、テレビドラマや有名人の会話などで耳にする機会も多く、親しみを感じる人もいるでしょう。
この記事では、そんな神奈川県で使われている方言を一覧でご紹介します。日常会話で使える基本的な表現から、地域ごとのユニークな言葉、そしてその歴史的背景まで、わかりやすく解説していきます。この記事を読めば、神奈川県の言葉の魅力にきっと気づくはずです。
神奈川県の方言一覧【よく使う基本表現】

神奈川県の方言と聞いて、多くの方が思い浮かべるのが「〜じゃん」や「〜だべ」といった特徴的な語尾ではないでしょうか。これらは神奈川県内で広く使われており、日常会話に溶け込んでいます。標準語に近いと言われる神奈川の方言ですが、これらの言葉があることで、会話に親しみやすさや独特のリズムが生まれます。ここでは、そんな神奈川弁の基本となる表現をいくつか取り上げ、その意味や使い方を詳しく見ていきましょう。
「〜じゃん」- 同意や確認を求める便利な言葉
「〜じゃん」は、神奈川県の方言として非常に有名で、県内で広く使われている表現です。 標準語の「〜じゃないか」が短縮された形で、相手に同意を求めたり、何かを確認したりする際に使われます。 例えば、「昨日言ったじゃん」は「昨日言ったじゃないか」、「これ、おいしいじゃん」は「これ、おいしいじゃないか」といった意味合いになります。
この「〜じゃん」という表現は、もともと静岡県や山梨県などでも使われていましたが、横浜の港湾労働者などを通じて広まり、横浜発祥の方言として定着したという説があります。 現在では神奈川県を越えて、首都圏の若者言葉としても広く浸透しており、方言だと意識せずに使っている人も少なくありません。
会話の最後に付け加えるだけで、少しくだけた親しみやすい雰囲気を出すことができる便利な言葉です。 そのため、友人同士のカジュアルな会話から家族とのやり取りまで、様々な場面で頻繁に登場します。神奈川県民のコミュニケーションにおいて、欠かすことのできない重要な言葉の一つと言えるでしょう。
「〜だべ」- 親しみを込めた同意や推量
「〜だべ」も「〜じゃん」と並んで、神奈川県を代表する方言の一つです。 これは、標準語の「〜だろう」や「〜でしょ」にあたる言葉で、相手に同意を求めたり、自分の推量を述べたりする際に使われます。 例えば、「明日は晴れるだべ?」は「明日は晴れるだろう?」、「君もそう思うだべ」は「君もそう思うでしょ」といった具合です。
この「〜だべ」という語尾は、関東地方の広い範囲で使われる関東方言の特徴的な表現でもあります。 神奈川県内でも、特に湘南地域や県央部でよく耳にします。藤沢市出身の有名タレントがテレビで頻繁に使っていたことから、全国的に「神奈川の方言」として知られるようになりました。
「〜じゃん」が事実の確認や軽い同意を求めるのに対し、「〜だべ」はもう少し話し手の推量や確信のニュアンスが強く含まれることがあります。語調によっては少しぶっきらぼうに聞こえることもありますが、基本的には親しい間柄で使われる温かみのある表現です。会話の中でこの言葉が出てきたら、相手が親しみを込めて話している証拠かもしれません。
「かったるい」- 面倒な気持ちを表す言葉
「かったるい」は、「体がだるい」「面倒くさい」「やる気が起きない」といった状態を表す言葉です。 神奈川県をはじめ、関東地方の広い範囲で使われており、標準語だと思っている人も多いかもしれません。 例えば、「今日は暑くて何もする気が起きない、かったるいなあ」とか、「この作業、単純だけど時間がかかってかったるい」のように使います。
この言葉の語源は、古語の「かひな(腕)だるし」が変化したものという説があります。 もともとは体の倦怠感を表す言葉でしたが、現在では精神的な面倒くささや億劫な気持ちを表す際にも広く用いられます。 若者の間では「かったりぃ」と語尾を伸ばして、よりくだけた表現で使われることもあります。
関西地方で同じような状況を表す際に「しんどい」という言葉が使われるのと対比されることがあり、関東特有の表現として挙げられることもあります。 日常のちょっとした不満や気乗りしない気持ちを的確に表現できる言葉として、神奈川県民の会話に頻繁に登場する、非常にポピュラーな方言の一つです。
「横入り」- 列への割り込みを指す言葉
「横入り(よこはいり)」は、レジや電車の待ち行列などに割り込む行為を指す言葉です。 標準語の「割り込み」と全く同じ意味ですが、神奈川県民はこちらの「横入り」を使うことのほうが圧倒的に多いと言われています。 例えば、並んでいる列に誰かが無理やり入ってきた時に、「ちょっと、横入りしないでくださいよ」と注意したり、「さっき、横入りされた」と不満を述べたりする際に使われます。
この「横入り」という言葉は、神奈川県だけでなく、東京や愛知県などでも使われることがあるため、方言であるという認識がない人も少なくありません。 しかし、特に関西地方などではあまり使われないため、他県の人と話していて初めて方言だと気づく、というケースも多いようです。
子どもたちの間でもごく自然に使われており、「横入りされたー!」といった会話が日常的に聞かれます。 このように、世代を問わず生活に根付いている言葉であることから、「横入り」は神奈川の文化を象徴する方言の一つと言えるでしょう。標準語の「割り込み」よりも直接的で、少し非難めいた響きを持つのが特徴かもしれません。
神奈川県の方言一覧【ユニークな単語】

神奈川県の方言は、「〜じゃん」や「〜だべ」といった語尾だけでなく、他の地域ではあまり聞かないユニークな名詞や動詞、形容詞もたくさん存在します。これらの言葉は、その土地の生活や文化から生まれたものであり、知れば知るほど神奈川への理解が深まります。ここでは、そんな特徴的な単語をいくつかピックアップし、その意味や使い方、そして背景にある面白いエピソードなどを紹介していきます。
「うっちゃる」- 捨てるという意味の言葉
「うっちゃる」は、「捨てる」や「放置する」という意味で使われる動詞です。 例えば、「この古い雑誌、もう読まないからうっちゃっておいて」は「この古い雑誌はもう読まないから捨てておいて」という意味になります。また、単に物を捨てるだけでなく、「問題をうっちゃっておく」のように、物事を放置したり、気にしないでおいたりする、といったニュアンスで使われることもあります。
この言葉の語源は、相撲の決まり手である「うっちゃり(打っ棄り)」と同じで、「打ち捨てる」が変化したものとされています。 相手を土俵際で逆転して投げる技のように、勢いよく放り出すようなイメージが伴う言葉です。
特に湘南地域や県西部で使われることが多いとされています。 標準語の「捨てる」と比べて、少しぞんざいで無造作な感じを与えるかもしれません。しかし、その響きにはどこか力強さや潔さが感じられ、神奈川らしい気風を反映した言葉とも言えるでしょう。日常会話の中で、物を片付ける際や不要なものを処分する場面などで、ごく自然に使われています。
「かたす」- 片付けるという意味の広い言葉
「かたす」は、「片付ける」「整理整頓する」という意味で使われる動詞です。 神奈川県だけでなく、多くの地域で使われる言葉ですが、神奈川では特に使用範囲が広いのが特徴です。一般的に「部屋をかたす」「机の上をかたす」のように、物理的に物を整理する際に使われます。
しかし、神奈川県の方言としての「かたす」は、それだけにとどまりません。例えば、「仕事をかたす」「宿題をかたす」というように、やるべき事を終える、完了させるという意味でも使われることがあります。 この用法は、他の地域ではあまり一般的ではなく、神奈川県民が県外に出て初めて意味が通じずに方言だと気づくケースが多いようです。
このように、「かたす」という一つの言葉が、物理的な整理整頓から抽象的なタスクの完了まで、幅広い意味をカバーしているのが興味深い点です。これは、効率を重視する県民性を反映しているのかもしれません。日々の生活の中で「早くかたしちゃいなさい!」と親に言われた経験を持つ神奈川県民は少なくないでしょう。
「おっかねー」- 「怖い」を表す感情豊かな言葉
「おっかねー」は、「怖い」「恐ろしい」という意味を表す形容詞です。 標準語の「怖い」と意味は同じですが、より感情的で、 colloquial(口語的)な響きを持っています。例えば、「夜道の一人歩きはおっかねーよ」とか、「あそこのお化け屋敷は本当におっかねーらしい」といったように使われます。
この言葉は、古語の「おほ(甚)きなし」が変化したものという説があり、もともとは「大変だ」「大げさだ」といった意味合いだったものが、次第に「恐ろしい」という意味で使われるようになったと考えられています。神奈川県だけでなく、関東から東北にかけての広い地域で使われている方言です。
「怖い」という直接的な表現よりも、話者の恐怖心や驚きといった感情がより強く伝わるのが特徴です。少し荒っぽい言葉に聞こえるかもしれませんが、その分、臨場感や親密さを生み出す効果もあります。 親しい友人同士の会話や、昔ながらの地域のコミュニティなどで、今でもごく自然に使われている言葉の一つです。
「しょっぱい」- 塩辛いだけじゃない多彩な意味
「しょっぱい」という言葉は、標準語では「塩辛い」という意味で使われますが、神奈川県の一部、特に湘南地域などでは、それ以外の意味を持つことがあります。一つは、「みすぼらしい」「けちくさい」「情けない」といったネガティブな評価を表す使い方です。「あの店の対応はしょっぱかった」と言えば、サービスが悪くてがっかりした、という意味になります。また、「しょっぱい試合」と言えば、内容がつまらない、レベルの低い試合だったというニュアンスになります。
この用法は、相撲界で使われる隠語が由来とされています。力が入らない、つまらない相撲を「しょっぱい」と表現することから、一般にも広がったと言われています。この意味での「しょっぱい」は、物事の結果や内容が期待外れであった時の不満や失望の気持ちを表すのに非常に便利な言葉です。
さらに、「つらい」「厳しい」という意味で使われることもあります。例えば、「この仕事はしょっぱいよ」と言えば、給料が安い、労働条件が厳しいといったニュアンスが含まれます。このように、単なる味覚を表す言葉にとどまらず、人の感情や物事の評価まで幅広く表現できる、奥深い方言なのです。
神奈川県の地域別方言一覧とそれぞれの特徴

神奈川県は、東京に隣接する都会的なイメージの横浜・川崎エリア、海と若者文化が融合する湘南エリア、内陸の工業・住宅地である県央エリア、そして自然豊かな山々に囲まれた西部エリアと、非常に多様な顔を持っています。 そのため、「神奈川弁」と一括りにはできず、地域ごとに言葉の特色が見られます。ここでは、県内を大きく4つのエリアに分け、それぞれの地域で使われる方言の特徴や代表的な言葉を一覧にしながら解説していきます。
横浜・川崎エリアの方言(横浜弁)
横浜市と川崎市は東京都心へのアクセスも良く、古くから多くの人が行き交う地域であるため、伝統的な方言は薄れ、首都圏方言(共通語に近い新しい方言)が主流となっています。 そのため、「横浜発祥と言い切れる方言はほとんどない」とも言われています。 しかし、全国区になった「〜じゃん」は横浜が発祥という説もあり、言葉の端々に横浜らしさが残っています。
このエリアの方言の特徴は、東京の江戸言葉の影響を受けつつも、港町として栄えた歴史から、少し荒っぽく聞こえる言い回しがある点です。 例えば、「大きい」を「でけー」、「違う」を「ちげー」と言うなど、言葉を崩した表現がよく使われます。 また、「横入り」も横浜でよく使われる言葉として知られています。
イントネーションは基本的に標準語と変わりませんが、語尾が少し強くなる傾向があるとも言われています。 現代では、生粋の「横浜弁」を話す人は少なくなりましたが、こうした言葉の断片に、かつての港町の活気や人々の気質を感じ取ることができます。
湘南エリアの方言(湘南弁)
藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市などを含む湘南エリアは、海辺の開放的な文化を反映した独特の方言「湘南弁」が話されています。 有名な「〜だべ」はこの地域で特によく使われる言葉で、全国的な知名度を得るきっかけにもなりました。
湘南弁の特徴は、リラックスした雰囲気を持ちつつも、少しやんちゃな響きを持つ言葉が多いことです。 例えば、「捨てる」を意味する「うっちゃる」や、「面倒くさい」を意味する「かったるい」などが代表的です。 また、言葉を短縮したり、リズミカルに話したりする傾向も見られます。イントネーションは、語尾が平坦になる特徴があるとも言われ、他の関東地方の方言とは少し異なる、独特のゆったりとしたリズム感を生み出しています。
近年は、メディアの影響や他地域からの移住者の増加により、伝統的な湘南弁は変化しつつあります。しかし、地元の人々の会話の中には、今でも「だべ」や「じゃん」といった言葉が息づいており、湘南らしいラフでフレンドリーな空気を作り出しています。
県央・相模原エリアの方言(相模弁)
厚木市、大和市、相模原市などの県央エリアで話されるのは、総称して「相模弁(そうしゅうべん)」と呼ばれる方言です。 この地域は、丹沢山地を挟んで南北、相模川を挟んで東西で言葉の違いが見られるのが特徴です。 例えば、相模川の西側では疑問を表す際に「〜けー」という語尾が使われることがあります。
相模弁には、農村地帯であった歴史を反映した、素朴で温かみのある言葉が残っています。例えば、肩ぐるまを意味する「でんがらまっこ」といったユニークな単語も、かつては使われていました。 また、「嘘」を「うそんこ」と言ったり、片付けることを「かたす」と言ったりするのは、この地域でもよく聞かれる表現です。
アクセントやイントネーションは、基本的には西関東方言の典型ですが、山梨県や多摩地域と隣接しているため、それらの地域の方言と共通する点も見られます。 宅地開発が進み、首都圏のベッドタウンとして発展した現在では、若い世代で方言を使う人は減っていますが、地域の高齢者との会話の中には、今でも昔ながらの相模弁の響きを聞くことができます。
西部・足柄エリアの方言(西湘弁)
小田原市や南足柄市、足柄上郡・下郡などの県西部エリアでは、「西湘弁(せいしょうべん)」とも呼ばれる方言が話されています。この地域は地理的に静岡県や山梨県に近いため、それらの県の方言の影響を強く受けているのが大きな特徴です。
例えば、発音においては、母音の「アイ」が「エー」に変化する傾向(例:「大根」→「デーコン」)が顕著に見られます。 また、文法面では、逆接の接続助詞「〜けど」を「〜けんど」と言ったり、疑問の終助詞に「〜けー」を使ったりするなど、静岡県の伊豆弁や静岡弁と共通する特徴が多くあります。
語彙に関しても、「しゃっこい」(冷たい)や「おっかねー」(怖い)といった、西関東から東海地方にかけて広く使われる言葉が日常的に用いられます。 アクセントも、県東部とは異なる場合があり、標準語とは違う独特のイントネーションを持つ単語が存在します。 このように、西部・足柄エリアの方言は、神奈川県の中でも特に個性豊かで、他の地域とは一線を画した魅力を持っています。
神奈川県の方言の歴史と成り立ち

神奈川県の方言は、どのようにして現在の形になったのでしょうか。その背景には、地理的な条件や歴史的な人々の交流が深く関わっています。東京に隣接していることから標準語の影響を強く受ける一方で、東海道の宿場町として、また開港地として多くの人々が行き交った歴史が、言葉にも多様性をもたらしました。ここでは、神奈川の方言が歩んできた道のりを、いくつかの側面から探っていきます。
西関東方言としての一面
神奈川県の方言は、言語学的には「西関東方言」というグループに分類されます。 これは、東京、埼玉、群馬、そして山梨の一部などで話される方言グループのことで、文法や語彙に多くの共通点を持っています。 例えば、同意や推量を表す「〜べ」や「〜だべ」といった語尾は、西関東方言に広く見られる特徴です。
また、ラ行の音が「ん」に変化する「撥音化(はつおんか)」と呼ばれる現象(例:「わからない」→「わかんない」)や、母音の「アイ」が「エー」に変化する融合(例:「お前」→「おめえ」)なども、西関東方言に共通する音韻的な特徴です。
このように、神奈川県の方言は、大きな枠組みで見れば関東地方の他の方言と地続きの関係にあります。東京に近く、標準語の影響を強く受けているため「神奈川ならではの方言は見出しにくい」と言われることもありますが、その基盤には西関東方言としてのしっかりとした土台があるのです。
東京(江戸)からの影響と交流
神奈川県、特に横浜や川崎といった東部地域は、江戸(現在の東京)と非常に近い距離にあり、古くから経済的・文化的に深いつながりを持っていました。 そのため、言葉の面でも江戸で話されていた「江戸言葉」の影響を色濃く受けています。
江戸言葉の特徴である、威勢がよくて少し荒っぽい言い回しは、神奈川の方言にも見られます。例えば、「ちげーねえ(違いない)」や「おっかねー(怖い)」といった表現は、江戸っ子の言葉遣いを彷彿とさせます。 また、文末に「〜ね」「〜さ」「〜よ」といった助詞を多用し、それを伸ばして発音する傾向も、東京方言と共通する特徴です。
さらに、明治時代以降、日本の中心となった東京の言葉(山の手言葉)が標準語のベースとなったことで、神奈川県の方言は急速に標準語化が進みました。 現在、私たちが「神奈川の方言」として認識している言葉の多くは、こうした東京との密接な交流の歴史の中で形作られてきたものなのです。
周辺地域(静岡・山梨)からの影響
神奈川県は東海道という大動脈が通っており、西の地域とも古くから交流が盛んでした。特に、県西部にあたる小田原・足柄地域は、箱根の山を越えればすぐに静岡県であり、言葉の面でも強い影響を受けています。
例えば、逆接の「〜けど」を「〜けんど」と言ったり、疑問の「〜かい?」を「〜けー?」と言ったりするのは、静岡弁と共通する特徴です。 また、「しゃっこい(冷たい)」などの語彙も、静岡方面から伝わったと考えられます。 このように、県西部の方言は、神奈川県の中でも異彩を放っており、まるで静岡弁の一部であるかのような様相を呈しています。
一方、北西部の旧津久井郡地域は、山梨県と隣接していることから、山梨県東部で話される「郡内弁」との共通点が見られます。 アクセントや一部の語彙にその影響が認められ、同じ神奈川県内でも他の地域とは異なる言葉の文化圏を形成しています。これらの事実は、神奈川県の方言が、決して均一ではなく、隣接する様々な地域との交流の中で育まれてきた豊かな多様性を持っていることを示しています。
まとめ:神奈川県の方言一覧から見えてくる言葉の多様性

この記事では、「神奈川県の方言一覧」というテーマで、代表的な言葉から地域ごとの特徴、そしてその歴史的背景までを詳しく解説してきました。 「〜じゃん」や「〜だべ」といった有名な表現は、もはや神奈川の代名詞とも言えるでしょう。 しかし、それだけでなく、「うっちゃる」や「かたす」といったユニークな動詞、さらには横浜、湘南、相模、西湘といった地域ごとに異なる言葉の文化があることもお分かりいただけたかと思います。
東京に隣接しているために標準語に近いと思われがちな神奈川の方言ですが、実際には江戸言葉の名残、周辺地域との交流の歴史、そして港町や海辺の文化といった様々な要素が混ざり合って形成された、非常に豊かな言葉の世界が広がっています。 普段何気なく使っている言葉が実は方言だったという発見は、自らの地域の文化を再認識する良い機会になるかもしれません。 本記事が、神奈川県の言葉の奥深さと魅力に触れる一助となれば幸いです。