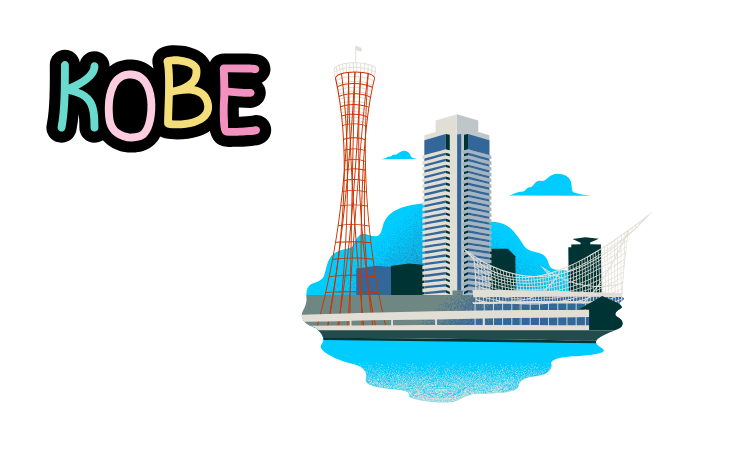神戸といえば、おしゃれな港町、異国情緒あふれる街並みを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。そんな神戸で話されている「神戸弁」には、上品でかわいらしい響きの言葉から、ユニークで面白い表現までたくさんあります。
この記事では、神戸弁一覧として、日常会話で使える基本的なフレーズから、知っているとちょっと自慢できるようなディープな言葉まで、例文を交えながらやさしく解説します。神戸弁の魅力に触れて、神戸をもっと身近に感じてみませんか?神戸旅行や、神戸出身の方とのコミュニケーションがもっと楽しくなること間違いなしです。
神戸弁一覧の前に知っておきたい!神戸弁の基本と特徴

神戸弁をより深く理解するために、まずはその基本的な情報と特徴から見ていきましょう。同じ関西弁でも、大阪弁や京都弁とはまた違った魅力があるのが神戸弁です。
そもそも神戸弁とは?どんな方言?
神戸弁は、兵庫県の南東部、主に神戸市周辺で話されている方言です。 大きなくくりでは近畿方言(いわゆる関西弁)の一つに分類されますが、その中でも独特の発展を遂げてきました。 兵庫県は非常に広く、地域によって話される方言が異なります。例えば、姫路市周辺では「播州弁(ばんしゅうべん)」、淡路島では「淡路弁」などがあり、神戸弁もその中の一つです。
港町として古くから海外との交流が盛んだった神戸の歴史は、言葉にも影響を与えていると言われています。その響きは、一般的によく知られる大阪弁のパワフルなイメージとは異なり、おっとりとしていて上品、そして柔らかい印象を与えるのが特徴です。 そのため、特に女性が話す神戸弁は「かわいい」と感じる人が多く、メディアなどで取り上げられることも少なくありません。 神戸の人々は、自分たちの言葉にプライドを持っており、「大阪弁とちゃうよー!」という意識も強いようです。
神戸弁の主な特徴3つ
神戸弁には、他の関西弁と区別されるいくつかの特徴的な点があります。ここでは、その中でも特に代表的な3つの特徴をご紹介します。
- 柔らかい響きの語尾:「~とう」「~よう」
神戸弁の最も大きな特徴は、語尾の使い方にあります。 例えば、標準語で「何してるの?」と尋ねる場合、神戸弁では「何しとう?」や「何しとん?」となります。 この「~とう」という響きが、神戸弁特有の柔らかさや温かみを生み出しています。 また、動作が今まさに行われている状態(進行形)を表す「~よう」と、動作が完了した状態を表す「~とう」を使い分ける点も、専門的にはなりますが重要な特徴です。 例えば、「蝉が死によう」は「蝉が死にかけている」状態で、「蝉が死んどう」は「蝉はもう死んでいる」状態を表します。 - イントネーションとアクセント
神戸弁のアクセントは、京都や大阪と同じ「京阪式アクセント」に分類されます。 しかし、全体的な話し方はゆっくりとしている傾向があり、これが上品で落ち着いた印象を与えます。 語尾を軽く伸ばすような話し方も特徴の一つで、例えば「~やでぇ」のように、優しい響きを生み出します。 一部の地域では、「七(しち)」を「ひち」と発音したり、「しません」を「しまへん」と言ったりするなど、音韻的な特徴も見られます。 - 独特の敬語表現
かつて神戸弁には、「~てや」という独自の敬語表現がありました。これは「してや」(してください)のように使われるもので、大阪でよく使われる「~はる」という敬語(ハル敬語)とは異なる「テヤ敬語」と呼ばれるものです。 しかし最近では、大阪弁の影響などもあり、この「テヤ敬語」を使う人は減り、「~はる」に近い「~ナハル」という表現や、「~はる」そのものを使う人が増えてきており、敬語にも変化が見られます。
大阪弁や播州弁との違い
同じ兵庫県内や隣接する地域で話される言葉とも、神戸弁には明確な違いがあります。
・大阪弁との違い
多くの人が「関西弁」と聞いてイメージするのが大阪弁かもしれません。 大阪弁は「なんでやねん」に代表されるように、リズミカルで断定的な物言いが特徴です。 一方、神戸弁は「何しとん?」のように、語尾が柔らかく、余韻を残すような響きがあります。 例えば、「来ない」は大阪弁では「けーへん」ですが、神戸弁では「こーへん」と言ったりします。 強調する言葉も、大阪弁では「めっちゃ」が多用されますが、神戸弁では「ばり」や「ごっつい」という言葉が使われることがあります。
・播州弁との違い
兵庫県の西部、姫路市などで話される播州弁は、神戸弁とは対照的に、力強く、少し荒っぽい印象を持たれることがあります。 「日本一汚い方言」と自虐的に言われることもあるほどで、その言葉の響きはかなり異なります。例えば、「~している」を播州弁では「~しとる」や「~しよる」と言い、神戸弁の「~しとう」とは明確な違いがあります。神戸から西へ行くと、この播州弁のエリアに入っていきます。
【初級編】日常で使える神戸弁一覧

まずは、普段の会話ですぐに使える基本的な神戸弁からご紹介します。これらの言葉を覚えるだけで、ぐっと神戸らしさが出ますよ。
「~とう」「~よお」 – 現在進行形・状態を表す言葉
神戸弁を象徴する表現といえば、何と言っても「~とう」と「~よお」でしょう。 これらは標準語の「~している」にあたる言葉ですが、微妙なニュアンスの違いがあります。
「~とう」は、動作が完了してその状態が続いていることを表します。 例えば、「あ、桜が咲いとう!」と言えば、「桜が咲いている状態だ」という意味になります。 友達に「今、何しとう?」と聞けば、「今、何をしているの?」という現在の状況を尋ねる質問になります。 この「~とう」は、イントネーションを変えるだけで疑問文にもなる便利な言葉です。語尾を上げずにフラットに言えば「(私は)知っている(知っとう)」、語尾を上げて「知っとう?」と聞けば「(あなたは)知っている?」という疑問の意味になります。
一方、「~よお」は、動作がまさに今、進行中であることを示します。 例えば、「蝉が鳴きよお」と言えば、「蝉が(今まさに)鳴いている最中だ」という臨場感が伝わります。文例として、「台風来ようから、たぶん電車止まりようで」と言うと、「台風がこちらへ向かってきている最中だから、もうすぐ電車が止まるだろう」という意味合いになります。
最近ではこの二つの区別が曖昧になり、「~とう」で両方の意味をカバーすることも増えてきましたが、この使い分けこそが神戸弁の奥深さの一つです。
「~とん?」「~よん?」 – 疑問を表すかわいい語尾
神戸弁で質問するときに欠かせないのが、「~とん?」という語尾です。 標準語の「~しているの?」にあたり、親しみを込めて何かを尋ねる際に頻繁に使われます。響きがとても柔らかく、かわいらしい印象を与えるのが特徴です。
例えば、友達が何かを食べていたら、「何食べとん?」と気軽に聞くことができます。 待ち合わせに遅れてきた友人には、「どこにおったん?」と尋ねることもできます。この「~とん?」と聞かれたら、基本的に「はい」か「いいえ」で答えられるような質問だと考えると分かりやすいでしょう。
大阪弁の「何してんねん?」という少しツッコミのような響きとは違い、神戸弁の「何しとん?」は、純粋な疑問や相手への関心を示す、穏やかで優しい問いかけになります。 この語尾があるからこそ、神戸弁は「上品でかわいい」というイメージを持たれるのかもしれません。 日常会話でこの「~とん?」を自然に使えるようになれば、あなたも神戸弁マスターに一歩近づけるはずです。
「~しい」「~しいや」 – 軽い命令・お願いの表現
誰かに何かをお願いしたり、少し促したりするときに使うのが「~しい」や「~しいや」という表現です。これは、標準語の「~しなよ」「~してみて」といったニュアンスに近い、柔らかい命令や依頼の言葉です。
例えば、友達に「早くこっちに来てほしい」と伝えるとき、「はよ来しい(きーや)」と言います。また、何かを試食させたいときには「これ、食べてみしい」と勧めたりします。強い強制力はなく、あくまで相手に優しく行動を促すような響きがあります。
「~しい」だけでも使えますが、「~しいや」と「や」を付けると、さらに親しみやすい、少し念を押すような感じになります。「もうええから、はよ寝しいや」(もういいから、早く寝なさいよ)といった具合です。
この表現は、家族や親しい友人同士の会話でよく登場します。相手への配慮が感じられる、温かい神戸弁の一つと言えるでしょう。強すぎず、それでいて自分の意思をきちんと伝えられる便利な言葉なので、ぜひ覚えて使ってみてください。
【中級編】感情が伝わる神戸弁一覧

基本的な表現に慣れてきたら、次は自分の気持ちをより豊かに表現するための神戸弁に挑戦してみましょう。感情がこもると、会話はもっと楽しくなります。
「めっちゃ」「ばり」 – 強調を表す言葉
何かを強調したいとき、標準語では「とても」や「すごく」と言いますが、神戸弁にはもっと感情のこもった表現があります。それが「ばり」や「ごっつい」です。
「ばり」は「すごく」「とても」という意味で、若者を中心に広く使われています。 例えば、「このケーキ、ばりおいしい!」と言えば、「このケーキ、すごくおいしい!」という感動がストレートに伝わります。 大阪では「めっちゃ」が主流ですが、神戸ではこの「ばり」がよく使われるのが特徴です。
もう一つの強調表現「ごっつい」は、「ものすごく」「とてつもなく」といった、さらに強い意味合いで使われます。「昨日見た映画、ごっついおもろかったわ」のように言うと、その面白さが並大抵ではなかったことが伝わります。
これらの言葉は、ポジティブなことにもネガティブなことにも使えます。「ばりしんどい」(すごく疲れた)や、「ごっつい雨やな」(ものすごい雨だな)のように、さまざまな場面で感情の度合いを表現するのに役立ちます。会話の中にこれらの強調表現を織り交ぜることで、より生き生きとしたコミュニケーションが生まれるでしょう。
「しんどい」「えらい」 – 疲れた時、大変な時の表現
疲労や困難な状況を表すとき、神戸弁では「しんどい」と「えらい」という二つの言葉がよく使われます。これらは似たような場面で使われますが、少しニュアンスが異なります。
「しんどい」は、主に身体的な疲労や、精神的な辛さを表す言葉です。標準語の「疲れた」「きつい」とほぼ同じ意味で使うことができます。「一日中歩き回ったから、もうしんどいわー」と言えば、体力を消耗してくたくたな様子が伝わります。
一方、「えらい」は神戸弁(および関西の広い地域)では、標準語の「偉い」とは全く違う意味で使われます。 「大変だ」「骨が折れる」といった、困難な状況や予期せぬ苦労を表す言葉です。 例えば、「昨日の引越し、ほんまにえらかったわ」と言えば、引越し作業が非常に大変だったことを意味します。 また、人混みを見て「うわー、人がぎょうさんでえらいこっちゃ」と言ったり、大雨を指して「昨日の雨はえらかったな」と言ったりもします。
標準語話者が「残業、えらいなあ」と言われると、「残業するなんて偉いね」と褒められているように勘違いしてしまうかもしれませんが、神戸弁では「残業、大変だね」とねぎらっている意味になります。 この「えらい」を使いこなせると、ぐっと地元民らしく聞こえるでしょう。
「かなん」 – 困った時、我慢できない時の言葉
「かなん」は、困った状況や我慢の限界を感じたときに使われる、非常に便利な神戸弁です。「困る」「嫌だ」「たまらない」「やってられない」といった、さまざまなネガティブな感情をこの一言で表現できます。
例えば、騒がしい隣人に対して「毎晩うるさくて、ほんまかなんわ」と言えば、「毎晩うるさくて本当に困る(我慢できない)」という強い不満が伝わります。また、子どもが言うことを聞か
ずに困り果てた親が、「もう、この子は言うこと聞かへんからかなんわ」と嘆くようにも使います。
単に「困る」というよりも、どうしようもない、お手上げだ、というニュアンスが含まれているのが特徴です。暑くてたまらない日には「こう暑いとかなんなあ」と言ったり、複雑で面倒な手続きにうんざりして「こんな手続き、かなんわ」とぼやいたりします。
この「かなん」という言葉は、直接的な強い言葉を使わずに、自分の困惑や不満を相手に伝えることができる、非常に便利な表現です。愚痴や不満を言う場面でよく登場する、人間味あふれる神戸弁の一つと言えるでしょう。
【上級編】知ってると通!ディープな神戸弁一覧
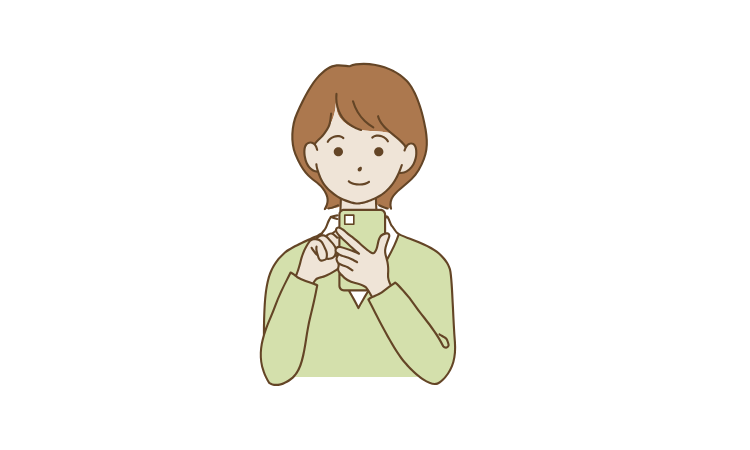
ここからは、知っていると「お、この人やるな」と思われるような、少しディープな神戸弁をご紹介します。使いこなせれば、あなたも神戸弁の上級者です。
「ダボ」 – 少し強いニュアンスの言葉
「ダボ」は、標準語の「ばか」や「あほ」にあたる言葉ですが、少し強めのニュアンスを持つ神戸弁です。 親しい間柄での軽いからかいから、本気で相手を非難する場面まで、文脈によって意味合いが変わってくる言葉なので、使い方には少し注意が必要です。
例えば、友達がドジを踏んだときに、「何やってんねん、このダボ!」と笑いながらツッコむような使い方ができます。 この場合は、親しみを込めた愛情表現の一種と捉えることができるでしょう。
しかし、真剣な口調で「このダボが!」と言うと、相手を強く罵る言葉になります。播州地方で使われることも多く、神戸弁の中でもやや荒っぽい響きを持つ言葉として知られています。そのため、むやみやたらに使うのは避けたほうが賢明です。
この「ダボ」という言葉を知っていると、神戸やその周辺地域を舞台にした映画やドラマなどで登場人物が使った際に、その感情の機微をより深く理解できるかもしれません。地元の人々の会話に自然に溶け込んでいる言葉の一つですが、使う場面をよく見極める必要がある、上級者向けの神戸弁です。
「ぎょうさん」 – 「たくさん」を意味する言葉
「ぎょうさん」は、「たくさん」「いっぱい」という意味で使われる、古風な響きを持つ関西弁で、神戸でもよく耳にします。標準語の「沢山(たくさん)」の音が変化したものと言われており、物の数や人の多さを表すときに使われます。
例えば、お店にたくさんの商品が並んでいるのを見て、「うわー、ぎょうさんあるなあ」と感心したり、お祭りの人出の多さに「人がぎょうさんおるわ」と驚いたりする場面で使います。また、お土産をたくさんもらったときに、「こんなにぎょうさん、ありがとう」とお礼を言うこともできます。
「めっちゃ」や「ばり」が程度の高さを強調する副詞なのに対し、「ぎょうさん」は量の多さを具体的に示す言葉です。最近の若い世代では使う人が減ってきているかもしれませんが、年配の方との会話ではごく自然に出てくる言葉です。
どこか温かみがあり、懐かしい響きを持つ「ぎょうさん」。この言葉をさらりと使えると、神戸の文化や歴史にも通じているような、粋な印象を与えられるかもしれません。日常のふとした場面で、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
「さら」 – 「新しいもの」を指す言葉
神戸弁で「さら」と聞いたら、それはお皿のことではなく、「新品」を意味します。「まっさら」という言葉があるように、「新しいもの」「未使用のもの」を指すときに使う、特徴的な言葉です。
例えば、新しい服を買ってきたときに「これ、まださらの服やねん」と言ったり、新学期に新しい教科書を見て「うわー、教科書がさらや!」と喜んだりします。中古品ではなく、まだ誰も使っていないきれいな状態を強調するニュアンスがあります。
この「さら」という言葉は、物に対してだけでなく、さまざまな場面で応用されます。例えば、新築の家を指して「あそこはさらの家やで」と言ったり、誰も手をつけていない料理を見て「まださらやから、先に食べてええよ」と勧めたりします。
非常に短い言葉ですが、これ一つで「新品である」という情報が伝わる、効率的で便利な神戸弁です。他の地域の人には少し分かりにくいかもしれませんが、この言葉を知っていると、神戸の人の会話がよりスムーズに理解できるようになるでしょう。物を大切にする神戸の気質が表れているような、興味深い言葉の一つです。
こんな場面で使ってみたい!シーン別神戸弁一覧

覚えた神戸弁を、実際の生活の中でどのように使えばいいのでしょうか。ここでは、具体的なシチュエーションに合わせた使い方を例文とともにご紹介します。
あいさつで使う神戸弁
毎日のあいさつに神戸弁を取り入れると、ぐっと親近感が湧きます。かしこまった場では標準語が基本ですが、親しい間柄ではぜひ使ってみましょう。
朝のあいさつは、標準語と同じ「おはよう」も使いますが、より親しみを込めて「おはようさん」と言うことがあります。 これだけで、一日の始まりがなんだか温かいものに感じられます。
日中の「こんにちは」は、少しくだけた感じで「こんちは」と言うこともあります。
そして、別れ際にこそ神戸弁の魅力が発揮されます。標準語の「それじゃあ、またね」は、「ほな、また」や「ほなね」となります。 この「ほな」という響きが、関西らしさを感じさせます。「ほな、さいなら」と言うこともあります。短いながらも、相手とのつながりを感じさせる、温かい別れのあいさつです。
夜、寝る前には「ほな、おやすみ」や、シンプルに「おやすみー」と語尾を伸ばすことで、優しい雰囲気が出ます。日常の何気ないあいさつから、神戸弁を取り入れてみてはいかがでしょうか。
お店で買い物する時に使う神戸弁
神戸の街でお買い物をするとき、少しだけ神戸弁を使ってみると、お店の人との距離が縮まるかもしれません。丁寧さを保ちつつ、自然に使えるフレーズを覚えておくと便利です。
お店に入って商品を見ているとき、店員さんに「これ、見てもいいですか?」と尋ねる代わりに、「これ、見せてもろてええですか?」と言ってみましょう。「もらう」の謙譲語「いただく」と同じように、「~してもらう」を「~してもろう」という形で使います。
商品の値段を尋ねるときは、「これ、なんぼですか?」が定番の関西弁です。これは神戸でももちろん通じます。
また、ある商品がまだ在庫にあるか、あるいは機能として大丈夫かを確認したいときには、「これ、いけますか?」という便利な言葉があります。 例えば、賞味期限が近い食品について「これ、明日までいけます?」と聞けば、「明日まで食べられますか(大丈夫ですか)?」という意味になります。
試着をしたいときは、「これ、着てみてもええですか?」と尋ねます。そして、何かを捨ててもらうときには、「これ、ほかしてもらえますか?」と言います。 「ほかす」は「捨てる」という意味の関西地方で広く使われる言葉です。 これらの言葉を自然に使いこなして、神戸でのショッピングを楽しんでください。
友達との会話で盛り上がる神戸弁
気心の知れた友達との会話では、もっとくだけた神戸弁を使って会話を盛り上げましょう。感情豊かな表現を使えば、お互いの気持ちがより伝わりやすくなります。
友達の話に驚いたときは、「ほんまに!?」「うそやん!」といった相槌が活躍します。「ほんま」は「本当」という意味で、関西弁の基本とも言える言葉です。
相手に同意したり、共感したりするときは、「せやねん」「せやろ?」と言います。「せやねん」は「そうなんだよ」と自分の意見を述べるときに、「せやろ?」は「そうでしょ?」と相手に同意を求めるときに使います。
話の途中で相手の注意を引きたいときは、「ちょぉ、ちょぉ」と呼びかけます。 標準語の「ちょっと、ちょっと」にあたり、かわいらしい響きがあります。
そして、会話の中で何か面白いことがあったら、「ばりおもろいやん!」とリアクションしてみましょう。 「ばり」は「すごく」、「おもろい」は「面白い」という意味です。 逆に、何かめちゃくちゃな状況になったときは、「もう、わややわ~」と言います。 「わや」は「めちゃくちゃ」「台無し」といった意味で、困惑や呆れた気持ちを表すのにぴったりな言葉です。 これらの言葉を使いこなして、友達との会話をもっと楽しんでください。
神戸弁一覧で知る方言の魅力とまとめ

この記事では、神戸弁一覧として、その特徴から日常で使える具体的なフレーズまで、さまざまな角度からご紹介してきました。
神戸弁は、同じ関西弁の中でも、大阪弁の持つ力強さや京都弁の雅やかさとは一味違う、上品で柔らかい響きが魅力です。 語尾に使われる「~とう」や「~とん」は、会話に温かみと親しみやすさを与えてくれます。
また、「ばり」「えらい」「かなん」といった感情を豊かに表現する言葉や、「ダボ」「さら」のような少しディープな言葉まで、知れば知るほどその奥深さに気づかされます。
方言は、単なる言葉の違いだけではなく、その土地の歴史や文化、そして人々の気質を映し出す鏡のようなものです。神戸弁の穏やかで洗練された響きは、港町として多様な文化を受け入れてきた神戸の街の雰囲気そのものと言えるかもしれません。
この一覧で紹介した言葉をきっかけに、ぜひ神戸弁に親しんでみてください。神戸を訪れた際に使ってみたり、神戸出身の方との会話で聞き取ってみたりすることで、あなたの神戸への理解はさらに深まることでしょう。言葉を知ることは、その地域をもっと好きになる第一歩です。