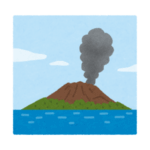鹿児島への旅行や、鹿児島出身の方との会話で「これってどういう意味?」と、言葉が聞き取れずに戸惑った経験はありませんか。鹿児島の方言、通称「鹿児島弁」は、正式には「薩隅方言(さつぐうほうげん)」と呼ばれ、独特のイントネーションや単語が多く、他の地域の人にとっては少し難しく感じられるかもしれません。
しかし、一度その意味を知ると、とても温かみがあり、親しみやすい言葉が多いのが魅力です。この記事では、鹿児島でよく使う方言を、日常会話ですぐに使えるフレーズやユニークな表現、さらにはその歴史的背景まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたもきっと鹿児島弁の奥深い魅力に気づき、鹿児島という土地や人々をもっと好きになるはずです。さあ、一緒に鹿児島弁の世界を探っていきましょう。
鹿児島の方言でよく使う基本のあいさつ

鹿児島の人々の温かさは、日々のあいさつにも表れています。観光で訪れた際に使ってみると、地元の人々との距離がぐっと縮まるかもしれません。ここでは、一日の様々な場面で使える基本的なあいさつをご紹介します。
おはようからおやすみまで!一日のあいさつ
朝のあいさつ「おはようございます」は、鹿児島弁で「あだっごあした」と言います。 これは「まだでございました」が変化した言葉だとされています。 少し変わった表現ですが、丁寧な気持ちが伝わります。
昼間の「こんにちは」は、標準語と同じように使われることが多いですが、親しい間柄では「よう」と軽く声をかけることもあります。
そして、鹿児島を代表するあいさつと言っても過言ではないのが、夕方の「おやっとさあ」です。 これは「お疲れ様です」という意味で、仕事や学校の帰りにすれ違う人同士で交わされる、労いの気持ちがこもった温かい言葉です。
夜の「おやすみなさい」も標準語と大きくは変わりませんが、親しい間柄では「よかばんな」と言うこともあります。 「良い晩を」という意味で、相手を思いやる気持ちが感じられる素敵な表現です。 鹿児島を訪れた際には、ぜひこれらのあいさつを使ってみてください。
「ありがとう」を伝える感謝の鹿児島弁
感謝の気持ちを伝える言葉にも、鹿児島ならではの表現があります。最も丁寧な「ありがとうございました」は、「あいがとさげもした」と言います。 これは「ありがとう申し上げ申した」という二重敬語が変化したもので、非常に丁寧な感謝の表現です。 少し前の世代の方がよく使う言葉ですが、覚えておくと敬意を示したい場面で役立つでしょう。
日常的によく使う「ありがとうございます」は、「あいがとさげもす」となります。 また、友人同士など親しい間柄で「ありがとう」と伝える際には、シンプルに「あいがと」と言うこともあります。
これらの言葉は、単に感謝を伝えるだけでなく、鹿児島の人々の誠実さや温かい人柄を表す表現でもあります。贈り物をもらった時や、親切にしてもらった時などに、心を込めて「あいがとさげもした」と伝えてみれば、相手もきっと喜んでくれるはずです。少し照れくさいかもしれませんが、旅の思い出に、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
「はじめまして」と自己紹介で使える方言
鹿児島で初めて会う人に挨拶する際、標準語の「はじめまして」ももちろん通じますが、鹿児島弁らしい表現を使うと、より親しみが湧き、会話が弾むきっかけになるかもしれません。
自己紹介の場面では、自分のことを指す「私」や「俺」を「おい」と言います。 例えば、「おいどんは西郷隆盛です」という有名なセリフのように、「おい」は男女問わず使うことができる一人称です。また、相手を指す「あなた」は「おまんさあ」や「おはん」と言います。
歓迎の言葉としては、「いらっしゃいませ」を意味する「おじゃったもんせ」が有名です。 これは鹿児島の空港やフェリー乗り場など、観光客を迎える場所でよく見聞きする言葉で、おもてなしの心がこもった表現です。
例えば、初対面の人に「おじゃったもんせ。おいが〇〇です。よろしゅうたのんます(よろしくお願いします)」といった形で自己紹介をすれば、一気に鹿児島の雰囲気に溶け込めるでしょう。少し勇気がいるかもしれませんが、温かく迎えてくれる鹿児島の人々との交流を楽しむ第一歩として、ぜひ挑戦してみてください。
日常会話で頻出!よく使う鹿児島の方言フレーズ

鹿児島弁には、感情を豊かに表現したり、会話をスムーズに進めたりするための便利なフレーズがたくさんあります。ここでは、日常の様々なシーンで使える、覚えておくと便利な鹿児島弁を紹介します。
感情を豊かに表現する鹿児島弁
鹿児島弁には、喜怒哀楽をストレートに、そして味わい深く表現する言葉が豊富です。
まず、すごい、とても、といった強調を表す言葉として「わっぜ」や「わっぜか」があります。 「わっぜか美人(すごく美人)」や「わっぜうんまか(とても美味しい)」のように使います。驚いた時には「いした!」や「たまがった!」という感嘆詞が口をついて出ます。 「たまがる」は「びっくりする」という意味の動詞です。
嬉しい、楽しいといったポジティブな感情は、「おもして」という言葉で表現されます。 これは「面白い」が変化した言葉です。 一方で、「かわいい」は「むぜか」や「もじょか」と言い、愛おしいというニュアンスが強く感じられます。
悲しい、かわいそうといった気持ちは「ぐらし」という言葉で表します。 また、恥ずかしい時には「げんね」と言います。 これらの言葉は、標準語の単語よりも感情が乗っているように聞こえ、鹿児島の人々の人間味あふれるコミュニケーションを支えています。
相づちで使える便利な鹿児島の方言
会話の中で相手の話にうなずいたり、同意したりする時に使う「相づち」にも、鹿児島弁ならではの表現があります。これらを使いこなせると、より自然な会話の流れを作ることができます。
最もよく使われる相づちの一つが、「そいじゃが」です。 これは「そうだね」「その通りだね」といった意味で、相手の発言に同意する際に使います。友人との会話では、「じゃがじゃが」と繰り返して使うこともあります。
また、「そうです」をより丁寧に、かつ柔らかく表現するのが「ですです」という相づちです。 標準語話者からすると少し奇妙に聞こえるかもしれませんが、鹿児島ではごく自然に使われる表現です。
驚きや意外な気持ちを表す相づちとしては、「んだもしたん」という言葉があります。 「あらまあ、知らなかった!」といったニュアンスで、特に女性が使うことが多い表現です。 予期せぬニュースを聞いた時などに使うと、その驚きがよく伝わります。
これらの相づちを会話の中に挟むことで、「あなたの話をしっかり聞いていますよ」というサインになり、コミュニケーションがより円滑になります。鹿児島出身の人との会話の際には、ぜひ意識して使ってみてください。
食べ物や飲み物に関するよく使う方言
食文化が豊かな鹿児島では、食べ物に関する独特な方言も日常的に使われています。
例えば、鹿児島名物のさつま揚げは、地元では「つけあげ」と呼ばれています。 観光でお店を訪れた際にメニューに「つけあげ」と書かれていても、戸惑わないようにしましょう。また、さつまいもを使った天ぷらは「がね」と呼ばれます。揚げた姿が蟹(かに)に似ていることから、その名がついたと言われています。
飲み物、特に焼酎に関する言葉も欠かせません。焼酎を飲むことを「だいやめ」と言います。「だれ(疲れ)をやめる(とめる)」が語源で、一日の疲れを癒す晩酌を意味する、鹿児島らしい温かみのある言葉です。
味の感想を言う時にも方言が活躍します。「おいしい」は「うんめなあ」や「うまか」と表現します。 そして、「たくさん」や「いっぱい」を意味する「ずんばい」という言葉もよく使われます。 「ずんばい食べやんせ(たくさん食べてくださいね)」と勧められたら、それは歓迎されている証拠です。これらの言葉を知っていると、鹿児島の食をより深く楽しむことができるでしょう。
鹿児島の方言が持つユニークな特徴

鹿児島弁が他の地域の方言と比べて難解だと言われるのには、いくつかの理由があります。その独特のイントネーションや文法、そしてユニークな単語が、鹿児島弁の個性を形作っています。
独特のイントネーションとアクセント
鹿児島弁の大きな特徴の一つが、その独特なイントネーションです。標準語では、質問文の最後は語尾を上げて発音するのが一般的ですが、鹿児島弁では逆に語尾を下げて質問することがあります。 例えば、「雨が降る?」と聞く場合、標準語では「ふる↑」と上がりますが、鹿児島弁では「ふる↓」と下がることがあります。 このため、初めて聞く人は質問されていることに気づかないかもしれません。
また、アクセントの置き方も標準語とは異なります。鹿児島弁のアクセントは、単語の後ろから2番目の音節を高く発音するA型と、最後の音節を高く発音するB型の2種類が基本とされています。 例えば、「雨」と「飴」は、標準語ではアクセントの位置が異なりますが、鹿児島弁では逆になることがあります。 このようなアクセントの違いが、鹿児島弁特有のメロディーを生み出しています。語尾が上がるように聞こえることもあり、会話が楽しそうに聞こえるとも言われています。
短縮形や変化形が多い鹿児島弁の文法
鹿児島弁は、言葉が短縮されたり、音が変化したりすることが非常に多いのも特徴です。これが、聞き取りを難しくしている一因でもあります。
例えば、母音が融合する現象が見られます。「ai」という母音の並びは「e」に変化することが多く、「大根(daikon)」は「でこん」、「灰(hai)」は「へ」となります。 同様に、「oi」は「e」に、「ui」は「i」に変化する傾向があります。
また、言葉の終わりにある「に」や「の」といった音が「ん」に変化することもよくあります。「犬(inu)」は「いん」、「西郷殿(saigodon)」は「せごどん」といった具合です。
さらに、促音(つまる音)が多用されるのも大きな特徴です。 「泣こかい、とぼかい、泣こよっか、ひっとべ(泣こうか、飛ぼうか、泣くくらいなら、飛んでしまえ)」という有名なフレーズにも見られるように、動詞などに「ひっ」や「ちん」といった接頭語がついて意味を強める際にも促音が使われます。 これらの音の変化のルールを少し知っておくだけでも、鹿児島弁の理解がぐっと深まるでしょう。
他の地域にはない面白い単語や表現
鹿児島弁には、標準語にはない、あるいは意味が全く異なるユニークな単語がたくさん存在します。その中には、聞いただけでは意味を想像するのが難しいものも少なくありません。
例えば、人の「頭」のことを「びんた」と言います。 「びんたを張る」というと、標準語では平手打ちをすることですが、鹿児島では頭を張るという意味になり、全く違う状況を指します。また、桜島の噴火によって降る「灰」のことは「へ」と言います。 面白いことに、「蠅(はえ)」や「おなら」も同じく「へ」と言うため、文脈で判断する必要があります。
動詞にも面白いものがあります。「しまう」や「片付ける」という意味で「なおす」という言葉を使います。 関西地方でも使われる表現ですが、知らないと「修理する」という意味に誤解してしまうかもしれません。
さらに、「け」という一文字だけで「貝」「買い」「来い」という複数の意味を持つこともあります。 そのため、「けけけけ」という一見暗号のような言葉が、「貝を買いに来い」という意味の文章として成立することもあります。 このように、知れば知るほど面白く、奥深い単語が多いのも鹿児島弁の魅力の一つです。
知っていると面白い!よく使う鹿児島の方言【単語編】

これまでに紹介したフレーズ以外にも、鹿児島弁には知っていると会話の理解が深まる特徴的な単語がたくさんあります。ここでは、人や物、状態などを表す基本的な単語をいくつかご紹介します。
人や物を指すときによく使う鹿児島弁
鹿児島弁では、人や物を指す際に独特の単語が使われます。まず、自分のことを指す一人称は「おい」ですが、相手を指す二人称は「おまんさあ」や「わい」など複数あります。 「わい」は親しい相手や時には対立する相手にも使われる言葉です。
若い男性を「にせ」、若い女性を「おごじょ」と呼びます。「よかにせ」と言えば「いい男」、「よかおごじょ」は「いい女・美人」を意味します。 また、お年寄りのことは「おんじょ」と呼びます。
物に関する言葉もユニークです。例えば、ゴキブリのことは「あまめ」と呼びます。 そのため、ゴキブリ捕獲器は「あまめホイホイ」となります。 また、魚のことは「いお」と言います。 鹿児島市にある水族館「いおワールドかごしま」の名前も、この方言に由来しています。 このように、日常的に使われる単語にも鹿児島ならではの言葉が根付いているのです。
状態や様子を表す形容詞・副詞
物事の状態や人の様子を表す形容詞や副詞にも、鹿児島弁ならではの表現が豊富にあります。
「とても」「すごく」といった程度を強調する際には、「わっぜ」の他に「てげ」という言葉もよく使われます。 ただし、「てげてげ」となると、「適当に」「いい加減に」という意味に変わるので注意が必要です。 この「てげてげ」という言葉には、悪い意味だけでなく「ほどほどに頑張ればいいよ」というニュアンスが含まれることもあり、鹿児島の県民性を表す言葉とも言われています。
また、「疲れた」は「だれた」や「だれもした」と言います。 「うるさい」は「やぜろしか」や「せがらし」と表現し、特に「やぜろしか」は強く一喝するような迫力のある言葉です。 「恥ずかしい」を意味する「げんね」や、かわいそうだという気持ちを表す「ぐらし」も、日常会話で頻繁に耳にする言葉です。
その他にも、髪がボサボサな様子を「やんかぶっちょい」と言ったり、くねくねしている様子を「よんごひんご」と表現したり、擬態語や擬音語が豊かなのも鹿児島弁の面白いところです。これらの言葉を使いこなせれば、表現の幅がぐっと広がります。
驚きや感動を表す感嘆詞
感情が動いた瞬間に、思わず口から飛び出す感嘆詞。鹿児島弁には、その時々の気持ちを的確に表す、印象的な感嘆詞がいくつもあります。
最も代表的なのが、驚いた時に使う「んだもしたん」です。 「あらまあ、びっくりした!」というニュアンスで、予期せぬ出来事に遭遇した際によく使われます。 同じく驚きを表す言葉に「いした!」や「たまがった!」もあります。 「たまがる」は「魂が消えるほど驚く」が語源とも言われ、その驚きの大きさが伝わってきます。
言葉にできないほどの感動や、どうしようもないという気持ちを表す際には、「なんつぁならん」という表現が使われます。 例えば、素晴らしい景色を見た時や、スポーツで劇的な勝利を収めた時などに「なんつぁならん!」と口にすることで、その万感の思いが表現されます。
これらの感嘆詞は、短い言葉の中に豊かな感情が凝縮されており、鹿児島の人々のストレートな感情表現を象徴しています。会話の中でこれらの言葉が聞こえてきたら、話し手が何かに心を動かされているサインだと捉えると良いでしょう。
鹿児島弁の歴史と学ぶ上での注意点

鹿児島弁をより深く理解するためには、その成り立ちや歴史的背景、そして現代で使う上での注意点を知っておくことが役立ちます。独特な方言が生まれた背景には、鹿児島の地理的・歴史的な要因が大きく関わっています。
薩摩藩の歴史と方言の成り立ち
鹿児島弁、すなわち薩隅方言が非常に難解である理由の一つとして、江戸時代の薩摩藩の政策が関係しているという説があります。 薩摩藩が幕府からのスパイ(隠密)の侵入を防ぎ、情報を守るために、意図的に方言を複雑にした、あるいは他国の者が聞き分けられるように作り替えたというものです。 この説は言語学的な根拠に乏しいとされていますが、第二次世界大戦中には、実際に早口の鹿児島弁が暗号として利用されたというエピソードも残っています。
言語学的には、鹿児島が都のあった京都から地理的に遠く、中央の言葉の影響を受けにくかったため、古い時代の日本語の形が多く残っていると考えられています。 例えば、「叫ぶ」を意味する「おらぶ」という言葉は、奈良時代の文献にも見られる古い言葉です。
また、地理的な要因だけでなく、隼人と呼ばれた古代の人々の言語的特徴が影響している可能性も指摘されています。 このように、鹿児島弁は長い年月をかけて、鹿児島の独特な歴史と風土の中で育まれてきた文化遺産なのです。
標準語と意味が異なる鹿児島弁
鹿児島弁を学ぶ上で特に注意したいのが、標準語と同じ言葉でありながら、意味やニュアンスが全く異なる単語の存在です。これを知らないと、会話の中で思わぬ誤解を生んでしまう可能性があります。
代表的な例が、「なおす」という動詞です。標準語では「修理する」という意味ですが、鹿児島弁では「片付ける」「しまう」という意味で使われます。 例えば、「その本、なおしといて」と言われたら、本を本棚に戻すことを指します。
また、「からい」という形容詞も注意が必要です。標準語では唐辛子のような辛さを指しますが、鹿児島弁では「しょっぱい」という意味でも使われます。料理の味が塩辛い時に「からい」と言うことがあるので、文脈で判断する必要があります。
さらに、「あたい」という言葉は、標準語では女性が使う一人称ですが、鹿児島弁では「値段」を意味します。お店で「このあたいは?」と聞かれたら、それは値段を尋ねられているということです。このように、知っているつもりの言葉が全く違う意味で使われる面白さと難しさが、鹿児島弁にはあります。
若者言葉と伝統的な鹿児島弁の違い
どの地域でも見られるように、鹿児島でも世代によって使う言葉に違いがあります。特に、若い世代はテレビやインターネットの影響で標準語に近い言葉を話すことが多く、伝統的な鹿児島弁はあまり使わなくなってきています。
例えば、「ありがとうございました」を意味する「あいがとさげもした」は、年配の方は使いますが、若い世代ではほとんど使われず、「ありがとうございました」と標準語で言うか、少しなまって「あいがとございました」と言う程度です。 また、「〜でございます」を意味する「〜ごわす」という語尾も、西郷隆盛のイメージで有名ですが、現代の日常会話で使われることはほぼありません。
一方で、イントネーションや基本的な単語(例:「わっぜ」「てげてげ」など)は、若い世代にも受け継がれています。しかし、祖父母世代が話すような難解な鹿児島弁は、若い世代にとっては理解できないことも少なくありません。
もし鹿児島で地元の人と交流する機会があれば、相手の年代に合わせて言葉を選ぶと、よりスムーズなコミュニケーションが取れるでしょう。伝統的な方言に触れたい場合は、年配の方と話してみるのが一番です。
まとめ:鹿児島の方言をよく使う場面と今後の学び方

この記事では、日常会話でよく使う鹿児島の方言を中心に、その基本的な挨拶から感情表現、ユニークな単語、そして歴史的背景や学ぶ上での注意点まで幅広く解説してきました。
鹿児島弁は、一見すると難解に聞こえるかもしれませんが、「おやっとさあ(お疲れ様)」や「あいがとさげもした(ありがとうございました)」といった言葉には、相手を思いやる温かい心が込められています。また、「わっぜ(すごい)」や「むぜか(かわいい)」などの感情表現は、会話をより豊かで人間味あふれるものにしてくれます。
その成り立ちには、薩摩藩の歴史や地理的な要因が深く関わっており、古い日本語の響きを残す貴重な文化遺産とも言えます。標準語と異なる意味を持つ単語や、世代による言葉遣いの違いなど、知れば知るほど奥深い魅力に気づかされるでしょう。
これから鹿児島を訪れる方や、鹿児島出身の方と交流する機会がある方は、この記事で紹介した言葉をいくつか覚えて使ってみてください。きっと、地元の人々との距離が縮まり、より深く鹿児島の文化に触れることができるはずです。方言は、その土地の人々の心をつなぐ大切な架け橋なのです。