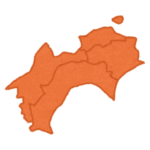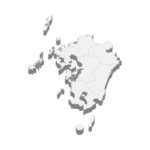「~しやはる」「~してはる」のような京ことばに似た、やわらかな響きが魅力的な滋賀県の方言。 かつて「近江の国」と呼ばれていたことから、「近江弁(おうみべん)」または「江州弁(ごうしゅうべん)」とも呼ばれています。 一言で滋賀県方言といっても、実は地域によって言葉に違いがあり、知れば知るほど奥深い世界が広がっています。
この記事では、代表的な滋賀県の方言を一覧で紹介しながら、その意味や具体的な使い方、地域ごとの特徴などをやさしく解説します。日常会話で使えるフレーズから、思わず「かわいい!」と言ってしまうようなユニークな表現まで、滋賀の言葉の魅力をたっぷりとご紹介。この記事を読めば、あなたも滋賀県の方言を使ってみたくなるはずです。
滋賀県方言一覧|まずは基本の挨拶から!

滋賀県の方言に親しむ第一歩として、まずは毎日の生活で欠かせない基本的な挨拶表現から見ていきましょう。標準語とは少し違う、滋賀ならではの温かみのある言い方を知ることで、地元の人々とのコミュニケーションがより一層楽しくなるかもしれません。
「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」- 時間帯別の挨拶
滋賀県では、全国的に使われる「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」という挨拶が基本ですが、年配の方を中心に、より丁寧でやわらかな表現が使われることがあります。
例えば、日中の挨拶である「こんにちは」は、特に改まった場面や目上の方に対して「お日様高うなりまして」といった古風な言い方をすることがあったようです。また、夕方から夜にかけての挨拶「こんばんは」は、「おしまいやす」と言うことがあります。 これは京ことばとも共通する表現で、一日の終わりをねぎらうような響きが特徴です。
これらの表現は、現代の若い世代ではあまり使われなくなってきているかもしれませんが、滋賀の言葉文化の豊かさを感じさせてくれます。もし耳にする機会があれば、その背景にある歴史や人々の暮らしに思いを馳せてみるのも面白いでしょう。地域によっては、さらに独自の挨拶表現が残っている可能性もあり、言葉の多様性を楽しむことができます。
「ありがとう」- 感謝を伝える言葉
感謝の気持ちを伝える「ありがとう」という言葉は、滋賀県では「おおきに」という表現が広く使われています。 これは関西地方の他の地域でもよく聞かれる言葉ですが、滋賀の「おおきに」は、京ことばのように少し穏やかで、ゆったりとしたイントネーションで発音されることが多いのが特徴です。
「おおきに」は、単に「ありがとう」という意味だけでなく、「どうもすみません」という恐縮する気持ちや、「お世話になります」といったニュアンスを含むこともあります。例えば、お店で買い物をした際に店員さんから「おおきに」と言われたり、何か手伝ってもらった時に「おおきに、助かったわ」と返したりします。
また、大変なことをしてもらった相手には、「おせんどさん」や「ごくろうさん」といったねぎらいの言葉をかけることもあります。 「ほんま、おせんどさんどしたなー、おおきに」のように重ねて使うと、より深い感謝といたわりの気持ちが伝わります。 このように、場面や相手との関係性に応じて感謝の表現を使い分けるのが、滋賀の言葉の奥深さの一つと言えるでしょう。
「ごめんなさい」- 謝罪の表現
軽い謝罪や、人に声をかける際の「すみません」という言葉は、滋賀県では「すんません」という少しくだけた言い方がよく使われます。 これは関西一円で共通して聞かれる表現ですが、滋賀では比較的穏やかな口調で使われることが多いです。
また、本当に申し訳ないという気持ちを伝えたい時には、「かなん」という言葉が使われることがあります。 「かなん」は「敵わない」「我慢できない」といった意味が元になっており、「ほんま、かなんわぁ」と言うと、「本当に申し訳ない、面目ない」という深い謝罪の気持ちを表します。感謝の気持ちを表す「うい」という言葉も、「申し訳ない」というニュアンスで使われることがあります。
さらに、相手に許しを請うような場面では、「こらえて」という言葉も聞かれます。これは「勘弁して」「許して」という意味合いで、「今回はこらえてください」のように使います。 これらの表現は、単に謝るだけでなく、その時の状況や話者の感情を豊かに表す言葉として、滋賀のコミュニケーションにおいて大切な役割を担っています。
【地域別】滋賀県方言一覧とそれぞれの特徴

琵琶湖を囲むように広がる滋賀県では、その地理的な特徴から、地域ごとに方言に違いが見られます。 京都に近い湖南では京ことばの影響が強く、北部の湖北では北陸地方の方言に似た特徴を持つなど、多様な言葉が使われています。 ここでは、滋賀県を大きく4つのエリア(湖北・湖東・湖南・甲賀)に分け、それぞれの地域で話される方言の特徴と代表的な言葉を一覧でご紹介します。
湖北(長浜市・米原市など)の方言
湖北地域は、福井県や岐阜県と隣接しており、その影響を受けた独特の方言が特徴です。 アクセントも京阪式(京都や大阪で使われるアクセント)とは異なる「垂井式アクセント」が用いられることがあり、滋賀県内でも特に個性的な方言圏とされています。
代表的な語尾には「~やある」「~んす」「~ほん」などがあります。 例えば、「来る」という意味で「きゃんた」、「おいしそうな匂いがする」を「うまくさい」 と言うなど、他の地域ではあまり聞かれない言葉が使われます。
・きゃんた:来た、来られた
(例)「うちの子がきゃんたわ」(うちの子が来たわ)
・うまくさい:おいしそうな匂いがする
(例)「なんかうまくさい匂いがするなぁ」
・ごんす:来なさる
(例)「明日、先生がごんすわ」(明日、先生がいらっしゃいます)
・やんす:~です、~ます
(例)「あの人が言うてやんす」(あの人が言っています)
・~ほん:~だろう(推量)
(例)「じきにもんでこんすほん」(じきに帰っていらっしゃるだろう)
これらの言葉は、特に年配の方々の会話で聞かれることが多いですが、湖北地方の言葉の個性を今に伝えています。
湖東(彦根市・近江八幡市など)の方言
湖東地域は、西は琵琶湖、東は岐阜県と接しています。方言は、湖北地方と共通する部分もありながら、アクセントは京阪式に近く、比較的穏やかです。 文の合間に「よ」を挟んで「~よ、~してよ」のように話したり、「それ」を「ほれ」と言うなど、発音に特徴が見られます。
また、湖東から湖北にかけては、彦根藩の城下町であった彦根市を中心に、「ほん」「なーし」「とさいが」といった特徴的な助詞が使われることもあります。
・ほれ:それ
(例)「ほれ取ってくれへんか」(それを取ってくれませんか)
・~よ:文中に挟む間投詞
(例)「昨日よ、買い物に行ってよ、ほんでな…」
・きんまい:美しい、立派な
(例)「きんまい着物やな」(立派な着物ですね)
・おせんどさん:ご苦労様
(例)「遠いところから、おせんどさんでしたな」
・あくさもくさ:洗いざらい、何もかも
(例)「あくさもくさ話しなさい」(洗いざらい話しなさい)
近江商人を多く排出した地域でもあり、丁寧な言葉遣いが根付いている一方で、親しみやすい表現も多く残っています。
湖南(大津市・草津市など)の方言
県の南西部に位置する湖南地域は、県庁所在地の大津市を含み、古くから京都との交流が盛んでした。 そのため、方言も京都の京ことばに非常に近い特徴を持っています。 現代では、京阪神への通勤・通学者が多いことから関西共通語化が進んでいますが、年配の方を中心に、やわらかく上品な近江ことばが聞かれます。
特徴的な表現として、過去や継続を表す「~らった」があります。 また、「~してはる」のような尊敬語も日常的に使われます。
・~らった:~いた、~していた
(例)「昨日テレビ見てらった」(昨日テレビを見ていた)
・なおす:片付ける、しまう
(例)「その本、棚になおしといて」(その本、棚にしまっておいて)
・ほかす:捨てる
(例)「このゴミほかしてきて」
・いけず:意地悪
(例)「そんなこと言うなんて、いけずやわ」
・えらい:とても、すごく、疲れた
(例)「今日はえらい人多かったな」(今日はとても人が多かったな)、「歩きすぎてえらいわ」(歩きすぎて疲れたよ)
京ことばに近い上品さと、親しみやすさを併せ持っているのが湖南方言の魅力です。
甲賀(甲賀市・湖南市など)の方言
滋賀県の最南端に位置する甲賀地域は、三重県の伊賀地方と隣接しているため、その影響を強く受けた方言が話されています。 大きくは湖南方言の一部とされますが、尊敬の表現やアスペクト(動作のどの段階にあるかを示す表現)などで、三重県伊賀弁や湖東方言と共通する点が見られます。
例えば、理由を表す接続助詞「デ」と「サカイ(ニ)」を両方使う傾向は、湖東地域と共通しています。 また、尊敬を表す「~ヤール」という言い方は、湖東でも使われることがあります。
・だんない:差し支えない、かまわない
(例)「これくらい、だんない、だんない」(これくらい、大丈夫、大丈夫)
・よばれる:食べる、ごちそうになる
(例)「晩ごはん、よばれていき」(晩ごはん、食べていきなさい)
・よぞい、よぞくろしい:おぞましい、気持ち悪い
(例)「あの虫、なんかよぞいわ」
・せんどする:飽きる、うんざりする
(例)「同じ話ばっかりで、せんどしたわ」(同じ話ばかりで、うんざりした)
・うい:申し訳ない、気の毒だ
(例)「そんなに気ぃつかわんで、ういがね」(そんなに気を遣わないで、申し訳ないから)
このように、甲賀地域の方言は、近隣の文化が混じり合って形成された、興味深い特徴を持っています。
日常会話で使える滋賀県方言一覧

滋賀県の方言には、日々の暮らしの中で気軽に使え、コミュニケーションを豊かにしてくれる言葉がたくさんあります。感情を表す言葉、行動に関する言葉、そして食べ物にまつわるユニークな表現まで、知っていると滋賀での会話がもっと楽しくなる方言をピックアップしてご紹介します。
感情を表す方言(うれしい・びっくり・疲れた)
感情を表現する言葉には、その土地ならではのニュアンスが込められています。滋賀県で使われる感情表現は、ストレートでありながらもどこか温かみを感じさせるものが多くあります。
・えらい・しんどい:「疲れた」
滋賀県をはじめ関西地方で広く使われるのが「えらい」です。「歩きすぎてえらいわ」のように、肉体的な疲労を表します。 「しんどい」も同様に使われますが、「えらい」の方がより強い疲労感を示すことがあります。「えらい」は「とても」「すごい」という意味でも使われるため、「えらい人やな」と言うと、「すごい人だね」と「疲れている人だね」の両方に解釈できる可能性があり、文脈で判断します。
・かなん:「嫌だ」「困った」
「敵わない」が語源で、どうしようもなく困った状況や、嫌でたまらないという気持ちを表します。 「雨に降られてかなんわ」や「宿題が多くてかなん」のように使います。深い謝罪の気持ちを表すこともあります。
・ほっこりする:「疲れる」「うんざりする」
標準語の「心が和む」という意味とは正反対で、「疲れてぐったりする」「飽き飽きする」という意味で使われます。 例えば、「一日中立ち仕事でほっこりした」のように使います。 意味のギャップが大きいので、使う際には注意が必要な方言の代表格です。
・うい:「申し訳ない」「気の毒だ」
相手の親切や心遣いに対して、恐縮する気持ちを表す言葉です。 「こんなにたくさんもらって、ういわぁ」のように、感謝と申し訳なさが入り混じったニュアンスで使われます。
これらの言葉を使いこなせると、より細やかな感情を伝えることができ、滋賀の人々との心の距離もぐっと縮まるでしょう。
行動を表す方言(行く・来る・帰る)
日常の基本的な動作を表す言葉にも、滋賀県独特の表現が見られます。移動に関する言葉は特に地域性が表れやすく、知っていると会話の理解が深まります。
・いぬ:「帰る」「去る」
「帰る」という意味で「いぬ」という言葉が使われることがあります。 「もうそろそろ、いのか」(もうそろそろ帰ろうか)のように使います。古語の「去ぬ(いぬ)」が残った形とされ、歴史を感じさせる言葉の一つです。
・もんてくる・もんでくる:「戻ってくる」
「帰ってくる」という意味で「もんてくる」や「もんでくる」が使われます。 「ちょっと忘れ物したから、もんてくるわ」のように使います。 「戻りて来る」が変化した言葉と言われており、温かみのある響きが特徴的です。
・きゃんた:「来た」「来られた」
主に湖北地方で使われる言葉で、「来る」の尊敬語、あるいは単に「来た」という意味で使われます。 「お客さんがきゃんたで」と言うと、「お客さんが来られましたよ」という丁寧なニュアンスになります。若い世代でも使われることがある、地域を代表する方言です。
・ほかす:「捨てる」
関西地方で広く使われる言葉ですが、滋賀県でも日常的に「ゴミをほかす」のように使われます。
・なおす:「片付ける」「しまう」
これも関西共通の表現ですが、滋賀では特によく耳にします。 「散らかってるから、はよなおしや」のように、整理整頓を促す際に使われます。標準語の「修理する」という意味ではないため、注意が必要です。
これらの言葉は、滋賀県民の日常に深く根付いており、ごく自然な会話の中で使われています。
食べ物に関する方言
食文化が豊かな滋賀県では、食べ物にまつわる独特の方言も存在します。食材の名前から、味や状態を表す言葉まで、食卓での会話を楽しくする表現を見ていきましょう。
・おかいさん:「おかゆ」
「おかゆ」のことを、親しみを込めて「おかいさん」と呼びます。 体調が悪い時などに「おかいさんでも炊いたろか」のように使われ、優しさを感じさせる言葉です。
・かしわ:「鶏肉」
鶏肉全般を指して「かしわ」と言います。 焼き鳥屋さんや精肉店でも「かしわ」という表示が見られ、すき焼きに鶏肉を入れる「かしわのすき焼き」は滋賀県の郷土料理としても知られています。
・こうらい:「とうもろこし」
「とうもろこし」のことを「こうらい」と呼びます。 これは、かつて中国(高麗)から伝わったことに由来すると言われています。
・うまそう・うまくさい:「美味しそう」
見た目や香りが美味しそうな時に使う言葉です。「このケーキ、うまそうやな」のように使います。「うまくさい」は特に湖北地方で使われ、「美味しそうな匂い」を指します。 決して「馬が臭い」という意味ではありません。
・ちゅんちゅん:「お湯が沸騰している様子」「とても熱い様子」
やかんのお湯が沸いている状態や、触れないほど熱いものを「ちゅんちゅん」と表現します。 「お鍋のふた、ちゅんちゅんやで気ぃつけや」のように使われ、そのかわいらしい響きから人気のある方言の一つです。
・じゅんじゅん:すき焼き
すき焼きのことを「じゅんじゅん」と呼ぶことがあります。これは、鍋で肉や野菜が煮える音から来ていると言われています。「今晩はじゅんじゅんにしよか」といった具合で使われます。
これらの言葉を知っていると、滋賀の食文化をより深く味わうことができるでしょう。
ちょっとユニークな滋賀県の方言
滋賀県の方言には、他の地域ではあまり聞かれない、個性的で面白い言葉もたくさんあります。意味を知ると納得したり、その響きに思わず笑みがこぼれたりするような、ユニークな方言を紹介します。
・ももける:「毛羽立つ」
セーターなどが摩擦で毛羽立ったり、毛玉ができたりする状態を「ももける」と言います。 「このセーター、よう着てるから、ももけてきたわ」のように使います。 なんとも言えない語感が、状態をうまく表しています。
・ちょかる・ちょける:「ふざける」「調子に乗る」
ふざけたり、おどけたり、調子に乗ったりする様子を指します。 「あんまりちょかると、先生に怒られるで」のように、子どもを注意する際などによく使われます。
・よこんちょ:「横」
「横」のことを、少し親しみを込めて「よこんちょ」と言います。 「その机、もうちょっとよこんちょにずらして」のように使います。
・おちょばい:「お世辞」「へつらい」
相手に気に入られようとお世辞を言ったり、ごまをする行為を「おちょばい」と言います。 「あの人はおちょばっかり言うて、信用できひん」といった具合で使われます。
・ちゅんちゅん:「沸騰している」「とても熱い」
前述の通り、お湯がグラグラと沸騰している様子や、物が非常に熱い状態を指す擬態語です。 「やかんのお湯がちゅんちゅんに沸いてる」 や「この鉄板ちゅんちゅんやから触ったらあかんで」のように使います。
・おが:「カメムシ」
あの独特の匂いを放つ虫、カメムシのことを、滋賀県の一部地域では「おが」と呼びます。 由来は定かではありませんが、地域に根付いた呼び名の一つです。
これらのユニークな方言は、滋賀の言葉の多様性と遊び心を感じさせてくれます。
知っておくと便利!滋賀県方言一覧【単語編】

ここでは、これまでに紹介した以外にも、知っておくと滋賀県での暮らしや旅行がさらに面白くなる単語を、品詞(名詞・動詞・形容詞など)に分けて一覧でご紹介します。日常会話で不意に出てきても戸惑わないように、チェックしてみましょう。
名詞(物や場所を表す言葉)
・うみ:琵琶湖のこと
滋賀県民にとって「うみ」と言えば、日本海や太平洋ではなく、琵琶湖を指すことが圧倒的に多いです。生活に密着した存在であることがうかがえます。
・かんてき:七輪のこと
炭火で魚などを焼く際に使う七輪を「かんてき」と呼びます。
・ごもく:ゴミ
「ごもく集め」は「ゴミ収集」のことです。
・げべっちゃ:最後尾、ビリ
競争などで一番最後のことを「げべっちゃ」と言います。
・こうらい:とうもろこし
夏の風物詩であるとうもろこしは「こうらい」と呼ばれます。
・おが:カメムシ
地域によっては、この呼び名が一般的です。
・めいぼ:ものもらい
目のふちにできる腫れ物のことを「めいぼ」と言います。これは関西広域で使われる言葉です。
動詞(動きを表す言葉)
・いらう:触る
「勝手にいらうな」(勝手に触るな)のように使います。
・かす:米を研ぐ
「お米をかす」と言えば、お米を研ぐことを指します。
・こぎる:値段をまけさせる、値切る
商人文化が根付く滋賀らしい言葉かもしれません。「もうちょっとこぎってーな」のように使います。
・さらす:する、やる
「はよ宿題さらしや」(早く宿題をしなさい)のように、少しぞんざいな言い方として使われることがあります。
・なぶる:触る、いじくりまわす
「いらう」と似ていますが、「なぶる」はしつこく触る、余計な手出しをするといったニュアンスで使われることが多いです。
・ほかす:捨てる
「その紙、ほかしていい?」(その紙、捨てていい?)のように日常的に使われます。
形容詞・副詞(様子を表す言葉)
・いかい:大きい
「いかいカバンやな」(大きいカバンだね)のように使います。
・きんまい:美しい、立派な
「きんまいお召し物で」(立派な服装で)のように、人や物を褒めるときに使います。
・はしかい:チクチク痛い、ヒリヒリする
虫に刺された時や、セーターが肌に当たってかゆい時などに「はしかい」と表現します。
・なまずけない:だらしない
身なりや態度がだらしない様子を指します。「なまずけない格好すな!」(だらしない格好するな!)のように使われます。
・よけまい:余計に
「よけまいなことせんでええ」(余計なことはしなくていい)のように使います。
・あんじょう:うまく、上手に
「あんじょうやりや」(うまくやりなさいよ)のように、相手を励ましたり、感心したりする時に使います。
滋賀県方言の背景と歴史

滋賀県の方言、近江弁がなぜこれほど多様で、地域によって特色があるのでしょうか。その背景には、滋賀県の地理的な位置や、都であった京都との深い関わり、そして人々の往来の歴史が大きく影響しています。言葉のルーツを知ることで、方言への理解がさらに深まるでしょう。
なぜ地域によって言葉が違うの?
滋賀県の方言に地域差がある大きな理由は、その地理的条件にあります。 県の中央に広がる琵琶湖が、かつては人々の交流を物理的に隔てる役割を果たしていました。また、周囲を京都府、福井県、岐阜県、三重県に囲まれており、それぞれの県境地域では隣接する地域の方言の影響を強く受けています。
・湖南地方:古くから都であった京都に隣接しているため、京ことばの影響が最も色濃く残っています。
・湖北・湖東地方:岐阜県(旧美濃国)に近く、美濃弁の影響が見られます。
・湖西地方:福井県(旧若狭国)と接しており、若狭弁と共通する言葉があります。
・甲賀地方:三重県(旧伊賀国)との県境にあり、伊賀弁の影響を受けています。
このように、滋賀県は様々な文化が行き交う「十字路」のような場所に位置しているため、地域ごとに異なる言葉が育まれ、モザイク状の方言分布が形成されたのです。
京ことばとの関係性
滋賀の方言、特に湖南地方の言葉は、京ことばと非常に似ています。 これは、地理的な近さだけでなく、歴史的な人の往来が大きく関係しています。江戸時代、近江商人が全国で活躍しましたが、彼らは商いの拠点として京都や大阪と深い結びつきを持っていました。
また、湖西地方などでは、娘や息子を京都へ女中奉公や丁稚奉公に出す習慣がありました。 こうした人々の移動を通じて、当時の日本の中心であった京都の言葉が滋賀県に持ち込まれ、広く浸透していったと考えられます。
そのため、「~してはる」といった丁寧な表現や、「おしまいやす」「おおきに」といった言葉が、滋賀でも日常的に使われるようになりました。 しかし、全く同じというわけではなく、滋賀独自の変化を遂げたり、京ことばよりも少し田舎風で素朴、あるいは荒っぽいと評されたりすることもあります。 この微妙な違いが、滋賀県方言の独特の味わいを生み出しているのです。
現代における滋賀県方言の使われ方
現代では、テレビやインターネットの普及、そして交通網の発達により、全国的に方言は標準語化・共通語化する傾向にあります。滋賀県も例外ではなく、特に若い世代では、昔ながらの表現を知らなかったり、使わなかったりすることが増えています。
特に大津市などの都市部では、京都や大阪への通勤・通学者が多く、いわゆる「関西共通語」を話す人が中心となっています。 そのため、滋賀県民自身も「滋賀に特有の方言はない」と感じている場合があります。
しかし、家族や親しい友人との会話の中では、依然として多くの滋賀県方言が息づいています。「なおす(片付ける)」、「ほかす(捨てる)」、「えらい(疲れた)」といった言葉は、世代を問わずごく自然に使われています。 また、「ちゅんちゅん」や「ももける」といったユニークな言葉は、その響きの面白さから、方言であることを意識しながらも親しみを込めて使われることがあります。
言葉は時代と共に変化していくものですが、滋賀県の方言は、その土地の歴史や文化を映す鏡として、これからも人々の暮らしの中で大切に受け継がれていくことでしょう。
まとめ|滋賀県方言一覧から見える言葉の魅力

この記事では、「滋賀県方言一覧」をテーマに、基本的な挨拶から地域別の特徴、日常会話で使える単語まで、幅広く近江弁の世界をご紹介しました。
滋賀県の方言は、京都に近い湖南では京ことばの影響を強く受けた上品な響きを持ち、福井や岐阜に近い湖北では個性的で力強い言葉が使われるなど、地域によって多様な顔を持っています。 「ほっこりする(疲れる)」のように標準語と意味が異なる言葉や、「ちゅんちゅん(沸騰している)」のような可愛らしい響きの言葉など、知れば知るほど興味深い表現がたくさんありました。
これらの言葉は、単なる地方の言葉というだけでなく、滋賀県の地理的な特徴や、近江商人の活躍に代表される人々の往来の歴史の中で育まれてきた文化そのものです。 現代では使われる機会が減った方言もありますが、今もなお多くの言葉が滋賀県民の日常に彩りを添えています。
この一覧を通じて滋賀県の方言に触れたことで、滋賀県への親しみや興味が少しでも深まれば幸いです。