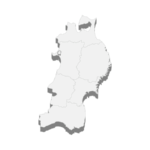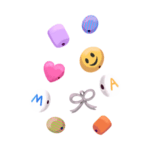「~ずら」「~けし」「こぴっとしろし!」などの言葉を聞いたことはありますか?これらはすべて、山梨県で話されている方言、通称「甲州弁」です。どこか懐かしく、力強い響きが特徴的な甲州弁は、アニメやドラマの影響で全国的に知られるようになりました。 しかし、その魅力は単なる言葉の面白さだけではありません。
この記事では、「山梨県方言一覧」というキーワードで検索されたあなたのために、甲州弁の基本的な特徴から、日常会話で使える具体的なフレーズ、さらには知っていると面白い豆知識まで、幅広く情報をまとめました。この記事を読めば、あなたも甲州弁の奥深い世界に触れ、山梨県をより身近に感じられるようになるでしょう。さあ、一緒に甲州弁の旅に出かけましょう。
山梨県方言(甲州弁)の基本的な特徴

山梨県で話されている方言は「甲州弁」として親しまれています。この方言は、ただ言葉が違うだけでなく、独特のイントネーションや語尾に大きな特徴があります。初めて聞く人にとっては、少しぶっきらぼうに聞こえるかもしれませんが、その意味を知ると、言葉の裏にある温かみや面白さに気づくはずです。 ここでは、そんな甲州弁の基本的な特徴を3つのポイントに分けて、やさしく解説していきます。
語尾に特徴がある甲州弁
甲州弁の最も顕著な特徴は、文末、つまり語尾に表れます。代表的なものに「~ずら」や「~ら」があり、これは「~だろう」という推量を表す際に使われます。 例えば、「明日は晴れるだろう」は「明日は晴れるずら」となります。この「ずら」は、長野県や静岡県などでも使われることがあり、近隣地域との言葉のつながりを感じさせます。
また、疑問を表す際には「~け?」がよく使われます。 「そうですか?」は「ほうけ?」という具合です。さらに、命令や依頼を表す際には「~し」や「~けし」が用いられます。 「早く食べなさい」は「はやく食べろし」や「はやくたべてけし」のように表現され、少し力強い印象を与えるかもしれません。しかし、これには「~してね」といった親しみが込められていることが多いです。他にも、理由を表す「~さよぉ」や、念を押す「~じゃんけ」など、多彩な語尾が会話を豊かに彩っています。
アクセントとイントネーション
甲州弁のアクセントは、一般的に東京式アクセントに分類されますが、その中でもやや平坦で、無アクセントに近い話し方をするのが特徴です。 標準語のように単語の中での音の高低差があまりなく、全体的に抑揚が少ないトーンで話される傾向があります。そのため、県外の人が聞くと、少しぶっきらぼう、あるいは怒っているように聞こえてしまうことがあるかもしれません。
しかし、これは甲州弁が持つ独特のリズムであり、決して話し手が不機嫌なわけではありません。例えば、「橋」と「箸」のように、標準語ではアクセントで区別する単語も、甲州弁では同じようなイントネーションで発音されることがあります。この平坦な話し方こそが、甲州弁の素朴で飾らない魅力の一つと言えるでしょう。言葉のニュアンスは、語尾や文脈、そして話している人の表情から読み取ることが大切になります。
地域による方言の違い(国中弁・郡内弁など)
山梨県と一口に言っても、地域によって話される方言には違いがあります。山梨県の方言は、御坂山地や大菩薩嶺を境として、大きく西側の「国中(くになか)地方」と東側の「郡内(ぐんない)地方」の二つに分けられます。
甲府盆地を中心とする国中地方で話されるのが、いわゆる「国中弁」です。これは長野県や静岡県の方言と共通点が多く、「~ずら」といった語尾が特徴的です。 一方、大月市や都留市、富士吉田市などの郡内地方で話されるのは「郡内弁」と呼ばれ、こちらは東京都の多摩地域や神奈川県の方言に近い特徴を持っています。 例えば、意志や推量を表す際に国中弁では「~ずら」を使うのに対し、郡内弁では「~べー」や「~だんべー」が使われます。 また、否定の表現も国中では「~ん」(例:行かん)ですが、郡内では「~ない、~ねー」(例:行かねー)が使われるなど、文法レベルでの違いが見られます。 このように、同じ山梨県内でも地域によって言葉が異なるのは、歴史的な人々の交流や地理的な要因が関係しており、非常に興味深い点です。
【シーン別】山梨県方言一覧(日常会話編)

甲州弁の基本的な特徴がわかったところで、次は実際にどのような場面で使われるのかを見ていきましょう。方言は、人々の暮らしの中で生き続ける言葉です。挨拶や感謝の気持ちを伝えるとき、嬉しい、悲しいといった感情を表現するとき、そして相手に質問したり相槌を打ったりするとき、甲州弁ならではの温かい言い回しがたくさんあります。ここでは、日常の様々なシーンで使える甲州弁を、具体的な例文とともに紹介します。
挨拶や感謝で使う方言
毎日のコミュニケーションに欠かせない挨拶や感謝の言葉も、甲州弁になると独特の響きを持ちます。「おはようございます」は、より丁寧に「おはようごいす」と言うことがあります。 「ご苦労様」という意味合いで「ごっちょでごいす」という表現もあり、これは手間をかけたことへの感謝や労いの気持ちを表す丁寧な言葉です。
また、食事の場面では「いただきます」や「ごちそうさま」の代わりに「よばれます」「よばれました」と言うことがあります。 これは「お呼ばれする」という謙譲の気持ちが込められた表現です。感謝を伝える「ありがとう」も、「ありがとうごいす」と丁寧になったり、「かたじけない」という古風な言い方をしたりすることもあります。別れ際の「さようなら」は「ごきげんよう」と言う地域もあり、言葉の端々に相手を敬う気持ちが表れています。
気持ちや感情を伝える方言
感情を表現する言葉には、甲州弁ならではのユニークなものがたくさんあります。例えば、標準語の「疲れた」「大変だ」という意味で「えらい」という言葉がよく使われます。 「今日の仕事はえらかった」と言えば、それは「今日の仕事は大変で疲れた」という意味になります。また、「かたい」という意味で「こわい」と言うこともあります。 「このせんべいはこわい」は、決して恐怖を感じているわけではなく、「このせんべいは硬い」ということです。
他にも、「くすぐったい」を「ももっちい」、「ずるい」を「しわい」 や「おぞい」、「捨てる」を「ぶちゃる」 と言ったりします。驚いた時には「てっ!」という感嘆詞が飛び出すこともあり、これはNHKの連続テレビ小説『花子とアン』で使われたことで有名になりました。 このように、感情や状態を表す言葉を知っていると、地元の人との会話がより一層楽しくなるはずです。
質問や相槌で使う方言
会話をスムーズに進める上で欠かせないのが、質問や相槌の言葉です。甲州弁では、相手に何かを尋ねるときに語尾に「~け?」をつけます。 「これ、食べてもいいですか?」は「これ、食っていいけ?」という具合です。この「け」は、柔らかく尋ねるニュアンスを持っています。
相手の話に同意したり、相槌を打ったりする際には、「そうでしょう?」という意味で「ほうずら?」や「ほうだら?」が使われます。 また、「そうだね」と同意を示すときには「そうだに」や「ほうじゃんね」と言います。 特に「~じゃん」という語尾は、今では首都圏の若者言葉としても定着していますが、もともとは山梨県などでよく使われていた方言です。 このように、相手との共感を示す相槌のバリエーションが豊かなのも、甲州弁でのコミュニケーションの面白いところです。
【品詞別】山梨県方言一覧(単語編)

甲州弁の魅力は、語尾や言い回しだけにとどまりません。名詞や動詞、形容詞といった一つ一つの単語にも、標準語とは異なるユニークなものが数多く存在します。中には、意味を知らないと全く見当がつかないような面白い言葉もあります。ここでは、そんな甲州弁の単語を品詞別に分け、一覧形式でご紹介します。これらの単語を覚えれば、あなたも甲州弁マスターに一歩近づけるかもしれません。
名詞・代名詞の面白い方言
甲州弁には、聞いただけでは意味を想像するのが難しい、面白い名詞や代名詞がたくさんあります。例えば、子供のことを「ぼこ」と呼びます。 「うちのぼこが」と言えば、「うちの子供が」という意味になります。また、あなたを指す代名詞として「おまん」、あなたたちを指す言葉として「おまんとう」が使われます。 少し強い響きに聞こえるかもしれませんが、親しみを込めて使われることがほとんどです。
食べ物に関する方言もユニークです。「おこうこ」は漬物のこと、「おつけ」は味噌汁を指します。山梨名物の「ほうとう」も、もともとは地域に根差した言葉です。 さらに、体育着やジャージのことを「ジャッシー」と呼ぶこともあります。 これは山梨特有の和製英語とも言えるかもしれません。このように、日常生活に密着した単語にこそ、その土地ならではの文化が色濃く反映されています。
動詞・形容詞のユニークな方言
動作や状態を表す動詞や形容詞にも、甲州弁ならではの表現があります。標準語と全く同じ言葉なのに、意味が異なるものもあるので注意が必要です。代表的なのが「とぶ」という動詞です。これは「飛ぶ」のではなく「走る」という意味で使われます。 「とんでいけし」と言われたら、走って行きなさい、という意味になります。また、「かじる」は「(体を)掻く」という意味で使われ、「背中かじって」は「背中を掻いて」というリクエストです。
他にも、「鍵をかける」ことを「かう」、「捨てる」ことを「ぶちゃる」または「うっちゃる」、「集まる」ことを「よっちゃばる」 と言います。形容詞では、「大きい」ことを「いかい」、「疲れた・大変だ」を「えらい」、「くすぐったい」を「ももっちい」 と表現します。これらの言葉を自然に使いこなせれば、地元の人との距離もぐっと縮まるでしょう。
驚きの副詞・接続詞などの方言
会話のニュアンスを豊かにする副詞や接続詞にも、甲州弁には面白い言葉があります。「とても」「すごく」という強調の意味で「ばか」や「ずでぇ」、「はんで」 という言葉が使われます。「はんでいい天気じゃん」と言えば、「すごく良い天気だね」という意味になります。また、「全く」「全然」という否定を強調する際には「いっさら」という言葉を使います。 「いっさらわからん」は「全くわからない」ということです。
「急いで」という意味では「はんで」が使われることもあります。 接続詞としては、「~だから」という意味で「~だからさ」と言うことが多く、語尾の「さ」が特徴的です。「そういうこと」を「ちゅうこん」または「ちゅこん」と略して言うのも甲州弁らしい表現です。 このような細かい言葉遣いが、甲州弁の独特のリズムと味わいを生み出しているのです。
知っていると面白い!山梨県方言の豆知識

甲州弁の具体的な言葉をいくつか知ると、その背景にある歴史や文化にも興味が湧いてきませんか。方言は、単なる昔の言葉というだけではなく、その土地の風土や人々の暮らし、歴史的な出来事と深く結びついています。ここでは、甲州弁の成り立ちや、メディアでの扱われ方、そして標準語との意外な関係など、知っていると誰かに話したくなるような豆知識をご紹介します。
甲州弁の歴史と由来
甲州弁のルーツを探ると、山梨県の地理的・歴史的な背景が見えてきます。山梨県は四方を山に囲まれた盆地であるため、古くからの言葉が残りやすい環境にありました。 江戸時代になると、甲斐国(現在の山梨県)は幕府の直轄領となり、甲州街道を通じて江戸との交流が活発になりました。 これにより、甲府の言葉には江戸言葉の影響が見られるようになり、例えば「高い(たかい)」が「たけー」となるような母音の変化は、江戸言葉から取り入れられたものだと言われています。
また、国中地方の方言が静岡県や長野県の方言と似ているのは、富士川の水運などを通じてこれらの地域との交流が盛んだったからです。 一方で、郡内地方の方言が東京の多摩地域や神奈川県の方言と似ているのは、地理的に近く、人の往来が多かったためです。 このように、甲州弁は古い言葉を守りつつ、様々な地域との交流の中で独自の発展を遂げてきた、歴史の証人ともいえる言葉なのです。
メディアで使われる甲州弁
近年、甲州弁が全国的に知られるきっかけとなったのが、様々なメディアでの登場です。特に大きな影響を与えたのが、2014年に放送されたNHKの連続テレビ小説『花子とアン』です。 山梨出身の主人公が話す「てっ!」「こぴっと」「~ずら」といった甲州弁は、その独特の響きと温かみで多くの視聴者に親しまれました。
また、人気アニメ『ゆるキャン△』のキャラクターたちが話す自然な甲州弁も、作品の魅力を高める要素の一つとなっています。地元のアナウンサーが方言でニュースを読むといったユニークな試みもあり、甲州弁の面白さや親しみやすさを伝えるきっかけになっています。 バラエティ番組で「日本一汚い方言」などと少し過激に紹介されることもありますが、それも甲州弁が持つインパクトの強さの表れであり、多くの人が関心を持つきっかけとなっていることは間違いありません。
甲州弁と標準語の意外な関係
甲州弁の中には、標準語と形は同じでも意味が全く異なる単語があることはすでに紹介しましたが、実は標準語だと思って使っている言葉が、もともとは甲州弁だったというケースもあります。その代表例が「ぶどう」です。今では全国で使われるこの言葉ですが、その語源には諸説あり、山梨の地名が関係しているという説もあります。
また、若い世代で広く使われる「~じゃん」という言葉も、もともとは山梨やその周辺地域の方言でした。 これが横浜などを経由して全国に広まったとされています。逆に、甲州弁では「行く」の勧誘形を「いかず」と言いますが、標準語の文法では「行かず」は否定形になるため、県外の人が聞くと混乱してしまうことがあります。 このように、方言と標準語の関係は一方通行ではなく、互いに影響を与え合いながら変化している、生きたものであることがわかります。
山梨県方言一覧を学ぶためのおすすめの方法

ここまで読んで、甲州弁にますます興味が湧いてきた方も多いのではないでしょうか。「もっと知りたい」「実際に使ってみたい」と思ったとき、どうすれば甲州弁を学ぶことができるのでしょうか。一番良いのは、やはり生きた言葉に触れることです。ここでは、甲州弁をより深く学び、楽しむための具体的な方法をいくつかご紹介します。机の上での勉強だけでなく、五感を使って甲州弁の世界に飛び込んでみましょう。
地元の人とのコミュニケーション
方言を学ぶ最も効果的で楽しい方法は、その土地の人々と直接話すことです。山梨県に旅行や仕事で訪れた際には、ぜひ勇気を出して地元の人に話しかけてみてください。食堂のおばちゃん、お土産屋さんの店員さん、道ですれ違うおじいさんやおばあさんとの何気ない会話の中に、生きた甲州弁があふれています。
最初は聞き取れなかったり、意味がわからなかったりするかもしれませんが、わからない言葉があれば「その言葉はどういう意味ですか?」と素直に尋ねてみるのも良いでしょう。きっと親切に教えてくれるはずです。そうしたコミュニケーションを通じて、言葉だけでなく、山梨の人々の温かさや人柄にも触れることができます。言葉は人と人とをつなぐもの。甲州弁を通じて生まれる一期一会の出会いは、きっと旅の素敵な思い出になるでしょう。
山梨県関連のテレビやラジオ番組
山梨県内で放送されているローカルなテレビ番組やラジオ番組を視聴するのも、甲州弁を学ぶのに非常に有効な方法です。特に、地元の人が出演する情報番組やバラエティ番組では、日常的に使われる自然な甲州弁をたくさん聞くことができます。アナウンサーがきれいに話す言葉とは違う、リアルなイントネーションやリズムを感じ取れるでしょう。
また、YBS山梨放送やUTYテレビ山梨などの公式サイトでは、番組の一部を動画で配信していることもあります。県外にお住まいの方でも、インターネットを通じて山梨の番組に触れる機会は増えています。映像や音声で繰り返し聞くことで、甲州弁の独特の響きがだんだんと耳に馴染んでくるはずです。楽しみながら続けることが、語学習得の何よりの近道です。
方言に関する書籍やウェブサイト
もっと体系的に甲州弁について知りたいという方には、方言に関する書籍やウェブサイトを活用することをおすすめします。山梨県や各市町村が、文化振興の一環として方言に関する資料やパンフレットを発行していることがあります。 例えば、甲府市では市のウェブサイトで甲州弁の紹介をしています。
また、インターネット上には、個人や団体が運営する甲州弁の辞書サイトや解説ブログも数多く存在します。 これらのサイトでは、意味や使い方だけでなく、その言葉が使われる背景やニュアンスまで詳しく解説されていることもあり、非常に勉強になります。この記事で紹介した「山梨県方言一覧」のように、様々な言葉を比較しながら見てみるのも面白いでしょう。こうした情報を参考にしながら、自分だけの甲州弁ノートを作ってみるのも楽しいかもしれません。
まとめ:山梨県方言一覧で知る甲州弁の奥深さ

この記事では、「山梨県方言一覧」をテーマに、甲州弁の基本的な特徴から具体的な使用例、そしてその背景にある歴史や文化までを詳しく解説してきました。
甲州弁は、「~ずら」「~けし」といった特徴的な語尾や、平坦なアクセント、そして国中と郡内という地域による違いなど、知れば知るほど興味深い要素に満ちています。 日常会話で使われる「えらい(疲れた)」や「ぶちゃる(捨てる)」といったユニークな単語は、山梨の暮らしや文化を色濃く反映したものです。
方言は、単なる言葉の違いではなく、その土地で暮らす人々の心や歴史が詰まった大切な文化遺産です。この一覧を通じて甲州弁の魅力に触れたことで、山梨県がより身近で、温かい場所に感じられたのではないでしょうか。ぜひ山梨を訪れた際には、耳を澄まして、そして少しだけ勇気を出して、甲州弁での会話を楽しんでみてください。言葉を交わすことで、きっと新しい発見と素敵な出会いが待っているはずです。