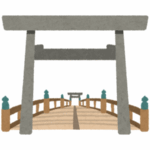「三重県の方言」と聞くと、どんなイメージがありますか?「関西弁に似てる?」「どんな言葉があるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。実は三重県の方言は、地域によって大きく表情を変える、とても奥深いものなんです。伊勢神宮や鈴鹿サーキットで知られる三重県ですが、その土地で話される言葉には、人々の温かさや歴史が詰まっています。
この記事では、「三重県 方言ランキング」というテーマで、Web上の声や一般的な認知度を参考に、かわいらしい響きの言葉から、思わず笑ってしまうユニークな表現、そして三重県民なら誰もが知る有名な方言まで、様々な角度からランキング形式でご紹介します。あなたもこの記事を読めば、きっと三重弁の魅力に引き込まれるはずです。
まずは知りたい!三重県方言ランキング【基本編】

三重県の方言、通称「三重弁」は、一口に関西弁と括ることができない多様性を持っています。ランキングを見ていく前に、まずはその基本的な特徴や地域ごとの違いについて知っておきましょう。三重県は地理的に近畿地方、中部地方、東海地方の結節点に位置するため、言葉もそれぞれの地域の影響を受けており、県内でもエリアによって全く違う方言が話されているのが大きな特徴です。この基本を押さえておくと、後から出てくる方言の面白さがより一層深まります。
三重県の方言ってどんな特徴があるの?
三重県の方言の最も大きな特徴は、基盤となっているのが「近畿方言」、つまり関西弁であることです。そのため、「あかん(ダメ)」「ちゃう(違う)」といった関西圏で広く使われる言葉は、三重県でも日常的に耳にします。しかし、アクセントやイントネーションが一般的な関西弁とは少し異なります。例えば、大阪弁がリズミカルで抑揚がはっきりしているのに対し、三重弁は比較的イントネーションが平坦(フラット)で、穏やかに聞こえることが多いと言われています。
この独特の響きが、三重弁の優しさや温かみを感じさせる要因の一つかもしれません。また、語尾に「~やん」「~さー」「~に」などが付くのも特徴的です。これらの語尾は、言葉のニュアンスを柔らかくしたり、親しみを込めたりする役割を果たしています。地理的な影響も大きく、名古屋弁など東海地方の方言の影響を受けた言葉も見られるため、「関西弁と東海弁のハイブリッド」と表現されることもあります。このように、複数の文化が混ざり合って形成された点が、三重弁の最大の魅力であり、面白さの源泉と言えるでしょう。
地域によってこんなに違う!伊賀・伊勢・志摩・紀州の方言
三重県の方言は、大きく4つのエリアに分類できます。それぞれの地域で話される言葉にははっきりとした違いがあり、県民同士でも出身地が分かるほどです。
まず、京都府や奈良県に隣接する北西部の「伊賀地方(伊賀市、名張市など)」では、京阪式アクセントが強く、関西弁に非常に近い「伊賀弁」が話されます。イントネーションも言葉遣いも関西風なので、他府県の人が聞くと大阪や京都の方言と区別がつかないかもしれません。
次に、県の中部に位置する「伊勢地方(津市、四日市市、伊勢市など)」では、いわゆる「伊勢弁」が話されます。これが一般的に「三重弁」としてイメージされる方言で、関西弁をベースにしつつも、名古屋弁の影響も受けており、イントネーションは比較的穏やかです。
さらに、南部の鳥羽市や志摩市を中心とする「志摩地方」で話される「志摩弁」は、非常に個性的です。漁師町として栄えた歴史からか、独特の言葉や言い回しが多く、他の地域の人には理解が難しいこともあります。例えば「行ってきました」を「行ってきましたん」と言うなど、独特の語尾変化が見られます。
最後に、和歌山県に隣接する南部の「東紀州地方(尾鷲市、熊野市など)」では、和歌山弁に近い「紀州弁」が使われます。アクセントや語彙も和歌山の色が濃く、同じ三重県内でも伊賀地方とは大きく異なります。このように、エリアごとに全く違う顔を持つのが三重県の方言の奥深さです。
関西弁との違いは?イントネーションがポイント
三重弁と関西弁は、語彙の多くを共有しているため非常に似ていますが、決定的な違いは「イントネーション」にあります。関西弁、特に大阪弁は言葉の抑揚がはっきりしており、高く発音する部分と低く発音する部分の差が明瞭です。例えば、「ありがとう」と言う時、関西弁では「”あ”りがとう」と最初の「あ」にアクセントが来る傾向があります。
一方、三重弁(特に伊勢弁)は、全体的にイントネーションが平坦で、言葉がなだらかに流れていくように聞こえます。そのため、同じ「ありがとう」でも、三重の人は「ありがとう→」とフラットに発音することが多いです。この穏やかなイントネーションが、三重弁特有の「優しい」「おっとりしている」といった印象を生み出しています。また、語尾も微妙に異なります。「~だから」という意味で使う「~やから」は関西で広く使われますが、三重では「~やで」「~やもんで」という表現もよく使われます。細かな語尾の違いと、このイントネーションの差が、似ているようでどこか違う、三重弁独特の響きを作り出しているのです。
みんなが選ぶ!かわいい三重県方言ランキング

三重弁には、その穏やかな響きから「かわいい」と感じられる言葉がたくさんあります。特に語尾に付く表現や、標準語とは少し違う意味で使われる言葉に、聞いていると思わずほっこりしてしまう魅力が隠されています。ここでは、多くの人が「かわいい!」と感じる三重の方言をランキング形式でご紹介します。県外の人が聞いたらキュンとしてしまうかもしれない、そんな愛らしい言葉たちを見ていきましょう。
第1位候補:「~やん」「~に」 – 親しみやすい語尾
三重県のかわいい方言ランキングで、まず間違いなく上位に入るのが「~やん」と「~に」という語尾です。「~やん」は関西全域で使われる「~じゃないか」という意味の言葉ですが、三重の人が使うと、前述の通り平坦なイントネーションになるため、響きが非常に柔らかくなります。「これ、おいしいやん(これ、おいしいね)」のように、同意を求めたり、発見を伝えたりする時に使われ、親しみやすさを感じさせます。
一方、「~に」は、より三重らしさが際立つ語尾です。「昨日、映画観てきたに(昨日、映画を観てきたんだよ)」のように、相手に何かを報告したり、自分の意見を伝えたりする際に使われます。この「~に」には、断定する強さがなく、「~だよ」と優しく語りかけるようなニュアンスが含まれており、特に女性が使うと非常にかわいらしく聞こえます。また、「そうやに(そうだよ)」「ちゃうに(違うよ)」のように単体で返事をする時にも使われ、会話全体を和やかな雰囲気にしてくれる魔法のような言葉です。この二つの語尾は、三重県民のコミュニケーションに欠かせない要素であり、その温かい響きがかわいい方言の代表格と言われる所以です。
第2位候補:「えらい」 – 意外な意味にキュンとする?
標準語で「えらい」と言えば、「偉大な」「素晴らしい」といった称賛の意味で使われます。しかし、三重県や関西、東海地方の一部で使われる「えらい」は、全く違う意味を持ちます。それは「しんどい」「疲れた」「大変だ」という意味です。例えば、仕事で疲れて帰ってきた時に「ああ、今日はえらかったわー」と言ったり、風邪を引いて体調が悪い友人に対して「えらそうやな、大丈夫か?」と声をかけたりします。
この意味を知らない人が聞くと、「偉そうだって?どういうこと?」と誤解してしまうかもしれません。しかし、このギャップこそが「えらい」のかわいいポイントです。一生懸命何かを頑張った後や、体調がすぐれない時に、少し困ったような顔で「えらい…」とつぶやく姿は、どこか健気で守ってあげたい気持ちにさせられます。
また、相手を心配して「えらいやろ、休みさー(大変でしょ、休みなよ)」と気遣う言葉からは、深い優しさが感じられます。標準語の力強いイメージとは真逆の、弱さや疲れを示す「えらい」という言葉。その意外な意味と使い方に、多くの人が人間味あふれるかわいらしさを感じるのではないでしょうか。
第3位候補:「だんない」 – 優しさがにじみ出る言葉
「だんない」は、主に伊勢地方で使われる歴史ある方言で、「大丈夫」「構わない」「心配ない」といった意味を持つ言葉です。誰かが失敗して謝った時に「だんない、だんない(大丈夫、気にしないで)」と返したり、何かを手伝おうか尋ねられた時に「これくらい、だんないよ(これくらい、平気だよ)」と答えたりする際に使われます。
この言葉の語源は、一説には近江商人や伊勢商人が使っていた「段無い(だんない)」、つまり「支障がない」「問題ない」という言葉から来ていると言われています。商売上のやり取りで使われていた言葉が、人々の日常会話に根付いたのかもしれません。この「だんない」という言葉の響きには、相手を大きく包み込むような、おおらかさと優しさが満ちています。
ただ「大丈夫」と言うよりも、もっと心に寄り添ってくれるような温かみを感じさせます。特に、年配の方が穏やかな口調で「だんないさー」と言っているのを聞くと、心が安らぐような気持ちになります。相手の失敗を責めずに許し、心配を和らげてくれる「だんない」。この言葉が持つ深い包容力と優しさが、かわいいだけでなく、美しい方言として多くの人に愛されている理由です。
番外編:女性が使うと特にかわいい三重弁
ここまで紹介した以外にも、三重弁には女性が使うと魅力が倍増するような、かわいらしい表現がたくさんあります。その一つが、依頼やお願いをする時の「~してくれやん?」という言い方です。標準語の「~してくれない?」にあたる言葉ですが、「~くれやん?」という少し甘えたような響きが、お願い事を柔らかく、そしてかわいらしく伝えてくれます。
例えば、「これ、持ってくれやん?」と言われると、ついつい「いいよ」と引き受けてしまいたくなるかもしれません。また、「~やんか」もよく使われます。「言ったやんか(言ったじゃない)」のように、少し拗ねたような、あるいは甘えたようなニュアンスを出すのにぴったりの表現です。
さらに、驚いた時に使う「うそやん!」も、ストレートに「うそ!」と言うよりも感情がこもっていて、チャーミングに聞こえます。食事の場面では、「このケーキ、めっちゃおいしいやん!」と感動を伝えたり、日常会話では「明日の予定、どうするん?」と尋ねたりする際にも、三重弁特有のイントネーションが加わることで、親しみやすく柔らかな印象を与えます。こうした何気ない日常会話の中に、三重弁のかわいらしさはたくさん散りばめられているのです。
思わず笑っちゃう?面白い三重県方言ランキング

三重県の方言には、標準語話者が聞いたら「え、どういう意味?」と思わず聞き返してしまうような、ユニークで面白い言葉もたくさん存在します。標準語と同じ音なのに全く違う意味だったり、言葉の響き自体が面白かったりと、そのバリエーションは豊かです。ここでは、そんなクスッと笑える面白い三重県の方言をランキング形式でご紹介します。意味を知ると、きっとあなたも使ってみたくなるはずです。
第1位候補:「つる」 – 机を運ぶ時にも使う?
面白い方言ランキングの第1位候補は、間違いなく「つる」でしょう。標準語で「つる」と言えば、魚を「釣る」か、壁に絵などを「吊る」ことを思い浮かべるのが一般的です。しかし、三重県(特に中部から北部)では、全く違う意味でこの言葉が使われます。三重弁の「つる」は、「(二人以上で机や椅子など、ある程度の大きさの物を)運ぶ」という意味なのです。
学校や職場で、先生や上司が「誰か、この机つってくれー!」と言ったとしたら、県外の人は「机を…釣る?吊る?」と頭にクエスチョンマークが浮かぶことでしょう。正しくは「誰か、この机を(一緒に)運んでくれ」という意味です。この方言の面白いところは、「一人で運ぶ」場合には使われず、必ず複数人で協力して運ぶ際に使われるという点です。
なぜ「運ぶ」が「つる」になったのか、その語源ははっきりしていませんが、もしかしたら物を両側から持ち上げる様子が、何かを吊り上げているように見えたのかもしれません。この言葉は、三重県民にとってはごく当たり前の日常語。引っ越しや大掃除の際には「つる」という言葉が飛び交う、三重を象徴する面白い方言の一つです。
第2位候補:「とごる」 – 飲み物の底に溜まるアレ
続いて紹介する面白い方言は「とごる」です。これは「(液体に溶けきらなかった粉などが)沈殿する」という意味で使われる言葉です。例えば、ココアや抹茶ラテを飲んでいて、カップの底に粉が溜まってしまった状態。この現象を、三重県民は「うわ、とごっとるわ」と表現します。他にも、カルピスの原液がグラスの底に濃く溜まってしまった時や、味噌汁のお椀の底に味噌が沈んでいる時などにも使えます。
この「とごる」という言葉、響きが何とも言えません。「沈殿する」という少し硬い科学的な表現を、「とごる」という一言で、しかも的確に表しているのが見事です。その現象を見事に捉えた音の響きが、聞く人によっては面白く、またかわいらしく感じられるかもしれません。
この言葉は三重県だけでなく、愛知県や岐阜県など東海地方でも使われることがありますが、三重県民にとっては非常に馴染み深い言葉です。次に粉末の飲み物を飲む機会があったら、ぜひ底を見て「あ、とごってる!」と使ってみてください。きっと三重県民との距離がぐっと縮まるはずです。
第3e位候補:「いらう」 – ちょっと触るだけなのに
「いらう」もまた、標準語にはない独特のニュアンスを持つ面白い方言です。「いらう」は「触る」「いじる」「弄ぶ」といった意味で使われます。ただ単に「触る(タッチする)」というよりも、もう少し継続的に、あるいは不必要に触っているようなニュアンスが含まれることが多いです。
例えば、子どもがお店の商品をベタベタと触っている時に、親が「こら、そんないらわんといて!(こら、そんなに触らないで!)」と叱ったり、髪の毛をいじる癖のある人に対して「また髪の毛いらっとる(また髪の毛をいじってる)」と言ったりします。
精密機械などを興味本位で触ろうとする人には「壊れるで、いらうなよ!(壊れるから、触るなよ!)」と注意する時にも使えます。この「いらう」という言葉、知らない人が聞くと何を言っているのか全く分からないでしょう。「触る」という直接的な言葉よりも、どこかやんわりと、しかし的確にその行為を表現しているのが面白い点です。特に注意する時に使われると、その独特の響きから、少しユーモラスに聞こえるかもしれません。何気ない日常の動作を表す言葉にも、地域ならではのユニークな表現があることがよく分かります。
その他、聞いたら二度見する面白い方言たち
三重県には、まだまだ面白い方言がたくさんあります。例えば、「鍵をかう」という表現。これは「鍵をかける」という意味です。「買う」と同じ音なので、「え、鍵を買うの?」と驚かれることがよくあります。「戸締りした?」「うん、鍵こうといたよ(うん、鍵かけておいたよ)」といった具合に使います。
また、「捨てる」ことを「ほかる」と言います。これも関西圏で広く使われますが、知らないと「え?」となる言葉です。「このゴミほかっといて」は「このゴミ捨てておいて」という意味です。さらに、日付の言い方も独特です。「明日」の次の日、つまり「明後日」を「あさって」と言うのは標準語と同じですが、その次の日、「明々後日」のことを「ささって」と言います。
これも東海地方で広く使われる言葉で、三重県民の日常会話では頻繁に登場します。最後に、駐車場を意味する「モータープール」という言葉。これは三重県というよりは関西圏で広く使われる言葉ですが、看板にも普通に「モータープール」と書かれているため、関東など他地域から来た人は「プール?車で泳ぐの?」と不思議に思うそうです。このように、日常の何気ない言葉にも、地域色豊かな面白い表現が隠れているのです。
これだけは押さえたい!有名な三重県方言ランキング

三重県の方言には、県民であれば世代を問わず誰もが知っていて、日常的に使っている「定番」の言葉があります。これらは三重県民のアイデンティティの一部とも言えるほど、生活に深く根付いています。もしあなたが三重県を訪れたり、三重県出身の人と話したりする機会があれば、これから紹介する言葉を知っておくと、コミュニケーションがよりスムーズで楽しくなるはずです。ここでは、特に有名で代表的な三重の方言をランキング形式でご紹介します。
県民なら誰もが使う定番:「ささって」 – 明後日のようで明後日じゃない?
三重県および東海地方で最も有名で、かつ県外の人を混乱させがちな方言が「ささって」です。これは「明々後日(しあさって)」、つまり「三日後」を意味する言葉です。標準語では「あさって(二日後)」の次を「しあさって」と言いますが、三重では「あさって」の次は「ささって」となります。
会話の中で「じゃあ、ささってに会おうか」と言われたら、それは三日後の約束を意味します。この「ささって」は非常に便利な言葉で、三重県民は日常的に使います。しかし、この言葉を知らないと、「あさって」と聞き間違えてしまい、約束の日を一日勘違いしてしまうという悲劇が起こりかねません。実際に、県外から来た人がこの「ささって」で失敗した、というエピソードは後を絶ちません。ちなみに、地域や人によってはさらにその次の日(四日後)を「しあさって」と呼ぶ場合もあり、日付の感覚が独特です。
このように、日常的に使う言葉だからこそ、その地域独特のルールがあり、それを知ることが地域理解の第一歩となります。三重県民と約束をする際は、「ささって」が何日後を指すのか、しっかり確認することをおすすめします。
日常会話で頻出:「~してまう」 – ついやってしまうニュアンス
「~してまう」は、関西弁でもよく使われる表現ですが、三重県でも非常に頻繁に耳にする有名な方言の一つです。これは標準語の「~してしまう」にあたり、主に二つのニュアンスで使われます。一つは「完了」の意味です。「宿題、全部やってまったわ(宿題、全部やってしまったよ)」のように、何かを終えたことを表します。
もう一つは「意図せずそうなってしまった」「ついやってしまった」という後悔やしまった、という気持ちを表すニュアンスです。「大事にしとったお皿、割ってまったんさー(大事にしていたお皿、割ってしまったんだよ)」のように使われます。この「~してまう(~してまった)」という表現は、言葉に感情的な深みを与えます。
単に「割りました」と言うよりも、「割ってまった」と言った方が、その時のショックや残念な気持ちがより強く伝わってきます。三重弁の穏やかなイントネーションで「あー、また食べ過ぎてまったわー」などと言われると、どこか憎めない、人間味あふれる印象を受けます。日常のあらゆる場面で使われるこの表現は、三重県民の感情を豊かに彩る、欠かせない言葉と言えるでしょう。
怒られた時に聞くかも?:「あかん」 – 強さと優しさの共存
「あかん」は、関西地方全域で使われる「ダメだ」という意味の言葉で、三重県でももちろん広く使われています。知名度で言えば、方言の中でもトップクラスでしょう。「そんなことしたら、あかんて!(そんなことをしたら、ダメだって!)」のように、禁止や否定を表す際に使われます。
親が子どもを叱る時や、危険な行為を止めさせる時など、強い口調で使われることも多いため、「怒られる時に聞く言葉」というイメージがあるかもしれません。しかし、「あかん」は単に厳しいだけの言葉ではありません。例えば、友人が落ち込んでいる時に「そんなに思いつめたらあかんで(そんなに思いつめたらダメだよ)」と優しく声をかけたり、自嘲的に「今日のテスト、全然あかんかったわ…(今日のテスト、全然ダメだったよ…)」と使ったりすることもあります。
三重の人が使う「あかん」は、関西弁の持つ力強さに加え、三重弁特有の穏やかさが混じり合うことで、どこか温かみのある響きになることがあります。相手を突き放すような冷たさではなく、「ダメなものはダメ」と伝えつつも、その裏に相手を思う気持ちが感じられる。この強さと優しさの共存が、「あかん」という言葉の奥深さであり、多くの人に親しまれている理由なのかもしれません。
三重県の方言ランキングで知る言葉の魅力と多様性

この記事では、「三重県 方言ランキング」をテーマに、かわいい方言、面白い方言、そして有名な方言を様々な角度からご紹介してきました。三重県の方言は、関西弁をベースにしながらも、地域ごとに伊賀・伊勢・志摩・紀州と異なる特色を持ち、独特の穏やかなイントネーションがその大きな魅力となっています。
「~やん」「~に」といった親しみやすい語尾や、「えらい(しんどい)」「だんない(大丈夫)」といった優しさあふれる言葉がある一方で、「つる(運ぶ)」「とごる(沈殿する)」のようなユニークな表現もたくさんありました。これらの言葉は、単なるコミュニケーションの道具ではなく、三重県の地理的な特徴や歴史、そしてそこに住む人々の温かい人柄を映し出す鏡のようなものです。
方言を知ることは、その土地の文化や心に触れることにつながります。もし三重県を訪れる機会があれば、ぜひ耳を澄まして、生きた方言の響きを感じてみてください。きっと、旅がもっと味わい深いものになるはずです。