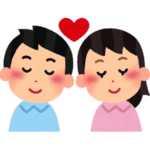佐賀県と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。雄大な自然、歴史的な街並み、そして美味しい食べ物など、魅力にあふれる県です。そして、その魅力をさらに引き立てているのが、独特で温かみのある「佐賀県方言」、通称「佐賀弁」です。
映画『がばいばあちゃん』で一躍有名になった「がばい」という言葉は知っていても、他にも面白い表現がたくさんあることはご存知でしょうか。佐賀県の方言は、一見すると少し無骨に聞こえるかもしれませんが、実は愛情深く、聞けば聞くほど愛着が湧いてくる言葉ばかりです。
この記事では、佐賀県でよく使う方言を、基本的な表現から日常会話で使える単語やフレーズ、さらには地域による違いまで、例文を交えながらやさしくわかりやすく解説していきます。佐賀県への旅行や移住を考えている方はもちろん、方言に興味がある方も、ぜひ最後までご覧ください。この記事を読めば、あなたも佐.賀弁の虜になること間違いなしです。
佐賀県方言でよく使う基本のあいさつと語尾

佐賀県の方言、佐賀弁に親しむ第一歩として、まずは日常で頻繁に耳にする基本的なあいさつや特徴的な語尾からご紹介します。これらを覚えるだけで、ぐっと佐賀県民との距離が縮まるはずです。
挨拶で使われる佐賀県方言
日常のコミュニケーションの基本となる挨拶にも、佐賀弁ならではの表現があります。例えば、朝の挨拶「おはようございます」は「おはようごたーす」と言うことがあります。 特に地域の人同士の親しい間柄で使われる、温かみのある表現です。
また、別れの挨拶では「そいぎ」や「そいぎんた」がよく使われます。 これは標準語の「それじゃあ」「じゃあね」にあたる言葉で、友人との別れ際や電話を切る際などに気軽に用いられます。 「そいぎ、また明日ね」のように使うことで、親しみを込めた挨拶になります。これらの挨拶を自然に使えるようになれば、あなたも佐賀ツウの仲間入りです。
よく使う語尾「~ばい」「~たい」
佐賀弁を特徴づける最も有名な要素の一つが、文末に使われる「~ばい」と「~たい」です。 これらは主に断定や主張を表す際に使われ、会話にリズムと佐賀らしさを与えます。
「~ばい」は、話者が事実だと確信していることや、自分の意見を述べるときに使われます。「今日は暑かばい(今日は暑いね)」や「おいが言うたとばい(俺が言ったんだよ)」のように、男性が使うことが多い表現です。
一方、「~たい」も同様に断定を表しますが、「~ばい」よりも少し柔らかいニュアンスで使われることがあります。「あそこのラーメンは美味しかとたい(あそこのラーメンは美味しいんだよ)」のように、相手に情報を教えたり、同意を求めたりする場面でよく耳にします。これらの語尾を使いこなすことが、自然な佐賀弁を話す上での第一歩と言えるでしょう。
疑問を表す「~と?」と同意を求める「~ごたっ」
相手に質問をするとき、佐賀弁では語尾に「~と?」を付けます。 標準語の「~なの?」と同じように使われ、イントネーションを上げることで疑問の意を表します。「これ、あんたんと?(これ、あなたのもの?)」や「もう帰ると?(もう帰るの?)」のように、日常のあらゆる場面で登場する便利な表現です。 同じ「と」でも、平坦なアクセントで「~のもの」という意味を表したり、強調で使ったりと、アクセントによって意味が変わるのも面白い特徴です。
また、「~ごたっ」または「~ごと」は、「~のようだ」「~みたいだ」という意味で、推量やたとえを表す際に使われます。 例えば、「雨の降りよるごたっ(雨が降っているようだ)」や「夢のごたっ話ばい(夢のような話だよ)」のように使います。相手に様子を伝えたり、自分の感想を述べたりする際に便利な言葉です。
これだけは知っておきたい!よく使う佐賀県方言【単語編】

佐賀弁には、標準語とは異なるユニークな単語がたくさんあります。ここでは、特に日常会話でよく使われる代表的な単語をピックアップしてご紹介します。意味を知っていると、佐賀県民との会話がもっと楽しくなるはずです。
「とても」を意味する強調の言葉「がばい」
佐賀弁と聞いて多くの人が真っ先に思い浮かべるのが「がばい」ではないでしょうか。 これは「とても」「すごく」といった意味の強調を表す言葉で、良い意味でも悪い意味でも使われます。例えば、「がばい嬉しか(とても嬉しい)」、「がばいぬっか(すごく暑い)」、「がばいすごか(ものすごくすごい)」のように、形容詞の前に付けてその度合いを強調します。
もともとは「急な動き」を表す言葉が変化したものとされています。 今では佐賀県を代表する方言として全国的に知られており、佐賀県民の気質を表す言葉としても親しまれています。何かを表現するときに「がばい」を付け加えるだけで、一気に佐賀弁らしい生き生きとした表現になります。
「かわいい」を意味する「やーらしか」
子どもや動物など、愛らしいものを見たときに思わず口から出るのが「やーらしか」です。 これは標準語の「かわいい」にあたる言葉で、佐賀の人々が愛情を込めて使う表現です。 例えば、かわいい赤ちゃんを見て「この子はほんとやーらしかねー」と言ったり、素敵な小物を見つけて「この飾りもやーらしか」と表現したりします。
言葉の響き自体もどこか優しく、温かみを感じさせます。「愛らしい」という言葉が変化したものとされ、その語源からも愛情深さが伝わってきます。 佐賀県民が「やーらしか」と言っている場面に出会ったら、それは心からの「かわいい」という気持ちの表れです。
感情を表す言葉「はらかく」「ちゃーがつか」
感情を表す言葉にも佐賀弁ならではの表現があります。「はらかく」は「怒る」「腹が立つ」という意味です。 例えば、「そがんことされたら、はらかくばい(そんなことをされたら腹が立つよ)」のように使います。直接的に「怒る」と言うよりも、少しユーモアが感じられる表現かもしれません。
一方、「ちゃーがつか」は「恥ずかしい」「みっともない」という意味の言葉です。 例えば、人前で失敗してしまった時に「うーわ、ちゃーがつかー」と顔を赤らめたり、「そがん格好はちゃーがつか(そんな格好は恥ずかしい)」と注意したりする際に使われます。 この言葉は「耐え難い」という言葉が変化したものという説もあります。 どちらも佐賀県民の感情を豊かに表す、なくてはならない言葉です。
状態を表す言葉「ぬっか」「ひゃーか」
気候や物の状態を表す言葉にも特徴的なものがあります。「ぬっか」は「暑い」という意味で、特に夏の蒸し暑い日によく使われます。 「今日はぬっかねー」は、夏の挨拶代わりにもなるフレーズです。
その反対に、「寒い」または「冷たい」を意味するのが「ひゃーか」です。 冬の寒い日には「今日はひゃーかねー」と言い、冷たい水に触ったときには「うわ、ひゃーか!」と声を上げます。この「ひゃーか」は、「蠅(はえ)」も同じ発音なので文脈で判断する必要があります。 これらの言葉は、佐賀の気候風土と共に人々の生活に根付いています。
標準語と意味が少し違う?「なおす」「くる」
佐賀弁の中には、標準語と同じ言葉なのに意味が異なるものがあり、他県民を混乱させることがあります。その代表格が「なおす」です。標準語では「修理する」という意味で使われますが、佐賀弁では「片付ける」「元の場所に戻す」という意味で使われます。「この本、なおしといて」と言われたら、本を修理するのではなく、本棚に戻してほしいという意味になります。
また、「行く」を「くる」と言うのも特徴的です。 例えば、これから相手の所へ向かうときに「今からくっけんね(今から行くからね)」と言います。 これは「相手の視点に立って、自分が『来る』」と表現する、佐賀県民の思いやりが表れた言い方なのかもしれません。初めて聞くと少し戸惑うかもしれませんが、知っておくとコミュニケーションがスムーズになります。
日常会話でよく使う佐賀県方言【フレーズ編】

単語だけでなく、まとまったフレーズを覚えておくと、より自然な佐賀弁での会話が楽しめます。ここでは、あいさつや感謝、驚きなど、さまざまな場面で使える便利なフレーズをご紹介します。
「ありがとう」を伝える感謝のフレーズ
佐賀弁で感謝を伝えるときには、温かみが感じられる表現が使われます。一般的には標準語と同じく「ありがとう」が使われますが、より丁寧に感謝を伝えたい場合や、年配の方との会話では「あいがとぐゎした」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは「ありがとうございました」にあたる丁寧な表現で、心からの感謝の気持ちが伝わります。
また、相手の親切に対して「すみませんねえ」というニュアンスで「すんまっせん」と言うこともあります。何かをしてもらったときに、感謝と恐縮の気持ちを込めて「わざわざすんまっせんね」のように使います。これらのフレーズを使い分けることで、より心のこもったコミュニケーションがとれるでしょう。
驚いたときの表現「うーわ、すごっ!」「たまがったー」
予期せぬ出来事に遭遇したり、素晴らしいものを見たりしたとき、佐賀県民は感嘆の声を上げます。よく使われるのが「うーわ、すごっ!」という表現です。「うーわ」という感嘆詞が驚きの大きさを表し、「すごい」という気持ちをストレートに伝えます。
また、「たまがる」という言葉も「驚く」「びっくりする」という意味で頻繁に使われます。 例えば、思いがけないプレゼントをもらって「こりゃたまがったー!(これは驚いた!)」と言ったり、見事な景色を前にして「たまがるごたっ景色たい(びっくりするような景色だね)」と感心したりします。どちらの表現も、驚きや感動を生き生きと伝える、佐.賀弁らしいフレーズです。
肯定・否定・相づちのフレーズ
会話をスムーズに進める上で欠かせないのが、肯定や否定、相づちの言葉です。佐賀弁では、同意を示す相づちとして「そいぎ」や「そいそい」がよく使われます。 「そうだね」「その通り」といった意味で、相手の話にリズムよく相づちを打つ際に便利です。
肯定の返事としては「なーい」が使われることがあります。 これは「はい」にあたる言葉で、年配の方などが使うことのある、少し古風で丁寧な響きを持つ返事です。
一方、何かを断るときや「できない」と伝えるときには「でけん」と言います。 「そいはでけんばい(それはできないよ)」のように使い、はっきりと、しかしどこか角の立たない響きで意思を伝えることができます。これらの短いフレーズを覚えるだけで、会話のキャッチボールがより楽しくなるでしょう。
その他の便利な日常フレーズ「どがんしたと?」「よかよか」
他にも、覚えておくと便利なフレーズはたくさんあります。相手の様子がおかしいときや、何か困っているように見えるときに「どがんしたと?」と声をかけます。これは「どうしたの?」という意味で、相手を気遣う優しい気持ちが込められた言葉です。
また、佐賀弁を代表する温かい言葉が「よかよか」です。 「いいよ、いいよ」「大丈夫だよ」という意味で、相手の謝罪に対して「気にしないで」と伝えたり、失敗した人を励ましたりするときに使われます。この一言には、相手を包み込むような優しさと大らかさが詰まっており、佐賀県民の温かい人柄を象徴する言葉と言えるでしょう。
佐賀県方言の面白い特徴と地域による違い

佐賀県の方言は、単語やフレーズだけでなく、その発音や県内での地域差にも面白い特徴があります。ここでは、佐賀弁の音声的な特徴や、エリアごとの言葉の違いについて、少し掘り下げてご紹介します。
擬音語・擬態語を3回繰り返す
佐賀弁のユニークな特徴の一つに、擬音語や擬態語を3回繰り返す傾向があります。 標準語では「雨がザーザー降る」「犬がワンワン鳴く」のように2回繰り返すのが一般的ですが、佐賀弁では「雨のざーざーざーで降りよっ」「犬のわんわんわんで吠えよっ」というように3回重ねて表現することがあります。
他にも、石が転がる様子を「ころころころ」、風が吹く音を「ぴゅーぴゅーぴゅー」と表現するなど、さまざまな場面でこの「3回繰り返し」が聞かれます。 この表現によって、言葉のリズムが良くなるだけでなく、その様子がより強調されて生き生きと伝わります。佐賀県民の豊かな表現力の一端がうかがえる、非常に面白い特徴です。
古語や漢語由来の言葉が残っている
佐賀弁には、古い時代の日本語(古語)や、かつて武士階級で学ばれた漢語に由来する言葉が今もなお残っているという特徴があります。 例えば、「へび」を「くちなわ」、「嘘」を「すらごと」、「空腹」を「ひだるか」、「トイレ」を「せっちん」と言うことがあり、これらは平安時代や室町時代に使われていた言葉の名残です。
また、佐賀藩の武士が学んだ漢語が庶民に広まり、話し言葉として定着した「漢語方言」も存在します。 「全部」を意味する「しっきゃあ(悉皆)」や、「表通り」を意味する「おうかん(往還)」などがその例です。 これらの言葉が日常会話に溶け込んでいる点は、歴史と文化が色濃く残る佐賀県ならではの興味深い特徴と言えるでしょう。
佐賀県内の地域による方言の違い
一口に佐賀弁と言っても、実は県内でいくつかの地域に分けられ、それぞれに言葉の違いが見られます。 大きく分けると、県南部の旧佐賀藩領で使われる「佐賀方言」、県北部の旧唐津藩領で使われる「唐津方言」、そして県東部の旧対馬藩領の飛び地だった地域で使われる「田代方言」の3つに大別されます。
例えば、「雨が降っている」という同じ状況でも、唐津地域では「あめのふっちょる」、佐賀西武では「あめのふいよっ」、佐賀東部では「あめのふっとる」といったように、地域によって微妙な違いがあります。 さらに、指示代名詞の「こんな・そんな・あんな・どんな」も、佐賀方言では「こがん・そがん・あがん・どがん」となるのに対し、唐津方言や田代方言では「こやん・そやん・あやん・どやん」のように変化します。 このように、住んでいる地域によって言葉遣いが異なるのも、佐賀県方言の奥深さであり、面白い点です。
まとめ:佐賀県方言は魅力満載!よく使う言葉から覚えよう

この記事では、佐賀県でよく使う方言について、基本的な挨拶や語尾から、日常会話で使える単語・フレーズ、さらには地域差まで幅広くご紹介しました。
「がばい」「そいぎ」といった有名な言葉はもちろん、「やーらしか(かわいい)」、「はらかく(腹が立つ)」、「ちゃーがつか(恥ずかしい)」など、感情を豊かに表現する言葉がたくさんあることがお分かりいただけたかと思います。 また、擬音語を3回繰り返したり、古語や漢語が残っていたりと、言語的にも非常に興味深い特徴を持っています。
一見すると少し無骨に聞こえるかもしれませんが、その言葉の裏には佐賀県民の温かさや優しさが込められています。「よかよか」という言葉に象徴されるように、大らかで人情味あふれる佐賀弁。この記事をきっかけに、ぜひ佐賀県方言に親しみを持ち、実際に使ってみてください。きっと、佐賀の人々との距離がぐっと縮まるはずです。