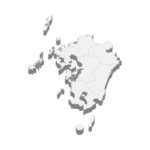群馬県で暮らしていると、地元の人たちが話す言葉に「おや?」と思うことがあるかもしれません。実はそれ、魅力あふれる群馬の方言、通称「上州弁」かもしれません。群馬県は関東地方にありながら、独自の言葉や言い回しが今もなお人々の生活に根付いています。 特に語尾に特徴があったり、標準語とは少し違うアクセントがあったりして、県外の人が聞くと「怒っているのかな?」と勘違いしてしまうこともあるようです。
この記事では、そんな群馬でよく使う方言を、基本的な特徴から日常会話で使える単語やフレーズまで、分かりやすく解説していきます。地元の人たちが何気なく使っている言葉の意味を知れば、群馬での生活や旅行がもっと楽しくなるはずです。あなたもこの記事を読んで、群馬の方言の奥深い世界に触れてみませんか?
群馬でよく使う方言の基本的な特徴

群馬の方言、いわゆる上州弁は、関東地方の方言の中でも独特の響きと特徴を持っています。その背景には、群馬県の地理的な条件や歴史が関係しています。山に囲まれた地域が多いため、古くからの言葉が残りやすかったのです。 まずは、そんな群馬弁の基本的な特徴から見ていきましょう。
語尾に特徴がある「~べえ」と「~だんべえ」
群馬の方言と聞いて、多くの人が思い浮かべるのが「~べえ」や「~だんべえ」という語尾ではないでしょうか。 これらは関東地方で広く使われる方言ですが、群馬では特に意志や勧誘、推量を表す際に頻繁に登場します。
例えば、「行こうよ」と友達を誘うときは「行くべえ」、「~だろう」と推測するときは「~だんべえ」といった具合です。 具体的には、意志や勧誘の意味合いでは「べえ」を、推量の意味合いでは「だんべえ」を使い分ける傾向があります。
この「だんべえ」は非常に便利で、とりあえず言葉の終わりにつけるだけで、一気に群馬弁らしい雰囲気になります。 「そうだんべえ!(そうだろ!)」「言ったんべえ!(言っただろ!)」のように、断定から疑問まで幅広く使えるのが特徴です。
イントネーションは平板アクセントが基本
群馬の方言のもう一つの大きな特徴は、そのイントネATIONです。標準語に比べて抑揚が少なく、平坦な「平板アクセント」で話されることが多いと言われています。
例えば、標準語では「は↑し↓(橋)」と「は↓し↑(箸)」のようにアクセントで意味を区別しますが、群馬弁ではどちらも平坦に発音される傾向があります。また、「いちご」や「半袖」といった単語も、多くの地域とは異なるアクセントで発音されることがあります。
この平坦なイントネATIONと、後述する少し早口で語尾が強くなる話し方が相まって、初めて聞く人には少しぶっきらぼうに聞こえたり、時には怒っているように聞こえてしまったりすることもあるようです。 しかし、これは群馬の人たちの素朴でストレートな気質を表しているとも言えるでしょう。
上州弁(群馬弁)と呼ばれる理由
群馬県の方言が「上州弁(じょうしゅうべん)」と呼ばれるのは、群馬県の旧国名である「上野国(こうずけのくに)」に由来します。 この「上野国」の別称が「上州(じょうしゅう)」であるため、そこで話される言葉が「上州弁」と呼ばれるようになりました。
現在でも、群馬県の人々は自分たちの土地や文化に誇りを持ち、「上州」という言葉を愛着を込めて使っています。例えば、群馬名物「上州からっ風」などがその代表例です。
この上州弁は、西関東方言に分類され、同じ北関東の栃木弁や茨城弁とは少し系統が異なります。 関東地方の中でも、東京や埼玉とは一味違った、独自の言語文化が育まれてきたのです。
日常会話でよく使う群馬の方言【単語編】

群馬の日常会話では、標準語とは少し違うユニークな単語が頻繁に飛び交います。知っていると、地元の人との会話がぐっとスムーズになるかもしれません。ここでは、特によく使われる単語をいくつかピックアップしてご紹介します。
「なっから」- とても、すごく
「なっから」は、「とても」や「すごく」といった意味で使われる強調の言葉です。「このまんじゅう、なっからうまいねえ」というように、食べ物がおいしい時や、何かにとても感心した時などに使います。
「でれぇ」という言葉も同じく「とても」や「ものすごく」という意味で使われることがあります。 どちらも感情を込めて何かを表現したいときに便利な言葉です。例えば、とてもかっこいい人を見かけたときに「なっからかっこいい」と言えば、その気持ちがストレートに伝わるでしょう。
「そうなん」- そうなんだ
相手の話に相槌を打つとき、群馬では「そうなん?」という言葉がよく使われます。 標準語の「そうなんだ」や「そうなの?」にあたる言葉で、会話の中で聞き返す場面などで頻繁に登場します。
例えば、「明日、急にテストになったんだって」「え、そうなん?」といった具合です。 語尾が少し上がるイントネATIONで使われることが多く、親しい間柄での気軽なコミュニケーションには欠かせない表現の一つです。
また、似たような相槌の言葉として「あーね」もあります。 これは「あー、そうだね」という意味で、相手の意見に同意するときに使われます。
「おせんたく」- 洗濯
群馬の一部の地域、特に年配の方々の間では、「洗濯」のことを「おせんたく」と言うことがあります。これは丁寧語というわけではなく、ごく自然な日常会話の中で使われる表現です。
このほかにも、言葉の頭に「お」がつくユニークな表現がいくつかあります。例えば、「おっこちる(落ちる)」や「おっぺす(押す)」など、どこか可愛らしい響きを持つ言葉が多いのも群馬の方言の面白いところです。
「かう」- (鍵を)かける
標準語で「かう」と言えば「買う」や「飼う」を思い浮かべますが、群馬では「(鍵を)かける」という意味で使われることがあります。家に帰ってきて「ちゃんと鍵かった?」と言われたら、それは「ちゃんと鍵をかけましたか?」という意味です。
この他にも、動詞には特徴的なものが多くあります。例えば、かき混ぜることを「かんます」、捨てることを「なげる」と言ったりします。 初めて聞くと意味を勘違いしてしまいそうな言葉も、意味を知ると面白い発見があります。
「なげる」- 捨てる
「このゴミ、なげといて」と言われたら、あなたはゴミを投げてしまうかもしれません。しかし、群馬で「なげる」は「捨てる」という意味で使われます。 ですから、この場合は「このゴミ、捨てておいて」と頼まれていることになります。
この「なげる」は、群馬県民にとってはごく当たり前の日常語ですが、県外の人にとっては最も誤解を招きやすい方言の一つかもしれません。同じように「ほっぽりだす」も「捨てる」という意味で使われることがあります。
「おっかく」- 折る、割る
「おっかく」は「折る」や「割る」という意味で使われる方言です。「枝をおっかく」や「せんべいをおっかく」のように使います。力が加わってものが二つに分かれてしまうような状況で使われることが多い言葉です。
似たような言葉に「ぶっかく」という表現もあり、これも何かを壊したり割ったりする際に使われます。 勢いのある言葉の響きが、いかにも群馬弁らしいと言えるでしょう。
知っていると面白い!群馬でよく使う方言【フレーズ編】

単語だけでなく、群馬ならではの言い回しやフレーズもたくさんあります。これらを使いこなせれば、あなたも立派な「グンマー」の仲間入りです。日常の様々な場面で使える、特徴的なフレーズを見ていきましょう。
「だんべえ」- ~だろう
すでにご紹介した通り、「だんべえ」は群馬弁を代表する語尾です。 推量や同意を表す「~だろう」という意味で、日常会話のあらゆる場面で登場します。 「明日は晴れるだんべえ」と言えば「明日は晴れるだろう」、「そうだんべえ」と言えば「そうだろう」といった具合です。
この「だんべえ」は非常に応用範囲が広く、とりあえずこれを付けておけば群馬弁らしく聞こえる、便利な言葉です。 もともとは「~だろう」という意味合いで使われていましたが、現在では軽い断定や相手への同意を求める際にも使われます。
「~(し)ないで」- ~しないで
否定の「ない」の使い方も特徴的です。「来ない」は「きない」または「きねえ」となります。 例えば、「彼はまだ来ないね」は「彼はまだきねえね」といった形になります。
また、「~しないでください」とお願いする際には、「~(し)ないで」という少し短縮された形がよく使われます。「押さないでください」は「押さないで」、「見ないでください」は「見ないで」となります。少しぶっきらぼうに聞こえるかもしれませんが、決して怒っているわけではなく、これが通常の言い方なのです。
「どうだい」- どうですか?
相手の様子を尋ねたり、意見を聞いたりするときに「どうだい?」というフレーズが使われます。標準語の「どうですか?」にあたる言葉で、例えば「最近、体のあんべ(具合)はどうだい?」のように使います。
似たような表現に「~だいね」という語尾もあります。 これは「~だよね」という軽い同意を求めるニュアンスで使われ、「そうだいね(そうだよね)」「困ったいね(困ったよね)」のように会話に挟むことで、より親しみを込めた表現になります。
「~するんさね」- ~するんだよね
群馬の方言では、語尾に「~さ」や「~さね」がよく付きます。 これは、自分の言っていることを強調したり、相手に同意を求めたりするときに使われる表現です。 「昨日、面白い映画を見たんだよね」というのを群馬弁で言うと、「昨日、面白い映画を見たしさ(見たんさ)」のようになります。
「~なんさ」という形も頻繁に使われます。 「彼は来ないんだよね」は「彼は来ないんさね」となります。この「さ」は、特に意識せずに会話の中に溶け込んでいることが多いため、群馬県民自身は方言だと気づいていないケースも多いようです。
「だから言ったんじゃねえの」- だから言ったじゃないか
少し強い口調に聞こえるかもしれませんが、「だから言ったんじゃねえの」というフレーズもよく耳にします。これは、相手が忠告を聞かなかったり、同じ失敗を繰り返したりしたときに、「だから言ったじゃないか」という意味で使われます。
標準語に直訳すると少しきつく聞こえますが、実際には「しょうがないなあ」というような、呆れつつも親しみを込めたニュアンスで使われることが多いです。似たような表現で「とっから言ったじゃん(だから言ったじゃん)」という言い方もあります。
群馬の方言は地域によっても違いがある?

一口に「群馬の方言」と言っても、実は県内でも地域によって少しずつ言葉に違いがあります。 これは、群馬県が地理的に広く、山間部や平野部、そして隣接する県との関係性など、それぞれの地域が独自の歴史や文化を育んできたからです。 大きく分けると、北部・西部の山間部、中部の平野部、東南部の3つのエリアで方言に特徴が見られます。
東毛地域(桐生市、太田市など)の方言
県の東部に位置する東毛地域、特に桐生市や太田市周辺では、隣接する栃木県の方言の影響が見られます。
例えば、太田市周辺では「~だんべえ」が「~だにぃ」に変化することがあります。 「そうだよね」が「そうだにぃ」、「言ったでしょ」が「言ったんにぃ」といった具合です。
また、桐生市周辺では「~だが」や「~だがん」という語尾が使われることもあります。 「そこにあるでしょ!」が「そこにあるがん!」となります。 さらに、東南部の邑楽郡地方では、栃木弁の特徴である「~っぺ」という語尾が使われることもあり、西関東方言と東関東方言が混じり合った興味深い地域となっています。
中毛地域(前橋市、伊勢崎市など)の方言
県の中央部に位置する中毛地域は、前橋市や伊勢崎市などを中心とする平野部です。この地域の方言は、都市部に近いこともあり、比較的標準語に近いと言われています。
しかし、標準語に近いとはいえ、やはり群馬弁らしさは健在です。日常会話の中では、「~だんべ」や「~なんさ」といった群馬特有の語尾がごく自然に使われています。
他の地域に比べて方言の色は薄いかもしれませんが、アクセントやイントネーションにはやはり群馬ならではの特徴が残っており、親しみやすい上州弁を聞くことができます。
西毛地域(高崎市、富岡市など)の方言
高崎市や富岡市などを中心とする西毛地域は、群馬県の西部に位置します。この地域でも、中毛地域と同様に「~だんべえ」などの基本的な上州弁が使われていますが、独自の言い回しも存在します。
例えば、富岡市周辺でまとめられた方言のリストには、「あんじゃねぇ(心配ない)」や「いっちょうめぇ(一人前じみた)」、「おやげねぇ(かわいそう)」といった、地域に根差した言葉が見られます。 これらの言葉からは、人々の生活の様子や気質が垣間見え、方言の奥深さを感じさせます。
北毛地域(沼田市、渋川市など)の方言
県の北部に広がる沼田市や渋川市、そして吾妻郡などの北毛地域は、山間部が多いのが特徴です。山に囲まれた地理的条件から、他の地域に比べて古くからの言葉や表現が色濃く残っていると言われています。
例えば、否定の助動詞「ない」が「来る」につく場合、多くの地域では「きない」や「きねえ」となりますが、吾妻郡では「こない」「こねえ」と、標準語に近い形が使われるという違いがあります。 このように、同じ県内でも地域によって細かな違いがあり、方言の多様性を生み出しています。
まとめ:群馬でよく使う方言を知ってもっと群馬を好きになろう

この記事では、群馬でよく使う方言、いわゆる「上州弁」について、その基本的な特徴から日常会話で使える単語やフレーズ、さらには地域による違いまで幅広くご紹介しました。
「~だんべえ」や「~なんさ」といった特徴的な語尾、平坦なイントネATION、そして「なげる(捨てる)」や「かんます(かき混ぜる)」といったユニークな単語など、群馬の方言には魅力がたくさん詰まっています。 一見すると少しぶっきらぼうに聞こえるかもしれませんが、その言葉の裏には群馬の人々の素朴さや温かさが隠されています。
最初は聞き慣れない言葉に戸惑うこともあるかもしれませんが、意味を知ることで地元の人たちとのコミュニケーションがより円滑で楽しいものになるはずです。この記事をきっかけに、ぜひ群馬の方言に親しみを持ち、群馬という土地をさらに深く味わってみてください。