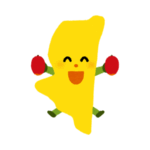「だっちゃ」「いずい」などの言葉で知られる宮城県の方言。独特の響きがありながら、どこか温かみを感じさせる魅力がありますよね。宮城県は、かつて仙台藩だった歴史的背景から、県内で話される言葉に大きな違いは少ないと言われています。 しかし、仙台市を中心としたエリアや、県北、県南、沿岸部など、地域によって少しずつ異なる特徴を持っているのも面白いところです。
この記事では、「宮城県の方言でよく使う言葉」をテーマに、日常会話で使える基本的な方言から、少しユニークな表現、そして地域ごとの違いまで、分かりやすく解説していきます。宮城の言葉の背景には、奈良時代や平安時代の都言葉がルーツになっているものもあると言われています。 この記事を読めば、あなたもきっと宮城の方言が持つ奥深さや面白さに気づき、実際に使ってみたくなるはずです。
宮城県の方言でよく使う基本の言葉と特徴

宮城県の方言、通称「仙台弁」は、東北地方の方言の一つである南奥羽方言に分類されます。 江戸時代に現在の宮城県全域が仙台藩の領地だったため、県内での方言差は比較的小さいとされています。 とはいえ、語尾のイントネーションや一部の語彙には地域ごとの特色も見られます。 ここでは、まず覚えておきたい基本的な宮城の方言とその音声的な特徴についてご紹介します。
まず覚えたい!代表的な宮城の方言
宮城県民が日常的によく使う、代表的な方言をいくつかご紹介します。これらを覚えるだけで、地元の人との会話がより一層楽しくなるかもしれません。
・いずい
「いずい」は、宮城の方言を代表する言葉の一つですが、標準語で一言に訳すのが非常に難しいとされています。 例えば、「目にゴミが入ってゴロゴロする感じ」や「服のタグが当たってチクチクする不快感」など、何かとしっくりこない、居心地が悪い、具合が悪いといった感覚を表すのに使われます。 この言葉のルーツは、室町時代に使われていた「恐ろしい」を意味する「えずし」にあるという説もあります。
・おばんです
「こんばんは」を意味する挨拶言葉です。 宮城県だけでなく、東北地方の多くの地域で使われています。日が暮れてからの挨拶として、お店に入る時や人と会った時などに「おばんでがす」「おばんです」と自然に使われます。 丁寧な響きがあり、どこか懐かしさを感じさせる言葉です。
・なげる
標準語の「投げる」と同じ意味で使うこともありますが、宮城県では主に「捨てる」という意味で使われます。 そのため、「ゴミをなげる」というフレーズを聞いたら、それは「ゴミを捨てる」という意味になります。 東北地方の他の県でも同様に使われることがある表現です。 知らないと少し驚いてしまうかもしれませんが、地元ではごく当たり前に使われている言葉です。
日常会話で頻出の語尾・接尾語
会話の最後に付くことで、宮城らしいニュアンスを生み出す特徴的な語尾や接尾語がたくさんあります。これらを使いこなせると、よりネイティブらしい話し方に近づけます。
・〜だっちゃ
宮城県の方言と聞いて、多くの人がアニメ『うる星やつら』のラムちゃんを思い浮かべる「〜だっちゃ」という語尾。 これは「〜だよ」という肯定や、「〜だよね?」という確認の意味で使われます。 実際には「〜じゃー」や「〜っじゃ」のように聞こえることもあります。 若者世代での使用頻度は減っているものの、宮城を象徴する方言として広く知られています。
・〜けさいん・〜けらいん
「〜してください」という丁寧な依頼を表すのが「〜けさいん」です。 例えば、「来てけさいん」は「来てください」、「食べてけさいん」は「食べてください」となります。 一方、「〜してあげてください」という意味になるのが「〜けらいん」です。 どちらも相手への配慮が感じられる、温かみのある表現です。
・〜べ・〜ぺ
「〜しよう」という誘いや、「〜だろう」という推量を表す語尾で、東北地方で広く使われています。 宮城県でも「行ぐべ(行こう)」「食べっぺ(食べよう)」のように日常的に使われます。 若者の間でも比較的使用頻度が高い方言の一つで、親しみを込めて相手を誘う際によく聞かれる表現です。
・〜さ
助詞の「〜へ」や「〜に」にあたる言葉として「〜さ」が使われます。 「学校さ行ぐ」は「学校へ行く」、「仙台さ遊びに行く」は「仙台に遊びに行く」という意味になります。 これも東北地方で共通して見られる特徴的な言い回しです。
イントネーションや発音の特徴
宮城の方言は、個々の単語だけでなく、その独特のイントネーションや発音にも特徴があります。これらが組み合わさることで、宮城弁特有の温かく、柔らかい響きが生まれます。
・ズーズー弁
東北地方の方言の代名詞とも言える「ズーズー弁」。これは、「し」と「す」、「じ」と「ず」、「ち」と「つ」の区別が曖昧になる発音のことを指します。 例えば「寿司」が「スス」に近くなったり、「地図」が「チズ」ではなく「ツズ」に聞こえたりします。これは、寒い地域で口を大きく開けずに話すため、あるいは発音の負担を軽減するために生まれたという説があります。
・語中・語尾の濁音化
単語の途中や終わりにある「カ行」や「タ行」の音が濁って、「ガ行」や「ダ行」の音になるのも特徴です。 例えば、「開ける」が「アゲル」、「旗」が「ハダ」のように発音されることがあります。 これにより、言葉全体の響きが柔らかく聞こえる効果があります。
・平坦なアクセント(無アクセント)
仙台市を含む県南地域では、言葉のアクセントに高低の区別がない「無アクセント」の傾向が見られます。 例えば標準語では「箸(は↑し↓)」と「橋(は↓し↑)」でアクセントが異なりますが、無アクセント地域ではこれらを同じ高さで発音するため、文脈で判断する必要があります。 これが、他県の人が聞くと「のっぺりしている」「平坦に聞こえる」と感じる理由の一つです。
シーン別!宮城県のよく使う方言フレーズ集

基本的な単語や特徴がわかったところで、次は具体的な会話シーンで使える方言フレーズを見ていきましょう。挨拶から感情表現、食事の場面まで、知っていると宮城でのコミュニケーションがもっと楽しくなるはずです。
挨拶で使う方言
毎日使う挨拶にも、宮城らしさが溢れています。朝から晩まで、様々な場面で使えるフレーズを覚えてみましょう。
・おはようがす・おはようござりす
「おはようございます」を意味する丁寧な朝の挨拶です。 「〜ござりす」という響きには、どこか古風で雅な雰囲気も感じられます。 毎朝の挨拶をこの言葉で交わすだけで、一日の始まりが温かいものになりそうです。
・こんぬずわ
「こんにちは」が訛った表現で、日中の挨拶として使われます。 親しい間柄で使われることが多く、少しユーモラスな響きが特徴です。誰かに会った時に「こんぬずわ」と声をかければ、場が和むかもしれません。
・おみょうにち
「また明日」という意味で使われる言葉です。別れ際の挨拶として「んでまず、おみょうにち(それでは、また明日)」のように使います。 日常的に頻繁に使われるわけではありませんが、年配の方との会話などで聞くことがあるかもしれません。
・どうもね
「ありがとう」と「さようなら」の両方の意味合いを持つ便利な言葉です。 親しい人との別れ際に「送ってくれてどうもね」と言うと、「送ってくれてありがとう、またね」というニュアンスになります。 感謝と別れの挨拶を一度に伝えられる、効率的で温かい表現です。
感情を表現する時に使う方言
喜び、驚き、戸惑いなど、様々な感情を表すユニークな方言もたくさんあります。標準語とは一味違った感情表現を知ることで、言葉の面白さをより深く感じられるでしょう。
・いぎなり・いきなし
「とても」「すごく」という意味の強調表現です。 「いきなり」と聞くと標準語では「突然」という意味ですが、宮城では「いぎなり嬉しい(とても嬉しい)」「いきなし面白い(すごく面白い)」のように使います。 強調したい気持ちを表現するのに欠かせない言葉です。
・だから
標準語の接続詞「だから」とは異なり、相手の言葉に強く同意するときの相槌として使われます。 「そうだよね!」「その通り!」といったニュアンスで、「だから〜」「だからね〜」のように言います。 話の途中で「だから」と言われたら、それは話の続きを促しているのではなく、共感してくれている証拠です。
・ごしゃぐ・ごしゃがれる
「怒る」を「ごしゃぐ」、「怒られる」を「ごしゃがれる」と言います。 「先生にごしゃがれた(先生に怒られた)」のように使います。少し強い響きがありますが、日常会話でよく登場する表現です。秋田県などでも使われることがあります。
・はかはかする
「ドキドキする」「ハラハラする」といった、胸が騒ぐような気持ちを表す言葉です。 緊張する場面や、何かが起こりそうで落ち着かない時に「はかはかする」と使います。擬態語のような面白い響きが特徴的です。
・やんだくなる
「嫌になる」という意味で使われる言葉です。 「学校さ行ぐのやんだくなった(学校に行くのが嫌になった)」のように、気が進まない気持ちを表します。 拒否の気持ちを強く示したい時は「やんだ、やんだ!」と繰り返して使うこともあります。
知っていると面白いユニークな方言
中には、その言葉だけ聞いても意味の想像がつきにくい、面白い方言も存在します。意味を知ると、思わず誰かに話したくなるようなユニークな表現を集めました。
・おはよう靴下
靴下に穴が開いている状態を指す、非常にユニークな表現です。 指が穴から「おはよう」と顔を出している様子から、このように呼ばれるようになったと言われています。「あっ、おはよう靴下してる!」と指摘されたら、靴下に穴が開いていないか確認してみてください。
・ジャス
「ジャージ」のことを指します。主に学生が使う言葉で、「学校のジャス」のように言います。宮城県民にとっては当たり前の言葉ですが、他県の人が聞くと「ジャズ音楽のこと?」と勘違いしてしまうかもしれません。
・あっぺとっぺ
ちぐはぐで、つじつまが合わない様子を表す言葉です。 「話があっぺとっぺだ(話がちぐはぐだ)」のように、言動が矛盾している時などに使われます。語感の面白さが印象的な方言です。
・うるかす
「水に浸しておく」という意味の動詞です。 例えば、食べた後のお米がついたお茶碗を水につけておくことを「お茶碗うるかしといて」と言います。米を研ぐ前に水に浸す際にも使われ、東北や北海道で広く使われている言葉です。
宮城県内で見られる方言の地域差

宮城県の方言は県内で大きな差はないとされていますが、細かく見ると地域ごとに少しずつ違いがあります。 県庁所在地の仙台市周辺、県北、県南、そして沿岸部では、それぞれ独自の言葉やイントネーションが育まれてきました。ここでは、それらの地域ごとの特徴について少し掘り下げてみましょう。
仙台市周辺でよく使う「仙台弁」
宮城県の方言の代表格として語られるのが、仙台市とその周辺で使われる「仙台弁」です。 商業や文化の中心地であるため、他地域との交流も多く、伝統的な方言と共通語が混じり合った特徴を持っています。
「〜だっちゃ」という語尾は、特に仙台エリアの象徴的な表現として知られています。 また、「いぎなり(とても)」や、同意を示す「だから」といった言葉も、仙台の日常会話で頻繁に聞かれます。
一方で、都市化の進展とともに、若い世代では共通語に近い言葉遣いをする人も増えています。しかし、アクセントが平坦であったり、ふとした瞬間に「いずい」や「なげる(捨てる)」といった方言が出たりと、仙台弁のアイデンティティは今も健在です。ビジネスシーンでも、親しい間柄であれば方言がコミュニケーションを円滑にすることもあります。
県北(大崎・栗原地域)の方言の特徴
宮城県の北部に位置する大崎市や栗原市などの地域は、岩手県南部の文化圏とも接しているため、その影響を受けた言葉も見られます。
この地域のアクセントは、仙台市以南の無アクセントとは異なり、東京式アクセントに近い「有型アクセント」に分類されます。 つまり、単語に高低のアクセントの型があるため、県南の人が聞くと少しイントネーションが違うと感じることがあります。
語彙の面では、県北地域で特徴的に使われる言葉も存在します。例えば、驚いた時に「じゃじゃじゃ」という感嘆詞を使うことがあり、これは岩手県の方言とも共通する点です。基本的な語彙は県内他地域と共通するものが多いですが、こうした細かな違いに地域の個性が表れています。
県南(仙南・白石地域)の方言の特徴
宮城県の南部、通称「仙南」と呼ばれる白石市や角田市などの地域は、福島県と県境を接しています。 そのため、歴史的に見ても福島県の方言と共通する部分が多いのが特徴です。
特にアクセントは、仙台市と同様に高低差のない「無アクセント」地域であり、平坦な話し方が基本です。 文法的な特徴としては、理由を表す接続助詞「〜から」を「〜がら」と濁音化して発音する傾向が見られます。
また、福島県で使われる「〜だべした(〜だったでしょう)」のような言い回しが聞かれることもあり、県境を越えた言葉の連続性を感じさせます。県北地域とはまた違った、穏やかでゆったりとした響きを持つのが仙南地域の方言の魅力と言えるでしょう。
沿岸部(石巻・気仙沼地域)で聞かれる方言
石巻市や気仙沼市など、太平洋に面した三陸沿岸地域は、古くから漁業が盛んで、他の地域との海上交流によって独自の言語文化を育んできました。 この地域は「三陸方言」に分類され、内陸部とは少し異なる特殊な語彙を持つことがあります。
例えば、石巻周辺では自分のことを「おら」と言うことがあり、これは年配の方を中心に見られる特徴です。 また、気仙沼地域は岩手県の沿岸部と文化的に近く、ケセン語と呼ばれる独特の方言圏に含まれることもあります。
漁師町らしい、少しぶっきらぼうで威勢の良い言葉遣いが特徴的に聞こえることもありますが、その根底には人々の温かい人情が流れています。東日本大震災以降、地域の絆とともに方言の価値を再認識する動きも見られます。
もっと知りたい!宮城県の方言の背景と豆知識

ここまで宮城県の様々な方言を紹介してきましたが、なぜこのような言葉が使われるようになったのでしょうか。ここでは、方言が生まれた歴史的背景や、言葉にまつわる面白い豆知識について解説します。
宮城の方言の歴史と成り立ち
宮城県の方言、特に仙台弁の基盤が形成されたのは江戸時代、伊達政宗が治めた仙台藩の時代です。 広大な仙台藩の領内で使われていた言葉が基礎となっているため、県内の方言に大きな差が生まれなかったと考えられています。
さらにルーツを遡ると、奈良時代や平安時代の都(現在の関西地方)で使われていた言葉が、長い年月をかけて東北地方に伝わり、変化していったものが数多く残っているという説があります。 例えば、「かわいい」を意味する「めんこい」は、万葉集に出てくる「めぐし」という言葉が変化したものだと考えられています。 また、「〜べし」や「〜けり」といった古語が、「〜べ」や「〜け」という語尾の由来になったとも言われており、宮城の方言は古い日本語の面影を今に伝える貴重な文化遺産と見ることもできます。
有名な「〜だっちゃ」の本当のところ
宮城県の方言として全国的に最も有名な「〜だっちゃ」ですが、この言葉を広めたのは、やはり高橋留美子さんの漫画『うる星やつら』のヒロイン、ラムちゃんの影響が大きいでしょう。
しかし、作者の高橋留美子さんは新潟県の出身であり、ラムちゃんの言葉は特定の地域の方言をそのまま使ったわけではないようです。一説によると、山形県出身で仙台育ちの小説家・井上ひさしさんの作品に出てくる言葉の響きを参考にしたと言われています。
実際の仙台では、特に年配の方が使うことはありますが、ラムちゃんのようなイントネーションで話す人はほとんどいません。 むしろ「〜だっちゃ」よりも「〜じゃん」に近い「〜じゃ」や、同意を示す「んだ」などが日常的にはよく使われます。 とはいえ、「〜だっちゃ」が宮城のシンボル的な方言であることは間違いなく、地元の人々にも親しまれています。
若者世代の方言の使い方と変化
どの地域でも見られるように、宮城県でも若者世代の方言の使い方は変化しています。テレビやインターネットの影響で共通語に触れる機会が増え、日常会話では方言をあまり使わない若者も少なくありません。
しかし、完全に方言が使われなくなったわけではなく、言葉のニュアンスはそのままに、表現が少しマイルドに変化しているケースが見られます。例えば、強い否定を表す伝統的な方言の代わりに、共通語と混ぜたような柔らかい言い方をしたりします。
また、親しい友人との会話やSNSなど、特定のコミュニティの中では、あえて方言を使うことで仲間意識を高めるという現象も見られます。標準語と方言を場面によって使い分ける「方言バイリンガル」として、たくましく言葉を受け継いでいるのが現代の若者たちの姿と言えるでしょう。
宮城県のよく使う方言まとめ

この記事では、宮城県でよく使う方言について、基本的な言葉から地域差、歴史的背景まで幅広く解説してきました。
・宮城県の方言は「仙台弁」とも呼ばれ、県内での差は比較的小さい。
・「いずい」「おばんです」「なげる」などが代表的な言葉としてよく使われる。
・「〜だっちゃ」「〜けさいん」「〜べ」といった特徴的な語尾が会話に彩りを添える。
・発音では「ズーズー弁」や語中の濁音化、県南の無アクセントなどが特徴。
・仙台市周辺、県北、県南、沿岸部でそれぞれ少しずつ異なる言葉やイントネーションがある。
・そのルーツには古語や都の言葉が影響しているものもある。
方言は、単なる言葉の違いではなく、その土地の歴史や文化、人々の暮らしが詰まった大切な宝物です。今回紹介した方言を知ることで、宮城県への旅行や、地元の人々との交流が、より深く、温かいものになることを願っています。ぜひ、機会があれば「おばんです」「どうもね」といった言葉を実際に使ってみてください。